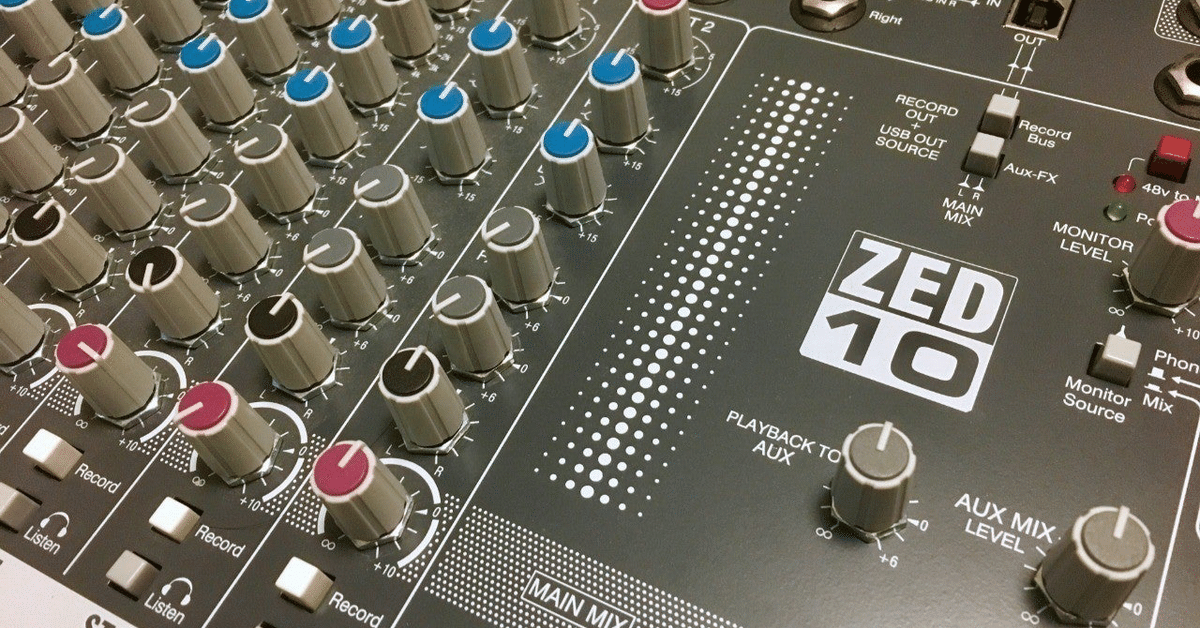
卒アルに寄せ書きがなくても
これは、私が高校を卒業した日の話。
卒業式の日の過ごし方に、私は別解を辿った。
みんなと卒業アルバムにメッセージを書き合うわけではない、卒業の日の追憶。
その日の早朝、私の下には一通のLINEがあった。
「卒業式終わった後、放送室に来て」
部活の副顧問からの連絡だ。
時は冬と春の狭間。
登校時間はまだまだ肌寒い。
最後の登校だというのに、程よい田舎道を自転車で往く私は茶色いダッフルコートに身を包んでおり、高校生のシンボルとも言える学生服はその下に隠れてしまっていた。
もうちょっと暖かくなっていたら桜なんかも舞って、もう少し思い出映えしただろうに。
学校に着いてから式典までの出来事は、もうあまり覚えていない。
体育館にたくさんのパイプ椅子が並んだその一つに座り、校長の言葉やら祝電やら送辞答辞を聞いた。
卒業証書授与は省略。代表者が受け取ったのを見ただけ。
すごくあっさり終わった。
式次第の全てが「とりあえずなぞりました」感。
卒業式が荘厳だったのは小学校や中学校までの話だったらしい。
わざわざ合唱までして、長い祝電や卒業証書授与の退屈さに耐えていたのも懐かしい。
特に人生の大きな節目を迎えた実感などないまま、体育館を後にした。
そうして式典が終わると教室へ戻り、最後のホームルームをした。
私のクラスの担任は泰然自若で、最後の日であってもいつも通りの調子でメッセージを残していく人だった。
生徒も全体的に落ち着いていてどこか自立した雰囲気のクラスだったこともあり、私たちはとても自然体なホームルームで幕を下ろした。
そして、解散した後。
高校生活で必要な時間を全て終えてから下校するまでの時間。
皆、自らの卒業アルバムとペンを手に持つ。
卒業アルバムの最後の方、真っ白な見開きのページにメッセージを書き合う時間がやってきた。
私はこの時間が好きじゃない。
もっと正確に言うならば、この「寄せ書きのし合い」という文化が私の性には合わない。
別に、皆がそれを楽しむのならそれはそれでいいと思っていたが、私はこの寄せ書きにどうしても積極的にはなれなかった。
どうしても、「作業」に見えてしまうのだ。
メッセージを書き合う時間。
同級生たちはクラスの友達に声を掛け、互いに書き終わっては別の人のところへ行き、メッセージを書き合う。
次から次へと足早に誰かの元へ行く。
人によっては、別に大して普段から親しくしていたわけではない「浅い友達」へのところへも行く。
私には、それがもはや寄せ書きを集めるという作業に躍起になっているようにしか見えなかった。
我ながら捻くれた人間だ。
確かに、大人になって歳を取って久々に卒業アルバムを開いたとき、その寄せ書きは一瞬で当時の記憶に色を取り戻させるのかもしれない。
そう考えると、寄せ書きは未来の自分への幸せに満ちた時限爆弾なのかもしれない。
だから、寄せ書き集めを無意味で愚かな行為だとは微塵も思わない。
ただ、私はそちらが目的になってしまうのが嫌だった。
せっかくの学校での最後の時間を、業務的な行為に費やしたくなかった。
「浅い友達」も含めたたくさんの知人と簡単に言葉を交わしながら言葉を集めていくよりも、学校生活を長く共にした大切な大切な友達と、最後の時間にじっくりと浸っていたかった。
だから、私は寄せ書きを集めようとはしないと決めて、高校生活最後の日に臨んでいた。
私は普段から、あまり写真を撮らない。
写真を撮ろうとすると、カメラを構えている間に自分が見ているのは、カメラの画面が映す姿。
写真撮影は、後に見返すことができるというメリットを生むが、そのカメラを構えている間は肉眼の時間を犠牲にする。
とはいえ、肉眼の景色は後から鮮明に思い出すことはできないので、合理的に考えると写真を撮っておくほうが「お得」には思える。
だけど私は、肉眼の時間を犠牲にしたくない。別にそれが正義だと思ってはいない。私がそうしていたいだけ。
寄せ書きもたぶん一緒なんだと思っている。
それは未来への仕掛けになるけど、その「行動」としての意識の存在が、今への没入を多少なりとも妨げる。
何故そこまでして澱みのない今を求めるのかは自分でもわからない。
だけど、そんな私に、寄せ書きを集める必要性などない。
ただ、その時限りの記憶でもいいから、大切な友達をゆっくり話せればいい。
ホームルームを終えた私は、同じクラスの友人と話をしていた。
寄せ書きを求められたりもした。別に求められたものを拒む理由もないので、求められたら書き合った。
時間が経つにつれ、自分が書き込むメッセージ欄が、だんだんたくさんの文字で埋まっていった。
態度には出さなかったけど、「よくこんな短時間でいっぱい集めるなあ」って思った。
嫌味のつもりじゃなく、単なる感嘆として。
しばらくすると、教室にクラスメイトの姿は減り、他のクラスの生徒が増えてきた。
私も友人と自然に会話が落ち着いたタイミングで他の教室へ向かう。
私の特に親しい友人は、ほとんど別のクラスにいた。
その、他クラスの友人たちも寄せ書きをするというのでメッセージを書き合ったが、そこで終わりはしない。
浅く広くではない、深く狭い友人とずっと喋っていた。
ただ、ずっと、早朝に受信した部活の副顧問からのLINEが頭の隅にはあった。
3年生の教室が並ぶ階を抜け出して放送室へ向かったのは、まだほとんどの同級生たちが廊下に溢れかえっている頃だった。
廊下の人混みを抜けて、階段に出る。
階段を下りる。
一気に人が減る。
元気な声たちが遠くなっていく。
実は、私が副顧問から放送室に来るよう頼まれていたのは、交通費の清算をするためだった。
うちの放送部では部費の徴収がなかったが、大会やイベントなどがあるとどうしても交通費が必要だった。
その交通費は部の予算から出ることになっていたものの、現役中ずっと自分で建て替えていて、その清算がなんだかんだ卒業の日まで縺れ込んでしまっていた。
放送室へ行く用件としては、ただそれだけ。
卒業とは関係ない。何の風情もない。
ただ、放送室へ向かう時間、その日最も心が躍動していた。
ただ交通費の清算をするだけなのに。
だけど、先生にお礼が言えたらいい。
ひょっとしたら、同じタイミングで放送部の仲間が清算に来ていて会えるかもしれない。
不確かな妄想に、私の足取りは弾んでいたと思う。
放送室に着いた。
放送室前の廊下には、副顧問は待っていなかった。
ただ、放送室のドアが開いていた。
入ると、副顧問と、共に部活を楽しんだ放送部のメンバーがいた。
私が来る前から、みんな談笑していた。
私が放送室を覗くと、いくつもの笑顔がこちらを向いた。
やっぱり、ここが一番暖かかった。
メンバーが全員集合した、というわけではないけれど、私が思っていたよりもたくさんのメンバーが放送室に来ていた。
そこでは副顧問とも一緒に、みんなでただただ話をした。
思い出の話をした。
それぞれの卒業後の話もした。
もう、教室には戻らなかった。
ずっと、放送室で、時間を忘れて過ごした。
寄せ書きは書き合っていない。
それでも、ただただ楽しかった。
それで十分だった。
やっぱり、帰る場所はここだと思った。
実は、これは2020年の話。
日本中の人々が家に篭るようになる少しだけ前。
例の病は騒ぎの渦中になっていて、卒業式は規模の縮小を強いられていた。
例年は卒業式に出席していた在校生や、OBOGなどの来校は禁止された。
また、卒業生は極力速やかに下校するよう勧告されていた。
当然、卒業生を部活動のOBOGや後輩が祝う、という定番のフリータイムは没収された。
放送部も例年は在校生やOBOGを招いて、放送室でパーティーのようなことをやっていたのだが、この年はできなかった。
だけど、多くの生徒が部室に行くこともない中、私たちは憩いの放送室で最後の時間を楽しんだ。
事実上、半ば密会のようなものだった。
先生や生徒たちの意識の向かう先は教室のフロア。
誰の気にも留められず、教室の喧騒からも離れた放送室は、まさに小さな孤城だった。
私たちが学び舎を出る頃、生徒の数はかなり減っていたように思う。
あの時の放送室は時間のない場所。
その日学校にいたほとんどの人の知らないところで、その時学校にいたほとんどの人の過ごし方を知らないまま、時間を溶かして外に出た。
寄せ書きなんか書き合わなくても、それ以上ない記憶を最後に手に入れた。
別に特別なことをしたわけでもない、掴みどころのない幸せな時間。
それまでに放送室で過ごした全ての時間と思い出が連れてきた不思議な感覚。
そう思うのは、過去が美化されているからなのだろうか。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
