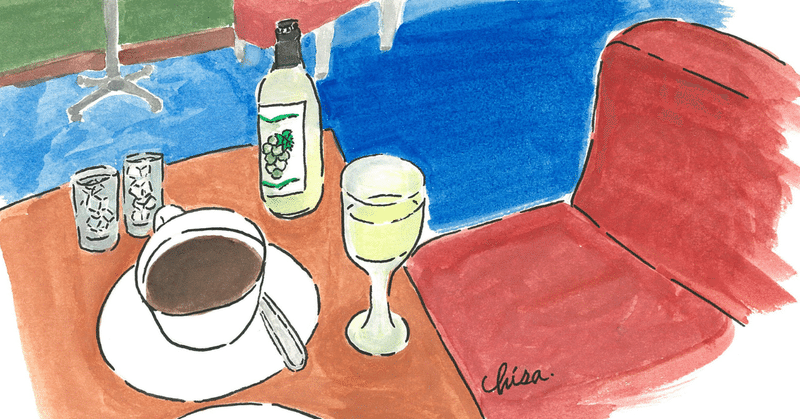
短篇小説【閑話休題 新宿駅23時30分】
1
宇都宮線の終電が視界から消えた後、
4番線ホームに残っていたのはその赤いコートの女だけだった。
チカチカと明滅する蛍光灯の灯りに身体の半分を浮かび上がらせ、
クリーム色のタイル地の壁を背に立っていたその女は、消え入りそうな白い肌から白い息を吐き、
向かいの5番線ホームの地面の辺りをじっと見詰めたまま動かなかった。
終電と業務終了のアナウンスが駅構内に響き渡る中、
その赤いコートの女に近付いていったのがこの話の主人公である剣崎薫だ。
この名前は1年前からバイトをしているホストクラブのオーナーである大野駿が適当に付けた源氏名だった。
薫にとっては自分の呼び名などどうでもいい事だったが、
この日新宿駅の4番線ホームで赤いコートを着た女を探して連れてこいと言ったのも、人使いの荒い大野駿であった。
薫がその日着ていた丈の少し長いカシミヤのダークグリーンのコートは、
大野駿の20年物のお下がりを譲り受けたものだった。
赤いコートの女は薫がすぐ隣に立っても何も気に掛ける事無く、
向かいのホームをただじっと見ていた。
胸元まで真っ直ぐ伸びた黒髪に、真っ赤な傘以外は何も持たずにその場に佇んでいる女の姿は少し異様で、薫は何と声を掛けたら良いか分からずに躊躇していた。
その日明け方から降り始めた雨は昼過ぎに雪に変わり、
音も無く降り続く雪はホームの端を白い絨毯の様に覆っていた。
女の視線の先にある5番線ホームには酒に酔った若者達の騒がしい姿が見える。
薫は意を決して口を開いた。
「あの・・・大野さんに頼まれて迎えに来ました」
赤いコートの女は肩をビクっと震わせ、ゆっくりと薫の方に顔を向けた。
その表情はかくれんぼで思い掛けない程容易く見つかってしまった人の様だと薫は思った。
驚きと恥ずかしさが混ざった様な。
張り詰めていた緊張の糸が唐突に切れてしまった様な。
女は暗い夜空を仰ぎ見て小さく息をひとつ吐いた。
「あなたには見えるのね」
女のその消え入りそうな微かな声は、その時薫の耳には届いていなかった。
「もうすぐ駅が閉まるので行きましょう。タクシーで15分位なので」
薫はそう言うと、コートの襟を立てて先に歩き出した。
寒さで指がかじかんでしまいそうだった。
振り向くと女はさっきの場所から全く動いていない。
「おい、マジかよ」
薫は小さく独り言ちて女の方へ引き返した。
女は相変わらず向かいの5番線ホームの方を見詰めたまま動かなかった。
「あの・・・ここ寒いんでもう行きましょう。俺、大野さんの店で働いている薫って言います。あの、怪しい者じゃないんで」
薫が両手に息を吹き掛けながら言った。
その時女の長い睫毛の先に雪の粒がひとつ乗ったのが見えた。
すると女はまるで雷に打たれたかの様に、
体を大きく仰け反らせて後ろに下がった。
手に持っていた赤い傘が音を立てて地面に落ちた。
その顔は蒼白で何かに追い詰められた様な表情をしていた。
薫は驚いて思わず女の手を掴んだ。
そのまま倒れてしまうのじゃないかと思ったのだ。
「大丈夫ですか?」
薫の問い掛けには応じず、女は大きく目を見開いて掴まれている自分の手を見た。
「あ、すいません」
薫は慌てて女の手を離した。
その時ホームの反対側から駅員が近付いて来るのが目に入った。
「とにかく、ここを出ましょう」
薫は女の赤い傘を拾い上げて言った。
女はまだ自分の手を見ていた。
冷たい風がホームを吹き抜けていく。
耳が千切れる様な寒さだと薫は思った。
「コーヒーが飲みたい」
女が小さく呟いた。壁一枚隔てたかの様な頼りない響きの声だった。
「あ、はい。コーヒーですね。分かりました。行きましょう」
薫は少し安心して階段の方へ歩き出そうとしたが、女の手が自分の方に差し出されているのに気が付いた。
「悪いけど、手を引いてくれる?」
女は本当に申し訳なさそうな顔で白い手を伸ばしていた。
薫は一瞬どうしたら良いか迷ったが、冷たくなった自分の手を擦り合わせて少しでも温めてから、女の手をゆっくりと取った。
微かな力で握り返してくる女のその手は、
薫がそれまでに触れてきたどんな人間の手よりも冷たく感じたのだった。
2
改札の時計は23時30分を差していた。
週末の新宿駅はこの時間でも人が絶えなかった。
商業施設の閉じられたシャッターの前で肩を寄せ合い、
電子タバコの水蒸気を巻き上げながら大きな声で騒いでいる若者達が多く見られる。
駅前の道路を走るトラックのチェーンがアスファルトを削る音が、
薫の耳にやけに大きく響いた。
真っ赤な傘を差し、真っ赤なコートに身を包んだ女の手を引いて歩く薫の姿は、昼間の様に明るい新宿の街の中でかなり目立っていた。
女も黙って薫の手を握って付いて来る。
歩道の水たまりに映る街の灯りに視線を落とし、
時折大きく白い息を吐きながら。
「ここにしましょう」
薫が雑居ビルの地下にある深夜営業の小さな喫茶店の看板の前で女に言った。
女は軽く頷いて静かに赤い傘を閉じた。
階段を降りた半地下にある店の入口には大きな姿見があった。
「ちょっと先に行ってて」
女が薫に言った。
「分かりました」
薫が先に入って店内を見廻すと、奥に4人掛けの席が空いているのが目に入った。振り向くとすぐ後ろに女が赤いコートを手に持って立っていた。
淡い黄色ランプの灯りがぼんやりと辺りを照らす店内はやや薄暗く、微かな音量のジャズが流れていた。
席に着くと、すぐに女性店員が水の入ったグラスを1つだけ持ってやってきた。
「ホットコーヒー2つ、あと水もう1つ下さい」
薫が店員に言った。
「はい、かしこまりました。少々お待ち下さい」
女性店員はそう言いながら少し怪訝そうな目を薫に向けた。
「あっ、コーヒーだけでいいですか?」
薫が向かいの席に腰を下ろした女にそう尋ねると、
女は静かに首を縦に振った。
「あ、じゃあ、それでお願いします」
薫がそう言うと、女性店員はあからさまに解せない様な表情をしながら去っていった。
「何だか愛想の無い店員だな」
薫が不服そうにそう独り言ちると、女はその日初めて薫の目を見て少し表情を緩めた。
薫もその時になって、初めて向かいに座る女の顔をまともに見た。
白い肌に長い黒髪。大きな目で真っ直ぐ見詰めてくるその女は、自分と歳もそう変わらない様に見えた。
新宿という街には不釣り合いな程の薄化粧で、薫が普段ホストクラブで相手する女達と比べるとどこか品の良さを感じた。
赤いコートの下は襟の詰まった黒いニットセーターで、胸元にシルバーのネックレスを下げている。
「あの、お名前聞いてもいいですか?」
薫がそう話し掛けると、女は少し困った様な顔をした。
「あ、いえ、別にいいんです。言いたくなかったら。俺も薫って本名じゃないし。あの、俺は1年前から大野さんの店で働いていて、色々と世話になってて」
薫が1人で慌てているのを女は不思議そうに眺めている。
薫はホストとしては純朴過ぎて、客に舐められると何時も大野にからかわれていた。
しかしそんな素直な性格が気に入って、大野は何かと薫の事を目に掛けてもいたのだった。
先程の女性店員がやってきてコーヒーを2つ薫の前に置き、
水の入ったグラスも薫の前に置いた。
伝票をテーブルの端に畳んで置き、薫の顔を一瞥して無言で去っていく。
その様子を女は静かに見守っていた。
「いや、何だろう。愛想が無いっていうか、変わった店員ですね」
薫がコーヒーカップと水の入ったグラスを女の方に寄せながら言った。
「あの人には私が見えないの。あなたが1人でコーヒーを2杯飲むのかと不思議に思ったのよ」
女が薫の目を真っ直ぐ見て言った。
「えっ?いや、どういう事・・ですか?」
薫は女の言っている事の意味が分からなかった。
「あなた出身は?趣味は?彼女はいるの?」
女がコーヒーを1口飲んでから矢継ぎ早に言った。
さっきまで無口だった女が急に捲し立ててきたので薫は少し驚いてしまった。
「えっと、出身は静岡県で、趣味はギターを弾く事で、彼女とは先月・・・・別れました」
薫はそう答えると喉が渇いていたのを思い出し、
グラスの水を半分一気に飲んだ。
「何で別れたの?浮気?」
女は殆ど無表情で薫に話し掛けてくる。
薫には女が本当にそんな事を知りたいのかがよく分からずに、
何と返答して良いのか困ってしまった。
「あなたから別れを切り出したの?それとも相手から?」
女は尚も質問を続けた。
薫には店内に流れるジャズの小刻みなスネアドラムの音が、
女の言葉をリズミカルに伴奏している様に聞こえていた。
変わった女だと薫は思った。
薫が新宿駅の4番線ホームで女を見付けた時、行ってしまったばかりの宇都宮線の終電を女はいつまでも見詰めていた。
真っ赤なコートに大粒の雪が降り掛かっていたが、殆ど身動きせずに女は列車の最後尾のライトが離れていくのを見送っていた。
薫は人影まばらな駅のホームで、それを少し離れた場所からしばらくの間見ていたのだ。
「その彼女は年上?それとも年下だった?もうすぐクリスマスなのに残念ね」
女はそこで大きく息を吐いて目を閉じた。
これは独り言の様なものなのだろうかと薫は思った。
答えを求めているのでは無く、ただ心に浮かんだ事を片っ端から吐き出しているだけの様に薫には見えた。
薫が黙っていても女は特に気にしていない様子だった。
2人の間を見えない壁が遮っていて、互いの言葉はテニスの1人打ち練習の様に跳ね返ってくるばかりだった。
「ねぇ、あなた歳はいくつ?」
女が少し間を置いて言った。
「今年22になります。ちなみに彼女も同い年でした。別れを切り出したのは彼女の方で、他に好きな男が出来たんだそうです」
薫は溜まっていた質問の答えを一気に清算した。
「あなたお酒は飲めるの?」
女は自分の質問の答えにはやっぱり興味が無いようだった。
「ええ、そりゃまあ一応ホストですから。それなりに飲めますよ」
薫は無駄な抵抗は止めて女のペースに合わせる事で、心を疲弊させるのを避ける事にした。
「この店ワインもウィスキーもあるみたい。頼んでも良い?」
女がテーブルのメニューを指差して言った。
「別にいいですけど・・この後大野さんの所に送って行くんで、余り飲み過ぎないで下さいね」
薫がメニューを女に手渡しながら言った。
本当にマイペースな女だと薫は思った。
そういえば別れた彼女も自分の事ばかり話し続けて、
人の話は全く聞かない人だったなと薫はふと思い出した。
「私は白ワイン。あなたは?」
女が薫にメニューを渡しながら言った。
「いや、俺はこの後仕事なんで。要らないです」
薫が店の入口付近で暇そうに立っていた女性店員に手を上げて合図しながら答えた。
店員が来ても女は黙っているので、薫は白ワインのハーフボトルを変わりに注文した。
女性店員は終始無言でまた怪訝そうな顔を薫に向けて去っていった。
「本当、愛想無い店員だな」
薫が店員の後ろ姿を見送りながら言った。
女は何か思案顔で一点を見詰めている。
こんな時女という生き物は碌な事を考え付かないものだと薫は経験で知っていた。
そしてそういった時の勘は大概当たってしまうものなのだ。
「ねぇ、ちょっと電話貸して。持ってるでしょ?携帯電話」
テーブルに掌を上向きにひらひらさせて女が言った。
「えっ?何でですか?自分の無いんですか?」
「無いの。全部家に置いて来ちゃったの。ちょっと電話したいから貸して」
女はひらひらさせていた手を薫の顔の前に付き出した。
「いや、別にいいですけど・・・まあ・・・どうぞ」
薫は渋々スーツの内ポケットからスマホを取り出して女に手渡した。
「ん?これ何?」
女は手渡されたスマホを見て固まっている。
「これどうやって電話掛けるの?ボタンが無いわよ」
初め薫は女が何を言っているのか分からなかった。
「電源入っているの?これ」
女は薫のスマホをひっくり返したり振ってみたりしている。
薫には詰まらない冗談としか思えなかった。それも余り笑えない類の。
「番号言って下さい。俺が掛けて渡しますよ」
薫がそう言うと、女はどこかの市外局番で始まる番号をスラスラと暗唱した。
薫は慌ててその番号をタップしてスマホをまた女に手渡した。
女はスマホを耳に当ててしばらく電話のコール音に聞き入っていたが、突然目を見開いて驚いた様な顔をした。
「出た!」
女がスマホを取り落としそうになりながら、右手から左手、
そしてまたスマホを右手に持ち替えて耳に強く押し当てた。
「もしもし、健!健なの?私よ!ねぇ!聞こえる!?」
女がそれまでとは全く別人の様に取り乱しているのに薫は驚いてしまった。
一体誰に何の用事があってこんな必死に呼び掛けるのだろうか。
女の尋常で無い様子に、薫は段々不安になっていった。
「ねぇ!聞こえてるの!?答えて!私よ!さゆりよ!」
薫はどうする事も出来ず女を見守るしかなかった。
女は尚も電話の相手に呼び掛けたが、
暫くすると黙ってスマホを薫の顔の前に付き出した。
「ごめんなさい。やっぱり私の声は聞こえないみたい。あなたにしか聞こえないんだね」
女は力なく俯き、目には薄っすらと涙が浮かんでいるのが見えた。
茫然としていた薫の目の前に、女性店員が黙って白ワインのハーフボトルを置いた。
追加の発生した伝票を畳んでテーブルの端に置き、また黙って立ち去っていった。
グラスはキンキンに冷えていて薄っすらと白い霜が覆っていた。
女はまだ黙ったまま何か考え事をしているようだった。
薫はゆっくりとボトルの栓を開け、グラスに白ワインを注いだ。
「あの、どうぞ」
女の前にグラスを置いた。
「ありがとう・・・頂きます」
女はグラスのワインを一気に飲み干した。
そして短く息を吐き、薫に視線を向け少し笑った。
「そういえば、どうしてあなたはここに私を連れて来たの?」
女は真っ直ぐ薫の目を見て言った。
「えっ、いや、だから俺はあなたを迎えにきて。大野さんに頼まれて、それであなたがコーヒーが飲みたいって言うから・・」
薫は少し混乱してしどろもどろになっていた。
今更ながら、話が出発点に戻ってしまった様に感じた。
「さっきからあなたが言っている大野さんって誰なの?私は知らないわ」
女は意に介さず、事も無げにそう言った。
「えっ、知らない?いや、だって俺、駅で大野さんに頼まれたって言いましたよね?それで迎えに来たって言いましたよね?」
薫は混乱しながらも、記憶を手繰りながら女に必死に食らい付いていった。
「言ってた。確かにそんな事言ってたわね。私、あなたに話し掛けられてとにかく驚いてしまって。何を言っているのかよく聞いていなかったのね。ごめんなさい。多分人違いだと思うわ。私に迎えを寄こす人なんて絶対にいないもの」
女は両手で長い黒髪を掻き上げてから、テーブルに肘を付いて両手で顔を覆ってしまった。
薫にはその時、少し思い当たる事があった。
それと同時にある記憶がふと蘇ってもいたのだった。
薫を何かと目に掛けてくれていたホストクラブのオーナーの大野駿は、
よく店の若い従業員に悪戯を仕掛けて楽しむ様な癖があった。
殆どは他愛の無い様なものだったが、
薫もよくからかいついでに騙されて痛い目にあった事があった。
少し前に店が暇な時、ホストクラブで怪談話をして盛り上がった事があった。
店の照明を全部落として、ローソクに火を灯し、スマホで怪談用のBGMを流しながら、明け方まで酒を飲んでいた。
その時、大野が披露したのが新宿駅の地縛霊の話だった。
恋人に捨てられて、借金を背負わされた女が新宿駅のホームから身を投げた。
この世に未練を残し、恨みを持って死んだその霊が、今も駅のホームで度々目撃されるという話だった。
薫は酒も入っていてよく聞いていなかったが、
大野の語り口は堂に入っていて中々迫力があった様に思った。
確かその時の女の地縛霊が赤いコートを着た女だった様な気がした。
「ごめんなさい。あなたの時間を無駄にしてしまって。私もあそこで人を待っていたの。来る事は無いって分かっていたんだけど。ずっと待っていて・・・どれ位の時間が経ってしまったんだろう・・」
薫は新宿駅の4番線ホームで宇都宮線の終電をいつまでも見送っていた女の姿をまた思い出した。
ついでに外の降りしきる雪の事を思い出すと急に寒気がしてきてしまった。
ふと気が付くと店の中は他の客の姿も無くなっていて、掛かっていたジャズの音も聞こえなくなっていた。
薫が妙に静まり返った店内を見廻すと、あの不愛想な女性店員の姿も無かった。
「あれ、誰もいなくなってる。もしかしたら閉店かな?」
薫が立ち上がろうとすると、女が薫の手を握ってそれを止めた。
「もう少し、付き合ってくれない?まだ夜は明けないわ」
女はそう言って自分のグラスにワインを注いだ。
薫は時間を確かめようとスマホの画面を見た。
電源を入れると1時16分というデジタル表記が浮かび上がった。
既に薫の出勤時間は過ぎていた。
「あっ、もうこんな時間。やばい遅刻だ。あの、すいません、俺行かなきゃなんで。えーっと、どうしよう。あなたは大野さんを知らないし、人違いをしたって事ですよね?すいませんでした。俺の方こそお時間を取らせちゃって。ここは俺、奢らせていただくんで。あの、ゆっくりしていって下さい」
薫がテーブルの端に畳んであった伝票を持って立ち上がった。
女は黙って白ワインのグラスを傾けている。
「それじゃあ、失礼します」
薫はその時、妙な胸騒ぎを感じていた。何かがおかしい。
新宿駅の4番線ホームであの女に声を掛けた時からずっと、
心のどっかに引っ掛かっていた違和感。
それが何なのかは自分でも良く分からなかったが、
大事な何かが抜け落ちている様な、妙に落ち着かない気分をずっと引き摺っていたのだった。
薫はテーブルに残した女が少し気掛かりだったが、既に仕事に遅刻していた為に気持ちも焦っていた。
店内を見廻すと他の客どころか、店員も誰一人姿が無かった。
薄暗い黄色ランプに照らし出され、静まり返った店内は妙に寒く感じた。
「すいません!ご馳走様です!」
レジカウンターにも人影が無く、薫は奥のキッチンを覗き込みながら声を張り上げた。
「どうしたんだ?急に。本当に変な店だな」
薫は財布から札を取り出すと、レジカウンターの上に無造作に置いて入口に向かった。
とにかく早く仕事に行かなければと、その時の薫は確かに少し平常心を欠いていたのかも知れない。
しかし店の入口のドアがどうやってもびくともしない事に気が付くと、
薫は一気にパニック状態になってしまった。
「おい!これ何だよ!全然開かねえぞ!」
半地下の店のドアまでは外の繁華街の灯りは届いてこない。
店の外の大きな姿見に僅かなネオン看板の光が反射しているだけだった。
「何なんだよ!」
薫は入口の傍の傘立てに入っていた頑丈そうな傘を見て、
ドアのガラスの部分を割ってしまおうかと考えた。
もしかしたら何かの拍子で外鍵が掛けられて、
そのまま閉じ込められたのかも知れないと思ったのだった。
薫が傘の先の鉄の部分をガラスに押し当てて息を吐き出したその時、
すぐ後ろに人の気配を感じた。
自分の首筋のすぐ後ろの辺りに、確かに誰かの吐く息を感じるのだ。
背筋に寒気が走り、吐く息も白いというのに額には汗を掻いていた。
体が痺れた様で上手く動かせない。
まるで金縛りにあった様だった。
ピンと張り詰めた静けさの中に、すぐ背後の誰かの息遣いが聞こえる。
きっとあの女に違いないと薫は思った。
赤いコートを着て新宿駅の4番線ホームから身を投げた女。
そういえばあの不愛想な女性店員は最初からあの女の存在が見えていなかった様だった。
今時スマホの使い方を知らないというのも妙だと思った。
大野の悪戯であったはずが、現実になってしまった。
あり得ない事に巻き込まれてしまった。
薫は声を出す事も出来ずに、手が震え出すのを何とか耐えていた。
「ねぇ」
突然後ろから声を掛けられて、薫は飛び上がる程に驚いてしまった。
ゆっくりと、傘を強く握り締めたまま薫は恐る恐る振り返った。
女がワイングラスを手に真っ直ぐ薫を見詰めている。
「閑話休題、それはさておき」
薫の耳元に女の声が一音一音こだまする様だった。
女は少し酔っているのか、白い肌の頬辺りに赤味が差している。
「彼女の相手はあなたの知っている人なの?」
「えっ?」
薫には女が何を言っているのかさっぱり理解出来なかった。
「だから、彼女に好きな人が出来たって言ってたでしょ?それはあなたの知り合いなの?」
その時突然、店の中に再びジャズが流れ出した。
薄暗かった黄色ランプに加え、明るい白熱電灯が煌々と辺りを照らし出す。
店の奥の化粧室の扉から先程の不愛想な女性店員が出てきたのが見えた。
薫の顔を見ると、女性店員はスタスタと近寄って来た。
「お客様、大変失礼しました。外の大雪の影響で停電になってしまいました。今復旧した様ですので、暫くしたら暖房も効いてくると思います」
店員はそれだけ言うとまたキッチンの奥に消えていった。
「停電?」
薫は何が何やら分からずに立ち尽くしていた。
女が目の前で薫を不思議そうに見ている。
「停電だって。妙に寒いと思ったのよね」
女はそう言うと、また奥の席に戻って自分のグラスにワインを注いだ。
薫はそれを暫く眺めていたが、ふと思い立って店の入口に近付いた。
自動ドアが音も無く滑らかにスライドし、
外の寒気が一気に室内に流れ込んできた。
薫は大きなくしゃみを一つし、
コートの襟を立てて振り返る事無く階段を駆け上がっていった。
完
illustration by chisa
あとがき
こんにちは。ころっぷです。
この度は【閑話休題 新宿駅23時30分】を読んで頂き、誠にありがとうございます。
この作品もこれまでと雰囲気の異なる作品を書きたいと思い、
試行錯誤の末にホラーコメディ風のショートストーリーになりました。
会話を中心として演劇的な作風を目指したのですが、中々難しかったです。
目標高く、レイモンド・カーヴァーの短編小説を
イメージしていたつもりだったのですが。
皆さんの日常のささやかな彩りになってくれたらと思います。
また次回作でお会い出来るのを楽しみに。
2023・9・30 ころっぷ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
