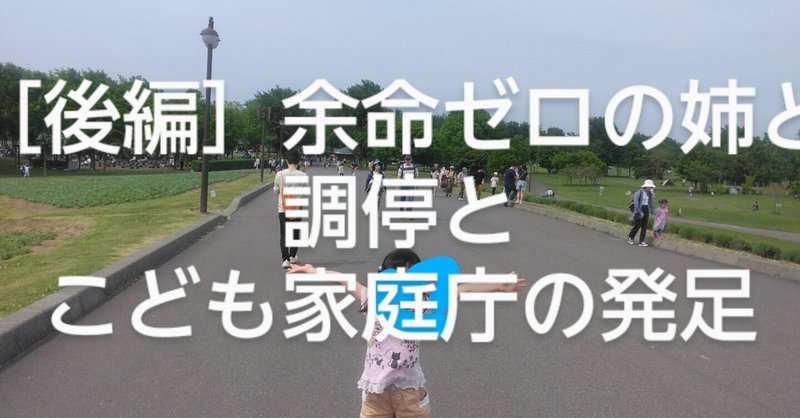
〈手記4〉余命ゼロの姉と調停と、こども家庭庁の発足[後編]
つづきです。前編はこちらからどうぞ。
〈手記3〉余命ゼロの姉と調停と、こども家庭庁の発足[前編]|涼原永美 (note.com)
[6]育て上げるつもりだったから
姉の擁護をするならば、気性の激しい母親と穏やかな娘はうまくいかない・・・ということはまったくないし、似た性格だから親子や家族やうまくいく・・・とも限らない。
すみれが何を感じていたかという私の分析はあくまで、起こった出来事を整理し、考察しているに過ぎない。
ただ、はっきりしていることは、姉はすみれが大人になるまで100%当たり前のこととして、自分の手で大切に育てるつもりでいた。
病気になる前も、なった後も。
生活に対していろいろ悩みはあったと思う。
だからお酒の量は増えていった。
それでも、まったく疑っていなかったのだ。途中で手放すことなんて。
「子どもの頃、こんなことでママ(パパ)によく叱られた」
「うちの母ちゃんこんな人でさ・・・」というのは、育ってしまえば笑い話になったかもしれない。
調停が始まった後、家庭裁判所調査官からの聞き取りで、すみれ本人が
「ママにいつも『早くご飯食べて!』と叱られることが嫌だった」
「パパとのケンカの時の声が大きくて嫌だった」
・・・と語っていたことは確かだが、裏を返せば「それが一番嫌な思い出」だったことになる。
調査官が「一緒に暮らしていた頃のママに関してほかに嫌だったことは?」と尋ねても、
「今は特に浮かばないです。ご飯のこととか、学校のこととかは、ちゃんとやってくれました。とにかく、この裁判を起こしたことが自分勝手」と答えているのだ。
これには姉本人も「こんな・・・こんなことなの? これがすみれに会えない理由なの・・・?」とある意味、拍子抜けしていたほどだ。
本当にこれが、余命ゼロになっても子どもに会えないほどの罪だったのだろうか。
それでも、姉は後悔していた。
〈こんど会ったら、すみれに、大好きとごめんなさいをたくさん伝えたい〉
[7]相談窓口がほしかった
姉の調停が行われている間、私は毎日のように
「この問題をどこに、誰に相談したらいいのだろう」と悩んでいた。
子どもの心のカウンセリング、子どもの相談窓口・・・いろいろ調べても、結局のところ、こういった場所は親が子どもを連れていくか、子ども本人が親に内緒で相談できる機関だった。当事者に問題意識がなければ意味がない。
有名な教育評論家にメールを送ろうかとも考えたが、断念した。奇跡的に返事をもらえたとしても、それを裁判所に提出してどれほどの効果が見込まれるだろうかーー結局、私は部外者なのだ。
そして、姉本人にも言われた。
〈いろいろ調べてくれて本当にありがとう。でも、沙世子が感じている問題意識は、裁判所の関係者たちはみんなわかっていることなんだよ。ただ、すぐにはどうにもならないの。調停を続けるしかない〉
本当にそうだろうか?
――いや、頭ではわかっていたが、リアルに子育てをしている親の一人として、納得いかないものを感じていた。
今まさに一人の子どもが、母親の愛情を信じることができない状況におかれている。
私は、ここまでこじれた問題をほんの少しでも解決に導く方法があるとすればそれは、誰かがすみれに「パパのことも、ママのことも、好きでいていいんだよ」と優しく伝えてあげることではないかと・・・感じていた。
大人双方の主張はともかく、すみれの心にとって何がいちばん良いかを考えたら、それしかないのではないか。
なのにどうして、すみれの心が一番穏やかになる方法を、私たちは選ぶことができないのだろう。
大人の争いは、あくまで大人の問題だ。
それで子どもが「両方の親から愛情を受ける権利」を失うのは、
「子どもの利益」に反していると思う。
だって、書いてあるじゃないか。
ユニセフのホームページにも。
当時はこども家庭庁はなかったが、私にはこれで十分だった。
〈ユニセフ 子どもの権利条約について〉
・第3条/子どもにもっともよいことを・・・子どもに関することが決められ、行われるときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません
・第9条/親と引き離されない権利・・・子どもには、親と引き離されない権利があります。子どもにもっともよいという理由から引き離されることも認められますが、その場合は、親と会ったり相談したりすることができます。
(日本ユニセフ協会ホームページより)
姉のケースの場合、子どもにとってもっともよいことは何だろう?
すみれが「会いたくない」と言うから、会わせない、これがもっともよいことだろうか?
ーー違うと思った。少なくとも、姉とすみれの場合は違う。
大人がすべきことは
「今、あなたがママに会いたくないという気持ちを持っていることはわかる。嫌な思い、辛い思いをたくさんしたよね。
でも、あなたの人生全体に関わることなの。
今ママに会わなければ一生後悔するかもしれない。
会わないことを『自分が選んだ』と考えてしまえば、余計に心が傷ついてしまうかもしれない」
子どもは怖いし、悲しいのだ。両親が争うことが。
見たくないし、本当は聞きたくない、どちらの批判も。
パパもママも好きでいていいんだよ・・・と言ってもらえたら、どれほどラクになることだろう。
子どもが親を思う時、
「あの人は自分が思っているような父親(母親)じゃなかった、欠点の多い人だった・・・」というのは、後から自分自身で気づけばいい。人にはそれぞれのタイミングがある。
子どもが親を思う時、「素晴らしい人間だったかどうか」よりも
「愛されていたか」どうかのほうがずっと大事だと、私は思う。
[8]可視化されづらい子どもの痛み
私はこの先、「こども家庭庁」に少しだけ期待する。
もしもあの時この「庁」があったとしたら、私はここへ繋がる末端の相談窓口を探し、何かを相談しただろうか?
――いや、たぶん無理だっただろう。
仮にどこかに相談したとして・・・いや、姉本人が相談したとしても、数え切れないほどある家庭の問題を個別に解決してもらえるとは、思わない。
そうした解決の場として家庭裁判所があるのだから、と堂々巡りになりそうだし、それに虐待やネグレクト、いじめや貧困、ヤングケアラーの問題などが優先事項になるだろう。
共同親権に関する議論、子の連れ去り、実子誘拐、片親疎外症候群・・・。
これらはもしかしたら、子どもが「今この時、飢えている、暴力を受けている」という緊急性は感じない問題かもしれない。
片方の親にきちんと養育され、清潔な服を着て、栄養のある食事をして、学校へ行き、なんら不自由のない毎日をおくっているのかもしれない。
そもそも問題が可視化しづらいのだ。
それでも、子どもはジワジワと心に傷を負う。
こども家庭庁が発足して、考えた。
どうか世の中が、可視化されづらい子どもの痛みに、もう少しだけ敏感になりますように。
省庁の役割は、大多数の人が不幸にならない枠組みを整え、ルールを決めることだろう。
それならば、片親疎外の問題に関して、こう呼びかけてほしいと私は思う。
「夫は妻の、妻は夫の批判を、子どもに聞かせないでください。
子どもは、父と母の半分半分です。
子どもは自分の半分が、傷つきます。」
ひと昔前、「しつけ」と称して子どもに暴力をふるう親の行為は、大方「家庭の問題」として黙認されてきた。けれど2020(令和2)年からは法律で禁止されるようになり、現在では逮捕される親もいる。
片親疎外の問題は、それと同じようにはいかないだろう。
言ってはいけないことを、ついぽろっと口にしてしまうことは誰にでもある。全部を法律違反だと騒ぐわけにもいかない。
それでも社会の枠組みとして、「子どもが幸せになる社会とは」という共通認識として、呼びかけてほしい。
「片親の批判を、子どもに聞かせないで――」
私が姉の無念死から得た教訓のなかで、とりわけはっきりと認識できるものが、これだ。
夫婦の諍いはなくならないだろう。
子どもを手放したくない思いから、相手の批判を聞かせてしまうことはあるだろう。
ーーそれでも、もうひとつ願わずにいられない。
「確かにここにある愛が、ちゃんと届きますように。
なかったことになりませんように。
ひとりの人間からひとりの人間への想いが、
壊れないまま届きますようにーー」
どうか、お願いします。
[9]憎しみではなく愛を教えて
私個人は義兄が姉 ―夫が妻― にしたことに対して、すべてを批判するつもりはない。
言い分はあるだろうと思う。
――けれど、子どものことは別だ。
調停をやっている間、裁判官や調停員もしきりに言っていた。
――子どものことは、別ですからね。
姉の葬儀の席で、父がたまりかねて吐露した。
――梨花子みたいに気の強い女、一緒にいたら苦労したかもしれないよな。それはわかる。
でも子どものことは別じゃねえか。絶対に会わせるって約束したんだから・・・。
子どもに会えない親の顔を毎日見てみろよ。辛くて、かわいそうで、
見てらんねえぞ・・・」
ーーすみれは、素直で聡明な子どもだった。
夫婦仲は良い時も悪い時もあったかもしれないが、2人とも子どもを深く愛していた。
姉一家と多くの時間を過ごした私は、夫婦が娘を愛でる眼差しをいつも見ていた。
だからこんなことさえなければ、すみれはすくすく育ったはずだ。
幸せになるために生まれてきたような、花のような子どもが夫婦の不和に巻き込まれ、最後には
「ママはパパに呪いをかけている。もうすぐ死んじゃうって聞いても会いたくありません。勝手に病気になって、今は根性だけで生きてるって聞きました」
――と発言した。
子どもが、本来であれば通らなくてもいい道を通った。
その道を歩かせたのは大人だ。
今、高校1年生のすみれは、どんな日々をおくっているだろう。
縁は切れてしまったから、もう会うこともない。
それでも、子どもにはぜひ、自分のことで悩んでほしいと私は思う。
勉強のこと、友人関係のこと、恋愛のこと、進路のこと・・・。
そして家は自分らしく過ごせる場所であってほしい。
それで十分だ。
どうか子どもが、通らなくていい道を通らなくてすみますように。
子どもの心が本当に「まんなか」にくる社会になりますように。
子どもの心のまんなかに愛が溢れますように。
ーーいつもいつも、願っている。
おわり
またいつか、姉のことを書きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
