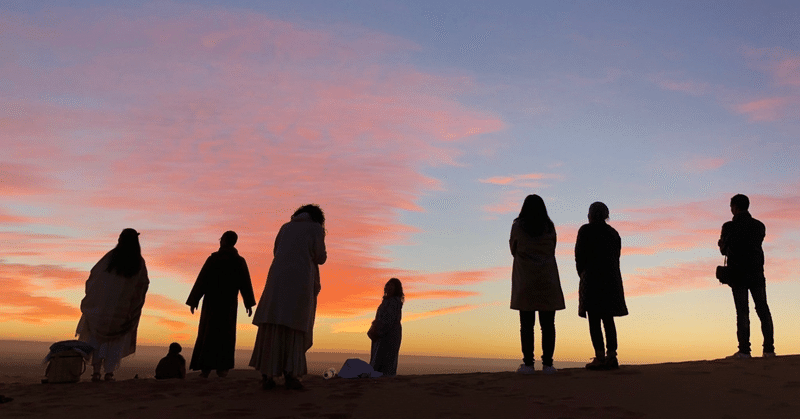
ミッション経営 Mission statement
「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。という格言があります。元プロ野球選手の松井秀喜選手は座右の銘として自身に掲げています。根源はチベットの言い伝えなどという情報もありますが、、、、「ウィリアム・ジェームズ」という心理学者が唱えてたものであり、少しニュアンスは変わりますが、ヒンズー教の教えにもありますし、マザーテレサも同様に似た名言を残しています。
何事も人によっては解釈が異なるものであり、発信者の意図が正確に伝わらない場合が多いものです。家族の中でも行き違いがあるのに、ビジネスではトップと末端スタッフの意思疎通などは、大きな乖離が生じがちです。だからこそ、経営理念や方針など、また顧客に対しダイレクトメッセージとなる声明、ミッションステートメントを掲げるのです。一本の矢よりも三本の矢の方が強いのは誰でも理解できるでしょう。みんなのベクトルを合わせる為には、とても重要な指標であることは言うまでもないでしょう。そして、そこに共感するお客様とも一緒に仕事ができることが望ましい形となるのです。
明確な理念も持たずに商いを行っていたり、不特定多数を扱っている商売ほど疲れる商いはないのです。そこで働く社員も疲弊するだろうし、給与の問題ではない。特に企業雇用の一番の問題点となるのは人間的コミュニケーションである。お金でも地位でも成功論でも無い、むしろ円滑な人間関係ともいうべき、愉しく、気持ちよく働きたいと思うのである。だからこそ、退社の一番の理由は人間関係なのである。また、タチが悪いことにそういう事に気づいていない上司や会社が日本には多くあるのも事実だ。
Mission statementを良く目にすることもあるし、設定している企業も多くある。
ミッション経営という定義はここでは多く語らない(検索で十分理解可能。書籍も沢山あります)が、必ず、戦略、戦術、戦闘と、必ず順番(従うという意味である)に応じたヴィジョンとポリシーを部門ごとに設定しなければならないという事である。また、リーダーだけが納得するものでなく、全て社員総意による理解が必要であり、総意を持って取り組む必要がある。ここまで行って初めて羅針盤がハッキリ見えるミッション経営のスタートである。
筆者は、いつも「考え方」、「捉え方」、「向き合い方」をベースにした教育を行っている。ツール一枚にも意味があるということ、物事は必然的に起こるということなど。
人は仕事を「労働」「キャリア」「天職」という3つの捉え方を大半の人がするらしいが、幸福度が対象になってくると「天職」が一番にくる。天職とは職種に関係無く「使命感」と言われるのですが、使命とはすなわち「命」を「使う」と書きます。つまり、使命感へ生きることでの喜びであり何よりも幸福を感じるのである。
産業が成熟期に入ると競争が最も激しくなり、その中で選ばれなければならない。同じ買い物をするなら、気持ちよく買い物をしたいものだ。値段が同じならサービスが高いほど良い。おいしい料理を作るには、やはりおいしい料理を食べて勉強するべきであろう。良い建築を手掛けるには、良い建築を見るべきであろう。その為には、完全に非効率であっても手間暇を惜しまない、手間をかけるからこそ素晴らしいものができあがる。それを共感する人にこそ、理解してもらえれば良いと思うのである。そして顧客だけでなく取引先や周辺の環境までも変化するのである。これが「価値」というものだ。
雇用もそうであるように、会社の使命感というか、理念というか、存在意義の価値ということに共感することで選択をする場合が大半である。規模に関係無く、必ず「理念」や「ヴィジョン」を掲げてもらいたい。
20210530
