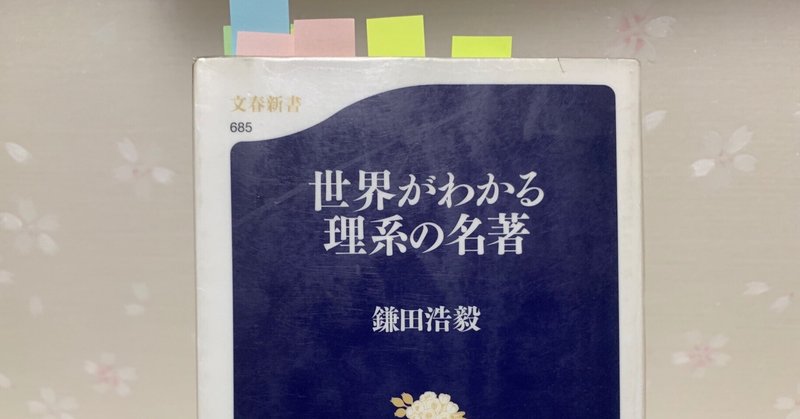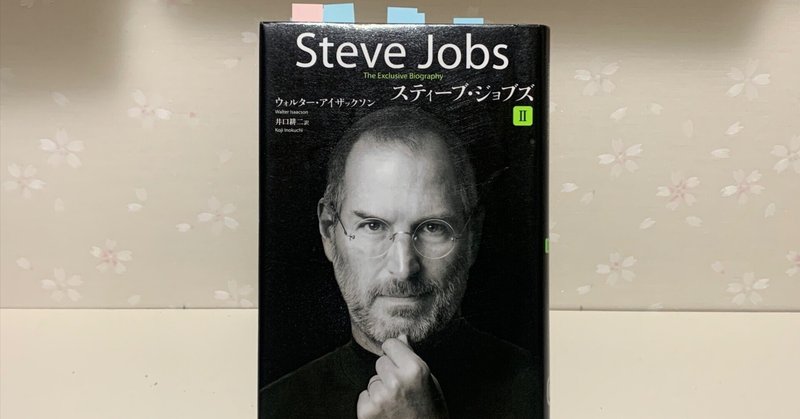- 運営しているクリエイター
記事一覧

自分を疑うことが予測の精度を上げる。完璧主義を抜け出して人生が楽になる新事実〜『超予測力』フィリップ・E・テトロック&ダン・ガードナーの読書記録〜
この本を読む目的は、「投資に活かす」だった。 完全に予測できないことでも、当たる確率さえ上げられれば、続ければ続けるほど利益を出すことができる。そのためのヒントが得られればと思って読み始めた。 読み終えた後の感想は、「予想以上に多くの収穫を得られた」である。 投資に活用するつもりで読み始めたが、あらゆる物事への考え方にも応用できそうで、自分の価値観としている、穏やかに生きることへももちろん応用できそうだ。 なので忘れないうちに要点をまとめておこうと思う。 いわゆる反

間違えること前提なら、穏やかに過ごせるー『Think right 誤った先入観を捨て、よりよい選択をするための思考法』ロルフ・ドベリから学ぶー
52種類もの様々なバイアスについての内容と対策法を、わかりやすく端的に紹介してくれている本です。 「穏やかに生きていく」を自分の価値観としている私にとっては、 参考になる事がたくさんありました。 今回も斎藤先生がお勧めしているOUTPUT方法、「引用ベスト3」というやり方でやろうと思ったのですが、 たくさんある場合、無理に3つに絞る必要もないかなと思いました。 ということで、今回はベスト5でやってみます。 大事だと思ったことなんだから、ちゃんとアウトプットしておいた方
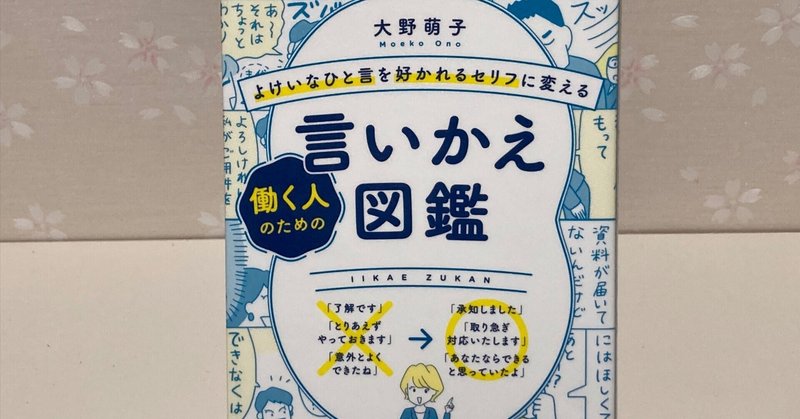
良好な関係作りには、言葉遣いの前にやるべきことがありそう〜『よけいなひと言を好かれるセリフに変える働く人のための言いかえ図鑑』大野萌子から学んだこと〜
最初に断っておきたいのは本の内容を批判しているわけではないことです。 むしろ逆で 本に紹介されている言いかえの言葉をざっとを見渡してみると ある共通点が見えてきました。 言葉遣いの前にやるべきこととは そのある共通点に関係しています。 言葉遣いの前のやるべきこととは この本を読んで自分なりに考えた個人的な考察です。 では言葉遣いの前にやるべきこととは何なのか? それはズバリ 「自分を責めない」 これに尽きると思いました。 やるべきことと言いながらやらないことにな

「毎日コツコツが上達のコツ」の本当の意味 ー 本当に上達する練習法はしんどいつまらないつらいの三拍子だから、凡人にはこれしか方法がないだけだったよ ー
どんなことでも上達するためには 「毎日コツコツ続けることが大切ですよ〜」 とよく言われる 確かにその通り その通りなんだけど 本当に上達する練習方法って ものすごくしんどいしつまらないしつらい そういうものらしい笑 この本から学んだ一流に上達する練習の条件をまとめてみる 本当に上達する練習の条件 ①自分の限界よりちょい上 →練習中はいつも全力全開 →しんどい ②うまくできるイメージが頭の中にはっきりできるまで その箇所を何度も繰り返す →練習中はいつもコケ