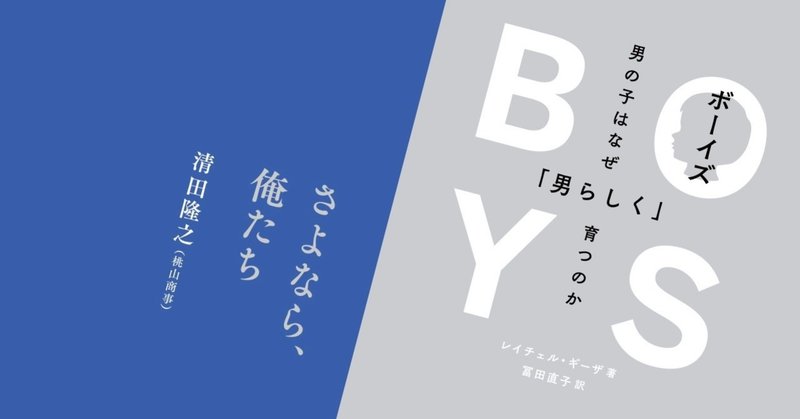
かつて男の子だった私たちに課せられた責任は小さくない~『ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』書評 by 清田隆之さん
『ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』(レイチェル・ギーザ著、冨田直子訳)が、おかげさまで6刷重版出来となりました。お手に取ってくださった読者のみなさまに心より感謝いたします。
このたびは重版を記念し、恋バナ収集ユニット「桃山商事」での活動で知られ、今年7月に刊行された著書『さよなら、俺たち』も話題の清田隆之さんに書評を寄稿いただきました。
子どもから大人まで、誰でも気軽に見ることのできるYouTubeでいま見受けられる「ミソジニー的価値観の拡大再生産」とは? ぜひご一読ください。
* * *
かつて男の子だった私たちに課せられた責任は小さくない
評・清田隆之(桃山商事)
人気YouTuberによって再生産される女性蔑視
ここ数年、「YouTuberとミソジニー(女性蔑視)」の問題が気にかかっている。女性の外見を悪意たっぷりに品評し、ナイトプールに集う女性たちに嫌がらせを仕掛け、道行く女性にいくら払ったら胸を揉ませてくれるかを検証する……といった酷い内容の動画が次々アップされ、昨年は「#MeToo」を茶化すようなドッキリ企画で人気YouTuberが大炎上した。
最近もマッチングアプリで出会った女性と肉体関係を持てるかを男同士で競い合う動画や、1万円で“激安風俗”と言われるお店を何軒もまわり、サービスを担当してくれた女性の年齢や容姿を嘲笑しながらレポートする企画が人気を集めている。
こうして文字にするだけでもおぞましいばかりだが……これは決して一部のマイナーなYouTuberによる悪ふざけではない。どれも数十万から数百万単位、ときには1千万を超える規模で再生されている人気動画であり、作り手たちはこれらによって大きな利益と知名度を獲得している。
もちろん批判されることも少なくないし、実際に「#MeToo」をネタにしたYouTuberは炎上の余波で大規模な主催イベントの中止を余儀なくされた。しかし圧倒的に多いのは肯定的な声で、“神企画”として絶賛されているばかりか、こういったYouTuberに憧れを抱き、彼らのマネをし始める男性たちが無数に存在する。若い世代にとって日常の一部であるYouTubeでミソジニー的価値観が拡大再生産されている現実を思うと、頭がくらくらしてくる。
本書は、社会に流布する「マスキュリニティ(=男らしさ)」のイメージがどのように形成され、(主に幼少期の)男の子たちがそれらをどう内面化していくのかについて考察した一冊だ。「マン・ボックス」という概念で説明されているそのイメージの中には、〈タフ、強い、大黒柱、プレイボーイ、ストイック、支配的、勇敢、感情を出さない、異性愛者〉といった要素が並ぶ。そこには〈性に関して主体的・攻撃的でなくてはならない〉というルールも含まれており、女性を〈妄想と快楽のためのモノに過ぎない〉と捉える傾向の存在も指摘されている。悲しいかな、YouTuberのミソジニー動画も男らしさの産物である可能性が高い。
様々なものの影響を受けながら後天的に形成される“男らしさ”
〈男であることと、ミソジニーや無条件の男性権利意識とを切り離すにはどうすればいいのだろう? マスキュリニティについて社会から受け取るメッセージについて批判的に考え、自分や他人を傷つけるようなジェンダー期待をはねのけるために、どんな手助けができるだろうか? 男の子や男性にとってより自由で広がりのあるマスキュリニティのかたちをつくるうえで、フェミニズムや、女の子と女性の平等を目指す闘いから学べるものは何だろうか?〉
著者のレイチェル・ギーザは「はじめに」でこのような問いを立てている。彼女はカナダ在住の作家で、女性パートナーとともに養子縁組で迎えた息子を育てており、「男性として良い人間に育てたい」「ありのままの自分を表現してよいのだと息子に感じてほしい」と切に願っている。
ジェンダーとは「社会的・文化的に形成された性差」と訳される言葉だ。持って生まれた「生物学的な性差(=セックス)」に対し、常識や教育、周囲からの扱われ方やメディアが発するメッセージなど、様々なものの影響を受けながら後天的に形成されていく“男らしさ”や“女らしさ”を指す。
私は恋バナ収集ユニット「桃山商事」の活動を通じ、これまで1200人以上の女性たちから恋愛にまつわるお悩みを聞いてきた。浮気や不倫、モラハラやセカンドレイプ、話を聞かない、家事をしない、謝らない、責任を取らない、何かと不機嫌になる──など、そこで語られるのはすべて異なる男性の話であるはずなのに、同一人物かと疑いたくなるくらい似通ったエピソードが頻出する。判で押したような言動が量産されている背景には、間違いなくジェンダーの影響がある。
恐ろしいことにそこには私自身も含まれており、「自分も同じようなことをしてしまったことがあるぞ……」と毎回ゾッとした気分になる。個々人がしでかしてしまった迷惑行為や加害的な振る舞いについては、真摯な謝罪や反省がなされるべきだ。その一方で、なぜそういった言動や価値観が生まれてしまったのかに関しては、ジェンダーの視点──つまり社会的・文化的な影響という観点から見つめ直してみる必要があるように思う。
新しい男性性のあり方を個々人が模索していく
著者は膨大な文献や取材結果に基づき、複雑に絡み合い、また強固に塗り固められたジェンダーの糸をひとつひとつ丹念に解きほぐしていく。流布する風説をエビデンスに当たりながら反証し、旧来的な固定概念に対しては「男の子たちの実態とは異なっている」「そう思い込みたい大人の側に問題があるかもしれない」と解体を迫る。また、ステレオタイプを強化することで利益を上げようとするメディアやマーケットの思惑を暴き、鋭い批判を投げかける。
それは男の子を育てている親たちの参考書となるばかりでなく、かつて男の子だった大人の男性たちや、今まさにジェンダーの影響を空気のように吸い込みながら育っているであろう若い男性たちが自らを省みるための鏡としても役立ってくれるように思う。
私も本書を読みながら、10代のときに抱いていた気持ちをいろいろ思い出した。本当は『ちびまる子ちゃん』や『ママレード・ボーイ』が好きだったのに、友達と話を合わせるために無理して『ドラゴンボール』や『スラムダンク』を読んでいたこと。“女々しい”自分を変えようとクラスメイトの前で積極的に下ネタを話していたこと。初めて失恋したときに男友達の前で泣いてしまい、笑われてさらに傷ついたこと……。
中学高校と男子校に通っていたこともあり、思春期のほとんどを女子と交流のないまま過ごした。女子は外見にしか興味が持てず、ひたすら恋愛や性の対象でしかなかった。一方、何度合コンに行っても彼女ができず、「どうせ女子はイケメンが好きなんだろ!」と非モテ意識をこじらせていた。もしもあの頃YouTubeがあったら、自分もミソジニーYouTuberに憧れる一人になっていたかもしれない。女性を馬鹿にし、モノのように扱う動画を見ながら、「いい気味だ!」とカタルシスを覚えていた可能性だって正直否定できない。
〈承認、仲間意識、ステータス、権力といったかたちでマン・ボックスが特権や利益を与えてくれているうちは、マン・ボックスを捨てることは難しいだろう。(中略)女性の場合、ジェンダーステレオタイプのもたらす不利益は、男性よりも明白に感じられる。(中略)低い給与から、生殖の選択肢の制限から、暴力に甘んじることまで、女性たちを従属させたままにしておくことを正当化するために用いられているのが、女というものは弱くて、ヒステリックで、表面的で、計算高く、ふしだらで、などなどというステレオタイプなのである〉
女性を貶めることで連帯意識を高めるというのは「ホモソーシャル」の典型的な風景だ。かつて自分もそういう空気の中にどっぷり浸かっていたように思うが、今振り返ると決して居心地のいい場所ではなかった。いつもうっすら競争意識が働いていて、なんでも人と比べてしまい、「寒いやつ」と思われるのが怖くてノリやイジリを拒否できず、女性とのコミュニケーションもうまくいかないことが多かった。
そんな当時の自分に対し、「苦しかったでしょう」「あれはジェンダーの呪縛だったかもね」と声をかけてもらえたような気がして、読みながら感極まる瞬間もあった。では、これからの自分はどうするか──。
メディアやSNSで頻繁にジェンダーイシューがクローズアップされ、男性性の問い直しが盛んに論じられている今、かつて男の子だった私たちに課せられた責任は小さくない。自分自身と向き合って内面の言語化を進めるとともに、男らしさを全否定することなく、よい部分を活かしながら新しい男性性のあり方を個々人が模索していくことが大事ではないかと私は考えている(例えばBTSが体現する「ハイブリッド・マスキュリニティ」など、本書には具体的な事例も紹介されている)。レイチェル・ギーザによる壮大な思索の旅の痕跡は、そのための大きなヒントとなってくれるはずだ。
* * *
〈評者略歴〉
清田隆之(Takayuki Kiyota)
1980年東京都生まれ。文筆業、恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表。早稲田大学第一文学部卒業。これまで1200人以上の恋バナを聞き集め、「恋愛とジェンダー」をテーマにコラムやラジオなどで発信している。『cakes』『WEZZY』『QJWeb』『an・an』『精神看護』『すばる』『現代思想』『yom yom』など幅広いメディアに寄稿。朝日新聞be「悩みのるつぼ」では回答者を務める。桃山商事としての著書に『二軍男子が恋バナはじめました。』(原書房)『生き抜くための恋愛相談』『モテとか愛され以外の恋愛のすべて』(共にイースト・プレス)、トミヤマユキコ氏との共著に『大学1年生の歩き方』(左右社)、単著に『よかれと思ってやったのに──男たちの「失敗学」入門』(晶文社)がある。
★最新著書『さよなら、俺たち』(スタンド・ブックス)
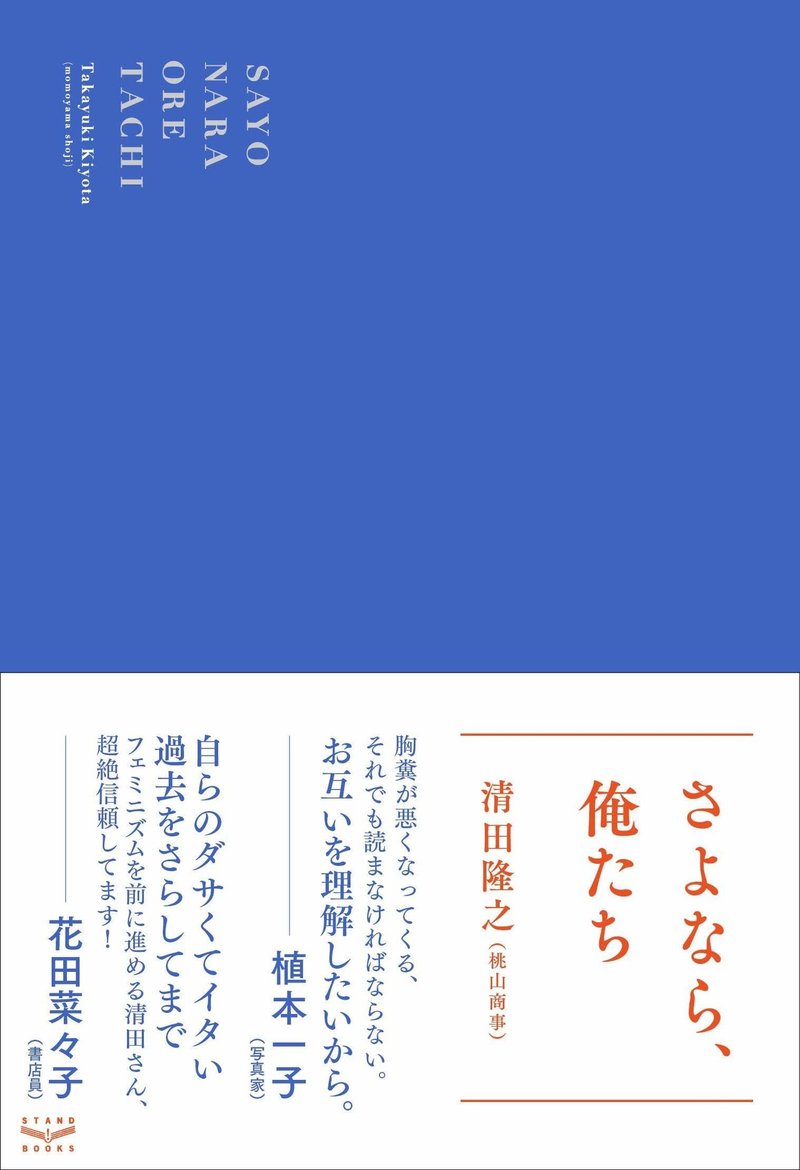
* * *
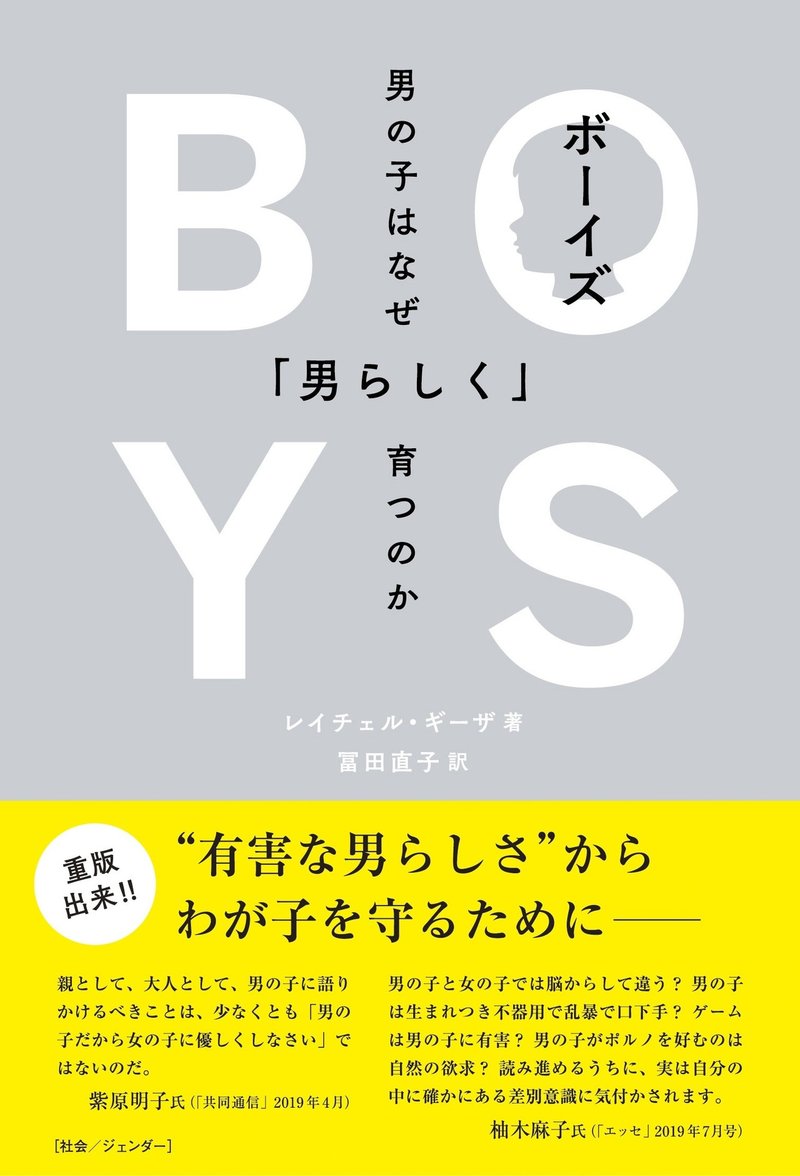
《書誌情報》
『ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか』
レイチェル・ギーザ=著 冨田直子=訳
四六・並製・376頁
ISBN: 9784866470887
本体2,800円+税
https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK228
好評7刷
〈内容紹介〉
自身も男の子の親である著者のギーザは、教育者や心理学者などの専門家、子どもを持つ親、そして男の子たち自身へのインタビューを含む広範なリサーチをもとに、マスキュリニティと男の子たちをとりまく問題を詳細に検討。
ジャーナリスト且つ等身大の母親が、現代のリアルな「男の子」に切り込む、明晰で爽快なノンフィクション。
〈目次〉
はじめに──今、男の子の育て方に何が起こっているのか?
1章 男の子らしさという名の牢獄──つくられるマスキュリニティ
2章 本当に「生まれつき」?──ジェンダーと性別の科学を考える
3章 男の子と友情──親密性の希求とホモフォビアの壁
4章 ボーイ・クライシス──学校教育から本当に取り残されているのは誰?
5章 「男」になれ──スポーツはいかにして男の子をつくりあげるのか
6章 ゲームボーイズ──男の子とポピュラーカルチャー
7章 男らしさの仮面を脱いで──男の子とセックスについて話すには
8章 終わりに──ボーイ・ボックスの外へ
■書評掲載■
・共同通信(2019.4.7)|親として、大人として、男の子に語りかけるべきことは、少なくとも「男の子だから女の子に優しくしなさい」ではないのだ|紫原明子氏
・日本経済新聞(2019.4.27)|フェミニズムはこうした「男性性」のもたらす負の側面を明らかにしてきたものの、その裏で見過ごされがちだったのが、男の子がもっか陥っている苦境への対応策だと著者は指摘する
・エッセ(2019年7月号)|男の子と女の子では脳からして違う? 男の子は生まれつき不器用で乱暴で口下手? ゲームは男の子に有害? 男の子がポルノを好むのは自然の欲求? 読み進めるうちに、実は自分の中に確かにある差別意識に気付かされます|柚木麻子氏
♢はじめに~終わりにをお読みいただけます♢
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
