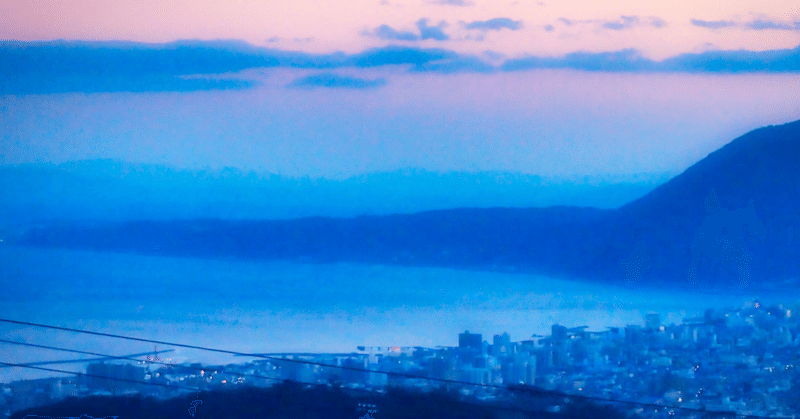
街風 episode.27 〜ネガイ カナエ タマヘ Part.Ⅰ カミノミゾシル〜
「おや、今日は朝帰りなの?」
神様はゆっくりと眠そうな顔をしながらフラフラと歩いてきたタマを見つけると声を掛けた。タマは眠そうな顔のまま神様の足元へ寄ってくると、神様の足に自分の身体をすりすりと擦りつけた。
「なんかお酒臭いよ、どうしたの?まさか…飲んでるの?」
神様は、怪訝そうな顔でタマを覗き込んだ。タマは神様の問いかけに答えようと身体をすりすりと擦り付けながら、神様の顔を見上げるように首をあげた。
「違うよー。昨日の夜に一緒に話した人がすごい酔っ払ってたんだ。ずっと膝の上で撫でてもらってたから、その時に少しだけ匂いが移っちゃったのかも。」
「ちょっと待って。あなた人間と話したの?」
「そうだよー。カナエちゃん以外の人と話せるなんて初めてだったよ。最初は驚いたけど、あっちも驚きつつも色々とお話ししてくれて楽しかったなあ。」
神様は大きくはあーっとため息をつくと、しゃがみ込んでタマを優しく撫でながら子供を諭すような口調でタマに注意した。
「タマ、あなたが人間と喋れるようになったのは、私の能力を少しだけお裾分けしてあげたからでしょう?それに、その能力はカナエちゃんとタマと私たち三人の秘密の作戦のためにって事で、特別に分け与えてあげたんだから。もしも、大神様にバレたら私が怒られちゃうのに。もう少し、きちんとしなさいよ。」
「分かったよー。」
タマは、聞いているのか聞いていないのか曖昧な返事をした。まるで宿題をやるように言われている小学生のようだった。
「まあ、別にいいわ。あなたも今のうちにその力を楽しんでいいわよ。」
神様は呆れたようにそう言い放った。
「あれー?神様は気づいているの?」
「当たり前じゃない。誰だと思ってるのよ。」
「えへへ、神様だもんね。」
タマはゴロゴロと喉を鳴らし始めると、今度は神様の足元に寝転がって撫でてくれとアピールを始めた。神様もやれやれといいながら、タマを優しく撫で続けてあげた。
すると、そこに遅れてカナエがやってきた。こうしていつものメンバーが祠に集まった。カナエはタマが珍しく朝早いこの時間にいることに驚いていたが、少しだけツンと香るお酒の匂いに更に驚いていた。
「朝から二人で飲んでいたんですか。」
カナエは神様とタマを伺うように尋ねてきた。
「違うわよ。タマが昨日の夜に私のお裾分けした力で、酔っ払った人とずっとお喋りしていたらしいのよ。」
「そうなんだ。たしか、リュウジ君って言ったかな。ユリエちゃんって人と別れた帰り道だったらしいよ。なんでも、そのユリエちゃんとノリって人がくっつくお手伝いをしたらしいんだー。」
カナエはタマの言葉を聞いて、また更に驚いて目を丸くした。
「そのリュウジ君って知ってる人かもしれない。」
カナエは驚きつつも、神様に気持ち良さそうに撫でられているタマを撫で始めてあげた。
「さ、タマの“撫で撫でタイム”は終わり!」
パンッと軽く両手を叩くと神様はスッと立ち上がった。タマは、もっと撫でてもらいたそうに撫でられていた部位の毛づくろいを始めたが、撫でてもらうのを諦めたのか毛づくろいが終わるとムクッと起き上がって大きく伸びをした。
「さて、じゃあ秘密の作戦会議をしますか!」
タマとカナエはその言葉を聞くと、祠の隅の定位置に座り始めた。この秘密の作戦会議は、なんだかんだでいつもただの井戸端会議となってしまう。その原因はタマのマイペースぶりによるものが殆どなのだが。
「というかさ、ふと思ったんだけど、カナエちゃんはやっぱりまだ私に敬語だよね。もっとフランクにいこうよ。」
「いやでも神様ですし。神様に対してフランクにいくのも難しいですよ。」
カナエの言い分は正しい。自分が何年も通っていた祠の主が、まさかこうして目の前に現れて、いきなりフランクに話しかけていいよと言われたところで、そんな事ができる人間がいるのだろうか。大好きな有名人に会っただけで気絶する人だっているのに、それが神様相手ならばより一層緊張するのが当たり前だろう。
「うーん、難しいかあ。分かった!じゃあ、私に名前を付けよう!今日の最初の議題はそれからね。」
神様は左手の平の上に右手をグーにしてぽんと叩くフリをしながら、思いついたようにそう言った。
「神様って名前あるんじゃないんですか?」
カナエは不思議そうに神様を見た。タマはうとうとと眠そうな目をしながら欠伸をしていた。
「あるっちゃあるけど、漢字だらけだしめちゃくちゃ長いし、何よりもダサいんだよね。大神様が付けてくれた名前だから文句は言えないんだけど、カナエちゃんみたいに可愛い名前の方がいいもん。」
神様は少し拗ねたように答えた。たしかに、日本の神様は古風で長い名前ばかりで覚えにくい。古事記に出てくるような神様も正式な名称はとても長いものばかりだ。
「どんな名前がいいですか?」
うーん、と神様は悩み始めた。カナエは眠そうに座っているタマの背中を撫でながら、一緒に神様の名前を考え始めた。
「私の外見から何か良いの思い浮かばない?」
「外見ですか。今の格好だと神様以外に思いつかないです。」
「それもそっか。じゃあ、ちょっと待ってて。」
神様は、静かにぐるりとその場で一回転をした。すると、回転しながら頭の上からつま先までみるみるうちに、現代風の顔と体型と服装に変身していった。
黒髪ストレートだけど毛先はウェーブが少しかかっているセミロングで光の反射によっては少し亜麻色っぽくも見える髪、大きな目と小さな鼻と口、透き通るように白くてきめ細やかな肌、触れた瞬間に折れてしまうのではないかと見紛うくらい細くて長い指、細い腕と足がくっついたスレンダーな体型、それらを覆う服装は、ダークグリーンのタートルネックのニットに、チェック柄が可愛いカシミヤのスカート、そしてオフホワイトのロングコートが優しく包む、足元も少しヒールのついたブーツを履いている。
「すごい!魔法使いみたいですね!」
「魔法使いじゃなくて神様って言ってほしかったなあ。」
すみませんとカナエが言うと、神様はカナエの申し訳なさそうな様子を見てニコッと笑った。
「さーて、これでどう。良い名前思いついた?」
「やっぱり人間っぽいほうが名前も色々と思い浮かびそうですね。うーん、そうですね。“ミカ”なんてどうですか。」
「“ミカ”、なんだか語呂は良さそうね。どうしてその名前にしたの?」
カナエは少し言い出しづらそうにして、そのままはぐらかそうとした。だが、ミカという名前がまんざらでもなさそうな神様を見て、ミカにした理由を話した。
「そんな素敵な理由なんてないですよ。神様だから、“神”を反対から読めば“みか”、だからミカでいいかなって。それに、なんだか“ミカ”って名前って今の神様の見た目にもぴったりな気がします。“神様”って呼ぶよりも“ミカ”って呼ぶ方が話しやすいですし。」
「神様の“ミカ”。いいわね。この秘密の作戦が終わるまでは、私はミカとして色々と動くことにしたわ。分かったわね、タマ。」
「分かったよ、ミカちゃん。」
タマは早速“ちゃん付け”で呼んだ。この猫には、神様の有り難さというか畏れというものは無いらしい。こうして名前も決まって、引き続き秘密の作戦会議が始まった。でも、いつもこれといった作戦が思い浮かばない。
この秘密の作戦の発起人というかキッカケはタマだった。カナエの生前の恋人であるダイスケが、未だにカナエを失った悲しみから抜け出せずにいるから、どうにかして新たな一歩を踏み出せるようにしようというのが目的だった。それなのに、当人というか当猫はこんな感じでマイペースなので、神様もといミカとカナエの二人で作戦を練っていた。
この作戦はなかなか難しかった。過去を忘れさせるキッカケをダイスケに作らなければならないし、そのキッカケも一筋縄ではいかなさそうであったからだ。ダイスケは、自分が働いている花屋にやってきたマナミと仲良くなってきており、お互いに惹かれつつあるのにも関わらずダイスケはずっとカナエの事を想い続けている。つい先日もほんの少しだけ神様がカナエに力を貸してあげてダイスケに一言伝えたのだったが、それもダイスケには届いていなかったようだ。
そして、この作戦の厄介なところは、いくらミカが神様といえどもミカ本人やカナエを実体化させるわけにはいかないからだ。できるできないでいえば、ミカやカナエがダイスケの目の前に現れることは可能であるが、そんな事をすればミカが大神様にどれだけ怒られるか想像もつかない。それに、ダイスケの目の前に現れるのは簡単だが、それで果たして本当にダイスケが心変わりするのかもあやしい。かといって、ミカは回りくどいことを考えるのが嫌いで、どんな作戦を練ろうとしても埒があかなくなると強硬手段に出ようとする。それを止めるのがカナエの役割でもあった。しかし、カナエもミカも他に良い案が思い浮かばない。
そうして今日も良い案が思い浮かばないままお開きになった。
ミカは一人と一匹と別れを告げて、祠で一人でボーッと過ごしていると大神様がいきなり目の前に現れた。
「こら、気が抜けすぎておるぞ。」
大神様はボーッとしているミカを見るなり喝を入れた。
「うわっ、びっくりしました。こちらへいらっしゃるなんて如何したのでしょうか。御用件があるならば、私からそちらへ伺いましたのに。」
ミカはボーッと腰掛けていたところに、大神様からの喝を入れられたので、驚いた拍子にシャキッと立って背筋をピンと伸ばした。
「全く。以前に送った手紙にも此方が落ち着いたら、お主のところに行って今後の話をすると伝えておったじゃろう。」
大神様はため息をつきながら蓄えた白ひげを撫でた。
「そういえば、そんな事を書いてあったかも。」
「お主は本当に昔から変わらんな。忘れっぽい上に色々と悪戯も企てる。この街では、変な気を起こしていないじゃろうな。」
ミカはカナエとタマの秘密の作戦を見透かされた気がしてドキリとした。しかし、平静を装おうとしてわざとおどけてみせた。
「そんな事しないですよ。いつまでも昔の私のままじゃありません。大神様も相変わらずお元気そうで何よりです。」
「やれやれ、お主と同年代の他の主らはみんな出世しているというのに、お主だけは昔から何も変わっておらぬように見えるぞ。実績だけでいえば、もう私と同格にいてもおかしくない事は周知の事実だ。」
「またその話ですか。何回も言うように、私は今の仕事が一番楽しいから別にいいのです。こうやって行く先々の街の人たちの幸せの一助になれるだけで十分私も幸せなのですから。」
「わかったわかった。もうこの話は終わりだ。さて、本題じゃが…お主の次の街が決まったので、そろそろ異動する日を決めようと思ってじゃな。」
「お待ちください。そんなに急に異動せねばならないのですか。」
「今回は、異動先の現在の主が急に異動することになってしまってな。本来であれば、もっと猶予があるものだが今回は特例でな。」
大神様はミカに分かってくれと静かな圧をかけながら伝えた。
「ここの後任はどなたになるのでしょうか。恥ずかしい話、このような寂れた状態で引き継ぐのは申し訳ないので、きちんと綺麗にしてから明け渡したいのです。」
ミカは大神様に詰め寄るように問いかけた。ミカとしては、秘密の作戦を終えるまでは次の街へ行きたくないのが本音だった。大神様は、詰め寄ってくるように尋ねてくるミカの真っ直ぐな目を直視できず、やや目を逸らしながら困ったような顔をして呟いた。
「それがな。困った事にここの後任が決まっておらんのじゃよ。お主が次に行く街は、今までどうも恋愛の分野に疎いものばかりが代わる代わる務めておったから、先方も恋愛に強いお主に早く来てほしいと切に願っているのじゃ。でも、私の担当する主達は既に他のところで手一杯だし、他の大神たちにも掛け合っておるのだが、どうにも適任がおらんのだ。それに、お主の行く先々での評判は広く伝わっておるし、この街も恋愛以外でも十分お主は務めあげてきたのも知っておるから、みんな暫くはお主に兼任してもらってもいいのじゃないかとも申しておる。」
それを聞いたミカは、呆れたと言わんばかりの顔をしてため息をついた。大神様も次にミカから何を言われるか感づいていた。
「大神様、あなたがいつも私に口うるさく色々と仰るから、私は仕方なく恋愛以外の分野も手を出しているのですよ。いつも、何かにつけて私をお叱りになるけれど、それに付け込んで他の主には頼まないような面倒ごともいつも私に押し付けるんだもの。」
不満そうに言うミカの言葉に、今度は大神様が反論した。
「付け込むとは人聞きの悪い。お主が、日頃から私に叱られるような悪さをしなければ、私だって何もお主に言う事は無いはずであろう。繰り返し聞くが、今は何も企んでおらぬよな。」
ミカの心に深く釘を刺すように大神様は鋭い眼光でミカの目をじっと見つめた。ミカは負けじと目を逸らさないようにしつつ、大神様に一つ提案をした。
「大神様。私はこの街でも頑張っていましたよね。」
「まあ、そうじゃな。立派に務めておる。」
「でしたら、ここの後任は私に決めさせてください。この街にはまだまだやり残した事がたくさんございます。だからこそ、そのやり残した事をきちんと遂げることのできるような後任を私が選ぶのが適任だと考えます。」
「お主の見る目は間違ってないと私も分かっておる。ただ、先程も言ったように今はどこも主達が手一杯で、そもそも主達の数が足りておらんのじゃよ。それなのに、お主は探し出せると言うのか。」
「私を誰だと思っていらっしゃるのですか。お任せください。きっと、大神様もあっと驚くけど必ず納得してくださると思います。」
大神様は、ミカの力強い言葉に気圧されるように了承した。そして、更にミカはもう一つだけ大神様にお願いをした。
「あと、最近になって年のせいか少しずつ神の力が減りつつあるので、次の街に行く前にもう一度大神様の力を分け与えていただいてもよろしいでしょうか。次の街は、今まで恋愛にあかるい主様ではなかったのでしょう。いくら私といえども、さすがに次の街に行くには今の力では足りない懸念が御座います。」
「ふむ、一理ある。ただ、私の見る限りだとお主の力はまだまだ全く衰えておらぬし、私のような大神と呼ばれる主達と同程度の力はあると感じるぞ。」
「何を仰いますか。私は上へと目指す事なく持てる限りの力を、行く先々の街の人々に使っているのです。さすがに少しずつ自分の衰えを感じておりますわ。」
「そうか。そう言われてしまうと私もその条件を飲むしかなかろう。よろしい、承知した。ただ、残り時間は僅かしかないので、早く次の後任を見つけるように。そして、見つけ次第まずは私に報告をするのじゃぞ。お主も引き継ぎ等で忙しくなるだろうから、また今日みたいに私がここへ来よう。」
こうして大神様とミカは、一つの提案と一つのお願いを約束した。大神様は帰り際もミカにくれぐれも悪戯をしないようにしつこく注意をしながら帰っていった。
ミカは、大神様の姿が見えなくなったのを確認してから、大きく息を吐いた。
「あー、疲れた。それにしてもすっかり忘れてたな。意外と私の残りの時間も少ないのか。ちょっとペースを上げていかないとダメだろうな。」
その数日後。またいつものメンバーで集まった。そして、いつものようにマイペースなタマはのんびりととぐろを巻いてスヤスヤと眠っている。ミカとカナエは相変わらずたった一つの案すらも出せずに悩んでいる。
「あー、もう悩むの飽きたわ。」
ミカは、髪をボサボサと搔きむしりながら声を出した。スヤスヤと眠っていたタマは驚いてビクッとして起き上がった。
「もー、せっかく寝ていたのに。」
「こら!誰のせいで私とカナエちゃんがこんなに悩んでいると思っているの。全く呑気なんだから。リミットは近いのよ。」
タマはミカの言葉を聞いてものんびりと毛づくろいを始めた。究極のマイペースぶりに、ミカも呆れを通り越して感心すらしていた。
「リミットってなんですか?」
カナエはミカに尋ねた。
「あー、あれよ。こんなにダラダラとやっても時間の無駄でしょう。だから、私の中で勝手に期限を決めておこうと思ってね。遅くても今年中には決着をつけたいと思っているのよ。」
「それってあと残り一ヶ月もないですよ。今のペースで大丈夫でしょうか。」
カナエは不安そうな表情をした。
「今のペースだとね。だから、もう私の強行突破作戦でいくわよ。本当は大神様に怒られるのは嫌だけど、このままグダグダと考え込む方がもっと嫌だわ。という事で、早速明日にでも作戦を決行するわよ。」
強引なミカに対して、タマもカナエも口を開けてぽかんとしているだけだった。
「タマ、あなたにあげた能力はそのままあなたにプレゼントするわ。それに、今回の作戦は私とカナエちゃんで成し遂げるから、あなたはその能力を思う存分に使いなさい。」
「ミカちゃん、ありがとう。じゃあ、僕は二人が頑張っているのを遠くから応援しているね。また落ち着いたら、ここに戻ってくるから。」
タマはそう言い残して、立ち上がるとスタスタと歩いていってしまった。それから本当に数日の間、ミカとカナエはタマの姿を見ることはなかった。
「さーて、じゃあカナエちゃん。秘密のガールズトークってやつを始めるわよ。」
こうして明日に備えて、ミカとカナエの秘密の作戦の決行会議が始まった。カナエはミカの強引な作戦内容を聞いてとても驚いた。そして、自分の役割分担を聞かされると、とてつもなく自信を無くした。
「そんな大そうな役割を私なんかが出来るでしょうか。それに明日に実行となるとあまりにも時間が無い気がします。」
「明日って決めたから明日やるわよ。カナエちゃんなら大丈夫!何かあっても私もいるから安心しなさい。それに、これはカナエちゃんにしかできないことよ。」
ミカは、カナエの背中をポンと優しく叩くとカナエを勇気付けた。
カナエも、よしっ!と覚悟を決めた。その顔には明日に向けての決意が現れていた。
翌日。いつもと同じ少し寂れつつある祠に二人は待ち合わせをした。いつもよりも少し遅い午後一に時間通りにカナエがやってくると、ミカは先日に変身した姿で祠の陰に静かに佇んでいた。遠目で見ても絶世の美女といわんばかりの姿に、隠しきれていない神々しいオーラを放っていた。
「お待たせしました。」
カナエは、一瞬ミカの姿に見惚れてしまったが、我に返って小走りでミカの元へと寄った。
「大丈夫よ。いつも通りここでぼーっとしていただけだから。」
今日の作戦の決行時間は夕方十五時頃から。ちょうど“逢う魔が時”と呼ばれる時間帯だ。この“逢魔が時”は古くからの言い伝えにあるように、昼と夜の境目、転じて常世と常夜、すべてが混ざり合う時間である。黄昏時とも言う。元々は、“誰彼”といったように相手が誰だか分からないような薄暗い曖昧な暗さの時間帯を示すという説もある。だからこそ、この時間帯はミカにとっても特別な時間だった。ありとあらゆるものが混ざり合う混沌さを含んだその時間は、神様の力もいつも以上に発揮されるらしい。
「じゃあ、そろそろダイスケ君の元に行こうかしら。今日はお店やってるはずよね。」
「そのはずです。私も覚悟を決めました。行きましょう。」
そうして、二人は祠から出発してダイスケのいる花屋へと向かった。カナエの足取りは少し重そうだった。そして、もう動いていないはずの胸の奥の部分から鼓動が大きくなっているのが伝わってきているようだった。それは、隣のミカも感じ取っていた。
「大丈夫だよ、精一杯頑張ろうね。」
背中を押すようにミカは優しく力強くカナエに対して声を掛けた。街は少しずつクリスマスのイルミネーションが増えている。ミカとカナエは誰にも見えていないのをいいことに、二人ではしゃぎながらガールズトークを楽しみつつ目的地へと向かった。花屋のすぐ近くの誰も通らない路地に入り、ミカは何もない路地の一本道に向かって両手を翳した。これでよし、と言って、ミカはくるりと振り返ると再び歩き始めた。カナエはミカが両手を翳した部分をじっくり見たが、先ほどと何も変化は無いように見えた。頭にはてなマークを残しながらも、ミカの言われるがままにその後をついて歩いた。
「じゃあ、作戦開始といきますか。カナエちゃんはここで見守っててね。」
そう言うと、ミカはくるくるとその場で二回転をした。すると、ミカの足元には先程よりもくっきりとした影が伸びている。
「これで人間にも見える姿になった。あ、でもカナエちゃんはまだ見えないから安心してね。」
ミカはニコリと笑うと、花屋へと向かった。その後ろ姿を不安そうに見ていたカナエだったが、いてもたってもいられず自分も花屋の店先までついて行った。
「こんにちはー。」
花屋に入るなり、透き通るような声でミカは店内に挨拶をした。
「いらっしゃいませー。」
相変わらず可愛らしい笑顔で出迎えたのはマナミだった。どうやら店内にはマナミ一人しかいないようだった。
「はじめまして。素敵な花屋さんね。」
マナミに向けてミカが微笑むと、マナミもミカにうっとりと見惚れてしまった。そして、我に返って接客モードにすぐに戻した。
「ありがとうございます。素敵なお客様に負けないくらい素敵なお花が揃っているんですよ。今日はどういったお花をお探しでしょうか。」
こういう表現を嘘偽りなく素直にすっと言えるところがマナミの魅力だろう。人柄の良さが言葉の一つ一つに滲み出ている。
「ごめんなさい。今日は店主に用があってきたの。」
バツが悪そうにミカは言った。マナミは、ミカを少し怪しむような目を一瞬したが、すぐに切り替えて笑顔で対応した。
「ダイスケさんですか。もう少しで配達から帰ってくると思うので、少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか。ちなみに、お二人はどういった後関係ですか。私からもダイスケさんに連絡入れてみます。」
マナミがポケットから携帯を取り出そうとすると、ミカはそれを制するように優しく声を掛けた。
「ううん、大丈夫よ。お気遣いありがとう。ここで待っているわ。」
二人がどういった関係かは答えてくれなかったのが不服だったのか、マナミは少しだけ口をへの字にした後に、分かりました、とだけ返事をした。
ちょうどそこにダイスケが配達から戻ってきた。
「ただいま戻りました。あ、いらっしゃいませ。すみません、配達に行ってたもので。何をお探しでしょうか。」
ダイスケは、エプロンを身につけながらミカに対して尋ねた。
「こちらのお客さんはダイスケさんに用があって来てくださったそうですよ。ダイスケさんのお知り合いですか。」
マナミはミカに自分の顔が見えない角度でダイスケに不満を露わにしながら尋ねた。ダイスケが全く記憶に無いといった表情をしたせいで、マナミは余計に膨れっ面になった。しかし、ダイスケは全くもって悪くない。ミカがダイスケのことを一方的に知っているだけなのだから。
「申し訳ございません。以前にどこかでお会いしたことのある方でしょうか。」
ダイスケは、自分の頭の中の引き出しを必死に引いては戻すを繰り返しながら、どこで出会った人かを思い出そうとした。それでも全く見当がつかないので、不思議そうにカナを見つめた。
「そうね、ここだとあれだから、少しだけ場所を変えてもいいかしら。そうね、三十分くらいダイスケさんをお借りするわ。ごめんなさいね。ダイスケさん、私についてきて。」
この発言には、お店の外でやり取りを見ていたカナエも驚いた。ダイスケとマナミが唖然とその場で立っていると、ほら早く来て、とミカがジェスチャーで促した。ダイスケはハッとして慌ててスタスタと店を後にするミカについて行ってしまった。店内で一人取り残されたマナミは、ミカとダイスケに掛ける言葉も無いまま、誰もいなくなった店内に立ち尽くしていた。
「ちょっと待ってください。正直、あなたのような女性と会った記憶が無くって、失礼ですがお名前を教えていただいてもよろしいでしょうか。」
スタスタと歩くミカの後ろ姿にダイスケは声を掛けた。ミカは、立ち止まってダイスケの方を振り向くと、ニコリと笑ってまたスタスタと歩き始めた。そして、ミカはカナエにもこっちへおいでとジェスチャーをして、ミカ、ダイスケ、カナエの順番で、先程の狭い路地へと入っていった。そして、誰もいない路地に全員が入ったところで、ミカは再びダイスケの方を振り返って話を始めた。
「強引に連れてきて、ごめんなさい。そして、ここから先はもっと信じられないことが起こるけれど、私を信じて後をついてきてね。」
その言葉を聞いたダイスケは不思議そうにミカを見た。そして、ミカが再び歩き始めたと思った次の瞬間、目の前の視界から姿を消した。ダイスケとその後ろにいたカナエは、えっ!?と驚きを隠せなかった。何がどうなっているのか理解が追いつかない。
だが、ダイスケはミカの歩いた道を辿るように歩き始めた。その後ろ姿についていくようにカナエも後をついていった。そして、ダイスケとカナエも路地裏からスッと姿を消した。
ダイスケが路地裏の次に見た景色は、どこか馴染みのある丘の上の公園だった。
「ここは...。」
「もう分かったかな。ここはあなたとカナエちゃんにとっても思い出の場所の一つでしょ。ここは素敵な場所ね。こうやって夕陽が海に沈んでいくのと夕陽に照らされているこの街が一望できるなんて。」
「どうしてカナエを知っているんですか。あなたはカナエの知り合いですか。」
夢か現実かも分からない中で、ミカがカナエを知っている事も相まって、ダイスケは余計に混乱していた。
「まあ、ゆっくり深呼吸してよ。」
ミカの言われるがままに大きく深呼吸をして、ダイスケはゆっくりとミカの隣に立つようにした。
「私は、あなたのことを知っていたわ。カナエちゃんが亡くなった後の事もね。あなたの願いを叶えられなくてごめんなさい。あの時は、私の力でもどうしようもなかったの。」
「ひょっとして、あなたは、あの祠の神様ですか。」
「ふふふ。私のことなんてどうでもいいでしょう。それにしても、本当にここは綺麗な見晴らしね。もっと早く教えてくれていれば、私のお気に入りスポットにして、毎日ここでゆっくりと夕陽を眺めたのに。本当に素敵な場所ね、カナエちゃん。」
ミカは、ダイスケのさらに後ろに声を掛けるように話した。ダイスケは、ミカの視線の先を追うように振り返った。そこには、白いワンピース姿のカナエが照れ臭そうにダイスケを優しく見つめていた。
「えへへ、久しぶりだね。見つかっちゃった。」
カナエは、照れ隠しに少しおどけてみせた。だが、ダイスケはカナエの姿を見るなり、身体ごと向きを変えてカナエとお互い向き合う形になった。
「カナエ...。」
ダイスケは、カナエの頭の先からつま先まで穴が空くのではないかと思わんばかりに見た後に、両目から大粒の涙をボロボロと流し始めた。
「もう、久しぶりの再会なんだから泣かないでよ。」
そう言ったカナエも、両頬にそれぞれ一筋の涙の煌めきが夕陽に照らされて輝いていた。
「今日はね、ダイスケ君に話したいことがあるの。」
夕陽が少しずつ海に沈み始めていく。少し肌寒い風がカナエの髪を揺らした。
宜しければ、サポートお願いいたします。
