
津田真一×ザ・キャビンカンパニー‼ 辰年のはじまりをかざる新作紙芝居『こたろうと りゅう』インタビュー
辰年の2024年は、紙芝居『こたろうと りゅう』ではじまります!
このたび、本作の脚本の津田真一さん、絵のザ・キャビンカンパニーさんにオンラインでお話をうかがいました。ザ・キャビンカンパニーさんにとっては、今回が初めての紙芝居です。

津田 真一(つだ しんいち)
栃木県生まれ。NHK・Eテレ「みいつけた!」「いないいないばあっ!」などのこども番組を中心に映像制作に携わる。アニメーションの脚本に『いすのまちのコッシー』『ぶうちゃんのおさんぽ』、作詞に『レグ・レグ・アイドル』『ばぁ!っておきがえ』など、絵本に『ふゆごもりのネム』(世界文化社)、紙芝居に『ひっぱりぬまの かっぱ』『うしになった おとこのこ』『ウイルスに まけないぞ!』『ねこの でしになった とら』『火をとりにいったウサギ』『アラジンとまほうのランプ』(いずれも童心社)などがある。
https://scrapbox.io/tdsnicportfolio/

ザ・キャビンカンパニー
阿部健太朗と吉岡紗希による二人組の絵本作家。美術家。ともに大分県生まれ。大分県由布市の廃校をアトリエにして、絵本、立体造形、アニメーションなど様々な作品を生み出し国内外で発表している。主な絵本作品に『だいおういかのいかたろう』<第20回日本絵本賞読者賞>(鈴木出版)、『しんごうきピコリ』<第23回日本絵本賞読者賞>『がっこうにまにあわない』<第28回日本絵本賞>(ともにあかね書房)、『きのこのこ』(得田之久・文/福音館書店)『ゆうやけにとけていく』(小学館)などがある。紙芝居は本作が初めて。
https://the-cabincompany.com/
『こたろうと りゅう』

むかし。りゅうが人のすがたをした子どもをうんだ。
名をこたろうという。
こたろうは、人間の村のばあさまにあずけられ、すくすくと大きくなった。こたろうの村はまずしかった。
石ころばかりで、じゅうぶんな食べものをそだてることができない。
こたろうは、村をすくうため、たびにでた。そうして、母りゅうとであったこたろうは……。
子どものころに出会った、それぞれにとっての紙芝居
――津田真一さんはこれまで10年以上、紙芝居の脚本を書いてくださいましたが、津田さんにとって最初の紙芝居の経験は、どんなものでしたか?
津田:おじさんが公園に自転車でやってきて、お菓子を食べながら観る、という街頭紙芝居を何度か体験しています。今思うと「俗っぽい」内容だったのではないでしょうか。紙芝居との再会は、大人になってからでした。テレビ番組の仕事をする中で童心社の編集者の方から声をかけてもらったんですが、初めて童心社の紙芝居を観たときは、「こんな紙芝居の世界もあるんだ」と思いました。街頭紙芝居とは別のものでしたね。
――ザ・キャビンカンパニーのおふたりは、子どものころに紙芝居を観たことは?
吉岡:私も津田さんみたいに街頭紙芝居を観てみたかったんですが、観たことはなくて。でも小学校によみがたりの方が来て、演じてくれたことがあります。そのときに強烈に印象に残っているのは、紙の質感やインクののり方を「美しいなぁ」と思ったことです。光沢があって、背景がベタ(一色)でこってりと塗られている作品も多かったので……なめてみたい、とまで考えていましたね。
阿部:ぼくも学校によみがたりの方が来て演じてくれていました。紙芝居の日はとても特別な体験をしている感じがありました。舞台があって、人形劇や演劇に近い感覚というのでしょうか。
大人になって街頭紙芝居やってみたい! と思って「黄金バット」を演じてみたこともあるんですよ。

おはなしのタネから、紙芝居の脚本に
――みなさんそれぞれに、子どものころ紙芝居との出会いがあったんですね。さて、今回の『こたろうと りゅう』は、「信府統記(しんぷとうき)」に収められたおはなしがもとになっているとうかがいました。どのようにおはなしを決めていくのか、津田さんにうかがいたいのですが。
津田:「定期刊行紙芝居」という月刊の紙芝居企画の中で、十二支の動物にまつわる紙芝居を10年以上つくってきました。1年のはじめに演じられるものでもあるので、十二支の動物が悪者だったり、観ている子どもたちが「きらい!」と思わないようなおはなしにしたいと思っていますが、竜のおはなしは、なかなか見つからなかったんです。その中で、「泉小太郎」というおはなしにたどり着きました。
「信府統記」は信濃国(しなののくに、現在の長野県)の地理や歴史がまとめられた書物です。松本藩主の命により1724年に編纂されました。
「信府統記」(旧俗伝、安曇筑摩(あづみちくま)両郡)によると、はるかむかし、周辺の山々から流れる水をたたえた、巨大な湖がありました。犀龍と白龍王のあいだにうまれた男の子、泉小太郎は、成長すると母・犀龍の背に乗り、岩山を突き崩し湖の水を流したとされています。そうして湖だったところにできた広大な土地が、現在の安曇野市、松本市などにまたがる盆地であると言い伝えられています。
「泉小太郎」のおはなしは、これまで発表されている民話絵本などにも一部取り入れられているようです。そんな「物語の原石」を紙芝居にしてみるのもおもしろいのではないかと思い、脚本をつくってみることにしました。先ほど確認してみたところ、2022年の1月ごろから調べていたようです。
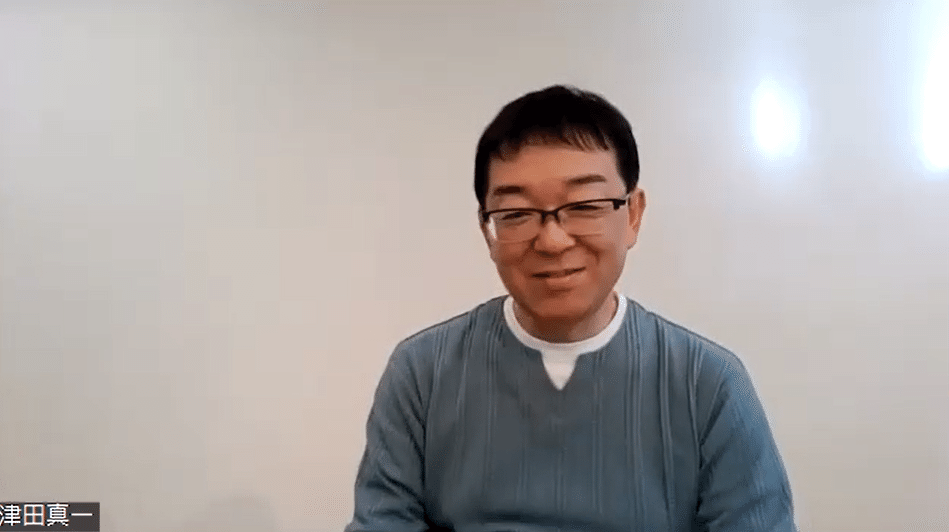
――おはなしのタネを見つけたあと、どのように「脚本」にしていくのでしょうか。
津田:「信府統記」は、わりと客観的で引いた視点で描かれているんです。紙芝居にしていくには、こたろうの気持ちの流れをつくったり、目的をはっきりさせるなどしないと、観客をひきつけることはできないと思いました。
もとのおはなしを肉づけし、見せ場をつくって第1稿を書きました。
そのころ、担当編集のKさんから、「絵はザ・キャビンカンパニーさんでいきます」とお話があって、「おっ!」と思ったんですよ。
編集K:津田さんは、絵がどなたか決まると、これからくる絵を想像しながら脚本に何度か手を入れていくんですよね。今回も、ザ・キャビンカンパニーさんにお渡ししたのは、第4稿になったと思います。ザ・キャビンカンパニーさんに絵を依頼したのは、いわゆる“むかしっぽい雰囲気”にしたくないと思ったからです。みんなが見たこともないような、新しい紙芝居をめざしていました。
はじめての紙芝居!
――ザ・キャビンカンパニーさんは、編集者から「紙芝居の絵を描いてほしい」という依頼が来て、どう思いましたか?
吉岡:絵本とは考え方が違うんだろうなと思いましたが、初めての紙芝居ということで嬉しかったです。ちょうどそのころ昔話の絵は描いていたんですが、線画だったこともあり、絵の具で思いっきり描けることにワクワクしました。
阿部:童心社には好きな絵本がたくさんありますので、依頼してもらえたことも嬉しかったですよ。津田さんの携わる番組は、子どもも大好きなので、いっしょにお仕事できることも楽しみでした。

――最初の脚本を読んだときは、どう感じましたか?
吉岡:今の子どもたちが入りこめるおはなしだと思いました。切れ味がよく、それでいて神話の雰囲気は失っていないんですよね。
阿部:本にある「ノド」がなく、文字もない。真ん中にドーンと絵が描けるというのも魅力的でした。1場面目の絵は、まん中にこたろうがいます。これは絵本の見開きではありえない構図なんです。この絵を吉岡が描いて、「きまった!」と思いました。


津田:ぼくもラフを見て、「これはきたぞ! すごいのきたぞー!」と興奮しました!
吉岡・阿部:よかったー!!
津田:味わったことのない感覚でした。本当にうれしかったです。このラフを見て、絵をいかす方向に直していこうと思いました。Kさんと話して、もっとおはなしの原石、「泉小太郎」に近づけていくことにしました。
絵を見てはっとしたのは、こたろうたちが身につけている衣服や髪型ですね。
阿部:昔話といっても、時代はさまざまですが、「泉小太郎」のおはなしは4世紀くらいではないかとされています。弥生時代~古墳時代のころと考え、入れ墨をいれていたという話もあったので、こたろうの頬に模様を入れました。弥生時代“風”、古墳時代“風”、という感じでしょうか。
津田:「天地創造」ともいえるおはなしだから、神話のイメージがぴったりなんですよね。
――紙芝居を観る子どもたちにとっては、はじめてふれる「神話」の世界かもしれませんね。絵を見てから脚本を変えていく、というのはどういったことなんでしょうか。
津田:こういった昔のおはなしは、俯瞰(ふかん)して、あらすじみたいに書かれたものが多いのですが、それを、登場人物の半径数メートルの距離まで近づいて、「会話」主体の、紙芝居の物語に変換していかなければならないんです。そうするとつじつまが合わないことも出てきてしまって……。書きながらわかってくる、最後まで考えつづける、という感じですね。
――今回は第何稿まで……?
津田:第17稿までいきました! ここまでくると数えるのが好きになってしまって(笑)。Kさんといっしょに脚本を読みあいながら直していくので、これは「立ち稽古」だと思うようになって、最近は「第17稽古」なんて言うようにしています。お芝居の稽古と考えれば、セリフはどんどん変わっていくものでしょ?
吉岡:最初にもらったものとはかなり変わっていきましたよね。どんどん洗練されていくのを感じていました。
絵本の絵、紙芝居の絵、ザ・キャビンカンパニーの絵
――ザ・キャビンカンパニーさんは、紙芝居の絵ということで絵本の制作と異なるところはあったのでしょうか。
阿部:大勢が遠くから観ることを考えて、対象をはっきりと、線を太く描くこと、背景にはあまり描きこまないことなど意識して描きました。
吉岡:ふだんは、曲線的な、いわゆる「命あるもの」を私が描いて、
阿部:ぼくは人工的なもの、建物や時計、車といった「命ないもの」を描いています(笑)。でも今回は自然物だらけだったので、岩や山、波、滝、模様などを描きました。
吉岡:この場面では、枝やひもを描いてくれたよね。最近ではどちらが何が得意なのか、だんだんわかってきました。

――1枚の絵の中で、そのように細かく役割を分けて描いているんですね! おふたりでいっしょに線を描いて、彩色をして……と進めていくのですか?
阿部:ぼくたちは線描きをしてから区切ったところに色を塗る、という方法ではないんですよ。この場面(2場面)でいえば、まずおばあさんの服の色を画面全体にぐちゃぐちゃーっと塗ってしまいます。そこから服の形をかたどって、服以外のところを白く塗っていくんです。偶発性と制御されているところのバランスを大切にしています。
津田:そんなふうに描いているとは驚いた! 絵ってどんなふうに描いてもいいんですね。
――『こたろうと りゅう』の舞台である、長野県の山も実際にご覧になったそうですね。
津田:本当ですか!?
吉岡:そうなんです。たまたま松本市に行くことがあって、せっかくだからと街を歩きまわりました。盆地から見た日本アルプスを描いたんです。
阿部:九州の山とはかなり違うなと思いました。九州の山はなだらかでまあるい形ですが、日本アルプスはとげとげしているというか。夏なのに上の方には雪が見えて、不思議だと思いました。

――山の背景にはあざやかな黄色が敷かれていて、とても印象的です。
吉岡:赤・黄・緑が今回の色と決めて描いていたんです。
――『こたろうと りゅう』の色、ということでしょうか。
吉岡:そうです。よく「カラフルですね~!」と言っていただくことがあるんですが、じつは色数はあまり使っていないんです。どの作品も大体3色程度です。そのくらいの方が、画面が破綻せず、きれいに見えるんです。
津田:こたろうの髪も赤色ですね。はじめて見たとき「竜の子だ!」と思いました。
――竜の表現も、変化していったとうかがいました。
吉岡:カタログ用に描いたカットでは、竜には模様がありました。ただ場面の中で竜が前面に出るようにしたいと思うと、模様がない方がいいと思うようになりました。結果的には白い色になりました。

阿部:竜は、お神楽の竜を参考に描いています。長谷川等伯など、昔の竜の絵は画面におさまっておらず、それが竜の大きさを表しています。今回ぼくたちも竜をとにかく大きく大きく、と思っていました。こたろうと竜が岩山にぶつかっていくクライマックスの10場面は、脚本を読みながら描いていきました。
吉岡:もう立ち上がって描いていたよね。そんなふうに脚本を読みあったり、絵をぬく動作をして確認したり、紙芝居ならではの制作だったと思います。

――津田さんは本番の絵をご覧になったときどのように思いましたか?
津田:絵を見て、また脚本を削っていこうと思いました。言葉で言わなくても大丈夫だ! と思えてうれしかったですね。自信をもって削っていきました。「つくりながらつくっていく」というか、どんどん変化していくのは、紙芝居のおもしろいところですよね。
子どもたちはどう観る? 保育園での試演を経て……完成!
――津田さんは毎回子どもたちに向け試演を行われるそうですね。
津田:編集者に向けて演じるのとはやはり違いますからね。今回も保育園の3、4、5歳児さんそれぞれに演じました。子どもたちはとても集中して見てくれました。最初の場面で「この子はどうなるんだろう?」とひきこまれていくんでしょうね。試演してみて、「うつりすむ」といった難しい表現は変えよう、最後の場面は子どもたちが安心できるような脚本にしよう、など変えていきました。子どもたちに演じてみて、自分自身が感じることもあるんですよね。
――そうしてついに『こたろうと りゅう』が完成! ザ・キャビンカンパニーのおふたりはお手もとに作品が届いてご覧になり、いかがでしたか?
吉岡:うれしかったです! 自分が子どものころさわりたいと思っていた紙芝居ができたんだ、と実感しました。
阿部:インクのにおいがいいですよね。ぼくも紙芝居舞台に入れてみて、「紙芝居ができた!」と思ってうれしかったです。今回はじめて紙芝居の絵を描いてみて、紙芝居ならではの魅力があると感じました。絵本は近くにあって、自分の頭の中にはいっていく感覚がありますが、紙芝居はもっと現実的だと思います。現実の世界の中に、異世界がぽんと現れるというか。紙芝居舞台があればその場ががらっと変わるんです。彫刻やインスタレーションに近いものを感じます。その場であることの意味をもつような紙芝居を今後つくってみたいなと思います。今何か浮かんでいるわけではないのですが(笑)。
吉岡:悩みつつでしたが、紙芝居の絵、楽しかったです!
津田:紙芝居の世界に新しい風がふいてきましたね。おふたりでつくっていくからこそ、他の人にはできない新しい紙芝居がつくれるのではないでしょうか。期待しています。
――津田さんは今後どんな作品を書いていく予定でしょうか。
津田:十二支の紙芝居をずっと書いてきましたが、これから「蛇」を書くことが決まっています。そうするとあと「馬」と「羊」が残るんです。紙芝居って毎回チャレンジだと感じているんですが、今回のように画家の方にも刺激を受けつつ、おもしろい作品をつくっていきたいです。オリジナルのおはなしも書きたいですね。
――早くもみなさんの次の作品も楽しみになってきました! これからもすてきな紙芝居を楽しみにお待ちしています。今日はどうもありがとうございました。
(聞き手:広告宣伝担当H)
#童心社 #紙芝居 #かみしばい #紙しばい #津田真一 #ザキャビンカンパニー #こたろうとりゅう #竜 #辰年 #たつ年 #干支 #十二支 #長野県 #泉小太郎伝説 #伝説 #おはなし会 #1月 #1月のおはなし会 #note書き初め
