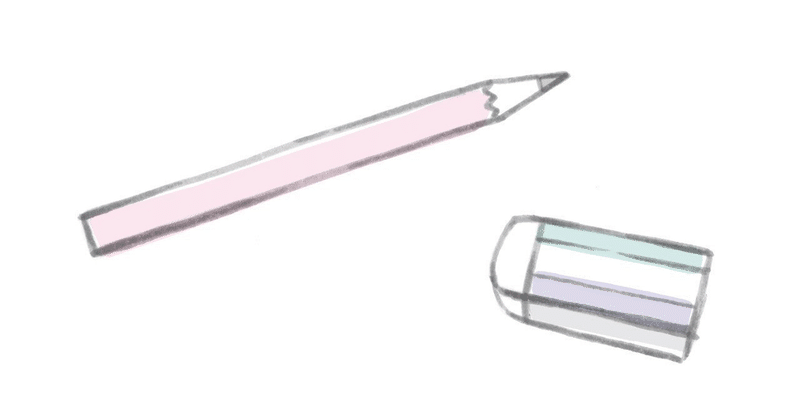
書くということ
①書きたい欲のはじまり
「将来の夢はなんですか?」
数え切れないほど投げかけられたこの問いに対して、一番小さい頃の記憶は動物のお医者さんだったと思う。
保育園で、大きな画用紙にその絵を描いたのも薄らと思い出す事ができる。
しかし、世の中を知るにつれ、こんなに世界は知らないものだらけなんだと、是非やってみたいと思うことも山ほど増えていくのである。
スポーツ選手、歌手、その他色々。
その中のひとつに【何かしらの作家さん】という漠然とした夢があった。
小説家…
詩人…
童話作家…
当時、銀色夏生さんの詩集が流行っていたというのが大きい気がしている。
まだまだ私は幼かったが、姉が何冊か持っていて、新しいものが揃うたびにワクワクしてページをめくった記憶が蘇る。
この淡い表紙を見るだけで、体内の何かが、ぶるぶるっとなっているかのような、懐かしさで身悶える気持ちになる。
そして、いかにもそれっぽい言葉を書きなぐっては、一歩近づいた気持ちになり、また夢が膨らむわけである。
そんな夢というか、書きたい!!と思う欲を満たすために、私はよく原稿用紙に思いのままに書きなぐった。徒然なるままに…である。
そして、もしか、何も思い浮かばなくとも、書けもしない量の原稿用紙を持っているだけで、
”私、文豪のごたる(九州弁で〜のようであるの意)”
と根拠のない自信が湧いてくるのだ。
そして、その勢いで当時の夏休みの作品展には、大学ノート1冊分の創作童話を書いて提出したのだが、何作かのうち、「木の人形のおどり」というものだけがぼんやりと記憶にある。
「あるおじいさんが夜中に木の人形が踊っているのを見つけて…」
といった内容だったと思うが、なんというか、その、タイトルと登場人物からして…、
誰もが知る例の世界的に有名な木の人形が脳裏をよぎる。
私だったら、
「え?これピノ○オと似てね?」
と口走ってしまいそうなところだが、上手上手と褒めてくれた母と先生に、私の自尊心を暖めてくれてありがとうとお伝えしたいところだ。
そして、私も母としてそうあるように努めよう。(決意表明)
②タイプライターからワープロ
なぜそんなものがうちにあったのか、未だにわからないのであるが、物心がつくとタイプライターを使うことが面白いことに気づく。
パチパチと印字して、紙の終わりになったらガーっとはじめに戻していく。しかしながら、もう、それはおおよそ壊れていたのか、どこだかの文字がきちんと戻ってこず、最後の方にはその文字の周辺のキーまで全部引っかかって上がらなくなっていた。
思い出すにあたり、欲しくなって来てしまい、ネットで探してみるものの、今や…Bluetoothでスマホと連動しているものも出ていて愕然とした…。
やはり、紙をガーーッとやりたいもんだ。
探してやっと出てきたガーッとさせてくれそうなタイプライターには、「昔ながらの」と表記されている。
実家にあったものも、相当レトロで可愛らしい見た目だったのだが、もう3つばかりキーが動かなくなってからは、こいつぁ使えねぇ、とすぐに違う機械に乗り移った。
それがワードプロセッサーことワープロである。
もう、これにはかなりお世話になったのではなかろうか。どれぐらいの期間ハマっていたのか、まぁまぁ大きくなってからも学校から帰ってカタカタとやっていた記憶がある。
真っ黒で、触り心地などもなんとなく覚えているのだが、私の中のよく分からない満足感は、溜まった原稿用紙や不完全タイプライターの時のようには生まれなかった。
いや、正確にはある時に一瞬で生まれなかったことにしたくなった。
何故なら、感熱紙なので時間が経つと消えてしまう部分が出てくるのである。
束になった私の作品たちが、ほぼほぼ読める状態でなく、サスペンスドラマの手がかりを思わせるほどの色褪せと文字の消失を見たときに、それまでのワープロへの愛が一気に冷めたのである。
ゆっくり積んできた積み木を、水平チョップで悪びれなく崩壊された気分だ。
もう、ワープロでは書かん。
となってしまうわけである。
③ついにこんな時代
この「書くということ」について、「書きたい欲」が出てきたのには理由がある。それは、ずっと自分の中にあったものが、より身近になったことに加え、恐ろしいほど手軽に触れ合える時代をふと感じたからである。
「何かしらの作家さん」という、小さい頃の夢を、「多くの人に自分の作品を読んでもらうこと」とするならば、このnoteとの出会いはそれを叶えたことになる。
正直、とても楽しい。ほかのクリエイターさんの作品を読んでいても、洗練される前の粗い文が、ビカビカに光ってしょうがない(どの立場で言ってんだ)ものにも出会えて、非常に刺激を受ける。
しかし、その中でハッとした。
原稿用紙を山ほど蓄えていた私が、小さな画面に向かって、両方の親指だけで書きたい欲を満たしている日々だということに。
かく言う今、実はパソコンで書いているのだが。
しかし、これですらもハッとする案件なのだ。
机に向かい、コーヒーを入れて、書斎にいる気分になりながら(あくまで雰囲気)リビングで書くときはパソコンで、そこからちょっと家事をする為に席を離れても、続きを別部屋にてスマホで。なんてことも出来てしまうわけだ。
わーお。めちゃくちゃ便利。
便利過ぎて怖くなる。
そしてきっと、もっと時間が経てば、私たち人間は、
考えるだけで書く。
という、「書く」そのものの概念がおかしくなっているんじゃないかとすら考えた。
【頭で考えただけで、その脳波を察知した装着マシーンがBluetoothを使用して、紙っぺらのような薄いマシーンにデータを送り、刻々と文字が浮かび上がり…。】
なんてオソロシイ。(むしろ、これぐらいならば既にありそう)
そんな怖さを感じながらも、今も書き続けているが、
私は、今でも原稿用紙を山のように持っている。
私がこれを手放した時、人が書くことを辞めた、あるいは書くという概念がひっくり返ったような世の中になっているかもしれない。
なので、もし書くことが
・頭に何か装着する事になったり、
・指先に出入りするレーザーペンを埋め込む
ような世界になったとしても、私はあの時の書きたい欲を忘れないように、この原稿用紙を大切にとっておこうと思っている。
「使わへんやん、要らんやん、捨てや。」
という声が、隣から聞こえてこなくもないが、これは私の小さい頃からの欲が詰まった、いわば書くということの有形物であり、時々は実際に使って、そしてまた蓄えようと思う。
---おわり---
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
