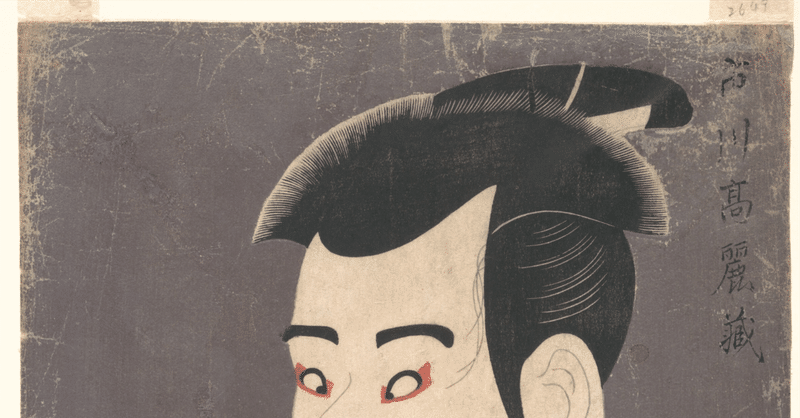
価値観の定食メニュー化を超えてーミニ読書感想『ネット右翼になった父』(鈴木大介さん)
ルポライター鈴木大介さんの『ネット右翼になった父』(講談社現代新書、2023年1月20日初版)が面白かったです。タイトル通り、闘病の末に亡くなった父の言動が「ネット右翼」になったと感じた息子の著者が、その「変節」の理由を探る物語。しかし、検証すればするほど、「本当に父はネット右翼だったのだろうか?」という疑問と向き合うことになる。本書はネット右翼になった父を断罪するのでも擁護するのでもない。むしろ「そんなに簡単に人の思考にレッテルを貼れるのか」という難題に向かい合います。
著者は父の死後すぐに『亡き父は晩年なぜ「ネット右翼」になってしまったのか』というタイトルの寄稿をウェブメディア「デイリー新潮」に発表しました。これはタイトル通り、父をネット右翼と断定し、その原因を探るものでした。本書も当初、同じ問題意識で、家族を分断するネット右翼の思想をターゲットにする予定だったそうです。
しかし、検証を進めると「企画意図はブレた」(p221)。このブレが本書の読みどころだと感じました。
著者は死後すぐの寄稿時、父が亡くなる直前に使ったヘイト性のある言葉や、死後チェックしたパソコンの閲覧歴に差別的な動画が多かったことから、父をネット右翼と断定しました。しかし、母など家族・親族、晩年の父と時間を過ごした友にインタビューしていくと、そうした「言動」が父の「思想」を体現しているわけではなかったと気付きます。
若い世代である著者の姪は「おじいちゃんは知ったばかりのネットスラングを口にしたいだけって感じもした」(p163)と指摘する。著者が「思想」と断定したネット右翼的な言葉は、見方を変えれば思想とは違う「流行への乗っかり」に見えてくる。著者の検証は、父ではなく自らの「偏見」に向かうのでした。
この言葉を使うということは、この思想だ。この意見を支持するということは、この思想だ。こうしたゼロサムの判別方法を、著者は「価値観の定食メニュー化」と指摘します。味噌汁をつけるなら、それは和定食。パスタ定食ではない。
そうした価値観の定食メニュー化を、著者は父に対して行なっていた。後半でこう振り返ります。
(中略)父を失った際に僕が感じたのは「父と僕は醜いイデオロギーによって分断されてしまった」という強い被害感情のようなものだったが、実際長い時間をかけて検証して見えてきたのは、その分断の半分もしくは半分以上が、僕自身の中に抱える「ネット右翼的なもの」や「弱者やジェンダーに対する無配慮で攻撃的な発言」に対する嫌悪感と、激しいアレルギーが原因だったから。つまり、分断を作り出したのは、半ば僕自身だったからだ。
ネット右翼になった父の「原因」は半ば、自分自身にあった。ネット右翼の父は、ネット右翼を嫌悪する著者自身が投影した幻影でもあった。
この発見は重要です。なぜなら、結局「相手」に矢印を向けても「自分」の苦しみは消えないとき、この発見が迂回路になるからです。検証すべきは本当は、自分自身の思考である。
このことは、ベンジャミン・クリッツァーさんの『21世紀の道徳』でも提示されたテーマでした。現代においてさまざまな問題は「社会化」されているけれど、いくら社会化しても個人の中に存在する苦しみは消えるわけではない。だとすれば、本当に向き合うべきは内心なのではないか、という問題提起でした。
著者はまさに、体当たりでこの問題提起を受け止め、その末にようやく父と和解できた。この営みは、同じように私たちが家族の思想的変節に悩む時、光になる。その時はきっと、私たちは私たちの心に眼を向けるべきなのでしょう。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
