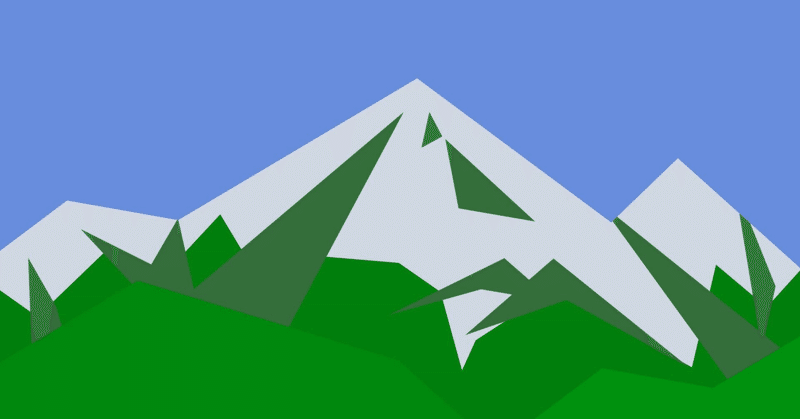
オノマトペは子どもを言語のエベレストにいざなう靴ーミニ読書感想『言語の本質』(今井むつみさん・秋田喜美さん著)
インターネット上でたいそう評判の『言語の本質』(今井むつみさん、秋田喜美さん著、中公新書、2023年5月25日初版)が面白い!と膝を打ちたくなるほど面白かったです。子どもの発達に詳しい今井さんと、オノマトペの可能性を追求してきた秋田さん。「言語ではない」と、端役扱いだったオノマトペが、実は重要な役割を果たしているのではないか?と問いかけます。その旅は、実にスペクタル。
いま、自分はまさに幼児を育てていますが、「この子はどうして言葉を覚えているのだろう?」と不思議でなりません。もちろん、それを言えばなぜ私は日本語を操れるのか、うまく説明できない。そういうものといえばそういうものなのですが。こんなにも複雑で壮大な言語というシステムを、自分でトイレにも行けないし、食事も手づかみのような小さな人がなぜ習得できるのか、やはり不思議です。
著者らは、言語システムの複雑さを「エベレスト」(p175)と表現する。そして、われわれ読者の、親世代の素朴な疑問を共有してくれます。なぜ子どもは言語のエベレストに登れるのか?
その最初の一歩が、オノマトペにあるのではないかというのが本書の仮説です。
言語の特徴を持ちながら身体につながり、恣意的でありながらもアイコン性を持ち、離散的な性質を持ちながらも連続性を持つというオノマトペの特徴は、ミッシングリンクを埋める有望なピースとなる。言語の進化においても、今を生きる子どもの言語の習得においても、オノマトペは、言語が身体から発しながら身体を離れた抽象的な記号の体系へと進化・成長するつなぎの役割を果たすのではないか。
ピチャピチャ、ドーン、スリスリ。そんなオノマトペが、言語になりきれない不完全な存在ではなく、重要な「つなぎ」なのかもしれない。この視点の転換がすごく刺激的だと感じました。
オノマトペは身体的である。面白いと思ったのは28ページあたり。カサカサやパタパタといった阻害音は口の中の空気が不規則に揺らぐ。たいして、ムニャムニャやユラユラは空気の流れが滑らかになる。これは、カサカサの鋭角的でざらついた感じ、ムニャムニャの柔らかい感じに直結する。つまり、口の中の感覚が、言語的な感覚にリンクしている。
このように、言語と身体感覚がつながることができるかどうかを、言語学では「記号接地問題」(pⅳなど)というそう。我々はメロンを食べることで、メロンが「甘い」とか「丸い」とかさまざまな身体的感覚を持って表現できる。でもAIは経験がないので、メロンは甘い、みつのように甘いなど別の記号による置き換えをメリーゴーランドのように回遊するしかない。
オノマトペは、人間における記号接地問題を解消するピースになる、というわけです。つまりラディカルに言えば、オノマトペが言語の礎である、とまで言えてしまうかもしれない。
子どもたちはオノマトペという靴を履いて、その靴が羽のようになって、エベレストの上へ上へ、いざなっているのかもしれない。
こんな風に、本書が提示するのはコペルニクス的転回です。新書で読みやすいのに、扉を開いた先に広がる景色は何とも高い空なのでした。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
