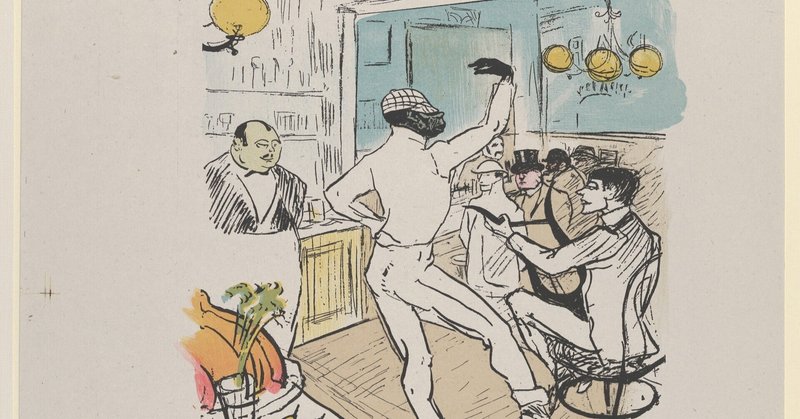
「賢い」が「正しい」を食い潰すー読書感想「実力も運のうち 能力主義は正義か?」(マイケル・サンデルさん)
いまの社会は何かがおかしいのではないかという違和感を、クリアに言語化してくれる本でした。マイケル・サンデルさんの新著「実力も運のうち 能力主義は正義か?」。タイトルが素晴らしい。普通は「運も実力のうち」と考えるところを、いやいや実際は「実力も運のうち」なんですよと説くのが本書のポイントです。サンデルさんが問題視するのは「能力主義(メリトクラシー)」。運も自分の実力(=能力)と考えてしまうような能力至上の考え方が、どれほどコミュニティーを破壊するか考えさせる。いつのまにか世界は「賢いこと」が「正しいこと」と同じくらい大切になってしまった。やがて賢さが正しさを食い潰してしまうのではないかという危機感を共有することができました。(鬼澤忍さん訳、早川書房、2021年4月25日初版発行)
敗者への過剰な烙印
成功は私が努力したから。この発想は何が問題なのか?
サンデルさんは冒頭で、米国の名門大学の学生の多くは保護者の所得が上位20%に当たるということを指摘する。優秀な学生が集まるはずの大学でも、その優秀さは家庭の経済状況に大きく左右される。ある種の「運」が「実力」を規定している欺瞞を炙り出す。
でもこれだけでは「競争が正しく機能していない」というだけではないか。能力主義そのものを否定するのはやりすぎでは?と疑問が浮かぶ。努力した人が大きな果実を得ること自体は、間違っていないのではないかと。
ここからがサンデル節。いやそうじゃない、能力主義そのものが致命的な欠陥を抱えているんだと怒涛のように話し始める。
もっとも響いたのは「敗者への烙印」。
能力が高いものが成果を得るという考えは、裏返すと能力が低いものは何も得られない、それでも仕方ないということになる。これが行き過ぎると、敗者には怒りと屈辱が蓄積していく。
しかも冒頭で示されたように、現実にある競争は能力を正しく測定するものでもない。もともとの勝者がかなり有利に配置されている。この状況では敗者が再び敗者になり、屈辱が再生産されてしまう。
あなたには能力が必要だ。そのために教育や訓練が必要だ。能力主義の勝者はこう語りかける。それが残酷なんだという作家トーマス・フランクさんの言葉をサンデルさんは引用している。
それは、実のところまるで答えになっていない。成功している側が、自ら占めている有利な立場から申し渡す道徳的判決なのだ。知的職業階級は手にした学歴によって定義されるため、彼らが大衆に向かって、あなたに必要なのはいっそうの学校教育なのだと語るたび、「不平等は制度の失敗ではない。あなたの失敗だ」と言っていることになる。(p131)
能力主義の苛烈さは「不平等はあなたの失敗だ」と「四六時中」語ることだ。それ以外に理由が見当たらないのだ。運でも、環境でもない。自分に実力がないから、今の自分は惨めなのだと思わざるを得ない。
四六時中あなたは無能だと呼びかけられる世界で生きていけるだろうか?
置き去りにされる正しさ
じゃあ、無能な人に施しを与えよう、ではダメなのか。ダメなのだ。
サンデルさんは、能力主義は分配の問題ではなく、社会的敬意の欠如だと説いている。つまり、敗者に屈辱と怒りを募らせることを許容すること自体が、社会的な不正義であると。そんな社会では「共通善(コミュニティにおいて共有する価値)」が達成できない、むしろ大きく棄損されるのだという。
つまり端的に言えば、能力主義は「賢さ」を追求し、「正しさ」を置き去りにしようとしている。
「賢い(スマート)」はキーワード。サンデルさんはスマートという言葉の使用頻度が2000年に掛けて急増し、さらに2018年までに倍増したと指摘する。
特に好んだのがオバマ元大統領やヒラリー・クリントン氏だという。138pで挙げられている例では「世界規模でのエイズとの闘いは、行うのが正しいだけではありません。賢明(スマート)でもあるのです」など。賢いことは、正しいことと並列になるまで尊重されている。サンデルさんがこう解説する。
評価のための対比として、「賢いvs愚か」は、「正義vs不正義」や「正しいvs間違い」といった倫理的あるいはイデオロギー的な対比にとって代わるようになった。クリントンもオバマも、彼らの有望な政策は「行うのが正しいだけでなく、行うのが賢明(スマート)な政策」だとしばしば主張した。こうしたレトリックをチェックしてわかるのは、能力主義の時代では正しいことよりも賢明なことのほうが説得力を持っているということだ。(p138)
能力主義が賢明であることは、たぶんそうだ。能力のある人間に仕事を振り、大きな成果を上げてもらうことは効率的でスマート。しかし、その代償として能力が劣る人に絶え間ない屈辱を与えることは、不正義のはずだ。つまり「賢明であっても正しくない」社会選択は存在するはずなのに、省みられていない。
むしろ賢さは価値中立的な装いをして、反論が難しい状態になっている。誰だって愚かなことを支持する気にはなれない。だからこそ政治家も賢い政策だと強調しているわけだけれど、「それは本当に正しいのか」という検証は不十分だ。
勝者も傷だらけになる
サンデルさんは止まらない。後半では「教育」と「労働」の2分野を取り上げて、具体的な社会改革を考えていく。そのうち教育の中で、実は能力主義社会の勝者も相当なダメージを負うことを指摘する。
なぜ、現代の勝者は自分の成功を実力の成果だと思いたいのか。それは、名門大学合格までに苛烈な競争があるからだという。競争が激しいからこそ、「自分は勝ち抜いた」「選ばれしものだ」と思いたくなる。
だからサンデルさんの元に来る学生は傷だらけだ。
能力の戦場で勝利を収める者は、勝ち誇ってはいるものの、傷だらけだ。それは私の教え子たちにも言える。まるでサーカスの輪くぐりのように、目の前の目標に必死で挑む習性は、なかなか変えられない。多くの学生がいまだ競争に駆り立てられていると感じている。そのせいで、自分が何者であるか、大切にする価値があるのは何かについて思索し、探求し、批判的に考察する時間として学生時代を利用する気になれない。心の健康に問題を抱えている学生の多さは、危機感を覚えるほどだ。(p260)
あまりに競争が激し過ぎて、人生の意味や楽しみを立ち止まって考える余裕がない。ある意味で、能力主義が能力主義的な発想を再生産しているようにも感じられる。賢さを得る道が苦しすぎるから、正しさにかまけている時間がない。
敗者の苦しみを考えた時と同じ問いが、ここでも浮かんでくる。こんな世界で、私たちは本当に生きていけるだろうか?
勝者になるためのゲームは一層ハードモードになる。敗者が与えられる屈辱はどんどん激しいものになる。成功するためには死ぬほど努力しろ。負けたらそれはあなたのせい。この世界の一体何が楽しいのか?
言い過ぎかもしれない。でも「市場価値を上げろ」とか「自分で稼げる力を」というメッセージが書店に溢れている今の社会は、言い過ぎなくらいの世界に片足を突っ込んでいるように思えてならない。
本書を今読めてよかった。私たちはまだ立ち止まれるはず。賢い世界よりもまず正しい世界を作っていくために、まだ何かできるはずだ。
次におすすめする本は
じゃあ立ち止まって考えるためにどんな本が必要かと言えば、エーリッヒ・フロムさん「愛するということ」(紀伊国屋書店)ではないかと思いました。モテとか恋愛工学ではなく、本当の意味での愛を問い直す。能動性や、技術についても考えられると思います。
サンデルさんの「それをお金で買いますか」も面白い。感想はこちら。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
