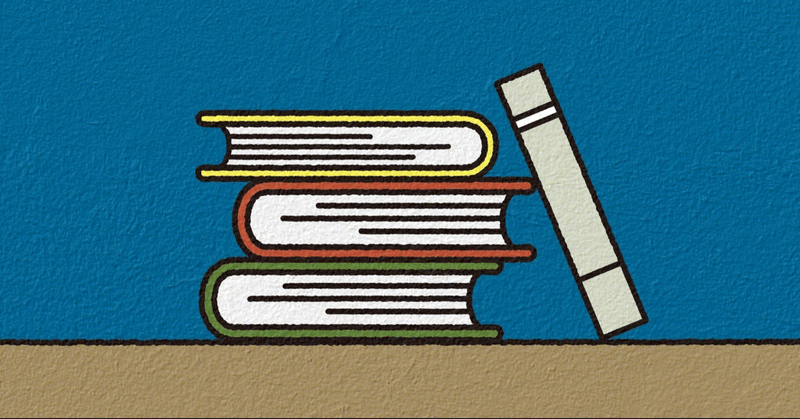
表現する言葉を奪われた子どもたちーミニ読書感想「ルポ 誰が国語力を殺すのか」(石井光太さん)
ノンフィクションライター石井光太さんの最新刊「ルポ 誰が国語力を殺すのか」(文藝春秋)にぐいぐいと引き寄せられた。読解力以前の国語力低下を問う。少年犯罪、あるいは不登校などのさまざまな課題の根本に、子どもたちの言葉の貧困があるのではないかというのが本書の主張。読了すると大変納得できる。子どもたちは、自分の感情や思いを表現する言葉を奪われてはいないか。
ジャーナリズム系の雑誌が減少し、ノンフィクションライターが発表する場、あるいはライターを育成する場が減少する中、石井さんは精力的に取材を続けている。当代きっての書き手と言って良い。川崎市の中学生殺人事件や、虐待死事件など、重いテーマに率先して取り組んできた。
そんな石井さんが目を向けたのが国語力。さまざまな困難の現場で、沼にはまるように問題に絡め取られてきた子どもたちの姿に胸を痛め、「どうしてこうなってしまうのか」と思い悩んだ末に選んだテーマは、これまた重みがある。
本書の冒頭、小説「ごんぎつね」を誤読する小学生についてのパートはネット上で拡散し、話題になった。鍋の中で煮えているのが遺体だという意見が出たことについて、ネット上では「それは葬儀の経験がないだけで、読解力の問題ではないのでは」という意見が出た。
しかし本書を通読すると、石井さんはそうした次元より一段違う、ある種「低い次元」の話をしていることが分かる。つまり、葬儀経験が乏しいからもはや古典的作品のごんぎつねの世界観が読み解けないという話とは違う。そもそも、「ひとを鍋で煮る」という表現が持つ残酷さや冷徹さ、異常さについて、口にする前に思いを馳せないことを問題としている。言葉への感度が低い、ということだ。
これを裏返すと、感情を何でもかんでも「ヤバい」という言葉にまとめることや、相手に怒りを抱いたときにとにかく「死ね」と言うことにつながる。言葉が持つ意味に無自覚なことと、感情を表現する適切な言葉を持たないことは表裏一体だ。
たとえば、フリースクールに来ている不登校の子どもたちが「なぜ学校に行きたくないか説明できない」と語るなど、本書では言葉を失い、その結果さまざまな問題に立ち止まるケースが多数紹介される。
難しいなと思ったのは、こうしたケースは必ずしも経済的に困窮する家庭の問題だけではなく、幼少から勉強をさせられるいわゆる「教育虐待」を受けた子もいるということ。もちろん貧困との関わりは大きいが、それ以上に子どもたちが家庭や学校で、安心して自己表現し、それを他者と分かち合う機会を失っていることが問題の根本にある。
後半は「ではどうやって言葉を養うのか」という点にフォーカスしていて、これが育児をする身にはとても参考になる。
たとえば「言葉のバブル」(247ページ)。少年院を出所した人たちの更生事業をしている団体で導入されている取り組みで、喜びの感情なら、「歓喜する」「小躍りする」「はしゃぐ」といった語彙について、大小さまざまなバブルのどこに当てはめるのかを考える。こうすることで、喜びという感情を細分化し、そのときに応じた適切な形を見つけ、表現できるようになる。
怒りを感じた時、それがはらわたが煮えくりかえるレベルなのか、カチンと来る程度なのか、適切な言葉が使えれば過小評価も過大評価も避けられる。結果、折り合いがつけられる。
本書はまず、言葉を失った子どもたちの存在に気付ける点で意義が大きい。かつ、そうした子どもたちを「異質化」せず、どうやって包摂するかにまで思い致すことができる点が優れている。タイトルの「誰が殺すのか」に応えるとすれば、この社会をつくって是認するわたしたち読者も含まれる。だからこそ、わたしたちも言葉を養う、回復する手段を世の中に増やしていく責任がある。
つながる本
カウンセラー東畑開人さんの「なんでもみつかるよるに、こころだけが見つからない」(新潮社)も本書に近い問題意識で書かれていると感じました。もやもやする思いにどうやって言葉の補助線を引くかが学べる本です。
また、まだ未読ですが、たまたま今日書店で見つけた「言葉をおぼえるしくみ」(今井むつみさん、針生悦子さん著、ちくま学芸文庫)は子どもがどうやって言語を発達させるかをテーマにしていて本書との関連がありそう。
今井むつみさんは本書にも登場します。言語の枠組み「スキーマ」について、今井さんの単著「英語独習法」(岩波新書)でも詳述されています。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
