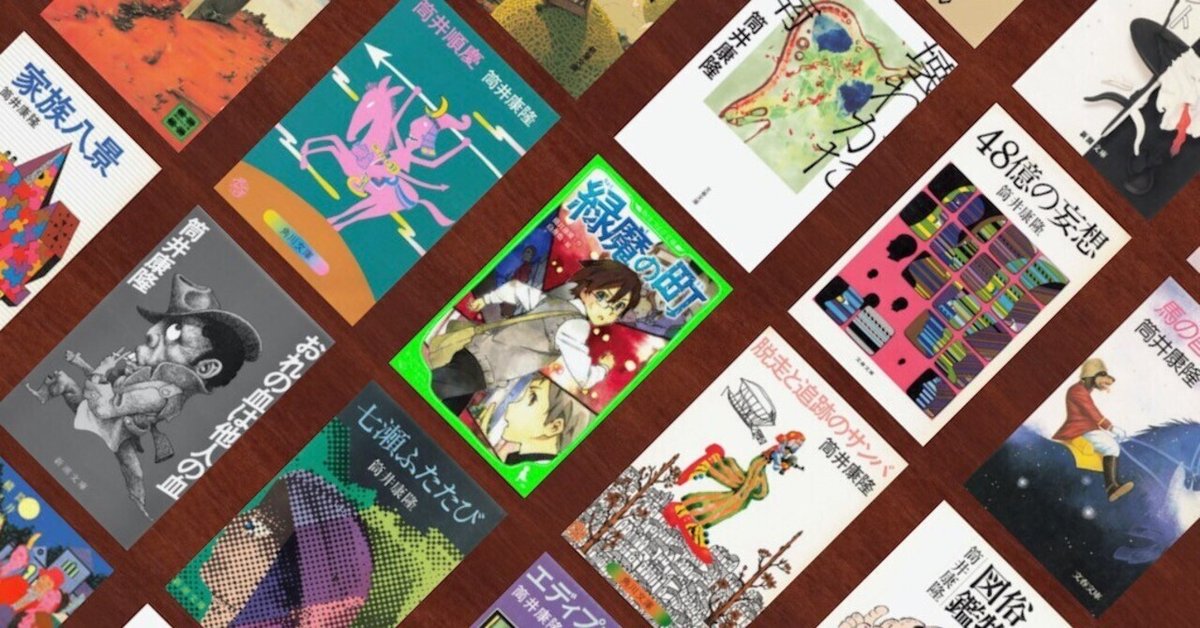
筒井康隆論(序)
はじめに
このテキストは「筒井康隆論」の序章にあたる部分です。
ミステリーのネタバレなど、ストーリーに触れている部分が数多くあります。その点諒解の上、ご覧ください。
※ストーリーに触れた部分があまりに多いので全体はkindle版として公開中です。
「筒井康隆論」
諜報
「コレラ」と『家族八景』
自分の意志でやっていると思っていることが実は操られているだけなのではないかという感覚が筒井作品を貫いている。
筒井作品の登場人物たちは、時として操る側であり、時として操られる方である。操り、操られるという関係性のドラマが筒井作品の中核を為し物語を駆動させていく。
「七瀬シリーズ」(『家族八景』『七瀬ふたたび』『エディプスの恋人』)の主人公火田七瀬はスパイである。といっても、無論社会的な地位としてのスパイだと言うのではない。彼女は精神感応者、テレパス(相手の心を読む能力を持つ人間)である。彼女は、その能力を使って人びとを操る存在である。その意味において彼女はスパイである。
『家族八景』の連作では、彼女は住みこみの女中をしており様々な家庭を転転とする。若くして身寄りもなく、テレパスの能力を隠して生きなければならない彼女は一カ所に留まるのが難しい。一つ処では、いつかはぼろを出して秘密を知られてしまうであろうからだ。従って、簡単に短期間で居場所を変更でき、そうだとしても怪しまれないで済む「住みこみのお手伝いさん」という立場が好都合なのだ。
七瀬が「掛け金」を外すと周囲の人間の考えている内容が彼女の中に流れこんでくる。
彼女はこの能力を使い、新しい家庭での家族たちが何を考えているか、どのような関係かをまず分析し自分の立ち位置を修正し安全な立場を確保していく。
ただし「気づき過ぎる」のは危険だ。掛け金をはずしたままにしてしまうと「相手の思考がどんどん流れこんできて、ついには相手の喋ったことと考えたことの見わけがつかなく」なってしまい、相手の内心の考えに相づちを打ってしまったりもする。
「澱の呪縛」(『家族八景』)で神波家の長男は、あまりにもテキパキと掃除する七瀬に対して「自分たちのうす汚ない秘密を見られたための負い目」を感じ、七瀬に敵意を抱く。「長男は心の中で彼女のことを、いみじくも(覗き屋)と名づけていたのである」。
七瀬のいる家族たちは、いつの間にか彼女に心の中を覗かれている。彼女は相手が自分に何をして欲しいかが瞬時に分かってしまう。だから理想的なお手伝いとしても振る舞える。ただし、相手の気持ちを分かりすぎてしまうと能力を悟られてしまう。やり過ぎないことが大切だ。
また、若く美しく魅力的な女性である七瀬は家庭内という無防備な状況で雇用者という立場の男性の行動にも警戒しなければならない。
「七瀬は、危険を感じた。勝美は本気で七瀬の肉体を求め、彼女を犯そうと考えていたからである」(「水蜜桃」(『家族八景』))
彼女は自分を守るためには他人を不幸に陥れもするし、時として殺害すら厭わない。女中部屋に侵入し七瀬を押し倒す勝美に対して、勝美の考えを逐一先読みしてことばにすることで衝撃を与え、彼の無意識にある原初的な恐怖を刺戟し発狂させる。勝美は「自分の超能力を知っているただひとりの人間であるというだけの理由で、どんなことがあっても抹殺しなければならない存在」となったのだ。
また、彼女は他人を操る快感を享受してもいる。
「芝生は緑」(『家族八景』)で七瀬は、隣同士の高木夫妻と市川夫妻がそれぞれ相手の配偶者を思いながら行為に及んでいるのを知って、この男女が本当に組合せを替えたらうまくやって行けるのだろうかといういたずら心を抱き、不倫の現場で四人が鉢合わせするよう画策する。しかし、配偶者の浮気心を目の当たりにした夫婦はかえって嫉妬で夫婦の結合を取り戻す。「負けたわ、と、七瀬は感じた」。思い通りに不幸になってくれない夫婦たちに七瀬は失望する。
彼女がテレパスとしての自分の使命などに目醒めるのは『七瀬ふたたび』以降であり、少なくとも『家族八景』においては彼女の行動には倫理的な問題が多い。もし、読者にとって彼女が性格の良い女性に見えていたとしたら、美少女という設定に幻惑されているのである。つまり、ハニートラップにすでに巻きこまれているのだ。
さて「コレラ」という短篇がある。
これはいかにもカミュの「ペスト」のパロディであるかのように装った作品であるが、実はもう一つの『家族八景』である。
下野緋五郎は光和商事の営業マン。彼は有楽町にある喫茶店「ピーター」で同じ会社の大木勉子とお茶を飲んでいた。彼女はお腹の具合が悪そうだ。トイレに行くと言う。彼女は、おそるおそる立つと背を丸めて便所に向かうが通路で動けなくなってしまう。そして店内の客が見ている中、激しく排便し、気絶してしまう。
緋五郎のその後の行動は最悪である。自分を人並み以上の美貌であると思いこみスタイリストを自認する彼は、公衆の面前で漏らした女性の同伴者であるのを知られるのが恐ろしくて、彼女の意識がないのをいいことに、その場をそっと逃げだして自宅に帰ってしまう。
そして次の日、会社に出勤すると、同僚から勉子がコレラで死んだことを聞かされる。
実は、緋五郎は喫茶店に行く直前まで新橋のつれこみ旅館にいたのだ。その上、その前日彼は韓国の李との商談ついでにホテルで関係を結んでいた。その李は空港の検疫所で引っかかり検疫所の病院に収容されていたのに、そこを抜け出して緋五郎と会っていたのである。従って、勉子にコレラを感染したのは緋五郎に間違いない。ただし、彼自身は発病しない免疫体質だった。
現代資本主義社会における経営者同士は男色関係で企業連携をはかっている。(と、この作品の中では設定されている)
緋五郎は、すでに保菌者であるのを知りながら会社の社長とも関係を持つ。社長は光和コンツェルンのパーティに出席し大業の経営者層に菌をばらまき、経営者たちは、それぞれの妻や妾、バーのホステス、芸者に菌を感染し政界財界芸能界隅ずみまで菌が浸透していく。結果的に東京は疫病によって完全に荒廃し封鎖される。
緋五郎は保菌者であり、免疫体質という特殊能力を持っている。七瀬がテレパスであるように。ただし、彼は確かに超能力者ではない。だが、彼は特殊能力のお陰で秘密を知り得る立場にある。それなのに自分を守るためその秘密を決して明かさない。七瀬が「芝生は緑」(『家族八景』)で自分の言動が高木夫妻と市川夫妻の間でどのような連鎖反応を生み夫婦が破滅へと導かれていくかを(その目論見が失敗したとはいえ)楽しんでただ眺めていたように、緋五郎は自分の行動が多数の感染者を生むのをただ眺めている。
自分の保身のための「見て見ぬ振り」。それは最悪の結果を生む。
「亡母渇仰(ぼうぼかつごう)」(『家族八景』)では、七瀬は、火葬される棺桶の中で恒子が蘇生しているのを自分だけが知りながら黙っている。自分が止めなければ恒子は死ぬ。しかし、それには自分がテレパスであることを告白しなければならない。恒子は嵐のような断末魔の叫びをあげ生きながら燃やされていく。緋五郎は東京が荒廃していく原因を知りながら、またそれを防げる唯一の立場にありながら行動しない。このような「悪意ある傍観者」の立場が二人の共通項だ。
七瀬は、『七瀬ふたたび』において同じテレパスのノリオやテレキネシスの能力を持つヘンリー、予知能力者岩淵恒夫、タイムトラベラーの藤子といった同志を得ることで、我々はなぜこの世に生まれてきたのか(「自然よ。なぜ超能力者などという突然変異を人類にあたえたのですか」)という問題意識に目醒めていく。最終的には『エディプスの恋人』において宇宙意志に見出された存在として世界を救う存在となる。しかし、これこそ究極的に操られる人間の姿ではないか。七瀬はもう誰を愛するかさえ他者に決められてしまっていて選択の余地は全くない。彼女は操る存在から操られる救済者に変貌する。完全に救済された人間とは完全に操られた存在である。
自分の意志でやっていると思っていることが実は操られているだけなのではないかという感覚。
それが筒井作品を貫いている。
スパイ
「七瀬はスパイである」と言った。
とはいえ、筒井康隆作品にスパイ物が多いわけではない。
「台所にいたスパイ」では「おれ」は家族の動向を盗聴によって探っている。何故なら妻はCIAのスパイであり頻繁にやって来る調律師も怪しい。またのんびり囲碁に興じる父はMI6、街ではKGBの諜報員が運転するタクシーが走っている。スパイブームが行き過ぎていまや皆がスパイなのだ。作品は最終的に町内全ての人間を交えての銃撃戦となる。
スパイに憧れている「寒い星から帰ってこないスパイ」の「おれ」はバラバラ星で勝手に諜報活動をはじめドタバタを演じる。
「深夜の万国博」。展示館内の治外法権を利用して日本に侵入しているスパイたちは夜ごと深夜の万博会場で戦闘をくり広げている。
「その情報は暗号」はスパイが主人公だが、言うまでもなくコメディ・タッチでナンセンスである。
これらは、スパイが登場するとはいえスパイ作品とは言いがたいだろう。
長篇作品。
『馬の首風雲録』は馬頭型暗黒星雲にある惑星、ビシュバリクの国家軍とブシュバリク共和国軍における戦争の物語である。国家軍はI作戦という陽動作戦を実施する。I作戦とは、ブシュバリクの第二衛星BUー2の二カ所に重力切断ビームを設置、トンビナイ市のま上を通過する時刻に爆発させるというものだ。成功すれば火球がトンビナイに降り注ぎ市は壊滅する。国家軍はブシュバリクの戦闘でわざと敗北を装いつつ後退し、かつ逆スパイを使って嘘の攻撃情報を流し共和国軍をおびき寄せハリボテのミサイルと偽の大要塞に敵の目を引きつける。そして爆発前夜に撤退する予定だ。トンビナイ市の住民数万人は死に、ブシュバリク共和国は壊滅状態に追いこまれるであろう。
「筒井順慶」。順慶にまつわる物語では、松永弾正久秀の東大寺焼き打ちが有名だが、久秀は主人の三好長慶を謀殺、息子の善継をそそのかして将軍足利義輝を殺させている。
『大いなる助走』で、市谷が執筆する小説『大企業の群狼』は大企業の暴露物でもあるが産業スパイ小説でもある。
『愛のひだりがわ』では、志津江が掃除婦として、歌子が経理として村松興業へ潜入し、歌子は帳簿、通帳の管理をまかされる立場となる。彼女らは社員を説得してこちら側に寝返らせた上で、社長の清水をハニートラップで油断させ、ついには会社を乗っ取ってしまう。
『歌と饒舌の戦記』では、珍しくソ連国家保安委員会所属のナタリーというスパイが、スパイとして登場し完全にスパイとして行動する。
身分を偽る・変装する
七瀬シリーズでは火田七瀬はテレパスであることを隠している。同様に筒井作品においては「身分を偽る・変装する」登場人物たちが多く見られる。
「時をかける少女」の深町一夫は未来人であった。未来からやって来た彼は、架空の偽りの記憶を与えることで周囲の人間を欺いている。彼は同級生ではない。彼は身分を偽っている。
「筒井順慶」の「もとの木阿弥」ということばにまつわるエピソードは非常に興味深いものだ。順慶の父順昭は精神疾患だったのではないかと言われる人物で、順慶が幼い時に死んでいるのだが、死ぬ前に重臣を集めて、死んでもしばらくは公表するなと言ったという。彼は、奈良に木阿弥というめくらがいて、おれによく似ているから替え玉にしろと言う。その時、順慶はまだ二歳。重臣たちはあわてて木阿弥をさがし出しつれてきた。化け方はたくみだった。周囲は一年もの間、すっかり騙され、一周忌でようやく死は公表された。木阿弥は「もとの木阿弥」として暮らすことになったのである。
『48億の妄想』。日韓戦争のきっかけとなった日本漁船への襲撃は韓国民衆党が日韓会談を決裂させ現政権に痛手を負わせるため大学生をそそのかし行った陰謀であり、日本船を銃撃したのは警備艇に偽装された漁船だった。また、海戦のまっただ中、銀河テレビの取材班に怨霊丸の四人が取材を受ける場面がある。ところが、またしても取材班は韓国側の偽装だった。カメラマンは期を見て望遠レンズに仕込んであった自動小銃を撃ちまくる。
『俗物図鑑』。家族から身を隠すため、風巻扇太郎と菊山宗吉は整形手術を受ける。
「メタモルフォセス群島」は筒井作品世界において非常に重要な意味を持つ作品だ。
水爆実験の放射能でコンプリ島の生物は突然変異体(ミュータント)化してしまっている。生物学者である「おれ」と滝はジャングルの生物を調査にコンプリ島に来ている。
小さな池のほとり。がさ、と背後の茂みが物音を立てる。あわてて銃を向けると、偶蹄目の足を持つ茂みそのものが立ちあがり森の奥へと消えていく。ブタが背中に灌木を生やし植物化しているのだ。二人は茫然とする。飼われていた豚が野生化したのだろうが、脂肪層に根を張って植物が寄生している。豚の方でも脂肪層を肥大化させて植物を受け入れていた。天敵がいるようにも思えないが、あらたな天敵ができて偽装しているのだろうかと二人は考える。
そして翌日。昨夜から行方不明の滝は食人植物に食べられてしまっていた。植物の果実は滝の顔をしている。「おれ」はその実をもぎ取り持ち帰る。滝そっくりの姿をしているその果実をせめて日本に持ち帰るためである。「おれ」はジャングルのエコシステムに組み込まれてしまったなと感じる。おそらくその植物は、人間の顔そっくりに果実を擬態し別の場所に埋葬させることによってテリトリーを拡げるのだろう。
『おれの血は他人の血』。絹川の腕っぷしを見込んだ左文字組幹部の沢村は組長の用心棒になって欲しいと絹川に依頼する。シマを見まわる夜だけでいい。「たとえ夜だけでも左文字組の中に身を置いた方が、昼間のあなたの身分を隠すことにもなるだろう」。
「富豪刑事の囮」では、神戸大助は刑事であることを隠し容疑者に接近する。「密室の富豪刑事」では、ダミーの会社を設立するという神戸の話を面白がる鶴岡刑事や喜久右衛門が集めるかつての部下たち、秘書の鈴江も身分を偽って作戦に参加する。「富豪刑事のスティング」では、子供が誘拐された家に刑事たちは偽装して駆けつける。また、銀行員に化けて偽の融資を実行する。「ホテルの富豪刑事」では刑事たちはホテルマンに化ける。
『イリヤ・ムウロメツ』。イリヤは乞食の変装のまま王の御座所にいる怪物イードリシチェ・ポガーノイエの前にすすむ。
『フェミニズム殺人事件』での地元の不動産業者長島。彼は教養ある知識人を装い、ホテルのロビーに飾られている中国古代の青銅器にも詳しい。しかし、実際にはロビーに飾られているのはフェイクだった。彼は偽物を見抜けない。長島の教養は非常に疑わしい。彼はある秘密の目的をもって富裕層に近づこうとしているだけだったのだ。ちなみに、彼は『48億の妄想』で、偽物の骨董を家中に並べて叩き割られてしまう秋園かおりの父親を思わせる。
「TANUKI」も偽装がテーマの作品だ。
狸吉郎の一家はいつものように柏原家の庭にやってきたが家の中はひっそりしている。柏原家の息子がマラソンで怪我したという。しかも、これ以上学校を休んだら落第なのである。ご恩がえしの時がきたと張り切る狸吉郎一家。太郎吉、次郎吉、三郎吉はいじめっ子にひどい目に会わされながらも息子に化けて学校に行く。殺してやると言われ我慢できず忍者ハットリくんの顔に化けたりする。ついに狸吉郎が校長に化けて諭す。しかし三人組はちっとも恐れない。お福は石田先生に化ける。
「ゲゼルシャフト」の江川は警察署の一室で整形手術を受け犯人と刑事の両方を演じマッチポンプを行うことで大衆とマスコミの両方を満足させている。
『夢の木坂分岐点』では、何度かサイコドラマの場面がある。サイコドラマは途中、身分(役割)を交換して演じられる。物語のもっとも終盤で演じられるサイコドラマでは他人の家庭の娘役になった真知子は母親が実際には継母であることを直感的に見抜く。「ぶったらいいでしょ。どうせ、ままははなんだから」。母親は継母だった。それは偽装されていた。真知子がその偽装を暴くことでドラマは参加者全員を伴って高みへと到達する。
『モナドの領域』の結野教授は究極の身分偽装といえる。人間の姿をしているが、彼は『GOD』なのである。神ともいえるが、より上位の存在なのだ。
秘密を探る・探られる
『聖痕』の葉月貴夫は絶対に人に知られてはならない秘密を持っている。彼は幼い頃、何者かに性器を切断されてしまったのだ。性的な欠陥が多くの人に知られ好奇の目に一生さらされ続けるのを恐れた家族は徹底的にその秘密を隠蔽する。プールの授業、旅行、言い寄ってくる異性、結婚など秘密が明らかにされそうな絶体絶命の場面を彼は何度もくぐり抜ける。
『文学部唯野教授』の唯野もまた物語冒頭から秘密を負わされる。彼はフランスに行っている筈の牧口が密かに日本に戻ってきていることを知ってしまう。どうしても昇進したい牧口は大学から受け取った金を運動資金としてくすねて自宅に隠れているのだ。もちろん、それが知られたら彼の立場はない。また、それを知って隠していた唯野にも累が及ぶのは避けられない。また唯野は牧口を立智大学の教授にするために秘密裏に工作する。
『朝のガスパール』。貴野原聡子は夫に内緒で株取引を始め多額の損害を負う。しかし贅沢な交際の味が忘れられない彼女は密かに自宅を抵当に入れ追加融資を受けサラ金から借りまくる。それでもパソコン通信上のゲームに夢中な夫は全く気づかない。
「筒井順慶」では、作者であり主人公の筒井康隆は、原稿を修文社の倉橋に渡すか八木書房の電子に渡すか悩んでいる。原稿はまだ書きあげていないと嘘をつきながら。
また、筒井順慶の洞ヶ峠の故事。光秀と秀吉が山崎で対陣した際、順慶はどちらにも加勢せず洞ヶ峠から見おろしどちらかが勝つのを見ていたという「洞ヶ峠をきめこむ」という諺の謎。筒井は、この伝説が嘘なのか本当なのか資料を漁って明らかにしなければならない。順慶の埋蔵金はどこにあるのかというのも、ラストにその秘密が明かされるサイドストーリーだ。
『おれの血は他人の血』。絹川は山鹿建設支社の経理課。たまたま秘密の仕訳帳を発見してしまう。
木島はま子は重役室内秘書。絹川は彼女から社内人事での派閥関係を聞かされる。また、はま子との関係は誰も知らない。絹川自身も川島総務部長に呼び出され極秘の依頼を受ける。「『経理課に、二冊目の仕訳帳がある筈だ』『その仕訳帳と、それに関係した書類、破棄されたか破棄される筈の伝票、いずれも誰かの認印の押されたものがいいわけだが、そういったものを集めてほしい。集めることが不可能なら、どこにあるかを探ってほしい』『スパイをやるわけですね』」彼が持ち出した書類の行方はいったいどうなるのだろうか。きっと『大いなる助走』で市谷が書きあげた小説にもこのようなシーンがあるに違いない。
「鍵」。昔の家の抽出し、ビルの屋上の物置、荒れ果てた高校の旧校舎のロッカー、それらには「青春の残滓」とともに「おれ」の秘密を解く鍵が入っている。「おれ」はいったい何者なのか。
「箪笥」で、文麿が毬子さんと入る土蔵の二階にあるロココ様式の装飾が施された箪笥。ここにも、取り外し可能な引き戸の中に秘密の鍵が隠されている。抽出しの鍵だ。
覗く・覗かれる
七瀬は人の心を覗いていた。「覗く・覗かれる」という関係も筒井作品に頻出するモチーフだ。
「公害浦島覗機関」はそのまま覗きがテーマの作品である。
築三十五年の紫苑ホテルは連日連夜どこかで工事をしている。「おれ」は事務所でホテルの平面図を見ているうちに一階と二階で柱の形が違うことに気付く。もしやと思って調べてみると、そこには秘密の隠し部屋があった。隙間から部屋を覗くと、そこには閣僚と、とある企業の社長がいる。「おれ」は彼らの重大な秘密を覗き見てしまう。
「優越感」。青山の建売り住宅を買った「おれ」。周囲の団地はスラム化している。建売りを買ったのは文化人ばかりで、周囲三方を団地に囲まれている。
「建売りは二階建て、団地は四階建て、おまけにこちらは三方を囲まれているため、常にどこか上の方から覗き込まれているか監視されているかしている」
「たまたま団地の窓を見あげると、必ず誰かがどこかの窓から首を出してこっちを睨んでいる」(「優越感」)
「奇ッ怪陋劣潜望鏡」は「覗かれる」ことそのものがテーマの作品。伊豆のホテルでの新婚第一夜の早朝、海岸を散歩する二人。彼らは、沖あい二十メートルほどに潜望鏡が突き出てこちらを見ているのに気付く。たちまち潜望鏡は十数本に増えた。逃げる二人を潜望鏡はいっせいに追う。二人とも非常に厳しい教育的な家庭に育てられ結婚するまで童貞と処女だった。医者の話では、その妄想は抑圧の反動であるという。やがて、部屋の中の水という水から潜望鏡は顔を出す。二人は潜望鏡に見られかえって興奮を高める。
「カチカチ山事件」。爺につかまって足をくくられ天井からぶら下げられる狸。婆が狸汁にいれる餅をついていると、狸はこの縄をほどいてくれれば餅をつきますよという。解放された狸は婆を杵で殺害する。しかし、その様子をランドセルをせおった色の白い男の子、女の子がながめているのだった。
「稲荷の紋三郎」。吾妻屋の乙多見は妻恋山の稲荷に長四郎と九郎右衛門が自分に横恋慕して困っているのですと訴える。それを聞いた荼枳尼天はそんなに大勢の男から言い寄られるとはどれほどの美人なのかと稲荷の格子の隙間からそっと彼女を覗き見る。
そして「融合家族」である。実は私はこの短篇は筒井作品世界を語るのに非常に重要なものだと考えている。従って、この後も何度か引用することになるだろう。
手違いで同じ土地に家を建て始めてしまった二つの家族。先に建ててしまった方が勝ちだとばかりに競争で建築を進める。両方の大工の奇蹟的な技によるのだろうか、設計図通りの家がキメラのように一つの場所に融合して建てられ、二つの家族はお互いを完全に無視し相手を無きものとして生活を始める。階段の下をくぐり、小さな穴を通り抜け、縄梯子で部屋から部屋に移動する。お互いを無視しながら、いつしか夫婦同士は仲の良さを見せつけ合っている。視線を意識し、妻は過剰にサービスし、夫はわざと優しくする。
ここではお互いがお互いをスパイしている。お互いの私生活・性生活を覗き見ている。非常に重要なのは、見られることで配偶者に優しくなる点である。この公然とした窃視は教育的効果を生む。
「露出症文明」の妻は夫に顔テレを買いたいとねだる。「顔テレ」とは、作品中でビューフォンと呼ばれる、要するにテレビ電話である。夫は、赤の他人からカメラで私生活を覗かれるのはいやだと拒絶するのだが、妻は「私生活を覗かれるくらいのこと、高級な消費生活をしようと思えば当然覚悟すべきよ」と反発する。カメラに映る自分の家庭をよりよく見せようと競い合い、ビューフォン文明は進歩していく。「他人に私生活を覗かれることを厭がる人は、現代ではむしろかたわです」
「融合家族」の二つの夫婦が「高級な消費生活」を先取りしているのは言うまでもない。現代文明では「私生活を覗かれるくらいのこと」は「当然覚悟すべき」である。むしろそれによって家族関係は円滑になるのだ。
「顔テレ(ビューフォン)」のモニターはお互いの生活を覗きあう。「覗くとき、覗かれている」。このモチーフは筒井作品に頻出する。
「緑魔の町」。物語終盤、病院の一室。武夫は思う。油断はならないぞ、と。
「ぼくは、アンタレス人たちの捕虜になり、アンタレス星へ、つれて来られているのかもしれないのだ。そして、こいつらはみんな、アンタレス人で、窓の外の風景というのは、あれは映画で、そして、ぼくは今、みんなの見世物にされているのかも——」(「緑魔の町」)
窓の外を覗く時、外から覗かれているのかも知れない。
『夢の木坂分岐点』。
交番の筋向かいにある映画館の看板。原作は主人公である大村恒昭の潮流文学賞受賞作品だ。大村が原作を書いたのは会社にいた頃だった。彼は映画館に入る。下町の三番館の便所の臭気で三十年前の大学構内の便所を思い出す。便所の窓からは隣家の裏庭が見える。隣家の茶の間では店主夫婦が昼食をとっている。その二階の窓から中学生ほどの白いセーターの女の子が上半身を見せる。女の子は大村に「その映画、面白くないわよ」と大声で語りかける。
窓の外を覗く時、外から覗かれているのかも知れない。
「ミラーマンの時間」。
「生まれてから今日まで、現実だった日は一日とてない、昌夫はまたそう思った。今日もそんな一日だ。いつものように」(「ミラーマンの時間」)
昌夫は顔の右半分に楕円形の痣があった。彼は自分の顔の醜さを自覚して以来、現実をなかば否定してきた。
「自分の住んでいる世界は別にある。その世界では自分の顔には黒痣など、ないのだ。自分の顔を見た人が、あわてて顔をそむけることもなく、子供たちが、遠慮のない眼でじろじろ見つめることもないのだ」(「ミラーマンの時間」)
昌夫は学校から戻ると手鏡を鏡面を左にして顔の中央部にあて右の眼を閉じ、姿見を覗きこむ。する左半身だけで左右対称の昌夫の顔が見られる。彼は鏡を覗く。そこにあるのは「理想的な自分」の姿だ。
『旅のラゴス』には、画力はさほどないのに絶大な人気を誇る似顔絵師ザムラという男が登場する。彼が描いた自分の似顔絵を見てラゴスはザムラの人気の秘密を悟るのであった。そこに描かれていたのは厳密に言うならラゴスの顔ではなくラゴスが理想とする顔だった。そこには、理想的自我の具現された顔、かくあれしと願い続けているラゴスの姿が描かれていた。ザムラは、ある種の洞察力、七瀬のような読心能力を備えているのである。ザムラの絵は理想の自分を映し出すモニターであり、鏡だ。そこに描かれているのは自分の心の中。似顔絵の画面を覗く時、人は理想化された自分を見ている。
さて「覗く」がテーマの作品といえば『48億の妄想』は外せない。
銀河テレビ局の地下三階にはアイ・センターと呼ばれる施設がある。そこは碁盤の目のように細い通路が拡がり、都道府県の数だけの部屋がある。各部屋の壁には平均で二万五千台ほどのアイ受像機が埋め込まれており、いつでも好きな場所を覗き見ることができるのだ。人びとは日本国中にある「アイ」を意識して生活している。あわよくばこの「アイ」に映った自分がテレビで放送されることを夢見て生きているのだ。
『巨船ベラス・レトラス』で作家錣山兼光は語る。「大昔のことだが、わたしはどこにでもテレビカメラが設置されている社会を長篇小説として書いた」。このカメラは人びとが意識して面白いことをしだすのを期待してテレビ局が設置したカメラだが、それを未来社会の予知だという人もいた。しかし違う。それは防犯カメラでお互いがお互いを見張るためのものだ。
ベラス・レトラスの船尾一キロ後方。空中に四階建ての教会風の建物が浮かんでいる。あれは「空中会館」であるという。文学関係の評論家が乗っており常に船上の作家たちを監視しているのだ。
『俗物図鑑』にも奇妙だが面白い描写がある。これは、本筋とは一切全く関係のない描写であり、省略しても物語の進行には全く差し支えがない。
「亮介は裏窓から外の景色を眺めた。小住宅やアパートがごたごたと並んでいて、真正面のアパートの半開きにした窓からは、いかつい顔をした初老の女がじっと亮介を睨みつけていた。オールド・ミス・スタイルの眼鏡が猜疑心で鈍く光っていた。(いつもこの部屋を観察しているらしいな)」(『俗物図鑑』)
彼女が何故こちらを見ているのかは分からない。しかしこれだけは言える。窓越しに覗く時、窓越しに覗かれている。
『敵』の渡辺儀助は物置で双眼鏡を見つける。質流れで安く売っていたので買ったものだが、彼は一時期「裏窓」を気取って書斎の電灯を消しこの双眼鏡であちこちを見ていた。多くの醜悪なものを見た。思春期にも傾向があった窃視症ではないかと気がついたが、しばらくはやめられなかった。
『わたしのグランパ』。
出所した珠子の祖父(グランパ)は、校内暴力常習犯の男子生徒の一団に「前科者」「人殺しがカッコつけるな」と絡まれる。グランパは「お前は看板屋の息子だろ。お父っつあんに電話するように言っといてくれ」という。もしかしたら自分の家のことも知っているのではないかと思ってみな黙ってしまう。
グランパは何故かカメラを買う。いつも珠子を苛めているともみが珠子を呼び出して堪忍してくれ、許してくれと言う。グランパに訊くと、彼はともみの母親の痴態を撮った写真を持っていた。その写真(母の秘密)をともみに見せたのだ。祖父はスパイ行為でいじめっ子を撃退したわけだ。
『フェミニズム殺人事件』。
竹内史子はこのミステリーにおける探偵である。
史子、石坂、松本は殺された長島の別荘を見に行く。別荘の中はラヴホテル然とした部屋だった。
「部屋の中央には円形のベッドが置かれ、煽情的な色のスタンド・ライトや三点セットや冷蔵庫。すりガラスの戸一枚でバス・ルームに接し、枕もとには管制盤の如きパネルがあった」(『フェミニズム殺人事件』)
パネルは照明や音楽の調整用だろう。暗室かとも思われた隣の部屋はマジックミラーを備えた「覗き専用の」部屋だった。
「『やはり遊び慣れていて、あのお歳の小曾根氏にとっては、実際に女を抱くよりも、覗く方が快楽としては刺戟的だと思う』」
「『こういう傾向はわれわれの年配の男性や、もっと若い男性にもあります。ただの性行為よりも覗くことを好むという性向ですが』」(『フェミニズム殺人事件』)
小曾根とは会員制の高級リゾートホテルで長島と知り合った人物で、誘われて長島の別荘を訪れていた。骨董を見に行くのだなどと言っていたが、実は他人の性行為を覗くのが目的だったのだ。
ただし、覗き部屋を発見した三人も、殺人事件に対する興味故とはいえ、他人の部屋を本人の許可なく覗いているのには変わりはない。
操る・操られる
「暗いピンクの未来」。
白井常夫は化学実験の事故で未来に飛ばされてしまう。未来の常夫はファッションデザイナーになっていた。彼はテレビ出演のため銀河テレビに向かう。局員の紺野ユリは恋人だ。しかし、彼女は「わたし赤井さんと婚約しちゃったのよ」と言う。赤井というのは同級生でガリ勉だった、あの赤井らしい。赤井は電子頭脳を使いモードをデザインしている。これからは電子頭脳の時代だ。あの人と結婚すれば生活が安定すると彼女は言う。
番組では常夫は赤井と対決させられる。二人はエキサイトして議論する。
番組が終り、帰ろうとすると、白井常夫の車に紺野ユリが乗ってきた。「どうして彼の車に乗らなかったんだ」「婚約はうそよ。赤井さんにはあなたと婚約したっていったのよ。だから番組は面白くなったでしょう」。
全ては彼女に操られていたのだ。
『48億の妄想』。
人気番組「長部久平ニュース・ショー」の司会長部はプレイ・ボーイ。アシスタントの草月弘子は自分のことをひそかに慕っているが、おれが冷たくあしらうので夜ごと淋しさにもだえ、むせび泣いていると思いこんでいる。また、そんな微妙な関係が番組と自分の人気の一部を支えていると彼は考えている。しかし、草月は生放送中の番組内で突然結婚を発表してしまう。彼は茫然とする。「『おれは利用されたんだ』長部は吐き捨てるようにいった。『彼女の陰謀にひっかかった!』」
「新宿コンフィデンシャル」の「おれ」は財産、地位、真の名声のすべてを手に入れたいという熱い思いで田舎からやってきた。ガレージを借り、とにかく何かを始めようと思っているが、いつしか事務所は乗っ取られてしまい自分は雑用係に。たまに来る司令をこなすだけの存在になってしまう。
「ベトナム観光公社」。新婚旅行にも年ごとの流行がある。たとえどんなに大変な場所でも前の年に評論家が指定したところに皆は行く。「流行が人の心を意のままにしていた」。
「火星のツァラトゥストラ」。何も知らないで火星にやってきたツァラトゥストラはトミヅカ教授の指南で、自分の自伝ということになっている『ツァラトゥストラ』を仕込まれる。朴訥な労働者だった彼は、テレビの人気者に仕立て上げられる。
「カンチョレ族の繁栄」。
南海開発株式会社の社員である「おれ」は辺境のジャングルに存在するカンチョレ部落に着任する。部落では開明的な酋長と保守的な反対派が揉めている。反対派は酋長の家の前で「外国人を入れるな」と騒いでいるが、追いかけ回され逃げていった。
ところが、家に戻ると、昼間逃げ去った反対派の若者が床いっぱいに腰を据えている。そして、ここを連絡場所に使わせてほしいと言う。ここを使えと提案したのは酋長側近のハベラダだった。実は、この連中は酋長が雇っている。反対派が暴れると長老たちにとっての敵になるので酋長は地位が安泰なのだと彼は言う。
ある日「おれ」が雇った通訳のカスマンは妻を犯していたのを見られ逐電していた。しかも苦労して作成した植物の分布図も盗んでいる。「やはり彼はスパイだったのだ、とおれは思った。オランダのスパイかイギリスのスパイかは知らないが、とにかくスパイだったのだ」
ハベラダの姿は一ヶ月ほど前から見えない。ワレシ族が攻めてくるという噂があった。おそらく酋長がハベラダを送り込み意図的に敵を作っているのだろう。
「あらえっさっさ」。
私立探偵、弁護士、総会屋、当たり屋、殺し屋まで抱えている芸能プロダクションである花井プロ。見栄えのいいキャラクターと部品専用のタレントを組合せ売り出す。タレントはロボットとしてしか扱わない。殺しは芸術だという殺し屋は、いかにも『俗物図鑑』の梁山泊にいそうなキャラクターだ。
今日は、軽井沢プリンス・ホテルで花井プロの芸能記者慰労大会。記者たちはおだてられて調子に乗っている。タレントを踊らせているつもりの芸能記者だって踊っているではないか。だが記者たち自身には踊らされているという自覚がない。彼らがそれを自覚する時-それはわれわれにとって扱いにくくなった時-その時は消えてもらわなければならないだろう。「われわれをあやつって踊らせているのは何者だろう。大衆か。テレビか。アメリカ資本主義か。マクルーハンか。いくら考えても、私にはわからなかった」
「家族場面」。従順でおとなしい妻を演じて三十年の彼女。彼女が良妻を演じるのは、おれを教育し支配するためである。
「最高級有機質肥料」。娘のミリは美しい。「彼女に一度でも会った男はみんな突如として通俗メロドラマを演じ始め、単なる愛欲の肉塊と化するのである」。愛欲の塊となる時、人は意のままに操られてしまう。
「エンガッツィオ司令塔」。
「おれ」は恋人柴田葉子の奴隷だ。ルビーの指輪が欲しいという彼女の願いを叶えたくてリスクは高いが割のいい薬の検体のアルバイトをする。いつしか「おれ」は「ドドメ色の電波」を発する東京タワーの命令で動くようになる。
「富豪刑事の囮」。大富豪の父を持つ刑事が、私財を使って気前のいいカモを演じて容疑者を引きつける。ただ、実際には逮捕の決め手となるのは父の秘書鈴江によるスパイの手口、色仕掛け(ハニー・トラップ)である。
「ホンキイ・トンク」。バカジア政府に安もののコンピューターを売りつける築井。操作を教えて欲しいとホテルにやって来るバカジアの王女ミオ。彼女が築井に近づいたのも典型的なハニー・トラップであった。プリンセスの愛は偽りであり、会社も首になる。
「イチゴの日」。素人の中からひどい醜女を見つけ出し皆で寄ってたかって美人だ美人だとおだてあげスーパー・スタアにしてしまうリアリティ・ショー。二十歳の誕生日に実はそれまでのことがすべてテレビ局によって仕組まれた壮大なプロジェクトであったことを公表し、彼女がうろたえるのを楽しもうという企画だ。
『おれの血は他人の血』。絹川はごく平凡なサラリーマンだがデ・ロベルティスというマフィアの血によって制御不可能な暴力を発揮する。
「邪悪の視線」(『七瀬ふたたび』)。ヘンリーは七瀬の命令によってのみテレキネスの能力を発揮する。
『脱走と追跡のサンバ』。「この世界へやってきたのはおれの意志ではない」「ひきずりこまれたか、だまされた上でつれてこられたか、そのどちらかである」。
『文学部唯野教授』。小説を発表していることを秘密にしている唯野は文芸誌「潮流」の編集者、番場と会う。「『君ねえ、大学へ電話されたら困るんだよね」』唯野は腰をおろすなり番場を詰った。『直通の方へかけてくれたからまだよかったけど、研究室にはほかのやつがいることもあるんだからさあ。助手なんてものはみんなスパイなんだよね』」。
『朝のガスパール』。
ゲーム「まぼろしの遊撃隊」の遊撃隊員たち。彼らは誰かに見られ操られているように感じている。
ゲーム内では、某出版社に勤めている細田という男がシャドウ(ゲームキャラに乗りうつり、その視点で操作できるようになる)に加わり非常識な罵倒をはじめた。このままだと展開が滅茶苦茶になると判断した花村隊長が他のシャドウに呼びかけて発病させた。「発病が退院の誰かによって発見されるような、そして細田という男にはわからないような難解なヒントを考えて花村隊長に奇妙な行動をとらせたのも、当時の花村隊長のシャドウたちです」
貴野原はふと思う。
「日本の政治と経済をゲーム感覚だけで推し進めようとしている何やら巨大な存在の陰謀も想像できなくはなかった。そうでなくても、大企業のトップ連中に同じゲームを競わせることは、日本の経済を動かしている彼らにコンピューター・ゲーム的なある単一の思考を植えつけることになる。眼に見えない制度側からの教育という想像は、センターの正体をよく知らぬだけに、貴野原にとってはいささか慄然とするものがあった。いや。センターなどというものはマスコミと同じでシステムの顔に過ぎず、コンピューター・ゲームひいてはコンピューターという技術そのもの、高度情報化・産業化社会の科学技術そのものが生み出されると同時に、そのものの中に、人間を教育し支配しようという構造が、自然に発生し、組み込まれてしまっているのではないだろうか」(『朝のガスパール』)
『銀齢の果て』。日本国政府によって無理やり老人同士バトルさせられ多くの友人や隣近所の人間を失ったバトル勝者たちは最後に厚生労働省を襲撃する。
「筒井順慶」。
筒井順慶の物語を執筆することになった人気作家筒井康隆。彼は考える。今度こそ、まかりまちがうと大変なことになる。今まで色々なものを“書かされて”きた。未来論、文明批評、風俗小説じみたもの、ルポ、ミステリー、しまいには童話まで。さいわいどれも批評家から褒められた。しかし、歴史小説などに手を出してあとあとまで悔やむことにならないだろうか。
順慶に関して問い合わせた父からはがきがくる。父祖をはずかしめるな、と。どたばたを書いて同族会から非難されるのを心配したのだろう。「どたばたにはしないから安心しろ」と返事するわけにもいかない。本当にどたばたになってしまう可能性もあるからだ。内的必然性とか文体とか体質とか編集者の要求など、作家にはどうしようもない事情がある。
さて、編集者の要求でどたばたにする、あるいは父親からの要求でどたばたをやめる、どちらにしても他人からの指図には違いない。実際「筒井」は『筒井順慶』の途中までの原稿を編集者に見られて「嘘を恐れていちゃ、歴史小説は書けない。フィクションなんだから会話を増やして面白くしろ」と指示されて文体をがらっと変える。
「猫が来るものか」も「作品を書く意識」について考えた作品である。
「『たしかに「薬を服んで書いた作品が面白くても、それは作家が書いたものではなく、薬が書かせたものに過ぎない」という言い方がある。しかし、これは作家の理性や常識といった健全なものが存在するという観点の、いささか古い考え方じゃないだろうか』と、おれは言った。『それだと素人が薬を服んで書いたとしてもいいものが書けるということになる。そうではなく、ここはやはりその作家でなければ、そしてその作家が薬の支援を得て、自意識を捨ててでなければ書けなかった作品として珍重すべきだろうな』」(「猫が来るものか」)
この議論が正当なのか的外れなのか、ここでは問題にしない。指摘したいのは、この議論では「薬が作品を書かせる」ことを“否定はしていない”という点だ。ここでは、すぐれた作家が自意識を捨ててまで薬に書かされることに身を委ねた結果である作品の価値を認めよと主張されている。
では『朝のガスパール』で作者が新聞読者による投書やパソコン通信会議室のメンバーの意見によって物語を進める時、それは「読者が書かせたものに過ぎない」のか、それとも「作家」という「自意識」すら捨てて読者の意見を取り入れた希有な作品として珍重すべきなのだろうか。実際には、この侵犯を企図したのは作者だし、この作品は破綻ではなく古典的な大団円で終幕を迎えるのだから、麻薬に溺れた作家の作品とは全く同一に扱えないのではあるが。
『ダンシング・ヴァニティ』。これはいわば人生ゲームを小説で表現したかのような作品である。同じシーンを何マスか戻りつつ別の選択肢を選んで物語が進んでいく。同じようでいて少しずつ違う多元世界が選ばれていくのである。そして、最後に当然、ではサイコロは振っているのは誰なのかという疑問が湧くのだが、そのような問題意識が『虚人たち』のような作品を生んでいるのだろう。
『虚人たち』。
主人公はスパイであるといえる。「彼」は何らかの役割を与えられ、その場に存在を始めたらしいのだが、いったいそれが何かを周囲をさりげなく探索しつつ探り当て演技していかなければならない。「彼」は自宅の表札を盗み見て自分の性を知り、家の中を探索することで息子と娘がいるらしいことを知る。しかし、それは我々の生そのものである。生まれた瞬間に所与の条件はあるのだが、我々はそれを当初全く知らない。周囲の反応を探りながら自分が何者であるのかすら判断していかなければならない。
「デラックス狂詩曲(ラプソディ)」で直美によって複製されてしまった牧啓三も似たような存在だ。
「『ぼくは生まれたばかりだから、どうしていいかわからない。でも、あなたは何かの必要があって、ぼくを作ったわけでしょう。いいですよ。ぼくは、あなたのいうとおりにします』」(「デラックス狂詩曲(ラプソディ)」)
「彼はたちまち、何年も前から友達だったような口調で、ちっとも不自然でなく、なめらかにしゃべり始め」る。牧は一美の服装にまゆをひそめる。牧が選んだミニに対して「『よしてよ。はですぎるわ』と、一美がかぶりを振ると「『いいかい。きみはなんでも似合うんだ。ところがきみは今まで、じみなものばかり着ていた。それが似合っていたからだ』」と牧はいう。「『だからきみは、自分にははでなものは似合わないと決めてしまっている。固定観念といって、それはよくないことだ』」
これは興味深い発言だ。似合わないから着替えろではなく、似合いすぎるのでよくないと彼は言う。これはまるで『虚人たち』の「彼」が言いそうな理屈ではないか。
「スパイ図鑑」としての『俗物図鑑』
人間の醜さ、精神の汚物を見せられ続ける七瀬シリーズと異なり、『俗物図鑑』はむしろ体制に逆らう人間たちの陽気な、多幸感さえ感じられる小説である。七瀬は確かにスパイであった。身分を偽り、相手の秘密を覗き、気付かれないうちに相手を操っていた。
しかし、『俗物図鑑』にも多くのスパイが登場するというと納得がいかないかも知れない。『俗物図鑑』は確かに「スパイ小説」でない。ただし「スパイ図鑑小説」ではある。
梁山泊に集う彼らはほぼ全員スパイとしての素質を持つ。
まず、風巻機工社長の風巻扇太郎。彼は盗聴が趣味だ。
扇太郎は会議から解放されて社長室に戻る。「『さて。精神浄化が必要だ』彼はそうひとりごちながらデスクの抽出しをあけ、携帯ラジオのような機械をとり出し、ダイヤルをまわしはじめた」彼は社内のあちこちにマイクを仕掛け、社員のだれかれの噂話や他愛ないおしゃべりを社長室で盗聴していたのである。「おれはマゾヒストかもしれんぞ」と思いながら彼自身の悪い噂話さえも楽しむ。
梁山泊の管理人城亀吉は盗視が趣味。
城は一仕事終えると合成皮革のジャンパーに着替える。天井裏を這いずりまわる時のノイズを防ぐためである。大学も卒業し手に技術もあり、もう少しは収入のいい職業を選ぶことも可能なのに安月給の管理人に甘んじているのは窃視がやめられないからである。
羽根田俊也はある理由から時限爆弾制作の手練れとなる。
風巻機工営業第二課長雷門亮介の息子豪介はカンニングで大学に合格したという。彼は、消しゴムに切りこみをつくりマイクロ・フィルムを仕込み、それを特殊な眼鏡で読む。また鉛筆には小型マイクが仕込んであり外部の人間とラジオでやりとりする。
亮介自身は接待する相手の好みを敏感に察知し気持ちよく酔わせて商談をまとめるプロだし、しばしば脛に傷持つ人間が身分を偽って蒸発するための手伝いをする。
亮介の部下の小口昭之助は亮介の命を受け社長の身辺を調査する。また口臭で相手の体調を見抜く。これもあるいはスパイに役立つ能力かも知れない。
同様にスポーツ紙の記者片桐は嘔吐した吐瀉物でその人の年齢・職業・性格・体調を当ててしまう。実際、スタジオでその技能を実演もする。当人の気付かないうちに情報を入手するのがスパイである。
後に贈答品研究家になる亮介の愛人であり営業庶務の平松礼子は一見スパイ行為とは無関係なように見える。だが、彼女が会社のお歳暮会議で「お歳暮は平凡なものがいい。たらいまわしにされたら誰にどの程度のものを送ったかがばれてしまうから」という亮介に対して「得意先の誰が誰のところにお歳暮をたらいまわしにするかをあらかじめ予測して相関関係を把握しておけばばれない」と言っていることに注目すべきだ。彼女は、自分に任せてもらえばお歳暮のたらいまわしによる情報の漏洩を完全に防げると豪語する。贈答とは企業における情報戦なのだ。
ガンマ・ジーゼルの本橋浪夫は、その明るい人柄に似ず、横領の手口に長けていて、自ら所属する組織を裏切ることをなんとも思っていない人間だ。
歌川華子は密かに性病に感染しておりハニー・トラップを仕掛けることで、それを男どもに感染しまくっている。それでも、まさか育ちもよく美しい彼女から性病が感染されたとは誰も気づいていない。
全身皮膚病の芥山虫右衛門。彼は一見スパイらしくはないが、単に襲撃してくる敵撃退用の秘密兵器ではなく、彼も立派なスパイである。何故なら、皮膚病は歌川華子同様見えない菌をいつのまにか他人に感染させて人を陥れるものだからだ。実際『馬の首風雲録』でアカパン党の露営地に紛れ込んでしまい縛りあげられていた絶体絶命の三人を救ったのはミシミシの伝染性皮膚病だったではないか。
沼田峰子は盗み。ただしよく捕まるのであまり腕はよくないらしい。
火事評論家の亜香は放火魔でスパイとは無関係のようだが、物語の最後の方で亜香は警察署に侵入して焼け落し一矢を報いる。彼女も優秀なスパイだ。
西条機械の西条圭一はパーティ評論家でスパイとはいえない。しかし、彼は参加者全員が楽しめるようなパーティを企画するのが得意だ。彼はパーティに集う人びとをじっくり観察し、その心の内を読もうとする。
雷門亮介は、まるで会社員時代に得意先に最適なお歳暮を割り振っていた頃のように、集まったスパイたちを梁山泊の各部屋に割り振る。彼の手により「スパイ図鑑」が編纂されていく。
(つづく)
2020.12.29 初出
2020.12.30 一部修正・加筆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
