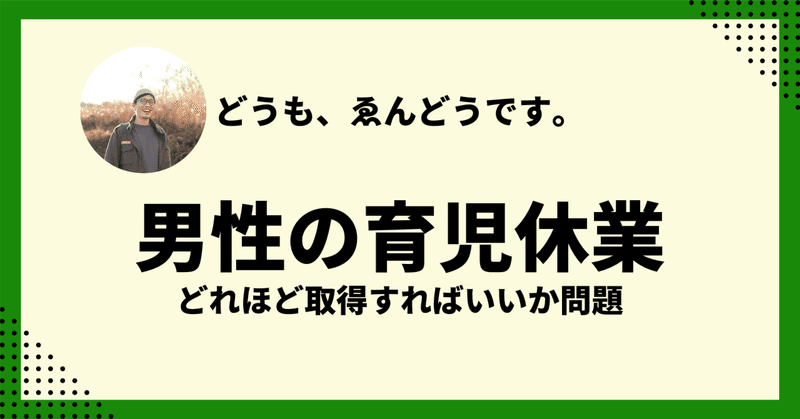
男性の育児休業を取得すべき期間についての一考察
みなさん、経団連ってご存知ですか。
正式名称を「一般社団法人 日本経済団体連合会」といいますが、この団体、何をしているのかというと、日本の産業と経済の発展を促進するための政策提言を行い、企業活動に対する理解と支持を広めることだとされています。
時の政府が経済に関わる政策を決める際には意見を出しますし、経団連に所属するメンバー企業に経済情報を提供。所属する企業間での協力を促すこともあれば、法人として社会貢献活動を行うなどする組織です。
その一環として、『「男性の家事・育児」に関するアンケ―ト調査結果』(調査対象は経団連企業会員1518社で、278社が回答。)なんてものがありましたので、そちらを眺めてみたんですよ。
そこから、男性の育児休業における取得期間ってどれぐらいが適当なんでしょうね…なんてことを考えてみたので、お付き合いいただける方は読み進めていただけますでしょうか。
どうも、ゑんどう(@ryosuke_endo)です。
男性の育児休業取得率は上昇中
今回、覗いてみた経団連のレポートをみてみると、経団連に所属している企業では、男性の育児休業率が上昇傾向にあるそうだってことがわかります。しかも、伸び方がすごい。2021年は29.3%だったのに対し2022年は47.5%と、10%以上もの伸長度合い。

これだけを見れば「男性も育児休業が取りやすくなってきてるんだなぁ…」とか「いよいよ会社側も少子化への危機感を抱いてるだけでなく、課題感と当事者意識を持ちはじめたんだなぁ...」みたいに思えるかもしれません。
法整備されたことも大きく影響しているであろうことから、取得対象となる従業員のうち、半数近くが取得できる状況にあることは好意的に捉えてもいいのかもしれません。
が、所属企業のうち、調査対象が1518社あったのに対し、回答しているのが278社、そのうち育児休業が取得可能な人材がいる企業に絞ると198社とあります。

残りの1000社以上はどうしたんだいってのと、そんなに取得対象者っていないものなのかいってことが気になってしまった次第です。まぁ、はい。
企業側も積極的に取得を促す取り組みを行なっている
企業側は企業側でいろいろな工夫を凝らしながら男性従業員に向けて育児休業の取得をさせるような取り組みをしているそうです。
以下、ズラーっと並べたうえでコメント入れていくようにしてみます。

経営トップから直々にメッセージを送付することで、プレッシャーを与えるってことが一番目に登場するあたり、なんだか日本っぽくて笑えてしまいますが、そうじゃないと取得しないってことなんでしょうね。
上司から直筆のメッセージなんてものもありますが、直筆だろうがメールだろうが口頭での説明だろうが、いずれにせよ組織内ヒエラルキーの上位層が当該従業員に向けて圧をかけることこそ、社畜のみなさんを育児に意識を向けさせるうえでは必要なことなんだってことがわかりました。

出生の申し出があった従業員に向けて2ヶ月ほど経過した段階で育児休業の取得を推奨し、取得しないのであれば理由を確認するといった取り組みをしている企業もありました。
この企業、かなり一生懸命じゃないですか。
「あ、この人、出生届出してから2ヶ月経つのに取得してない。取ってもらわないとなぁ…ねえねえ、〇〇さん、育休、取得しなよ。え?取得しないの?なんで?どうして?」
こんな感じでコミュニケーションをしてくれるんですよね。すごくないですか。ちょっと詰められてる感があるため、ボクとしては詰められる場面を想起してしまうために少しツラくなってしまいますが…。

あとは雰囲気づくりを懸命にやったりするところもあるそうで、何をしているのかと覗いてみると「男性社員の育児休業1ヶ月取得推進、取得率100%を目指す」ことを人事部長名で通知、とかあります。
これはもうかなりの圧ですね。下手したら、取得していない部署や課は吊し上げにあう可能性すら透けて見えてきますが、それだけ懸命に啓蒙しないとダメなのかもしれません。

中には、1ヵ月以上最大3ヵ月までの育児休業に対し、「育児休職支援手当」を支給といった形で、お札でほっぺたを叩きながら育児休業の取得を促す動きもあります。
目にみえるお金ではなく、年次有休制度を特例的に運用するって形で運用しているところもあるそうですから、会社員側からすると非常に喜ばしい状況であるといえるのかもしれませんね。

とはいえ、育児休業を取得する人がいるってことは、その代替要因を見つけなければならないって台所事情もあるでしょうから、それに向けた対策も講じる必要があります。
派遣社員や友章契約社員の受け入れってところが現実的なところなのかもしれませんが、『育児休業取得者が増加することを前提とした新卒・経験者採用の拡大』なんてのもありますから、これは応援したいところです。
適当な取得期間はどれぐらいなんだろう
さて、本題です。男性の育児休業期間はどれぐらいが適当なんでしょうか、と。
経団連の調査に協力した企業で、取得した人たちの実数を見てみると43.7日が平均となっていますが、取得日数が多いのは5001人以上の規模を保有する大企業が多く、300人以下の小規模事業者は5日未満が約半数の46.2%となっています。

もう、なんていうか平均って数字の出し方やめてよって思うような結果で、残念な気持ちが胃の奥底からため息として出てきそうになりました。
まぁまぁ、いいでしょう。平均取得期間が40日以上ありますね、と。女性はどうでしょうか。女性は367.1日が平均となっていますから、実に9倍。うん、知ってた。知ってたよ。わかってたけどさ。

もちろん、女性の方が長期化しやすいんでしょうよ。
身体的なものもあるでしょうし、心理的にもかわいい子どもの側にいたいってこともあるでしょう。
でも、余りにも差がありますよね。ボク自身、育児休業なんて取得してきませんでしたから偉そうなことはいえませんよ。だけれども、この差ってのは本当に大きなものだよなって実感する毎日なわけです。
不登校な長男くんがいるからってのもありますが、在宅で仕事をすることによって育児休業を取得できなかった期間の補填をしているとも言えるわけですが、そうでもしないと妻さんとの平衡性が成り立ちません。
「下手に何もできない人間が増えるんだったら、自宅にいてもらったら逆に迷惑だ。」
育児休業について妻さんに意見を求めたら、そんな風に辛辣な意見が返ってきたのですが、適当な取得期間ってのは男性と女性の取得期間が同等になることなんだろうってことは3名の子どもと暮らす人間としての実感値です。
40日を多いと捉えるのは、子どもとの生活にコミットメントしていない人たちの価値観であり、いつ死んでしまうのかわからない乳幼児を相手にしている側からすると、そんな「育児体験」なんかいらないってのが本音でしょう。
ありがたいんでしょうけどね。
おわりに
結局、男性が取得することがいいのか悪いのかはわかりませんが、取得することを制度などで仕組み化して強制的に取得する方向で進捗しなければならないであろうことと、取得期間は女性と同等にならないとダメなんだろうってことがわかりました。
「いやいや、現実的に無理でしょ」とかいってくれる人もいるでしょうが、だったら女性が367.1日も取得していることはどう説明するのかって話になります。
「自分でなければできない仕事があるんだよ」とかいう人もいるのかもしれませんが、仮にそうだとしたら会社が会社として機能していないってことになるじゃないですか。
子どもと過ごすってのは本当に簡単なことではないわけですが、仕事が好きなんだったら好きだっていえばいいのにねぇ…なんてことを思う、嫌なヤツでございました。
ではでは。
ゑんどう(@ryosuke_endo)
#えんどうnote 、マガジンでフォローすると通知が届くのでオススメです!
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
