
Twitterとイーロン・マスク @elonmusk と匿名アカウントと
ようこそ、お越しくださいました。
どうも、えんどう @ryosuke_endo です。
実業家で野心家、かつ革新者であるイーロン・マスクが全Twitter廃人たちの夢であるTwitter社買収をやってのけた。しかも非上場化ときたものだから、媒体社特有の収益化云々に悩まされることもなく、それによって株主への説明責任に晒されることがなくなることになった。
ぼくも基本的に...というか、そもそもTwitter廃人側の人間でもあるため夢を感じただけでなく、どこかしら勇気を分け与えてもらった気分にもなっている。
佐々木俊尚さんが以下のように解説をする記事を書いているため、詳細を確認することも含めてチェックしてみてほしい。
ツイッターの「ビジネス」と「言論の自由」はどう変わるのか?
Twitterがどうなるんだろうっ話はぼくみたいな愚鈍な人間が考察したところで蓋を開けてみたら...みたいな話になりかねないので、匿名アカウントの方々の悲鳴を目にしたことを受けての主観を書いてみる。
▶︎ 2chの代替となったTwitter
日本のTwitterユーザーは実名アカウントよりも匿名アカウントの方が多い。
以下はTwitter内に投稿されている報道番組の内容を咀嚼したものを投稿されているのだが、結果を見れば分かる通り匿名アカウントの比率が飛び抜けて高い。
マスク氏、全ての個人を認証したい、
— たらお (@tarachannnew1) April 28, 2022
と仰っているようだが、Twitter匿名性なくなったら誰が使うん??と
思ったが、匿名でTwitter使うの日本人だけでワロタ pic.twitter.com/8OUdhR9z9f
おそらくだが、Twitterが2006年、Facebookは2008年に登場し、それぞれ2008年に日本語にローカライズされてリリースされたことから、徐々に2ちゃんねるユーザーが移行していったとみられている。
ところが、Facebookは実名登録が前提となるため、2ちゃんねるユーザーにとって「好き勝手書ける場所」ではなかったことから、その代替手段としてTwitterを利用する人たちが増えたとみている。
ところが、2ちゃんねるの場合、「ソース出せ」や「根拠は?」といった形でデマやウソを厳しく取り締まる文化があったものの、Twitterではユーザー数の増加とともに見る影も無くなってしまうことになった。
2ちゃんねる自体は5ちゃんねるとして残っているものの、多くのユーザーは他の媒体を重ねて利用しつつ、それぞれのレイヤーに合った投稿を行なっているのが2022年現在の標準仕様なのだろう。
▷ 匿名ユーザーの筋違いな悲哀
今回のイーロン・マスクによる買収を受け、匿名アカウントがどのような投稿をしているのかというと、割とネガティブな投稿をしていることが散見される。
例を挙げると以下のようなものだ。
学校でいじめられる
会社を辞める羽目になる
脅迫される
自宅が晒される
下手したら殺害の可能性も
一体、どんな投稿をしているのか気になってしまうが、どうやら匿名だから好き勝手に投稿をしていいと思う人は一定数いて、その人たちはネット上の行動が実名と結びついてしまうと不利益を被ると思っている、なんて図式だ。
匿名を安全地帯だと思い込んでいる時点でネットについてググるなどして研鑽を重ねてほしいものだが、匿名だからといって誹謗中傷をおこなっていいわけでもないし、それによって起こされた訴追を逃れることもできない。
春名風花さんのTwitter上での誹謗中傷を受けて行われた裁判は、はるかぜちゃん側の勝利といえる示談金額で成立していることからも分かる通り、匿名=安全地帯でもなければ、匿名だから何でも投稿していいというわけではないことは知っておくべきだ。
▷ ネットで健全な言論空間は可能なのか
匿名アカウントによって救われている感情があると投稿している人たちも一定数いるのは事実だ。
「素直に気持ちを投稿できる」「実名では投稿できない趣味や関心について気軽に投稿できる」といった投稿があるように、彼らにとって物理的な人間関係に影響を及ぼしかねない自身の思考や性癖など、実名になると投稿できないという。
投稿しなければいいではないか。
そもそも趣味や嗜好ならまだしも、性癖なんてものは他人に晒すものでも何でもない。それを晒したいとか承認欲求を得たい、なんてのはあまりにも下品である。
そもそも物理的な人間関係の間で趣味嗜好性癖といった事柄を会話に盛り込まない、もしくは親密な関係になった人たちの間のみで行われる限定的な会話内容であることを踏まえると、それ以上でもそれ以下でもない。
ネット上で健全な言論空間を構築していくためには、村文化や井戸端会議といった根暗な性質を持った人たちの寄合をなくす方向に舵を切らなければならないわけだが、そういう意味でも差別や偏見や誤解によって他人の尊厳を傷つけるような物言いが実名かによって避けられるのなら、それ自体が健全化にとって大きな一手ではないか。
▷ TwitterはメディアであってSNSではない
Twitterのアプリ分類は「ニュース」であり、初期の日本で他の媒体で紹介される際には「140文字のミニブログ」と紹介されていた。
いつの間にかFacebookのような他者との関係を構築するサービスであるSNSと混同されてしまっているが、Twitterは媒体としての価値のある歴としたメディアであって、他人との関係を構築するものではない。
他人が発する投稿内容をニュースソースとして取り上げるのは、それが媒体としての特性を他の報道各社が認めているからで、それこそTwitterの目指す立ち位置なのだろう。
しかし、例によってメディアは金銭を獲得することが難しく、金銭を獲得することが難しい以上は運営することも難しい。結局、広告による収益を立てようと躍起になるものの、TwitterはFacebookなどと比較して広告収益によって運営を安定させるほどには至っていない。
本音をぶちまけるのが自分以外の他者にとって価値があるのかどうかは、実名であるかどうかに関わらず他者が判断するものだ。
Twitter内でウケる投稿は、誰が述べているのかも大事だが、コンテンツが有益であるのかどうかも大きい。根本的にはそれなわけだが、炎上などに際しては「誰」という形で人が全面に立つ。
このことからもTwitterがメディアとして機能していることの証左だとは思うし、実名化によって汚い言説や醜い他者への誹謗中傷などが減るのであれば、大いに賛同したいところだ。
実名と顔出しで物理的に対面した際にいえないことはネット上であろうがいうべきではない。この点に尽きるだろう。
ではでは。
えんどう
▶︎ おまけ
▷ 紹介したいnote
大事なことはTwitterには書かれていない
“Twitterは、距離がわからなくなるツールだ。”この一文を上記の匿名アカウントを残したい人たちにぶつけたいものだ。物理的な距離感が測れない、もしくは測りたくないと思っているから匿名で好き勝手投稿できると勘違いしているのだろうが、そうではない。
Twitterライフが辛いときの処方箋
ある程度、各種ソーシャルメディアとの距離をとることは重要なことだと思っている。ぼくも過去にメンタルが崩壊していた時期があったものの、その時には各種媒体を覗くことはなかった。そのおかげで自分がどうありたいのかを冷静に考えることができたし、今でもたまにスクリーンタイムを減らすようにしている。
第552回:WEB3.0、宇宙産業、イーロン・マスクとTwitter
マスク氏のTwitter買収に融資をしたのが、実は日本の地銀であるとかって可能性があればワクワクする。低金利であることを全面に押し出しつつ、マスクみたいな経営者とのパイプが作れるような地銀があるのかどうかは知らないが。
▷ 紹介したい関連書籍
レイヤー化する世界 テクノロジーとの共犯関係が始まる (NHK出版新書)
佐々木俊尚さんの書籍だが、今の若い人たちがLINEによって各種レイヤーを渡り歩きながら処世している様子を2013年の時点で書籍として記載されているもの。
▷ えんどうのTwitterアカウント
僕の主な生息SNSはTwitterで、日々、意識ひくい系の投稿を繰り返している。気になる人はぜひ以下から覗いてみて欲しい。何ならフォローしてくれると毎日書いているnoteの更新情報をお届けする。
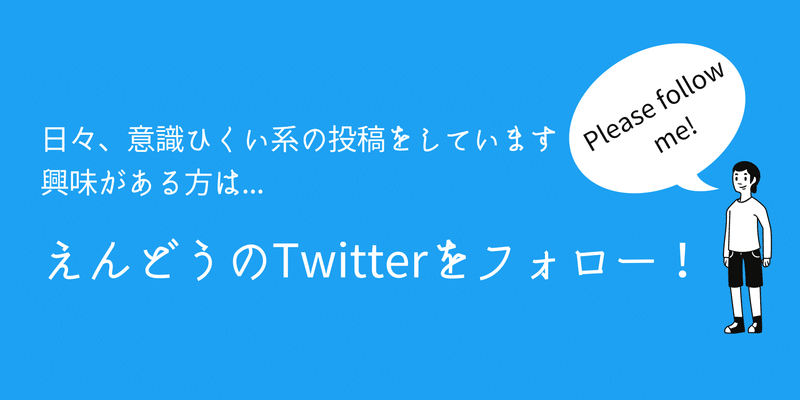
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。 お読みいただき、それについてコメントつきで各SNSへ投稿していただけたら即座に反応の上でお礼を申し上げます!
