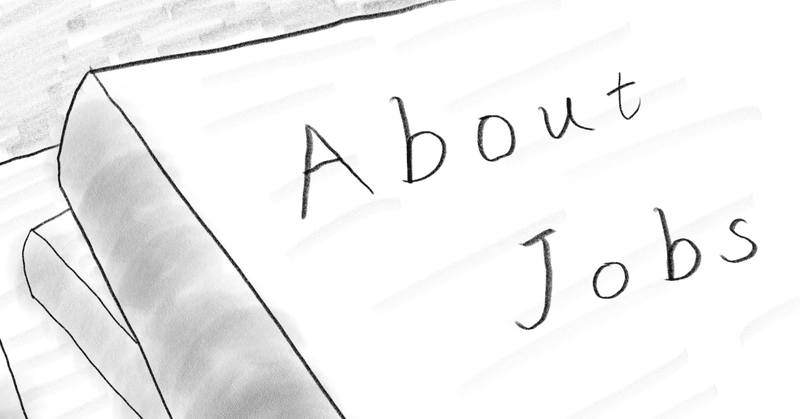
米労働市場の需給逼迫には薄日も~労働参加率の改善にも着目~
あと半年で完全復元?
2月4日に公表された米1月雇用統計は非農業部門雇用者数(NFP)変化に関し前月比+46.7万人と市場予想の中心(同+12.5万人)を大幅に上回りました:
失業率は3.9%から4.0%へ上昇しているものの、後述するように労働参加率が明確に上昇しており、労働の需要(求人)よりも供給(人手)が増えないことに悩んでいる米経済にとっては「良い失業率上昇」と言えます。これでパンデミックにより失われた雇用は最悪期の▲2000万人超から▲287.5万人まで縮小しています:

業種別の復元状況を見ると、職場離脱が相次ぐ医療・社会福祉や行動規制の影響を最も受ける宿泊・飲食でも8割弱、それ以外では8割強が喪失した雇用を復元しています。NFPは振れを伴いながらも+50万人前後の増勢は維持しておりますので、あと6か月もあれば失われた雇用は完全に復元されることになるでしょう:

こうした中、雇用・物価情勢に照らし、FRBが正常化を検討すること自体は自然な展開と言えます。
1月ADP雇用統計が前月比減少という衝撃的に悪い内容だったこともあり、今回の雇用統計に関しては発表前から米政府高官が単月の結果に狼狽すべきではないと市場の警戒ムードに異例のけん制を行っていました:
蓋を開ければ強い内容であり、3月FOMCの+50bps利上げも本稿執筆時点で3割程度織り込まれております。これに合わせ米10年金利は遂に1.90%台に乗せ、実質30年金利のプラス圏復帰など、市場は正常化プロセスの加速に態勢を整え始めています。為替市場も素直にドル高・円安で反応し115円台に乗せており、1~3月期中の年初来高値更新は十分あり得る話です。
「労働供給の復調」も進んではいる
非常に厄介なことですが、今回は「強い結果→米経済の力強さを確認→インフレ懸念→タカ派観測の強まり」という受け止めが拡がりましたが、一方で「弱い結果→労働需給ひっ迫→インフレ懸念→タカ派観測の強まり」という理解もまかり通るのが現状です。目下、米国経済が直面しているのは「労働需要>労働供給」による賃金上昇なので、今回のように強い結果ならば「強い結果→労働需給の不均衡解消→インフレ懸念後退→タカ派観測の弱まり」という期待の修正が進む可能性もあったはずです。
しかし、実際は景気の強さを理由に「労働需要の強まり」だけに焦点が当たり「労働供給の復調」には目が向かいませんでした。市場はやはり賃金を見ているのでしょう。1月の平均時給は前年比+5.7%と2020年5月以来の大幅な伸びを記録し(図)、これが労働需給の不均衡拡大を印象付けたと言えます。3月の50bps利上げシナリオもこうした賃金動向を踏まえてのものでしょう。賃金主導の一般物価上昇は持続性を伴う恐れがあるものです:

長期失業者割合は顕著に減少中
もっとも、労働供給に薄日が差し込んでいることも事実です。1月は労働参加率が前月比+0.3ポイントの62.2%と顕著に上昇しました。労働参加率が最後に62%台をつけていたのは2020年2月、すなわちパンデミックにより雇用市場が崩壊する直前であり、徐々に正常な姿には近づいていると言えます。労働参加率が十分に上昇すれば、低い失業率とインフレ率の低下が両立し、身動きが取れない現状を打破することに繋がります。さらに、失業期間が27週間以上に達している長期失業者の割合も顕著に下がっています:

長期失業者は就労意欲の低下などを通じて労働市場から退出する予備軍と見なされ、目先の人手不足はもちろん、労働投入量減少を通じて一国の潜在成長率低下にまで至る話です。長期失業者割合は1月時点で26%でしたが、これは前回利上げ着手となった2015年12月(27%)を下回っています。
パンデミックにより大きな穴が開いた米国の労働市場ですが、遅々たる歩みながらもその穴は着実に塞がりつつあるのも事実でしょう。米国の労働者が求人に応じない(応じられない)背景にはワクチン接種を忌避したり、感染懸念から対面接触型の職場復帰を拒んだり、もしくは移住してしまったりする層など、パンデミック特有の要因が存在すると言われます。
しかし、理由はどうあれ労働市場に復帰しなければ多くの人は生活ができません。株や不動産が上昇し(沢山の純資産を抱えるようになったので)労働意欲がなくなった層も労働参加率低下に寄与したとパウエル議長は12月に言及していましたが、それが多数派ではないでしょう。
上述したパンデミック関連の要因は時間が解決する話と考えられ、労働需要の大きさになびくようにいずれ労働者は戻ってくると期待されます2019年12月時点の労働参加率が63.3%であったことを踏まえると、労働需給のひっ迫解消には(最低でも)あと1%ポイントほどの復元が必要なイメージが抱かれます。通常、労働参加率は非常に緩やかにしか変化しないため1%は小さな数字とは言えません。
しかし、パンデミック特有の要因が剥落する中でこれまでよりも幅を持って改善する可能性もあるでしょう。例えば2020年4~6月期だけで▲6.3%ポイントが低下するという断層が生じた経緯がありますし、今回1月分の改善を見ても55歳以上は+0.6%ポイント(38.5%→39.1%)と急改善していることが目を引きます。今後の回復過程も通常より幅を持って構えるべきでしょう:

NFPの前月比変化や平均時給の動きは元より、今後は労働参加率も重要な計数として目が離せなくなっていると言えます。その点では改善の兆候が見られることも知っておきたいところではあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

