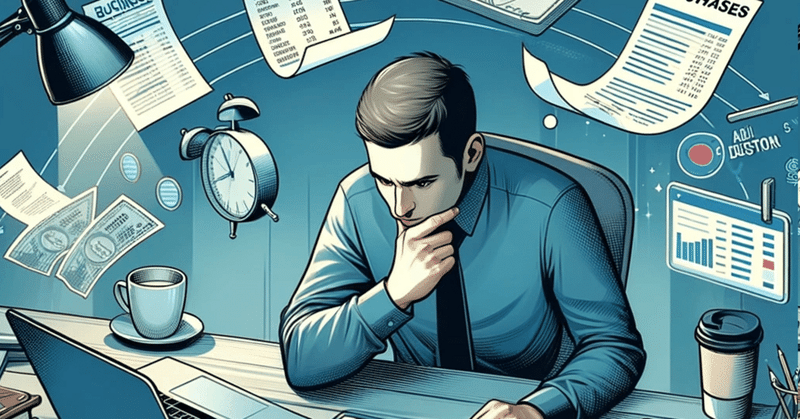
382 売り手市場
はじめに
大学、短大、専門学校などを卒業予定している学生の就職内定率が発表されましたが、歴代でもトップクラスの高さということですから、まさに売り手市場ということになります。
今日の教育コラムでは、空前の売り手市場に見えてくる教育のある側面について少しお話してみたいと思います。
売り手市場とは
まずは、売り手市場とはどのような状態なのかを簡単に整理してみます。高度経済成長期などに顕著に見られたこの現象ですが、現在は少子高齢化に伴う労働力不足が売り手市場を作り出していると考えてよいでしょう。
売り手(供給)よりも買い手(需要)のほうが多い状態なわけですが、 学生にとっては安心して就職活動ができる状況には間違いないでしょう。
新卒採用の就職活動に失敗するとその後の人生も大きく変わってきます。ですから、売り手市場のように就職したい就活生よりも、採用したい企業の数が多い状況の方ができるだけ自分の希望の職種や企業を選択することができます。
この就職活動で取引するのは、「労働力」なので、売り手は学生、買い手は企業にあたります。つまり、買いたい人が多いので強気で売れるわけです。勝手な印象ですが、就職氷河期のような圧迫面接も少ないでしょうし、倍率も軽減されているので精神的な負担も低いのではないかと思えます。
親も一緒に会社見学
売り手市場の現状において、いかに新卒者の内定を確かなものにしていくか、企業は様々な方法でその獲得に動いています。いくつかの企業の取り組みを見ていく中で、私が驚いたのは子どもが内定をもらった会社に親が同伴で見学や説明を受けに行き、そこで就職を決定するという取り組みでした。
一緒に同伴している保護者が、会社の様子や条件などを判断し子どもの就職先を決めていくというわけですから、私個人としては想像しにくい世界です。
こうした取り組みの背景には、本人は入社を希望したが、親が反対したために内定者が、別の内定を得ていた企業に就職したという事例があると言います。
過干渉
過干渉という言葉がありますが、そのとらえ方は人それぞれだとは思いますが、私個人的には子どもの就職にまで強い決定権を持ち接するのは過干渉ではないかと思ってしまいます。
親が子どもの行動や人生に対して過度に干渉する場面は、教育の現場ではよく目にします。過干渉の意味や子どもに与える影響を理解していない人は、無意識に子どもの視野や将来性を狭めてしまっていることを認識する必要があります。
親は心配で口を出しているようにも思えますが、実は自分の理想に近づけることで得られる達成感や満足感にとらわれている可能性があるのです。これを別の言い方で言えば、「見栄」「権威」などを得るための行動とも言い換えることができるのです。
受験でも、進路選択でも普段の定期テストに対する意識の持ち方でもそうですが、当事者ファーストを横に置き過干渉を発揮すると間違った方向へ流れていきます。
売り手市場の日本において、自らの夢や目標を実現することのできる会社を選びやすい環境にあっても、親と相談して仕事を選ぶ若者が多いことは、皮肉ではありますが、今日の教育のある意味での"賜物"と言えるのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
