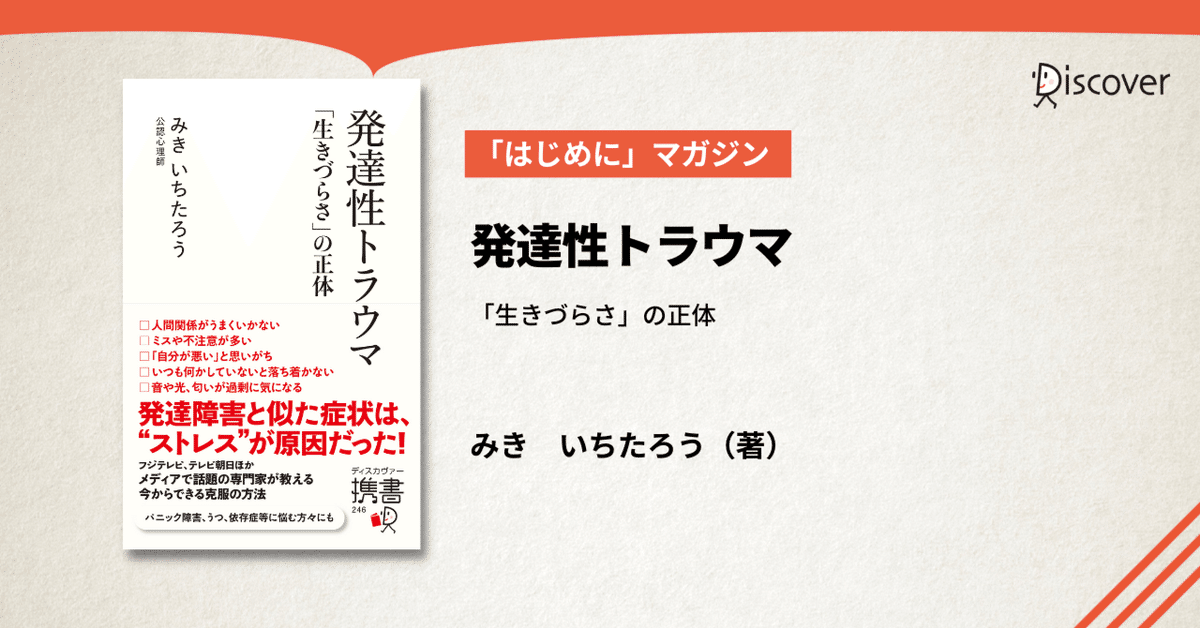
【6月16日限定】kindle日替わりセール!『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』試し読み
2023年6月16日限定で『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』がkindleで日替わりセールを実施します。
通常価格1,200円→キャンペーン価格399円の超お得なセールです!
本記事では対象書籍の「はじめに」を試し読みいただけます。
はじめに
眞子さまの診断名「複雑性PTSD」とは
2021年10月1日、ご結婚に関して、執拗な報道やバッシングにさらされていた眞子さまが「複雑性PTSD」と診断されたと宮内庁から発表がありました。おそらく、多くの一般国民にとっては「複雑性PTSD」という診断名は記憶には残らず、よくわからないけれど心身のご不調に対して診断がくだされた、と受け取ったのではないでしょうか。
いわゆる「PTSD(Post Traumatic Stress Disorder:心的外傷後ストレス障害)」が、災害など主として一回の出来事から不調をきたすのに対して、「複雑性PTSD(Complex PTSD)」とは繰り返し強いストレスにさらされることで心身に不調をきたすことをいいます。ジュディス・ハーマン(Judith Lewis Herman)という精神科医が提唱し、紆余曲折がありながら最近ようやく公式の診断基準として認められたものです。
私は、トラウマや愛着障害を専門にしている公認心理師ですが、今回のニュースに接した際、画期的な診断であると感じました。
専門家の中には、この診断名に異論もあるようです。おそらく基準通りであれば、「適応障害」か「うつ状態」などと診断されたことでしょう。公式の基準では、命の危険にさらされるようなストレスや症状が複雑性PTSDの対象とされているからです。
ただ、診断名とは本来、適切な治療につなげるために付けられるものです。「適応障害」などの診断名が付いていた場合と「複雑性PTSD」とでは、伝わるメッセージが全く異なります。
第2章でも触れますが、もし「適応障害」と診断されたとしたらどうだったでしょう。「適応障害」もストレス関連障害ではありますが、診断名の印象から眞子さまご本人に責任が帰せられ、存在が脅かされるほどの重大な問題であることは曖昧になってしまいます。また、マスコミ報道や世論のあり方に警鐘を鳴らす効果も失われたと思われます。
さらに、眞子さまのように、ハラスメントなどによって周囲から急激に責められる、孤立した状況に陥る、といったことは誰の身にも起こり得ます。特に幼い子どもにとっては家族や学校は世界そのものです。そうした日常で起こる生きづらさに悩む人たちにとっても、今回の診断は大きな意味を持つと考えます。
「発達性トラウマ」は複雑性PTSDの原因でもある
もう一つ、今回の診断が画期的だと感じるのは、複雑性PTSDが本書のテーマである「発達性トラウマ」と関係があるためです。
あなたは本書のタイトルでもある「発達性トラウマ」という単語を見てどのようにお感じになったでしょうか?
「発達性? 発達障害というのは聞いたことあるけどな」「トラウマという言葉が付いているのはどういうことだろう?」など、人によって様々ですが、何か関心を引かれるものがあったことと思います。
「発達性トラウマ(Developmental Trauma)」とは、複雑性PTSDの原因となる子ども時代に負ったトラウマのことです。
子どものころに家庭や学校などで負った慢性的な(反復性)ストレスが複雑性PTSDの原因であることがとても多いのです(もちろん、眞子さまのように成人してからのストレスも同様に複雑性PTSDにつながるトラウマの原因となります)。
そのため、発達性トラウマは、私たちが抱える生きづらさの原因を明らかにするものとして近年注目されています。複雑性PTSDという診断が公になされるようになったということは、あわせてその要因である発達性トラウマについても今後広く知られるきっかけとなると考えられます。
トラウマ研究の第一人者であるベッセル・ヴァン・デア・コーク(Bessel van der Kolk)は『身体はトラウマを記録する』(紀伊國屋書店)の中で、「私たちの社会は今、トラウマを強く意識する時代を迎えようとしている」と述べています。
これはトラウマという概念が、ただいたずらに拡大解釈され適用されていく、ということを意味しません。そうではなく、様々な研究から明らかになったことを受けて、私たちが人間らしく生きるための要件とは何か、そしてそれを破壊するものとは何かを捉え直す時代が来た、ということではないかと思います。
その「生きづらさ」は発達性トラウマから来ているのかもしれない
トラウマ研究は、強い忌避感や無関心などからその歩みは決して順調とはいえませんでした。複雑性PTSDも発達性トラウマも認知されるまでに長い時間を要しました。そんな中でも近年急速に研究が進み、トラウマは身近に扱えるものになってきたと感じます。
トラウマ研究が足取り重く進んでいる間に、生きづらさを説明する言葉としてアダルトチルドレン、パーソナリティ障害、発達障害、新型うつ、HSPなどといった概念がその代わりを務めてくれていました。ただ、それらは「なんとなくそうだが、すべてを説明してくれていない」「名前が付いて安心するけれど、個別の当事者の解決策には必ずしもつながりにくい」といったものでもありました。そのために、次々にいろいろな概念が生まれては消費されてきたともいえます。
結論から言えば、「発達性トラウマ」あるいは「トラウマ」という概念から生きづらさを眺めてみると、多くのことが了解でき、適切なケアにつながっていくことがわかります。これまではトラウマというと、戦争や災害、レイプといったある限定された状況による症状(PTSD)というイメージでしたが、そうしたものとトラウマの全貌は異なります。
京都大学人文科学研究所の立木康介教授も、論文(「トラウマと精神分析」『トラウマ研究1 トラウマを生きる』(京都大学学術出版会))の中で「一部のタイプの『トラウマ』のみが診断学的に、あるいは治療上、特権的な地位を享受しているようにみえる」「PTSDを特権化する一部の言論によってともすれば忘れられたり、その背後に隠れてしまったりする種類の『心的外傷』に、あらためて光を当てることが重要なのだ」としています。その光を当てる対象とは「日常風景といってもよい外傷」や、「家族の言説のなかにタブーとして存在し続け、間接的に、主体に対して持続的な影響をおよぼすような外傷」と表現しています。
本書では、近年の知見や私自身の現場での経験・体験をもとに、読者が感じているかもしれない生きづらさを、トラウマ(発達性トラウマ)という視点から照らしてみたいと思います。
続きが気になる方は
kindleにて6/16限定で399円セール実施中です。
目次
第1章 この「生きづらさ」はどこから来るのか?
第2章 トラウマをめぐる経糸と緯糸
――“第四の発達障害”を生む発達性トラウマ
第3章 トラウマがもたらす“自己の喪失”と様々な症状
第4章 トラウマを理解する
――ストレス障害、ハラスメントとしてのトラウマ
第5章 トラウマを克服する
著者について
みき いちたろう 三木 一太朗
公認心理師。大阪生まれ、大阪大学文学部卒、大阪大学大学院文学研究科修士課程修了。在学時よりカウンセリングに携わる。大学院修了後、大手電機メーカー、応用社会心理学研究所、大阪心理教育センターを経て、ブリーフセラピーカウンセリング・センター(B.C.C.)を設立。トラウマ、愛着障害、吃音などのケアを専門にカウンセリングを提供している。
著書に『プロカウンセラーが教える 他人の言葉をスルーする技術』(フォレスト出版)がある。
雑誌、テレビなどメディア掲載・出演も多く、テレビドラマの制作協力(医療監修)も行なっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
