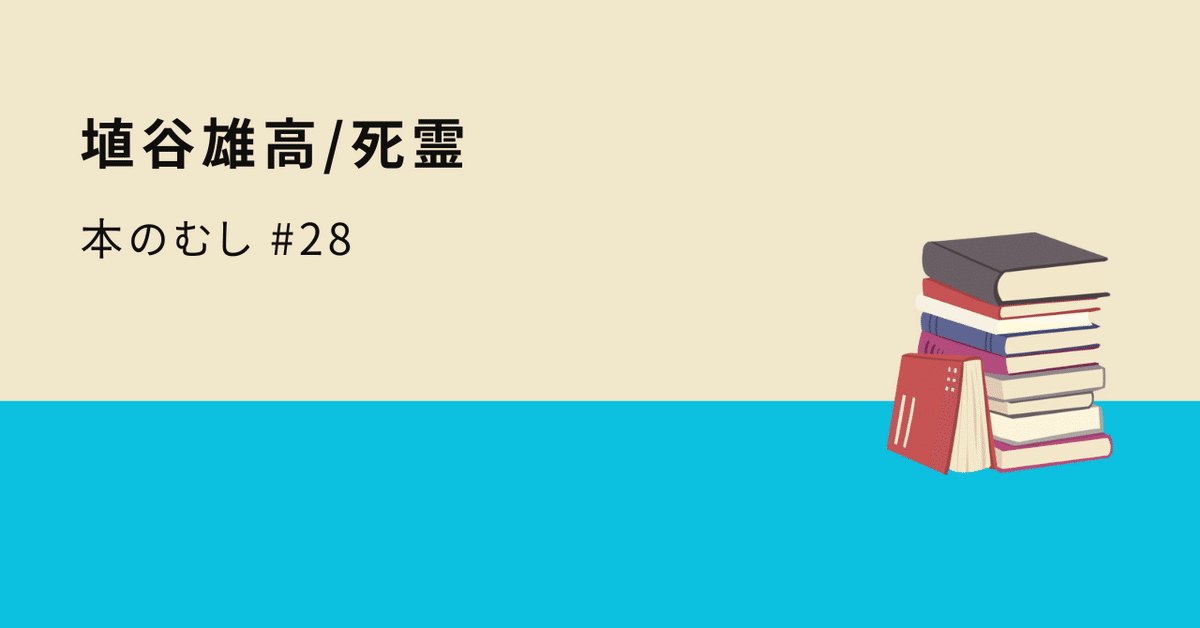
【おすすめ本】50年かけて書く、15年越しに読む(埴谷雄高/死霊)
今週もこんにちは。今日は朝から仕事です。日曜日なのに〜GWなのに〜〜😭
それはさておき。きれいでも小粒な作品より、荒削りでもスケールの大きな作品が好きです。それはぼくの性格かもしれないし、仕事で効率性や完成度を求められるから、本くらいはのびのび読みたいと思っている反動かもしれません。
今日の一冊は埴谷雄高(1910-1997)の「死霊」(しれい)。著者が36歳で発表し始め、87歳で亡くなる直前までなんと半世紀以上にわたり書き継いだエネルギーの塊のような未完の大作です。
余談ですが、この本はぼくがたしか中学生の時に買って、さっぱり読めず、十五年以上引き出しに放置していました。息を長くして書かれた作品は、読者にも、長いスパンで付き合うことを求めるように感じています。
▼▼今回の本▼▼
めくるめく「死霊」の世界
この作品、中身はほぼほぼ哲学的な議論です。ひとりの人物が100ページ以上ぶっ続けでしゃべったりするから凄まじい。テーマは「存在の罪深さ」だとぼくは勝手に思っています。私が私であることの罪深さを個性豊かな登場人物たちが5日間にわたり侃侃諤諤議論する、そんな作品です。
晩夏酷暑の或る日、郊外の風癲病院の門をひとりの青年がくぐる。青年の名は三輪与志、当病院の若き精神病医と自己意識の飛躍をめぐって議論になり、真向う対立する。三輪与志の渇し求める<虚体>とは何か。三輪家4兄弟がそれぞれのめざす窮極の<革命>を語る『死霊』の世界。全宇宙における<存在>の秘密を生涯かけて追究した傑作。
そんなのは小説じゃないぞって言われそうですが、ちゃんと小説だし、面白いのが読んでいても不思議です。とにかく難しくて大変な読書だけど、それだけの価値は絶対にある。文章はこんな感じです↓
その名状しがたい幅の恐ろしさをまざまざとお前の眼前に思い浮べるためには、いいかな、思いのほかに詩人らしい閃きもあるお前がまさにこれまで持っていた胸のなかのがらくたの一切を投げ捨てその純一無垢の魂にだけまっすぐ向きあって、いわばかたちもない未出現のなかに快も不快もないぼんやりした無感覚のまどろみをまどろみつづけている不思議な無限とさて不快に駆られて目覚めかけたまましかも敢えて待ちきれぬ苛らだたしさに充ちみちた未出現をなお保ちつづけている不思議な無限がぼんやり向きあっている不思議絶妙な景観を思い描いてみろ!
いやいやいやいや。
藪から棒に「不思議絶妙な景観を思い描いてみろ!」と言われても困ります。この「幅」は「『はじめのはじめ』の盲目王国と『おわりのおわり』の絶対王国」との間にある幅らしいのですが、それも「なんだ、これ?」です。
それでも、引き込まれる。繰り返しを恐れない、高揚した文章が、目の前にぐんと迫ってくるようです。例えば、下の文章は「川の水がきらきら光っている」描写なのですが、この緻密さとこの濃度。
凝っと注視していると、確かに晩夏の水がそこを流れていることを示す小さな光の波動がそれぞれそのまま生きて走り廻っているような縞模様を絶えずそこに動きゆらめかせていたけれども(…)そこは、さながら、絶えず動いている或る種の思いもよらぬ志向をもった水の微粒自体が自身と自身をすりあわせて自身のなかで自身のなかから静謐に発光しているかのごとくであった。
議論の部分からも登場人物たちの白熱した様子が伝わってきます。
――宇宙の責任が真に追求されたとき、新たな形而上学が可能になるのです。
――とすると……どんな方法で?
と、傍らから首猛夫がぽつりと訊き質した。(…)
――無限の可能性を判別し、うけいれる眼をもって、です。
――というと……どんな眼?
――無限の未来に置かれた眼です。
――というと……どんな眼なのだろう?
――それは、死滅した眼です。
と、黒川健吉はぽつんと云った。首猛夫はぴたりと立ち止った。
――あっは、死滅した眼だって? おお、おお、『未来の眼』と君がいった意味ははたしてそうだったのだろうか。ふーむ、解ったぞ。君はつねに未来の場所から現在を見る。
「これで解ったんかい!」とツッコみたくなりますが(笑)議論だけでなく、こうした描写が丁寧で熱が伝わるからこそ、読者が作品を信頼して、読み進めることができるのだと思います。
「罪深さ」の奥ふかく
主人公三輪与志は「存在の罪深さ」に向き合い続ける潔癖な純粋さを持ち合わせた人物として描かれています。その対立軸として登場するのが、存在の罪深さを最初から認めて、進んで罪に汚れようとする首猛夫です。彼は意地悪で挑発的なことを言う役回りなんですが、みんなにそうしている様子を見ると、すごくおおらかな性格なんじゃないかと思います。
ぼくも日々生活する中で人の罪深さを感じることがあります(最近はパレスチナのこともあってとくに)。この作品は、そんな「罪深さ」を人間からすべての存在に押し広げて考え抜こうとする、本当にむちゃな試みです。本作品の解説で吉本隆明さんもこう言っています。
五十五歳から上の人で、生きている人がいたら、そして生きていて、現実に反抗する文学、あるいは芸術に反抗する政治思想というものをあい述べている、そういう人がいたら、そしてその人がいまもいたら、たいていいんちきだと思ったほうがいい。そんなはずはないので、絶対に生きられなかったと僕は思います。
その弱さを作品に昇華できた稀有な作家、それが埴谷さんだと。
ひとりの人間としては、だから自動的に何が悪いという話ではなく、その罪深さをある時は受け入れて、ある時は意地を張って抗う、そんな揺れ動きが大切なんだと思っています。
まあでも、難しいけどね。生活に追われて、「存在の罪深さ」なんて考える余裕がない方も多いはずです。ぼくもそう。でもだからこそ、ぼくはこの本をこれからもずっと本棚に置いておくんだと思います。
(おわり)
▼▼前回の本▼▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
