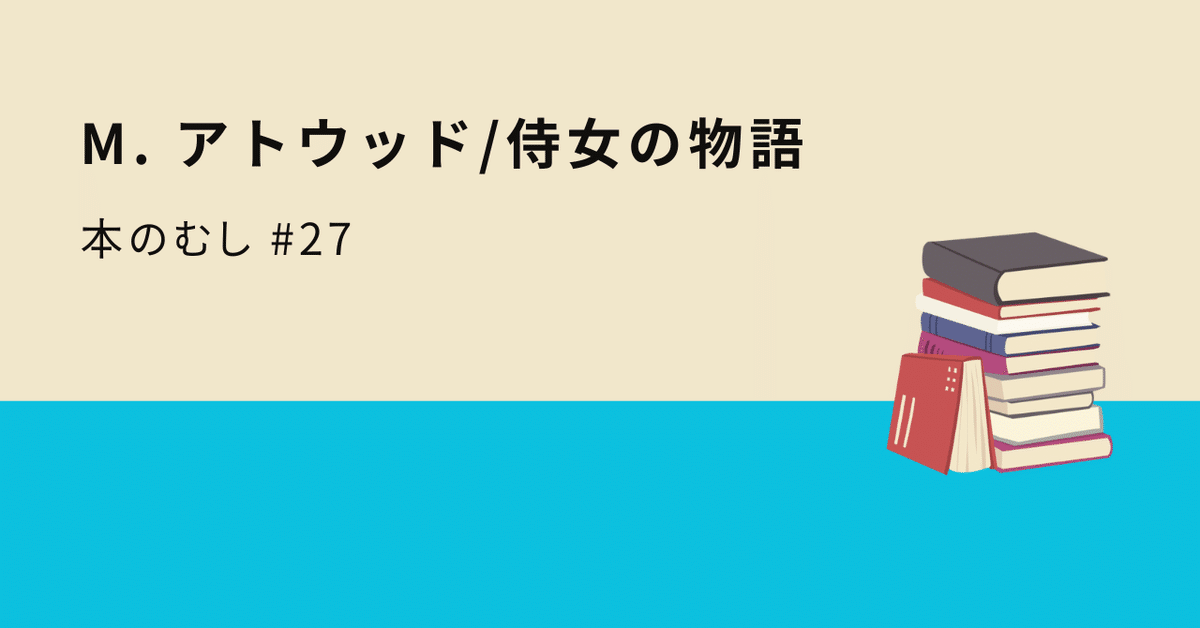
【おすすめ本】本棚の遠い女性たち(アトウッド/侍女の物語)
今週もこんにちは。関東はよく晴れた週末です🍡
今週の一冊はマーガレット・アトウッド「侍女の物語」(1985年発表)。男性が支配する、出生率の低下した近未来で、自由を奪われ、囚われの身となった女性たちの戦いを描いたディストピア小説です。
アトウッドは元々詩人としてデビューしたカナダの作家。1939年生まれの大ベテランですが、80歳だった2019年に(!)、本書の続編「誓願」でイギリス最高峰の文学賞ブッカー賞を受賞しています。
▼▼今回の本▼▼
本作のフォーカスは「女性」。主人公のオブフレッドの身分は「侍女」で、社会が必要とする「司令官」の子供を産むためだけに彼の家に住まわされているという醜悪な状況です。
「にもかかわらず、女性は出産によって救われるであろう。信仰と慈愛と貞操を保ちつづけるならば、つねに真面目な気持ちで」
出産によって救われるねえ、とわたしは考える。ひと昔前、わたしたちは何によって救われると考えていたのだろう?
侍女の生活は監視され、子供を産むための性行為を「儀式」として行うことを強制されています。彼女たちがそれ以外に身体的な暴力を受けることはありませんが、その境遇ゆえに、女性である自分自身を受け止められなくなっています。
鐘が鳴る。わたしはその前に、定刻より前に起きている。そして自分の体を見ないようにして服を着る。
そんな社会はある意味でこっけいです。例えば、侍女のひとりジャニーンが出産するシーン。出産の貴重さから何十人もの「侍女」たちが立ち会い、スポーツの応援のように一斉に呼びかけます。
助産婦のひとりがジャニーンの額を湿った布で拭う。ジャニーンは汗をかいている。(…)
「早く息をして! 早く! 早く!」わたしたちは声を出す。
女性の過酷な状況を描く本作は最近個人的に考えていたこととつながりました。
それは「男性を書くのが上手な女性作家は多いのに、女性を書くのが上手な男性作家は少ないのはなぜだろう?」ということです。
特に最近、何冊か大正〜現代の男性作家の日本文学を読んで、女性描写の単調さに衝撃を受けました。性格や言動がステレオタイプで、現実味がないのです。もちろん面白い部分はたくさんあって、人物の心情も丁寧に書かれています。でも、対象が女性になるとその解像度が一気にガクッと下がる。どうして……?
もしかすると、彼らは女性のことを深く考えなくても作品が「書けてしまう」社会や環境にいたのかなと思いました。女性を深く書くことは彼らの作品の評価軸ではなかった。そこは適当でも「他の部分で」勝負することができた。
もしそういう面があるとしたら、社会だけでなく、文学という空間もまた、男性が優位に立つことを許してきたのだと思います。自由なものであるはずの本棚が、女性の不自由さを生み出してきたとしたら、それはすごく悲しいことです。
そう考えると、本作は、女性の戦いを描きながら、一冊の本としても文学の世界で戦っているのかもしれない。そんなことを考えました。
(おわり)
▼▼前回の本▼▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
