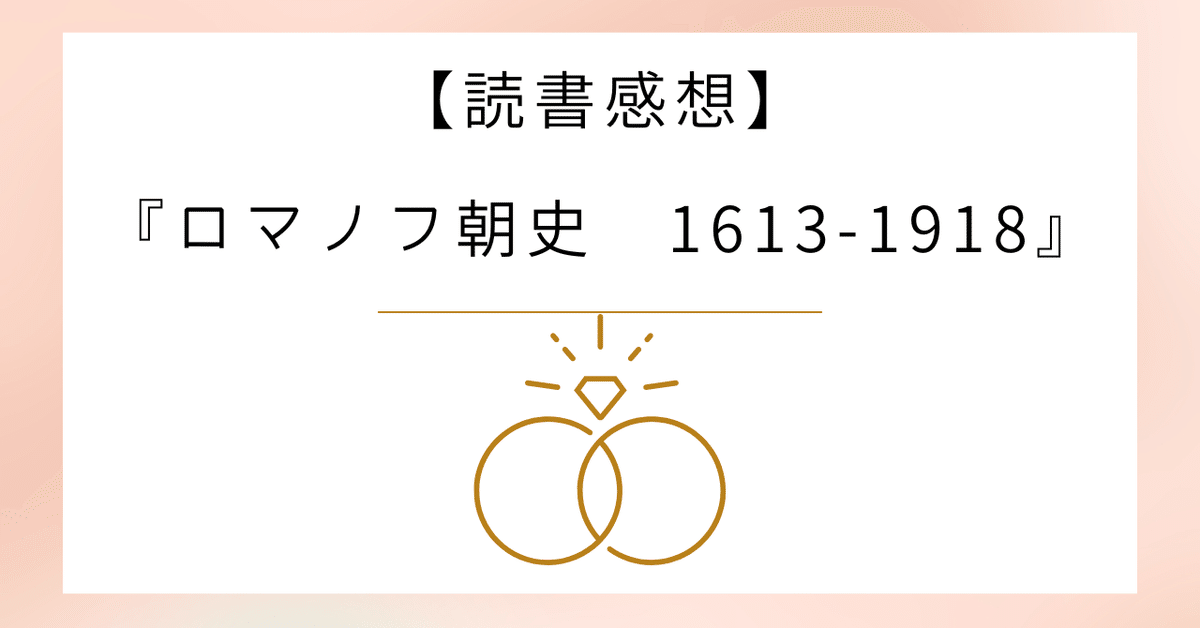
ロシア=専制政治の歴史〜【読書感想】『ロマノフ朝史1613-1918』 サイモン・セバーグ・モンテフィオーリ[著]
その時、プーチンは側近たちに約束した。「私はみずから退位することは決してしない」。
ロマノフ朝は過去のものである。しかし、ロシアの専制独裁制がもたらす諸問題は今も続いている。
17世紀初頭から300年間ロシアに君臨し、革命の最中に一族が惨殺されたロマノフ朝。
その皇室の歴史を描いた、サイモン・セバーグ・モンテフィオーリの『ロマノフ朝史1613-1918』上下巻(白水社 2021年:原著2016年刊)を読んだ。
1 『ロマノフ朝史1613-1918』の全体的な印象
宮廷の群像劇
『ロマノフ朝史』は、ロシア皇帝とその一族(愛人を含む)、そして寵臣たちの言動や人間関係を中心に宮廷を描いた群像劇となっている。
そのため、国家や社会といったロシア全体に関わる内容について触れるのは、物語の進行に必要最小限なものとなっている。
この点は、他の近代ロシア史の書籍とは毛色の異なる部分だ。
たとえば、同じロマノフ朝という題材を扱った通史なら、土肥恒之『よみがえるロマノフ家』(講談社選書メチエ 2005年)というコンパクトな好著がある。
近代ロシア史を概観した本として、おすすめできるものだ。
(ちょうど今2024年4月27日現在Kindle unlimited の対象にもなっているので、関心のある方はどうぞ)
『よみがえるロマノフ家』の方は、皇帝の政策やロシア社会にも十分に記述を割いた内容となっている。

『ロマノフ朝史』も『よみがえるロマノフ家』も同じ題材を扱っているので、似通った内容になるのが自然なはずだ。
しかし、人々の行動を、政策などを見てマクロに把握するのと、個人的な人間関係というミクロな視点から理解するのとでは、その行動の見え方は変わって来る。
ロシア皇帝をロシア国家や社会との関連で捉えて記述した『よみがえるロマノフ家』と、ロシア皇帝個人の人間関係を中心に記述した『ロマノフ朝史』。
同じ近代ロシアの皇帝という題材を扱っていても、両者が描く皇室像はだいぶ異なった印象を与えるものだった。
おそらく(失礼な話ながら)『よみがえるロマノフ家』には類書があっても、『ロマノフ朝史』の描く皇室像にはなかなか似た本は見当たらないのではないだろうか。
詳細かつ分厚い記述
『ロマノフ朝史』は、ピョートル1世やエカチェリーナ2世のような世界史の教科書にも登場する有名どころだけではなく、ロマノフ朝の歴代君主のすべてに対してページ数を割いている。
そして、300年という長い期間を扱うこともあり、たくさんの人物が登場して来る。
そのおかげで、巻末にある典拠情報を除いても、上巻下巻ともに約600ページもある大作となっている。
読み始めるのをためらってしまうような結構なボリュームだ。
しかし、読み始めるとどんどん読み進めていくことができた。
(もちろん全部読むにはそれなりの時間がかかってしまったが)
専門書が扱うような細かい内容に触れていても、読み物として書かれているから読みやすくなっていたのではないかと思う。
また、登場人物一覧と簡単な人物説明を各章の冒頭に付ける、同名の人物をあだ名で呼び分けるといった工夫もあり、読み進める時には助けられた。
(ちなみに人名索引は下巻の巻末に一括されている)
そして、メインである宮廷での物語からフェードアウトした後の登場人物や事物のエピソードも多く紹介されている。
現ロシア大統領プーチンの祖父、怪僧ラスプーチンの切り取られたペニスの行方のようなネットでアクセス可能なレベルの話から、皇帝に近侍した無名黒人や犬の「その後」という本当に瑣末なトリビア話まであり、楽しめるものとなっている。
2 『ロマノフ朝史1613-1918』上巻
『ロマノフ朝史1613-1918』上巻は、ロマノフ朝誕生前夜の「動乱時代」から、ナポレオン戦争の勝者となった皇帝アレクサンドル1世の治世が終わる1825年までを扱っている。

流血に彩られた皇帝の代替わり
エカチェリーナ2世(寵臣への手紙)
「タキトゥスの歴史書を翻訳するか、あるいは、ロシア史を本格的に勉強するよう助言します」
スタール夫人
「ロシアの政治といえば、それは専制政治であり、専制の苛烈さを抑制しようとすれば、君主を殺害する以外に道はなかった」
古代ローマ帝国の歴史書、タキトゥスが書いた『年代記』には、有名なネロをはじめとする「愚帝」たちの行状、寵臣や近衛兵の専横が描かれている。
それらと肩を並べ、勝るとも劣らない、多くの血生臭いエピソードによって、この時期のロシア史は彩られている。
特に目を引いたのは、代替わりに前後する激しい権力闘争の数々。
皇帝が死去する時期の前後には、その皇帝の下で権勢を誇っていた勢力と、次期皇帝最有力候補の勢力との間で、流血をともなうまさに命懸けの権力闘争が発生する。
先帝の下での権勢を維持する、あるいは次期皇帝に抹殺されないためには、次期皇帝候補や新皇帝を殺害することも厭わない歴史が繰り返される。
かつて下女をしていた農民出身の「洗濯女」が、先帝の正妻という資格を理由に支持者から担ぎ上げれられ、新皇帝に就任する事態まで起こってしまうほどだ。
代替わり時の権力闘争の理由はさまざまだ。
先帝の先妻(皇太子の母)派閥と先帝の後妻派閥という寵臣間の対立だったり、
ヨーロッパ(近代)重視とスラヴ(伝統)重視との間の政策ないし文化的な対立であったり、
先帝と不仲であった次期皇帝と、先帝が期待した別の後継者候補との間という、先帝の人間関係に端を発する対立だったりする。
しかし、権力闘争の理由やその展開が多種多様でも、それらの本質は同じようにも思える。
「皇帝は絶対的な権限を有する。
対立相手の側に皇帝が立つと、何をされるかわかったものではない。
皇帝から強権的に支配されることを予防するために、臣民は流血を含めた強権を発動して対抗するしかない。
臣民からの反抗を抑え込むために、皇帝は絶対的な強権で支配するしかない」
皇帝の絶対性が導くこのマッチポンプは、絶対的な存在であるはずの皇帝の命をいくつも刈り取っていった。
多様な恋愛・愛人関係
18世紀のロマノフ家の恋愛事情は、幸福なものも破局にいたったものも、どれも個性的で面白かった。
特に、ピョートル1世と皇妃(後の皇帝エカチェリーナ1世)、エカチェリーナ2世と寵臣ポチョムキンとの関係は、やり取りされた手紙からも色々と引用されていて、独特の味わいがある。
エカチェリーナ2世とポチョムキンとの関係は、どこかラクロの『危険な関係』を彷彿とさせる上品な香りを感じた。
(こちらは小説とは異なり幸福な結末となっている)
3 『ロマノフ朝史1613-1918』下巻
『ロマノフ朝史1613-1918』下巻は、アレクサンドル1世が死去した1825年から、第一次世界大戦の勃発、ロシア革命下で皇帝一家・一族が惨殺されるまでの100年足らずの期間を扱っている。

真面目だが無力な皇帝たち
アレクサンドル1世
「ただ一人の人間がロシアを統治して、ロシアの進路を正しく保つことは不可能だ。
私のような凡俗にとってだけでなく、天才的な皇帝にとっても不可能だろう」
アレクサンドル2世
「自分の家の中に反逆者がいるというのか?
もしそうなら、ロシア帝国の皇帝よりも、貧しい農夫の方がよっぽど幸せということになる」
ナポレオンを破りアレクサンドル1世がパリへの入城を果たした時が、もっともロシアが栄光に輝いた瞬間だった。
しかし、ロシアは反革命の立場を維持するあまり、軍隊をはじめ近代化に乗り遅れ、クリミア戦争に敗北してしまう。
近代化の必要性を痛感して、農奴解放など、さまざまな近代化改革を模索した。
アメリカ南北戦争では、南部を支持した英仏に対して、北部の唱えた奴隷解放をロシアが支持するという異様な事態まで生じたほどである。
しかし、上からの近代化は国内での支持を得られなかった。
テロが横行し、皇帝の冬宮内が爆破されたり、挙げ句の果てには皇帝自身の暗殺までもが成功してしまった。
皇帝一族の中には近代化への態度を著しく硬化させる者もあり、改革は暗礁に乗り上げていく。
上巻までの皇帝たちとは異なり、19世紀の皇帝たちは(その方向性はともかく)真剣に国家のことを考え、仕事に取り組む人々だった。
しかし、哀しいかな。
専制君主という見かけにも関わらず、国家に近代化を強制しつつ秩序を保つことはできなくなっていた。
むしろ、改革への試みがかえって崩壊を加速させたようにも思えて来る。
下巻に登場する皇帝たちは、(後知恵でしかないかもしれないが)運命の荒波に翻弄される無力で哀れな存在に見えてしかたがない。
体制側から見たロシア革命前夜(革命に結びつけないロマノフ朝末期像)
ストルイピン
「ロシアで革命が成功するための必須の条件は戦争だ。
戦争が起きなければ、革命派はどうすることもできない」
日露戦争やロシア革命時の皇帝ニコライ2世(在位1894-1917)の20年間に対して、下巻では4割以上のページ数があてられている。
下巻が扱っているのは約90年間であることを考えると、破格のフォーカスをされている。
皇帝サイドから見たロシア革命前夜の歴史は、革命側、共産党側によって描かれてきた従来の歴史像とはまた違った趣きがある。
たとえば、国会をめぐる出来事や反体制側の動きなど、従来のロシア革命史において多くのページを割かれている内容について、本書の中で言及される機会ないし分量はとても少なくなっている。
むしろ、皇帝と閣僚たちとの政治方針のズレ、閣僚への不満など、体制内に対する言及の方が多く取り上げられている。
これだけでも皇帝の関心が違う方向を向いていたことがうかがえる。
また、皇帝の発言で特に目を引いたのは、反ユダヤ主義的な言葉の数々だ。
ユダヤ人という集団に対する直接的なヘイトスピーチだけではなく、政治経済的な問題を反ユダヤ主義のフィルターで捉えている。
皇帝、そして当時の民衆の心を反ユダヤ主義が大きく捉えていたことは想像以上のものがあり驚かされた。
もし革命が起きなかったら…もし第一次世界大戦が起きなかったら…
第一次世界大戦以前のロシアの歴史は、ロシア正教や反ユダヤ主義に注目すると、まったく違った一貫性ある物語を見せてくれるのかもしれない。
ニコライ2世の視点には、その可能性を感じさせるものがあった。
怪僧ラスプーチンの本質
ニコライ2世の皇妃アレクサンドラ(祖母の英国ヴィクトリア女王への返信)
「お婆さまは誤解している。ロシアはイングランドではない。
ロシアでは臣民の愛情を獲得する努力は必要ない。ロシア人は皇帝を神として崇めているからです。
ペテルブルグの社交界について言えば、彼らは完全に無視しても構わないような連中です」
ラスプーチン
「皇帝は移り気で、いつも不幸だ。彼には力が欠けている」
フランス人治療師フィリップなど、ラスプーチン以前にも皇帝ニコライ2世夫妻に精神的に取り入ることに成功した者はいた。
では、なぜラスプーチンはもっとも成功することができたのか?
(性的な関係という俗説以外の)その理由を2つ本書は提示してくれている。
ひとつは、ラスプーチンの言動は、本質的には阿諛追従でしかなかったという見方だ。
皇帝夫妻が自分達に対して言って欲しいことは何なのか、ラスプーチンは常にそれを意識して発言していた。
そのため、宮廷から遠ざけられた先駆者たちと異なり、彼を排除しようとする者は皇帝夫妻の信を失うこととなっていた。
もうひとつの理由は、皇帝夫妻にとってラスプーチンが「本物のロシア農民」(下巻382頁)であり、かつ(民間信仰に傾いてはいるが)ロシア正教的な聖者の体裁をともなっていたことだ。
上流階級の人々に不信感を抱き、スキャンダルにあふれた社交界を嫌って新興ブルジョワジー層とも接点を持たなかった皇帝夫妻。
周囲から孤立しがちな彼らに残されていた精神安定の方法は、皇帝と数百万の農民との間の神話的な繋がりにすがり、その想像によって自分たち皇室の権威を自己肯定するだけだった。
そして、この皇帝夫妻の統治の理念、願望を他の誰よりも体現する人物として、ちょうどラスプーチンが現れた。
上流階級の者達とは異なって卑屈ではなく、農民の出を感じさせる粗野な言動を取り、そして宗教的な聖者として振る舞うラスプーチン。
その姿は、皇帝夫妻にとって、個人的な精神的安定だけではなく、政治的な自己肯定感までもをも与えてくれたのだった。
ニコライ2世の政治的な願望と、ラスプーチンが持っていた諸要素がシンクロしてしまったこと、それがラスプーチン寵愛の象徴的な意味合いだった。
ラスプーチンへの皇帝夫妻の精神的な依存をとても説得的に説明できている解釈だと思う。
4 専制政治はロシアの伝統か
最後の皇太子アレクセイ
「でも、皇帝がいなくなったら、これからは誰がロシアを治めるの?」
スターリン
「人民は皇帝を必要としている。
崇敬する皇帝のために生き、そして、皇帝のために働くことが必要なのだ」
革命以降のロシアを統治した、ソ連や現役の「皇帝たち」について軽く言及して、本書は締めくくられている。
ロシアの専制的な政治体制という伝統は、今後もずっと変わらないものなのだろうか。
専制的な体制は、ロシア固有の要素、お国柄ないしロシア人の国民性にどこまで由来するものなのだろうか。
それとも、地政学的な関係、あるいは国内の民族多様性、はたまたロシア正教的メンタリティが要請するものだろうか。
支配される側が専制を求めるのか、支配する側が求めるのか。
いや、そもそも400年以上にも渡る強権的な支配を、すべて「専制的」と言って一括りにして扱ってもいいものだろうか。
本書の多くの皇帝たちのエピソードに触れながら、そういった思いが浮かんでは消えていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
