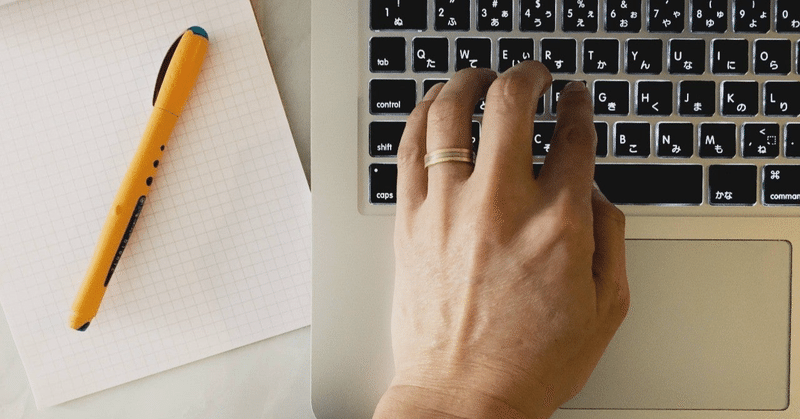
※23/03/06 加筆版【文章術】いつもこうやってnote書いてるよ《筋の通った文を量産しよう》
文章と自意識
当然ですが、物を書いて生計を立てているわけではないので、文章を書くということに関してはずぶの素人です。
そんな素人から文章書くことについて何が学べんねん…?と皆言うでしょう。
自分で言うのもなんですが、私はずぶの素人にしては文章を書くのが上手い方です。
ですから、自分より上手くないずぶの素人の人に対しては、どうやって書けばそれなりの形をなした文章をつくることができるかを説くことができます。
一方、文章で生計を立てているプロの方、小説家・ノンフィクション作家・ライターetc.
彼らにとっては何も得るところのない文章ですので、このままお引き取りください。
と言いたいところではあるが、実はそうでもないかもしれない。彼らは(基本的に)文章が上手すぎる。たくさんの語彙を持ち、それらを巧みに結合して、美しい建造物(文章)をつくる。彼らの弱点は、「知りすぎていること」「持ちすぎていること」ではないか、とずぶの素人である私は思う。つまり、いろんなことばを知りすぎているし、表現の技法もたくさん知っている。「たくさん知っている」「たくさん持っている」ということは、それだけ選択の余地が生まれる。表現の場合の数が無数に存在する。
で、困ったことに人間というのは自意識がある。これは文章を上手に書ける人の特徴でもあるのだが、時に困ったことになる。自意識が強い人というのは、他者から自分がどう見えているのかを常に気にしている人である。つまり、これを文章に置き換えると、相手の立場になって自分の書いた文章がどう見えているのか、がわかってしまう、ということである。相手の立場になって考えながら書ける。
だから、相手がおもろいと思う(独り善がりではない)文章が書けるのだ。だが、これは諸刃の剣である。自分が相手からどう見えてるのかがわかってしまう、ということは、相手から見える自分の印象をうまく操作しようという欲が出てきてしまう、ということで、この欲に呑まれると途端に文章はつまらないものになる。あきらかにこの人ウケ狙いやなあ…と思って聴く他者の話に冷めるのは多くの人が経験していることだろう。
で、結局、何が言いたいかというと、「相手からどう見えてるのかは把握しつつも(相手から見える自分を把握するときにだけ自意識を使いながら)、書くときはきわめて機械的(システマティック)に手順を踏んで書け」っていうことかな、と思う。
この記事はそもそも、どうやって整った文章を書いたらいいのかすらわからない、ずぶの素人向けに書いたものなので、プロの人があんまり読むものではないかと思うがそんなところ。
そして、素人が上手に文章を書くときに意識すること、いろいろありますが、上で述べたのと基本的にはおんなじです。逆説的ですが、とりあえずは「上手に書こうとしないこと」。これ、めっちゃ大事な気がしてます。文章から「ああ…こいつええ格好しようとしとんなあ…」てのがなんとなく読者に伝わると、その時点で読んでる側は冷めちゃうところがあるので。
要は「下手でも良いから自分の言葉で喋れ」っていうやつです。かくいう私もけっこう(無意識のうちに)他者のことばを借りてきて、そしてそれをその場の感情なりなんなりにあてがって自分のことばで喋った気になってる、なんてことがまあよくあること。これは、文章が好きで、幼い頃から小説読んだり、いろんな本読んだりしてきた人ほど気をつけた方がいいです。それだけ、他者のことばのストックをたくさん持ってるわけなので。
あとは、下記に示した私の手順なりなんなりを真似するなり、自分なりにカスタマイズするなりして取り込んでもらえれば、おもしろいかどうかは別として(おもしろいかどうかを決めるのは小手先の技術ではなく、書き手のアタマの中身に何が格納されているか、それらがどういう風に混ざり合っているかに強く依存する)、ある程度整った、かつ、筋の通った文章が書けるようになるのではないかと思う。
*私の文書作成力(23/03/04時点、参考)
参考までにずぶの素人である私の文書作成能力(いわゆる額面上のスペック)を示しておこう。
先に断っておくが、プロフィールにも記載の私は双極性障害を患っているため、鬱期には特に認知機能が大きく減じる。逆に躁期には、下記スペック表以上の性能が出ることもある。アベレージをとったとき、どれくらいかな?と考えたとき、これくらいかな…?というのが以下の値。
》速度
〈エッセイ・日記・雑文など〉
3,000字/h (PC)
2,000字/h (スマホ)
〈思索*を要する文章〉
1,000字/h (PC)
1,000字/h (スマホ)
*後述するように、思索の結果を書く系の文章は、いろいろ資料(文献etc.)をあたって構想を練る時間の方が長い(というかそちらがほとんど)なので、構想にどれくらい時間をとられるかによって、文書完成までの時間が大きく変わってきます。書く〈作業〉自体ならば、上記に書いたよりも速く書けそうな気もします。
》連続稼働時間
16時間がMAXだったと記憶しております。
2020年末くらいに16時間くらい稼働して7.5万字/day程度がMAX。
平均を取ったら4時間/dayくらいかなと思います。
午前中いっぱい、あるいはお昼~夕飯前くらいという感じ。
とはいえ、双極の影響はかなり大きくて毎日コンスタントに4時間/day書くというのは私にはムリそうです…。
さっき言ったみたいに書くときに10時間くらい書く。書かない日(書けない日)は寝ている、というのが私の今の執筆能力の限界のようです。
》後述する私の弱点
双極の(軽)躁のときにアイデアはとめどなく出てくる、ということがあるので一応ネタにはそんなに困っていません。ただ、ネタどうしをくっ付けて1つの構造物にするための〈接着剤〉的な役割を果たす知識が私には足りないな…と文章を書いていて感じることが多いです。ここが私の〈伸びしろ〉ですねぇ……。
以上、本題に入りましょう。
》最初に
今日は私なりのnoteの書き方について、話そうと思う。今日は手短に。とはいえ、書きたいことが重なって9,000字くらいになってしまいました……。
(余談等含まれるので、適宜飛ばして読んでほしい)
私自身、noteという比較的長文が許されるプラットフォームとはいえ、だいたい2,000字くらいがBESTでそれ以上は中々読んでもらうのが難しいだろうなあ、というのを自覚しており、できるだけ短い文章の中に同じ内容を詰め込めるようにしたいと常々思っている。
「時間がなくて方法だけ知りたい!」という方は、目次から「まとめ」の項に飛んでいただければ、かんたんな手順がわかるようにまとめてある。
今、記事のストック(完成品)が15個くらいあって、タイトルだけとかチョロ書きのモノも含めると、45個くらいはあると思う。ネタだけは、「もう出てこないだろう……」と思ったら、出てくるというのを繰り返してここまで5ヶ月半、noteをだいたいではあるが、2日に1回のペースで記事の平均文字数としては7,000字程度を書き続けてこれた。
だいたいnoteを書き始めると、あとは作業興奮で勝手に筆が進むので、書くこと自体に困ったことは1度もない(どうやら私は、指→脳という経路を辿るタイプの書き手らしい)。というのも、書くことに入るのは、もうすでに「思考」の段階ではなく、「作業」の段階だからである。
書くのが大変なのは、「作業」の段階ではなく、「思考」の段階である。この「思考」が固まりさえすれば、文章は8割方完成したとみて良いだろう。
》メモの取り方
具体的な話をしよう。私がnoteを書くときにいちばん大事にしているのは、「メモをとること」である。
いわゆる「ネタ帳(アイデア帳)」なのだが、私の場合、このネタ帳の段階で物語(ストーリー)を完成させてしまう。言い忘れたが、メモは紙のメモでも、スマホのメモでも、PCのメモでもその人に合った方法であれば何でも構わない。
私としては、デジタルのメモをおすすめする。特にLINEを使ったメモは優秀だ。時系列にメモが並ぶというのがすごく良い。
Twitterでも時系列に並ぶが、メモが増えてくると、遡れなくなる。Twitterには、たしか過去ツイートの検索機能が搭載されていたが、私はそれを使っても見たいツイートが出てこなかったことがある。たぶん、遡れるツイート数に限界があるのだろう。
他のアプリやWebサービスなどで、ツイートを遡ることも試みたが、どうやら3,200件あたりが遡れる限界であるようだ(少なくとも私の知る限り)。私のツイートは約1.3万ツイートだから、1年前のツイートなどには遡れないモノもある。
しかし、LINEは検索機能を使えば、トークルームのメモを4年前まで遡れることは、すでに確認済みだ。私のLINEメモはすでに1万件を超えているはずだから、検索機能の面でLINEの方がメモとして優れていると私は思う。
他にEvernote等を使っていた時期があるが、アクセシビリティの点でLINEに分があると思った。ワンタップですぐにメモを確認できる。
あとは、気になったツイートやニュース等を共有するときにTwitterや多くのニュースサイトにはLINEへの共有ボタンが搭載されているが、Evernote等は共有ボタンをあまり見ない(私だけか?)。汎用性の面でもLINEに分がある。
で、LINEでどうやってメモをとるかというと、そのとき思ったこと・考えたことをとりあえず書きなぐるだけである。そうしたら、LINEが勝手に時系列に並べてくれる。
あとは、気になったツイートやニュースサイトをコピー&ペーストしたうえで、リンクも貼っておく。該当ツイートやニュースに対して思うところがあれば、それも書き添えておく。
このメモがコンテンツブロック(1つの意味・主張のカタマリ)になる。文章を書くことは、このコンテンツブロックに論理的結合をつくることである。
》メモを繋ぐ
次にバラバラに散逸しているメモを並びかえたり、繋いだり、要らないものは省いたりして(必要なモノのみKeepメモに抜き出すなどして)、〈妥当な〉論理的結合をつくる。
〈妥当な〉論理的結合とは、要は「*推論を正しくしましょう」ということで、たとえば、「AだからB」という記述をしたときにAがBの理由になっていないというのは、〈妥当ではない〉推論である。
──*余談①(知ってる人は読まなくていいです)──
この記事を読んでいただいている諸賢はすでにご存じだと思うが、「推論が正しい」というのは、「結論が正しい」ことを必ずしも示さない。
あくまで、命題と命題を<妥当な>論理的手続きで橋渡しするということであって、それが完全にできていたとしても前提が誤っていれば結論は誤りになる。
前提(最初の命題)が正しいかどうかは、何処を拠り所とするかをしっかりと選定するということしか私にはいえない。誰にとっても自明な事実・公理(のようなモノ)であったり、もう少し自明性を落とした定理から始まる場合もあるかもしれない。
そうでなくても、よくあるのが、学術論文などから結論を引っ張ってきて、「この論文では〇〇と述べています。だから、、」と論を展開していくパターン等も見受けられるけれども、ああいう場合は、いくつか比較対象を持ってきて、それらをズラーッと並べて比べてみるということが肝要だ。
要は、数学で言うところの「大数の法則(平均値回帰の原理)」を前提の選定に用いる、みたいな話である。「大数の法則(平均値回帰の原理)」というのは、試行回数を無限に近づけるほど、期待値に近づく、という原理で、カジノなんかはディーラー側が勝つ確率(=期待値)が50%より微妙に高く設定されているおかげで、一部にバカ勝ちする客がいるが、大量の客がギャンブルをすると、試行回数が無限に近づき、期待値である50%超となる、すなわち、カジノ運営側が勝つという仕組みになっている。
これを前提の選定にも使う。つまり、論文や文献を1つ読むだけでなく、何個も持ってきて、並べて比較するのだ。そうすることで、選んだ1本の論文が、1冊の文献がトンデモだった…という確率を下げることができる。情報の信憑性というのは、基本的には多数の情報を比較することで得られる。論文でもメタ分析といって複数の論文の主張を比較する論文が一番信憑性が高いしね…。
(偶にトンデモじゃね…と思ってたらガチの天才でした、というパターンはありますが、基本的にはたくさん集めれば集めるほど的外れなところに的を射る確率が減ります)
──*余談ここまで──
他にもありがちなのが、「AだけどB」といったときにAとBが逆の傾向を示していない等がある。これらの推論の誤りは上記の例のように短く単純な文章ならすぐに間違いであると気がつくが、文章が長く複雑になればなるほど、いま自分が〈妥当な〉推論をしているのか、を見失いやすくなるので注意が必要だ。前提から〈妥当な〉推論を繰り返して、文章を繋いでいけば、正否は置いておいていずれは結論にたどり着く。つまり、ひとつの論理的構造をした文章が完成する。
この作業をする際に、メモが時系列に並んでいることが役に立つ。時系列に並んだコンテンツブロック同士は論理的結合をつくりやすい。論理の飛躍が小さいからだ。
人には思考の〈流れ〉というモノがある。その流れの中で任意の点Aと点Bを論理的に繋ぐという作業をする際に点Aと点Bの距離が離れていればいるほど、繋ぐのが難しくなる場合が多い。離れた点同士の関連性や繋がりは見えづらい/気づきづらいからだ。で、コンテンツブロック同士を(論理的に)連結させていくともうすでにストーリーはできているから、ストーリーをKeepメモに並べていく。
》noteにアウトプット
あとは、もう「作業」に過ぎない。LINEのメモをnoteの下書きにコピー&ペーストして(これもスマホならワンタッチで可能)、助詞や接続詞、言葉の響きなどを微調整して1本の大きな文章(構造体)を完成させる。
》下調べや文献調査等
そして、(経験的な主観を除く)自分の主張等が含まれる場合は、裏付け(根拠)になるような文献等を探して、それを読み込む。読んだ上で要点を纏める。
あるいは、論文ならアブストラクト(冒頭の要約)をとりあえず読む(できれば、全文読む)。この「わからないこと/裏付けのないことを適切な資料を見つけて読む」というのが、文章(特に論考のようなモノ)を書くうえで、最も大変なことだと私は思う。
この作業がうまく行かないせいで、文章が完成させられない(まとめられない)ということは多々ある。私も今参考文献が読みきれなくて、完成せずに溜まっている文章が何本もある。
文章を書くうえで、重要かつ大変なのは、(少なくとも私にとっては)、「アウトプット(作業)」ではなく、「インプット(ネタ探し・下調べ)」である。
大学・大学院で研究をするときも、既存研究やトレンドの調査のために論文を読むのが最も骨の折れる仕事であった。
私もnoteを書くうえでは、そのような下調べをサボって、ラクをしてWikipediaなどで済ませてしまうことが多いが(「ブログだからいいか~」という気持ちに逃げてしまう)、本当に自分の代表作となるような作品を書きたいのであれば、この「下調べ」の仕事はおろそかにはできない。
》メモを取ることの重要性
繰り返すが、文章を書くうえで大変なのは「インプット」であって、「アウトプット」ではないというのが私の考え方である。しかし、「インプット」の労力のうち、「ネタ集め」の労力は、LINEで「思考メモ」を取るということで、限りなく小さくすることができる。
私は極度のメモ魔だ。人との会話の中で気になるフレーズがあれば、一言一句違わぬようにメモを取るし、気になるツイートやニュースがあれば、スクリーンショットをとったうえで、文章をLINEのトークルームにコピー&ペーストし、さらにツイートやニュースのリンクも貼っておくという三重体制でメモを取る。家でボーッとしているときに思い浮かんだことや電車の中で考えたこともメモをとるし、見た景色も写真を撮ってLINEのトークルームに投稿しておく。
とにかく、何でもメモする。こうすることで、ネタ切れは極力防げる。ネタに困ったときはメモを読み返せば、いくらでもあるという状況をつくっておく。
──*余談②ですがだいじなこと(できれば読んでください)──
究極的なメモは「覚えておく」ということである。つまり、記憶。記憶力が高い人の方が一般的に上手に文章を書ける傾向があるように(私の今までの経験上)思うし、実際に私が文章を書く際にも記憶(≠記録)に頼って書くところが大きい。特に、文章の臨場感というか、ライブ感、読者を惹き込むような〈引力〉のある文章を書くためにはディテールを詰めることが極めて大切になってくる。人がサラッと流してしまうところをネバネバしつこくあーでもないこーでもないと思索を巡らせるから、その人にしかないおかしさが生まれるのであり、それを支えているのは、結局のところ記憶である部分が大きい。では、記憶と記録、なにがちがうのかというと、これはたぶん〈鮮度〉である。食べ物でも生のモノとそうでないモノがあるが、生にあたるのが記憶、そうでないのが記録。当然、前者の方が鮮度は良い。だから、メモを書けとは言ったが、それは次善の策であって、すべてを記憶で記述できるのであれば、その方が良いのは言うまでもない。(ただ、そんなことは不可能であるから、記録=メモの仕方を示した)
──*余談ここまで──
》慣れれば準備なしでも書けるようになる
これらの一連の作業も慣れてくれば、noteの下書きからいきなり書き始めても、それなりの記事が書けるようになる。情報を収集して、論理的結合をつくって、ストーリーにして、それをアウトプットして、自分の主張に関連する文献を探して、それを(できるだけたくさん)読んで、要約して、援用するという思考回路が身につき、一連の作業が一手に行えるようになるからだ。
ここまで来たら、その場で、ある程度の記事(緻密な下調べの要らない記事)なら簡単に書けてしまうようになると思う。
》私なりのnote執筆手順まとめ
ここで、私のよくやるnote執筆の手順をまとめておこう。
1) そのとき思ったこと・考えたことをLINEのトークルームに書きまくる(投稿しまくる)。気になったツイートやニュースサイトのリンクも貼っておく。
2) 時系列に並んでいるメモから不要なモノを省いて、Keepメモなどに移す。必要なコンテンツだけが残る。
3) 選り抜かれたメモに論理的結合をつくる。必要があれば、メモを並び替えたり(LINEは時系列に並ぶので、並べ替えは不要だと筆者は考える)、接続詞などで繋いだり、1つのストーリーとして筋が通るように、文章の体裁を整える。
4) これで、論理的破綻のない1つのストーリー(構造体)が構築される。
5) あとは、(主観的な経験を話す場合等は除く)自分の主張と関連する文献等を探してきて、それらを読んだうえで要約して、援用する。出典の明記は忘れずに。この作業が最も時間を食う。
6) 完成した文章をほぼそのままアウトプットすれば、記事は完成する。あとは、完成した文章を読みなおして、推敲する。おかしな部分があれば微調整。
こうして、私のnoteは完成する。主観的な体験談などを語るエッセイ調の文章の場合は、5) の手順が省かれるだけである。とはいえ、5) の手順が最も骨の折れるところではあるから、これがなくなると、文章を書くのはかなりラクになる。
ここでのポイントは、「インプット」と「アウトプット」の時間を完全に分割するということと「時系列に並ぶメモに思い浮かんだことや考えたことをブレインストーミング的に書きなぐる」ことである。
「インプット」と「アウトプット」の時間を完全に分割することで、「アウトプット」の速度が劇的に速くなる(∵準備をした上で書くことができる)し、「インプット」に時間を取ることで、論理的に破綻の少ない(∵複数の情報の比較→より真値に近い前提+情報が整理されていることによる論理的結合の作りやすさ)記事が書けるようになると思う。
そして、「思い浮かんだことや考えたことをブレインストーミング的に書きなぐる」ことで、その「思考メモ」が「ネタ帳」になり、ネタ切れに困ることがなくなる(とまでは言わないが、その頻度はかなり減る)。さらに時系列に整理されたメモを眺めることで、思考も整理され(思考の流れ≒方向が見える)、論理的に文章を結合することが容易になる。
こういった寸法である。最近、やたらとLINEでメモを取ることを勧めているが、私はLINEの回し者でもなんでもない。ただ単に便利だから、使っているだけだ。これ以上に便利なツールが出てきたら、迷わずそれに乗り換えるという節操なしだ笑。
ちなみに皆さんもご経験があると思うが、LINEにメモを一元化することには、一定のリスクがある。そう、端末の機種変更等の際に、引き継ぎに失敗して、トークルームのデータがすべて消えてしまうということだ。心配な人は、各携帯キャリアのショップ店員の方に頼んで引き継ぎをやってもらおう。
》終わりに(あとはイキリ自慢とか)
そんな感じで、今日は私なりのnoteの書き方にを説明した。こんなに説明した後でなんだが、この文章は、上記の方法に沿わず、思いつきで一気書きした…笑。
21/03/01の深夜1時ごろから書き始めて、書いている途中で睡眠導入剤が効いてきて、2時を待たずに眠りについた。そのあと、朝の6時ごろに起きて完成させた文章である。
(*これは、初稿の話です。初稿はだいたい5,000字くらいの分量でした。23/03/06に加筆)
私もさすがにnoteではこれまで77記事(だったっけな?)ほど文章を書いていて、その間70万字程度の文章を書いているので、未だ初心の域を出ないものの、書くこと自体にはだいぶ慣れてきたモノだ(ヒント:ダニング=クルーガー効果)。特に文献調査等を必要としない文章(エッセイとか日記)であれば、ジャンルにも依るが、1~2時間で1本3,000~4,000字の記事が書けるくらいにはなった。
しかし、私の文章にはたくさんの「弱点」がある。数えきれないほどの。これは、私の読書経験(つまり、知識)の乏しさ・偏りによるところが大きいと考えているので、これからたくさん勉強が必要だ。たぶん、読むにしても、普通に通読するだけではあかんやろうなあ…と思っている。数学書であれば一行一行書いてある数式の意味を完全に理解するくらい、哲学書であれば一語一句の用語の定義からおさえて「わからないところがない」くらい理解する必要があるんじゃあないか、つまりは精読する必要性を今感じている。とはいっても、いきなり山の頂点には登れないので、今できることとして、私の尊敬する作家の文章や「この人巧いなあ」と思うその他媒体の書き手の文章を読んで自分に取り入れようとしている。
というわけで、皆さん、私と一緒に鍛練して文章、うまくなろう(ライバルが増えるのは正直イヤだが)、今回は皆さんが文章を書く上で何かお役に立てばということで、私のnoteの書き方を開示することにした。以上。ここまで読んでくれた人たちありがとう!
ご支援ありがとうございます。また見にきてくださるとうれしいです。頂戴したお金は大切に使わせていただきます。
