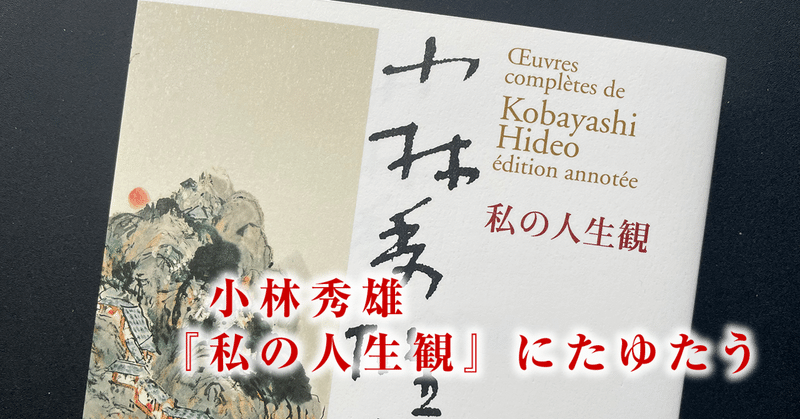
正岡子規の客観写生と小林秀雄の「観」
「話が脇道に外れてしまいました」と小林秀雄も認めたところで、次は再び短歌に話が戻る。
これまで、諸行無常や「空」を交えて西行の歌について語ってきたが、西行よりも源実朝を評価した、明治時代の歌人である正岡子規の「短歌革新」について触れる。 正岡子規は「貫之は下手な歌よみにて『古今集』はくだらぬ集に有之候」ときっぱり『古今和歌集』を否定し『万葉集』を尊重することで、「ただ自己が美と感じたる趣味をなるべく善く分るやうに現すが本来の主意に御座候」と、対象をありのままに観て写し取る「写生」を説いた。
さらには歌人・斎藤茂吉の「短歌に於ける写生の説」から「実相観入」を紹介したり、平安時代の僧侶・空海の詩論から「目撃」という言葉を示したりしたうえで、それらがすべて、小林秀雄が『私の人生観』でこれまで論じてきた「観」に通じると指摘する。
注釈を付けるならば、正岡子規は西行を全否定したわけではない。「短歌革新」の発端となった新聞連載『歌よみに与ふる書』において西行の「さびしさに堪へたる人のまたもあれな庵を並べん冬の山里」を引き、「庵を並べん」という斬新な趣向は西行ならではであり、とくに「冬の」と書き添えたのも余人をもっては代えがたいと述べている。
また、「実相観入」については、斎藤茂吉自身が、「実相」は仏教用語だが、「観入」は自らの造語だと認めている。仏典にある言葉なのだろうという小林秀雄の指摘は異なる。
あらためて、なぜ小林秀雄は「写生」を持ち出してきたのだろうか。もちろん、仏教でいう観法と通じ合っていることを指摘したかったのは分かる。空海が「目撃」という言葉を用いたことを含め「心に物を入れる、心で物を撃つ、それは現実の体験に関する工夫なのである」と指摘している。
たしかに正岡子規は、ありのままの姿を写しとるという意味で「写生」を提唱した。しかし、ただ見たままの姿を描写し、言葉にしただけでは、単なる説明だったり、平凡な歌になったりすることも分かっていた。他方、単なる知識のひけらかしの歌も嫌っていた。小林秀雄の言う「物知り」やインテリめいた歌である。
ともすれば、どうしても自分というものを含めがちな歌について、それを打ち消しつつも、どこか滲みでる感性や情緒がある。それは心の眼で見るもの、いわゆる「心眼」である。そこに小林秀雄は「見る」ことと「考える」ことの同一化、すなわち「直観」があると考えたのではないだろうか。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
