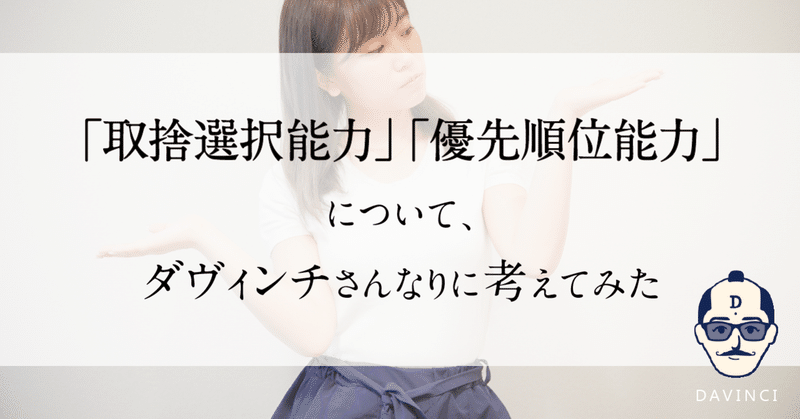
「取捨選択能力 」「優先順位能力」についてダヴィンチさんなりに考えてみた
どうも、元クリエイターの思考コンサルタント
ダヴィンチさんです。
内容に少しでも共感して頂けたらでよいので
👍🏻スキとフォローをお願いします。
👍🏻フォロー頂いた方は必ずフォローバックさせて貰ってます(^^)
💎ツイッターフォローもよろしくお願いします!
本日もよかったら音楽聞きながら読んでください。
本日のテーマはこれです。
「取捨選択能力」「優先順位能力」について
ダヴィンチさんなりに考えてみた
という事で、音楽聞きながら本題へ入りましょう。
2つの能力をタイトルに入れました。仕事をする上でとても大切な能力とわたくしダヴィンチさんは考えています。2つの能力とは言ったものの、この2つはほとんど同じような能力です。
この能力を持っていない人が今の日本に多い気がします。
「取捨選択能力」が無い人の特徴は簡単です。「物が捨てられない」です。結構いますよね?そんなに大事なものでもないのになぜか捨てられない。
取捨選択能力が無い人にはもう一つ特徴があります。それは「大事なものもそうでないものも、同じように扱っている」です。これは無自覚な人が多いと思います。「優先順位能力」もこの点は同じですよね。
特徴を「物」で説明しましたが、これは「情報」「状況」でも同じです。
トドのつまり、これは「整理整頓能力」と言い換えても良いのかもしれません。この能力が無い人は、自分の置かれている状況を整理できない、自分がインプットした情報を整理できない。結果、よくわからないアウトプットしかできない。という事になってしまいます。
このような人を現代ではこのように呼びます。=「完璧主義」
少し飛躍しているように感じるかもしれませんが、すべての情報を捨てない、すべての情報を同じ優先度で扱うという点においては=完全主義ではないかと、わたくしダヴィンチさんは思うわけです。
という事で
取捨選択能力・優先順位能力が無い人=完璧主義の人という事になります。
そんな人が今の日本に多いと思うのです。
このような能力、いったいどのような人に必要なのか?
これはやはり「リーダー」だと思います。
リーダーの役割その1は、マネジメントです。自分が管轄するプロジェクト、部署の情報・状況を体系的に理解し、どうすれば良い方向へ向かえるかを高い抽象度で考えます。次に、抽象度を少し下げて実際にそれを実行する具体的なイメージに落とし込みます。最後に、部下の誰に何を任せるのが最適かを考えます。
リーダーの役割その2は、部下へのアウトプット&指示です。部下へ指示を伝える際は、抽象度を極力下げてアウトプットします。この時、どのように伝えれば部下がミスをしないか、誤解をしないかを考え伝える事が重要です。場合によっては、途中途中で部下の様子を観察し、順調に進められるようにサポートします。サポートの仕方も、部下の自尊心を削ぐ様な形にならない様に配慮できないといけません。この心遣いができない人はリーダーに向いているとは言えないでしょう。
リーダーの役割その3は、部下からの質問対応です。部下が、作業に行き詰ったとき、作業に行き詰ったとき、一番わかりやすい答えや、一番わかりやすい指示を伝えます。最初のアウトプットが悪かったり、自分が想定していなかった事が原因で、部下は質問にきます。要するに、部下が仕事に行き詰るのは全てリーダーの責任です。
以上リーダーの役割1~3ですが「取捨選択能力」「優先順位能力」がないと、行うことができません。そもそも、この能力が無い人がリーダーをやっている場合、部下の失敗は自分の責任と感じることができません。
たまにこんな事を言っちゃうリーダーがいます。
「いやぁ~自分の部下は無能な人間ばかりなんですよぉ~」
これ冗談でも言っちゃうリーダーは、リーダーやめた方がいいです。ほんと、自分のためにやめた方がいいです。なぜか?これを言っちゃうという事は
「いやぁ~自分は部下のマネジメントも教育もできない無能人間なんですよぉ~」
と公言しているのと同じだからです。
こうならない為にも「取捨選択能力」と「優先順位能力」はリーダーなら必ず身に着けたいですね。
よく、ステレオタイプのリーダーは「何でもかんでもわからない事を聞くな、背中を見て仕事を覚えろ」と言います。しかし大丈夫、部下は貴方の背中を見ています。とても、とても良く、注意深く見ていますよ。
逆にこのようなリーダーは、こんな風に言われても大丈夫か考える必要があります。貴方の背中、本当に部下に見せられますか?部下は貴方をとても注意深く見てますよ?
と言う事で以下に私の思う説明を書いてみたいと思います。
「取捨選択能力」は文字通り取捨選択を行う能力です。
取捨選択を行うには、情報整理を行い、必要な事とそうでない事に分類する能力がないといけません。複雑に見える情報を因数分解して、わかりやすく脳内でタグ付けして、本質のわかるきれいな形に分類できないと、取捨選択はできません。
複雑な情報=本質がわかりにくい情報=散らかった情報を、自分でも理解せずに、雰囲気だけで部下に説明しても、部下の頭の中は「???」でいっぱいになります。こんなレベルの低いアウトプットは「上司からの指示」とは到底呼べません。
頭のよい部下がいた場合は最悪です。「この人馬鹿なんだな」と完全に見透かされます。
よって、取捨選択能力は「分析力」「因数分解能力」「分類力」「再構築力」が総合的に必要とされる能力だと思います。
「優先順位能力」も文字通り優先順位をつける能力です。
優先順位をつけるには、未来を経験から予測する能力がないといけません。どの順番で優先する事が一番明るい未来になるかを、自分で予測・想像できなければなりません。
料理をする時がわかりやすいですよね。
煮物をしている間に、魚を焼く準備をして、サラダの野菜を切って、お味噌汁を作りながら、グリルに火をつけて魚を焼き始める。お味噌汁を保温しながら、洗い物を始めて、洗い物が終わるころには、煮物が出来上がって、魚も焼きあがって、ご飯も炊きあがっていて。サラダを取り分ければ晩御飯完成!みたいな。
ただし、この優先順位能力ですが、必ずしも大成功でなくても良いのです。リーダーが思う一番よい順番を、部下へ伝えて、その結果に責任を持つ!ここが重要です。これができないリーダーが本当に多い気がします。
自分は責任を持たない。部下が勝手に失敗した。という事を言っちゃうリーダー、、、これ「自分は責任感のないリーダです」と言ってるのと同じなので、本当に言わない方がいいです。
まとめていうと「取捨選択能力」「優先順位能力」とは
「複雑状況に対する明確な分析&意思決定とアウトプット能力」という感じでしょうか。
以上、ダヴィンチさんでした。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
サポート頂いたお金は、noteでの有料記事購入に使おうと思っています。良い記事を参考に自分の記事をレベルアップさせ、最高のアウトプットを目指します。
