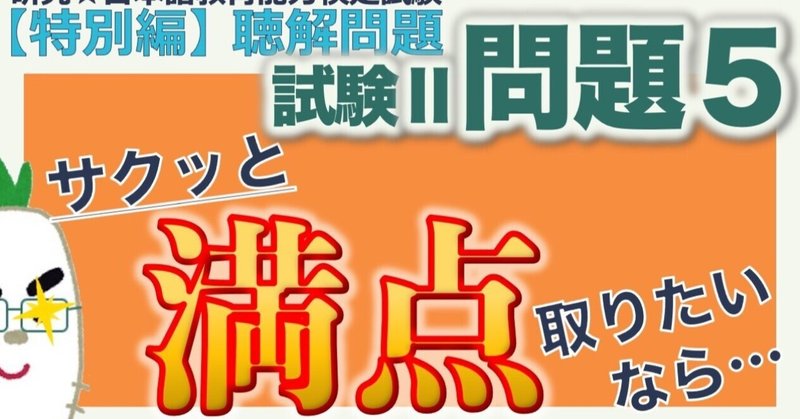
【特別編・試験Ⅱ問題5】日本語教育能力検定試験まとめ
みなさん、こんにちは。大根です。この記事は、以下の動画の原稿を公開しているものです。(全9475文字)
以下の表は、動画の中でお伝えした”過去9年間の選択肢に出た用語のうち、僕が難しいと感じる用語の一覧表”です。表をヒントに、ぜひご自身でそれぞれの用語の意味を調べてみてください。

以下の表は、動画を作るにあたってまとめた、”平成25年度から令和3年度までの問題5を分析した結果をまとめた一覧表”の抜粋です。一覧表の全てをご覧になりたい方は、この記事を購入していただき、記事の最下部のPDFをダウンロードください。みなさん自身が過去問研究するのに役立つと思います。

*2023年7月6日に、”平成25年度から令和4年度”までの問題5を分析した結果をまとめた一覧表を以下のリンク先の記事にて有料公開し始めました。最新の一覧表が必要な場合は、以下のリンク先の記事にてご購入ください。
オープニング
今日は特別編、「試験Ⅱ 問題5」の研究です。
前回から試験Ⅱ、いわゆる「聴解問題」攻略のための動画をお届けしています!
聴解問題は昼食休憩後の一番眠い時間帯に、“聞くこと”に集中しなきゃいけない試験です。主催団体のJEESさん、相当いじわるだな〜と思います!
実際に受験してみて感じたのは、脳のリソースを節約しながら音声を聞いて、スピーディーに問題を解いていくことができるかどうかが、“勝負の分かれ目”だということです。
前回の特別編では問題4を、今回は問題5を、そして次回は問題6を徹底分析します。これら3本の動画で、みなさんが脳のリソースを節約しながらスピーディーに問題を解けるようになって、聴解問題を得点源にしてもらえれば嬉しいです。
なお、問題1〜問題3については、すでに素晴らしい解説動画がYoutubeにあります。ももこ先生・はま先生・めがね先生の動画をぜひご覧ください。個人的に一番おすすめなのは、ももこ先生です!
また、問題3対策のために、こせんだ先生の音声学の動画を見るのもおすすめです!
聴解問題ができなくて悩んでいる方は、僕の動画と合わせて他の先生たちの動画も参考にしてください。
さて、今回扱う問題5ですが、ざっと他の聴解問題との相違点を3つお伝えします。
①例がありません。事前に1度も問題を解かずにぶっつけ本番で検定試験に臨むような方がいるとすれば、問題5がどういう問題かということを理解するので精一杯で点数は伸びないでしょう。この動画を見ている時点で、まだ一度も問題5を解いたことがないという方は、この動画を見た後に、すぐにでも解いてみましょう!
ちなみに、問題4も例がありません。
②音声を聞くことができるのは1度だけです。つまり、集中力が切れるなどして少しでも聞き漏らしたら致命的ということです。
ちなみに、問題4も例がありません。
③問題5は「日本語学習者向けの聴解教材」がテーマのため、学習者の誤りが出てきません。
他の聴解問題とは一風変わった問題5のため、苦手だという方も多いんじゃないでしょうか? 事前準備をしっかりして、解くためのテクニックを身につければ、問題5は満点だって夢じゃありませんよ。
今日は平成25年度から令和3年度までの9年間の過去問を徹底分析した結果を基に、次の5つのトピックでお届けします!
1.学習者向け聴解教材とは?(知っておくべき聴解教材の4つの特徴)
2.問題5の真実が判明!(問題5の設問パターン)
3.問題5はどうやって解く?(問題5の流れ)
4.これで満点ゲット!必勝の5テクニック!(試験当日のテクニック)
5.問題5は●●を準備せよっ!(試験までの準備)
動画の最後には、僕から皆さんへの重要なお知らせ2つもあります。ぜひ最後までご視聴ください!
では、1つ目のトピックに行きましょう〜!
1.学習者向け聴解教材とは?(知っておくべき聴解教材の4つの特徴)
解いたことがある方ならもうお分かりでしょうが、この問題5には設問が1番〜3番まであり、みなさんが聞く音声は「日本語学習者向けの聴解教材」です。この動画の中では「学習者向け聴解教材」と呼びます。その1番〜3番の中にさらに設問が2つ。合計で6問(6点)あります。
過去9年間の「学習者向け聴解教材 27回分」について研究し、みなさんに知っていただきたい4つの特徴があると分かりました。
特徴1
学習者向け聴解教材で流れる音声は、日本語母語話者の音声のみです。
学習者向け聴解教材ですから、そりゃそうですよね!
基本的には、男性と女性のペアの会話です。たまに女性2人の会話や、男性のみ・女性のみのニュース報道のような場合もあります。男性2人の会話というのは、過去9年間には1度もありませんでした。
特徴2
音声の冒頭、「1番 これから聞くのは、日本語学習者向けの聴解教材です。」のように説明があります。基本的には特定の条件は付かないのですが、たまに条件が付いていることがあります。
例えば「初級の日本語学習者向け」のように聴解教材の対象の学習者のレベルが付いている場合です。過去9年間では、「初級」の他に「初中級」、「中級」、「上級」という場合もありました。また、「教育実習生が作成した日本語学習者向け」というものもあります。
特定の条件が付いている場合には注意が必要です。詳しくは4つ目のトピック「これで満点ゲット!必勝の5テクニック!」の中でお話しします。
特徴3
学習者向け聴解教材の構成は、3つのパートでできています。
はじめに学習者が答えるべき設問、次に学習者向けの問題本文。約1分ほど流れます。最後に冒頭の設問が再び読まれ、選択肢が4つ提示されます。必ず4択問題です。
この後4つ目のトピック「これで満点ゲット!必勝の5テクニック!」の中でもお話ししますが、皆さん自身も日本語学習者になったつもりで、はじめの設問〜問題本文〜最後の選択肢までしっかり聞いて、4択問題を解いてください。実際に解いてみると、学習者向け聴解教材に問題点があること等がわかってきます。
日本語学習者になったつもりで解いてみる!これ、重要です!
特徴4
問題冊子に関する特徴です。1番〜3番のみなさんが解くべき設問それぞれには、四角の枠が描かれています。その枠の中に、学習者向け聴解教材に関する情報が記載されています。と言っても、大きく2種類しかありません。
1つは、枠内に「イラストやグラフ」などが描かれている場合。これは、学習者向け聴解教材が、そのイラストやグラフを見ながらリスニングして問題に答えるタイプということです。平成25年度以降では、平成26年度を除く8年間で毎年1問ずつイラストやグラフのある問題が出題されています。令和4年度以降も、3問中1問は「イラストやグラフ」などが描かれている問題が出ると思った方が良いでしょう。
もう1つは、「音声のみの聞き取り問題です。」という記載。つまり、学習者向け聴解教材が、設問〜問題本文〜選択肢まで、すべて音声のみで完結するタイプということです。このタイプが、毎年2問〜3問出ています。
学習者向け聴解教材には、これら4つの特徴があるんだと知っておけば心の準備ができるので、試験当日は問題を解くことに集中できると思います。
2.問題5の真実が判明!(問題5の設問パターン)
どんな設問が出るのかわかっていれば、学習者向け聴解教材の何に注意して聞かなければいけないかがわかります。そこで、過去9年間の「問題冊子に記載された設問 54問」を徹底分析しました!その結果、問題冊子に記載された設問は大きく5パターンしかないと分かりました。
ここから先は
¥ 590
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
