
外国籍の方が関わる不動産登記の添付書類

弊事務所が面している大通公園では、3年ぶりにさっぽろ雪まつりが開催されています。年明けから大雪像を作っている様子を眺めておりましたが、今はきれいにライトアップされていますね。外国からのお客様も大勢いらっしゃっているようです。
それにちなんで、今回は外国籍の方が不動産登記をするときに必要な書類についてお話ししたいと思います。なお、ここでは日本に居住していない外国籍の方を対象といたします。
【1】外国籍の方も日本の不動産登記をすることができるの?
まず、日本では外国籍の方(個人・法人)も原則として日本人同様に不動産の売買をすることができます。また、相続については被相続人(亡くなった方)が日本国籍の方なら相続人が外国籍の方でも日本の不動産を相続し登記できます(被相続人が外国籍の場合は事情が異なります。)。
不動産登記の手続で適用される法律は、日本の不動産登記法などの法令になります。
【2】外国籍の方も登記申請に必要な添付書類を用意できるの?
次に、日本の不動産について登記を申請する場合の添付書類を見てみます。法令で規定されている添付書類の中には、以下のような書類があります。
いずれも市区町村や登記所など公的機関が発行した書類であることが必要です。
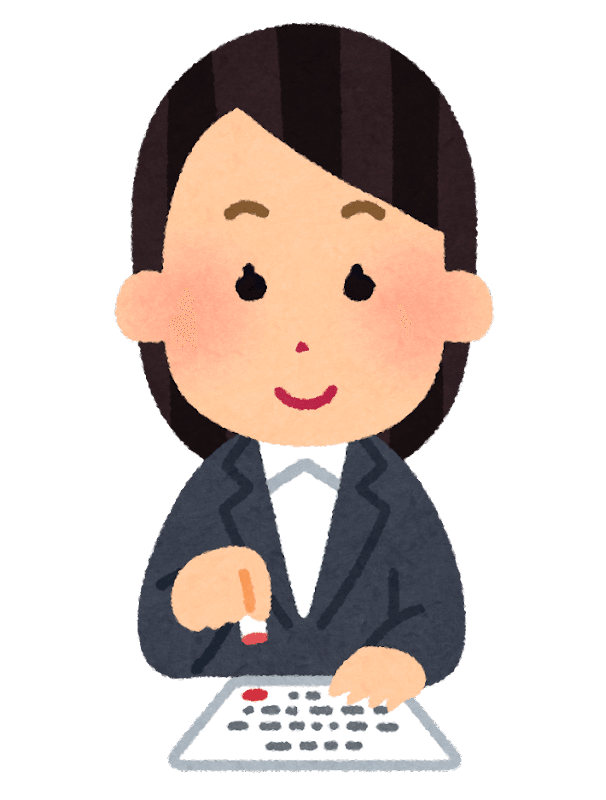
・売主の印鑑証明書
・買主の住民票
・法人の場合は、資格証明書
では、外国籍の方は印鑑証明書や住民票を用意できるでしょうか?
日本に居住している外国籍の方でしたらお住いの市区町村で住民登録をして印鑑証明書や住民票を発行してもらう方法がありますが、外国に居住している方は当然日本の公的書類を入手できません。
それでは居住している国の公的機関から発行してもらえるかというと、多くの国の公的機関では日本の印鑑証明書や住民票のような書類を発行していません。
印鑑登録制度は日本の他は韓国と台湾にあるだけですし、日本のような住民登録制度が無い国も多くあります。
法人の資格証明書は、日本で登記されている法人の場合は法人登記簿謄本や代表者事項証明書となりますが、国によっては日本の登記簿謄本のような形の書類がない、またそもそも法人のつくりが日本と異なることもあります。
このように日本の法令が不動産登記に関して求める書類そのものを用意することができない場合、これらの書類の添付が求められる趣旨を解釈して別の書類を用意することになります。
具体的にどのような書類を用意すればよいのかは、不動産登記制度の始まりから累々と積み重なった登記先例に従い、ある程度定型的な方法をご案内しております。
多くの案件では、お客様に「宣誓供述書」の作成を依頼しております。
【3】宣誓供述書
宣誓供述書とは、供述者が認証を要する事項を記載した書類を作成して現地の公証役場又は自国の大使館・領事館に持参し、公証人又は大使館・領事館の担当者の面前で記載内容が真実であることを宣誓し署名したものです。公証人等は供述者について本人確認や自発的な供述であること等の確認を行ったうえで同じ書類に認証した旨を記載し、これをもって宣誓供述書の完成となります。日本の法令が求める「公的」という要素は、公証人等が関わることで要件を満たすとされております。
公証人等の面前で行われる供述者の署名も本人確認を含めて認証されるので、特にこの点に着目して「署名(サイン)証明書」という呼び方をすることもあります。これは印鑑証明書として機能します。
住民票や資格証明書として作成する場合は、それぞれの記載事項を抜き書きした書類を作成し、これに公証人等の認証をしてもらうことになります。
「供述者が自分で認証してほしい事項を記載して持っていくなら、都合の良いことを適当に書けばいいんじゃないの?」と思われるかもしれません。しかし、多くの国(アメリカやオーストラリアでは各州ごと)では、公証に関する法律に「宣誓の上虚偽の事実を述べた場合は罰則を科す」ことが定められています。
また、宣誓は究極的には神に対して行うものであり、お国柄によっては私たちの想像以上に重いものであるようです。
認証してもらうのはどこの公証人等でもよいわけではありません。
原則として個人なら住所のある国の公証人又は母国籍の大使館・領事館(例:日本に来ているアメリカ人なら在日アメリカ領事館など)となります。
法人の場合は、原則として本店所在地の国の公証人またはその国の大使館・領事館となります。
弊所ではお客様に宣誓供述書の作成を依頼する場合、お客様からの聞き取りや収集した証拠を基に必要な情報を列挙した宣誓供述書文案を作成し、お客様にお送りして認証してきてもらいます。
宣誓供述書の作成はお客様にとって費用も時間もかかることですし、一度認証された宣誓供述書は訂正できないので文案作成は慎重に行います。また、先例に従ったものでなければ登記所が受け付けないので、海外から弊所へ発送していただく前にメールで写真データを送ってもらうようにしております。そして問題があれば再度の認証をお願いする場合もあります。

登記の内容によっては宣誓供述書だけでは足りず、別途の証明書を用意してもらうこともあります。例えば出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などです。 また、法人形態を理解し宣誓供述書作成の裏付けをするためお客様の会社の定款をいただいたり設立準拠法を調べたりします。 登記先例でカバーしきれていないところもあるので、必要なら登記所との事前の打ち合わせも行います。
こうした事情があるので、外国籍の方が関わる登記は通常の場合と比べて時間や費用を多めに見積もらせていただくよう、お願いしております。
【4】不動産登記法の改正
最後に、外国にお住まいの方に関係がある不動産登記法の改正についてご紹介します。
昨今所有者が判らない土地の問題が注目されております。よくあるのは土地所有者が亡くなったのに相続登記がされないまま放置され、世代を重ねるうちにもはや誰が所有者なのかつきとめるのが困難になってしまったというケースです。
「所有者と連絡が取れない」という点では、外国にお住まいの方が所有する不動産でも起こりがちです。日本人でも外国に移住すると同じ事が起こりえます。
そこで不動産登記法を改正し、令和6年4月1日から所有権の登記事項に「国内における連絡先」が加わることになりました。
(所有権の登記の登記事項)
第七十三条の二 所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 (略)
二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
2 前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
詳細を決める法務省令はまだ交付されていませんが、具体的には国内における連絡先となった者(個人・法人いずれも可)の氏名・住所等を登記事項とするとのことです。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
3年ぶりのさっぽろ雪まつり、皆様お楽しみください。
司法書士法人第一事務所 司法書士 木村佳子
おはようございます │*´ㅅ`)"
— 司法書士法人第一事務所・行政書士法人第一事務所【公式】@札幌 (@dai1jimusyo) February 5, 2023
週の始まりげつようびの札幌は晴れ☀
弊所のビルの前にある、さっぽろ雪まつり会場の大雪像は恐竜でした🦖
今日もお天気が良いので、雪まつり日和🎶#札幌Twitter会 #さっぴよ#企業公式相互フォロー#企業公式冬のフォロー祭り#企業公式が毎朝地元の天気を言い合う pic.twitter.com/jHz7XvmMb0
お問い合わせはこちらから👇
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
