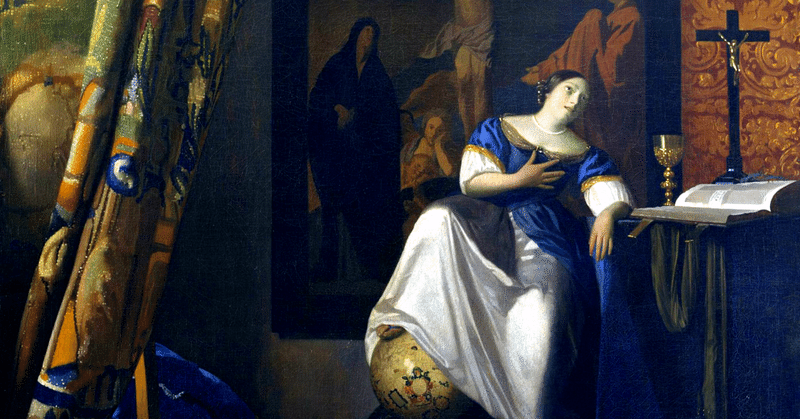
私の中の「信仰」
私はいつしか、「私」を捨てることになった。
「なんで、胸の下に線があるの?おもしろい。」
小学校のプールの授業の時間に言われたこの言葉を、十数年たった今でも、鮮明に思いだすことができる。
それは、初夏盛りの午後だった。お昼休みのあと、水泳の授業のために水着に着替え、プールサイドに集まって整列していた時のことだ。
この発言をした同級生は、きっと面白半分で言ったことなのだろう。
ただ、私にとっては、今でも残る《心の刻印》として、この言葉が機能していることを否定することはできない。
「なんで?って、なんで?」
「だって、他の奴には無いじゃん?」
それ以上のやりとりを思い出すことはできない。
しかし、たしかにその時、この言葉は私の身体に刻み込まれたのだ。おそらく、一生消えることのない事実として。
私はそれ以来、他人に体の一部を見られたり、触わったりされることに、全くではないとはいえ、嫌悪感を覚えるようになった。
その嫌悪感を確かめる行為はだいたい試した。やはり、嫌悪感は消えることがなかった。試しながら、その回数が増えるにしたがって、この嫌悪感は幻想なのではないか、と思うようになったが、やはり肝心な時に、あの出来事が頭をよぎってしまうのだ。
いろんな事実の前後を区別するような出来事は、たしかにあるだろう。
私の胸の下の線について同級生に言及されたという事実は、まさしくそれ以前とそれ以後を区別する出来事となった。
そして、それが今感じる嫌悪感の元となっていることは否定できない。
けれども、なぜ私はそう「感じている」のだろう。
好奇心にも似たこの感情は、そのように「感じる」対象について、思考を繰り返すことを命じた。
しかし、いくら考えたところで、分かりやすい答えが出てくるわけでもなく、わたしは過去にそのような発言をした同級生を、殺したいほど恨むことで、どうにか折り合いをつけている。
私は切実に、面白半分であの発言をした彼に、「消滅してほしい」と願っている。
しかし、いくら願ったところで、それが叶うことは無い。
私は、「願った」。
彼の消滅、ひいては《彼の言葉》の死を。
言葉が頭によぎるたびに、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、願い、恨み、そして願った。
終わりのない恨みと願望の円環の上を、私は知らず知らずに浮遊していた。
この恨みと願いは、私の「信仰」だ。
「信仰」をしたいから、恨みと願いを繰り返してきたわけではない。
けれども、たしかに私の中の恨みや願いとは、「信仰」として機能していることを、自己実現的に証明しているのだ。
「信仰」するたびに、過去の事実が色濃くなっていく。
「信仰」するたびに、それが絶対になっていく。
「信仰」するたびに、それが神になっていく。
「信仰」するたびに、それは見えなくなっていく。
「信仰」しなくても、「信仰」できるようになっていく。
私自身が何を考えているのか、わからなくなっていく。私が、どんな事実を持っている存在なのか、わからなくなっていく。なにかを「信仰」していたことさえも、わからなくなっていく。どんどん、私が少なくなっていく。どんどん、私自身が消滅していく。
気付いたら、私の周囲には、「私ではないもの」であふれていた。
誰の「私ではないもの」なのだろうか。一つ言えることは、ここには「私」はいない、ということのみだった。
「私」でいるために、彼を殺してやりたい。
「私」でいるために、過去の事実の「信仰」を止めたい。
このように「私」もいつしか、さらに「私」自身を捨てることとなるのだろう。
何かを欲し、その上を浮遊し、そのような「信仰」し続けるかぎり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
