「互酬性」から捉える医療者と患者の関係~文化人類学的な視点を学ぶ~
「文化人類学の思考法」を読んで考えたこと
文化人類学とは、「当たり前とされていることを問い直すこと」である。
学問の営みの中で、新たな視点や疑問が浮かび上がってくる。
ありえたかもしれない世界を思うことができるらしい。
もともと私が抱いていた文化人類学のイメージとはいささか異なるもののようだ。
未開の地に住む民族に加わり、数十年間の生活を共にすることでその民族の価値観や世界観を捉える。
それを知ることで人類がいかにして文化や共同体を形成していったのかを知ることに尽きるものである。
そのようなイメージである。
この本を読んだ後にわかったことは、私のイメージは非常に限定的な取り組みであるということである。
なかなかに先入観を抱いて、様々な本を読んでいたことを自覚する。
医師として病院という組織に加わることそれ自体を文化人類学的な行為ととらえると、新しい世界が見えてくる。
未開の地に入り込むことによって全く違った世界観を持っている人に出会うことができる。
その価値観に気づくということは、自分の中で当然とされていたものが当然ではないことを自覚することへと発展する。
多くの言語を比較する過程でロラン・バルトは記号学という言語に共通するルールを発見した。
それによって私たちは、日頃当然のように使っている日本語の豊かさを知ることができる。
日本語には存在しない物事の捉え方があることに気づくことも想像することもできるだろう。
レヴィ・ストロースが南米奥地で発見した家族関係を通じて、自分の家族関係をどのように構築するべきか考えるきっかけになる。
文化人類学の営みの中で、与えること与えられることが世界の根本原理であるとする考えが生まれた。
人はだれかに何かを与えられるとそれへ返さなければならないという罪悪感を抱く。
しかも、同等かそれ以上の何かを与えなければ気が済まないという焦燥感に駆られ、与えるという行為が繰り替えされる。
それは単に視覚的に捉えられるものだけにとどまらない。
背中をさすってもらうこと、「おはよう」といってもらうこと、目の前の他者から差し伸べられるすべてのものにあてはまる。
マーシャル・サーリンズはこの相互に報いあう営みを互酬性と定義し、互酬性に3つの類型があることを発見した。
①近親者の間のあまり返礼を求められない「一般化された互酬性」
②社会関係の乏しい相手から少なく渡してできるだけ多くを得ようとする「否定的互酬性」
③その間にある対等な立場で価値の等しい交換「均衡的な互酬性」である。
そして、中でも「一般化された互酬性」は権力関係に陥りやすいことが指摘されている。
一方的に与えることによって、近親的な関係性であったものの、与えられる側に潜在的な罪悪感が蓄積して、上下関係が生じてしまう。与える側が、強くなってしまうのである。
その不均衡さがこれまで親密であった関係性を権力的な関係性に移行してしまう。
医療現場を顧みるとこの権力関係を様々なところで見ることができる。
たとえば、介護する側とされる側である。時にニュースで介護職による高齢者や障害者の虐待が取り上げられている。
介護する側は、入浴を手伝ったり、食事を用意したり、様々な与える行為を行う。
一方で、それに対して介護される側は、感謝の言葉やまなざし、笑顔で応える。
2者の関係性とは、想像するとこのようなものだろう。ニュースを見るたびに「なぜ介護者は高齢者を虐待するのか」という問いで番組が作られていることに気づく。
多くの視聴者もそれを見て介護者を非難している。
「きっと介護者に嫌なことがあったためのストレスだろう」とか、
「収入が少ないから社会的な地位が低いからだ」とか、
「介護者がもともと暴力的な性格なのだ」とか暴力をする側に帰する論調に目が向いている。
しかし、この「一般化された互酬性」が不均衡に継続したために権力関係が構築されたのではないかという視点を加えることで虐待の原因に新しい可能性が見えてくる。
少なくとも虐待は、その介護士だけに原因があるととらえる考え方は大きく異なるものとなる。
贈与という営みと捉えることで、介護するものと介護されるものとの関係性にこれまで見えてこなかった違う一面が見えてくる。
虐待が起こるということに関して、贈与を取り巻く社会保障システムの構造や介護施設のあり方に問題があるのではないかという視点である。
もちろん介護士は、プロフェッショナルとして働き、その報酬を得ている。
でもそれを与える主体は社会保障という制度のなかで支払われる税金が主である。
もらっているという感覚はうまれにくい。
感じ方の問題だという指摘はもちろんであるが、既知のとおり介護職の収入は非常に少ない。
自分が介護している目の前の高齢者から報酬をもらっているという感覚をもつことは難しい。
そういう社会システムなのだ。決してそれ自体が悪いとか良いという話をしているわけではなく、その中でどのように介護する側と介護される側の関係性を構築するかを考えていく必要がある。
高齢者や障害者が介護者に与える感謝の言葉やねぎらいの言葉をもっと介護者に伝わるようにするための何かが必要なのかもしれない。
言葉に限らない何かを介護者へ「与える」という営みの機会をデザインすることや強調することが必要かもしれない。
介護者のプロフェッショナルとしての教育課程で「互酬性」に関する権力関係についての教育を行うことが虐待を防ぐのに有効かもしれない。
介護者の感受性を豊かにするためのプログラムや評価制度が必要かもしれない。
今あげただけでも様々な解決のアイデアをもつことができる。
文化人類学的な視点を持つことでこれまで当然とされた介護する側とされる側の関係性を再度問い直し、新たな関係性を構築するチャンスを与えてくれる。
それは、これまで以上に、医療者と患者の関係性を良いものにして、よりよい医療の実現につながるに違いない。
医師は、患者から何かをもらっているという感覚を抱く機会が少ない。
医療システムは、行った検査や治療を報告して診療報酬を請求し、7割ー9割が国の財源から支払われている。
窓口で患者が払うのはその半分にも満たない。
自分がやった医療行為に報酬が付かないこともある。
例えば、患者が点滴をしてほしいと言ってもそれに対して医学的な必要性がなければその必要性がないことを説明し、納得してもらった上で帰宅してもらうことがあるというのがそれだ。
針を刺すことで皮膚の細菌が体内に入る可能性や針を刺すことが迷走神経反射を引き起こすかもしれないことなどのリスクから結構頑張って「点滴をしてもらったら治る」という認識を修正する。
患者さんは自分のニーズが満たされずに癇癪をおこして医者を非難することもある。
合理的に考えるとなんとも理不尽な扱いを受ける場合がある。
それに対する目に見えた報酬はない。
医師によってはそれを与えてばっかりであると感じる場面が多いのかもしれない。
一方でその関係性を大きく覆される体験が存在する。
それは、患者さんから手紙をもらうことや感謝の言葉をもらうときである。
多くの医者は、何年も前にもらった患者さんの手紙や似顔絵などは、宝もののようにして大切に保管している。
医局に行けば、それを自分のデスクに張り付けている医者がたくさん見つかる。
田舎のクリニックでは、収穫の季節になると患者さんから果物や野菜を頂戴することがある。
自分が治療している患者さんが畑で働き、その気持ちのこもった収穫物を頂くというシーンは、こころ温まる場面である。これまで、何となく捉えていた診療所の世界は「互酬性」という概念によって全く違うものに見えてくる。
これらの営みによって、その営みがなかったら患者さんを支配の対象と捉えてしまうような恐ろしい関係性に自分が陥っていたかもしれない。
虐待は決して他人事ではない。
もっと言うと最近は、ドクターコトーのドラマに見る患者と医者の近しい関係性は、都会の医者と患者の関係性にはないので、「一般化された互酬性」というよりは「均衡的な互酬性」と捉える方が適切なのかもしれない。
医者と患者という関係性は一歩間違えたら危険な関係性になりうるという自覚をもち、双方にとってよい関係性となるようなあり方をいかにして作っていくか。
考えなければならないことはたくさんあったということに気づくことができる。
文化人類学的な視点は、医療現場を考える上でとても重要な要素となる。
気が付いたら大変なことになる前に、まだ私たちにできることはある。
当然とされるものを改めて捉えなおす営みの中にもっと良い医療を提供するための工夫が見つかるかもしれない。
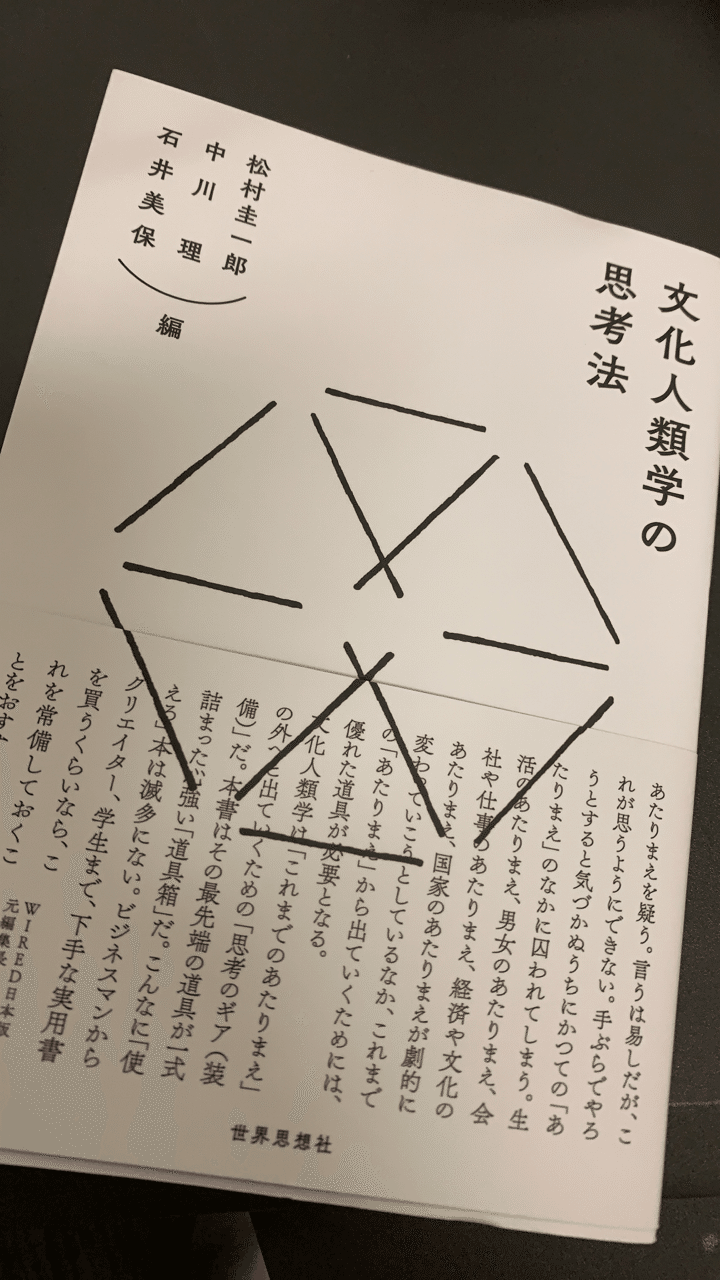
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
