
「わたくしといふ現象」という即興音楽
3月11日に公開した「空耳図書館のはるやすみ2021映像版」は、宮沢賢治が生前唯一残した詩集『春と修羅』の冒頭「序」で綴られた”心象スケッチ”を、古いIphone1台で即興的に撮影した「私たちの記録」でもあります。映像のロジックではなく、「目できく、耳でみる」ようにサウンドスケープ・デザインの思考で再編集した音楽領域の作品です。この手法は共感覚的な賢治の世界観とも親和性が高かったと感じています。
今は「音楽家」の肩書を持つ私ですが、実は大学卒業後に最初に就職したのはアート系洋画の配給会社でした。「仕入部」に配属になった私は小さな試写室で1日に何本もフィルムを見たり、字幕翻訳の校正をする作業をしていました。第1回東京国際映画祭の「女性監督映画週間」の担当もしました。当時は音楽活動とのダブルワークだったので、「仕事」だったそれらの作業が30年近い時を経て「今」につながることの不思議。コロナ禍が無かったら1年に2本の映像作品を作ることもなかったと思います(東京アートにエールを!では「空耳散歩01 LISTEN/THINK/IMAGINE」)を公開しています。
まだ携帯電話もなかった20代は「コニカビッグミニ」という小さなフィルムカメラの登場で、写真を撮る行為が「スナップ」として身近になった時代でもありました。そうは言っても撮り直しの出来ないフィルムですから、一枚一枚、日常の中の「決定的瞬間」を逃さないために、フレーミングも含めて全身の感覚を研ぎ澄ますような撮影者の姿勢や感覚が要求されました。それは一音一音を逃さずに全身で時空を捉える即興演奏とも通じます。身体感覚を延長して楽器を扱うように、映像撮影には古いIphone一台を選びました。解像度が高すぎず、機能が多すぎず、機械と自分の身体感覚を乖離させないことを第一条件にしたからです。
物心ついた時からピアノを演奏している自分には、モノとの相互関係を築くための「身体の記憶」があります。特にピアノは楽器であると同時に近代工業製品でもあり、単なるモノ(キーボード)として対峙すると「人間が支配する存在」に成り下がってしまいます。楽器との相互関係を築くためには指先の感覚や想像力を鍵盤の先にある世界に延長させ、弦やハンマーの感触を感じ取り、さらにはその楽器がどのような環境(メンテナンス)を生きてきたか、楽器が発する情報を瞬時にくみ取らなければなりません(その楽器がタフなのか、繊細なのかも含め)。さらに、楽器から放たれる音と空間の「間」の関係性を「きく」ことです。ピアノは指先/音を通して世界と自分を双方向につなげるメディアなのです。
2011年から研究しているサウンド(音/耳)スケープ(風景/目)という思考には、共感覚的な世界の捉え方が欠かせません。例えば映像でも聴覚と視覚を調和させて撮影します。機械に任せすぎない、反対に支配されない。きれいな映像と、映像の美しさは似て非なるものがあります。解像度や完成度を越えて、たとえ傷だらけのフィルムで撮影された粗削りの作品にも「名作」があることを過去の作品は教えてくれます(例えば、キアロスタミ監督の『オリーブの林をぬけて』など)。
結局、音楽も映像も機械が作るのではなく、人間の頭と手と全身の感覚が作るのです。機械(機能)に委ねすぎた創作は、そこにコンセプチュアルな意図が無い限り、いずれAIの作品と区別できなくなるでしょう。ロジック通りの創作は人工知能の方が得意分野だからです。機械が思いつかないような即興性や「完成しすぎないこと」、時には失敗することも体験しないと、人間の尊い営み、生きる知恵であるはずの「芸術」もいずれ機械に取って代わられてしまうかもしれません。
緊急時代宣言下では野外撮影の制約も多く、今回はいわゆる演出をした「撮影」ではありませんでした。賢治の「序」の世界観を地にして、メンバーで即興的に出し合ったアイデアを「記録する」かたちで進んでいきました。知恵を出し合い、出来ないことの中から出来ることを「発掘する」作業は即興音楽のセッションの時間にも似て、創作の原点に立ち返るような非常にクリエイティブな時間でもありました。
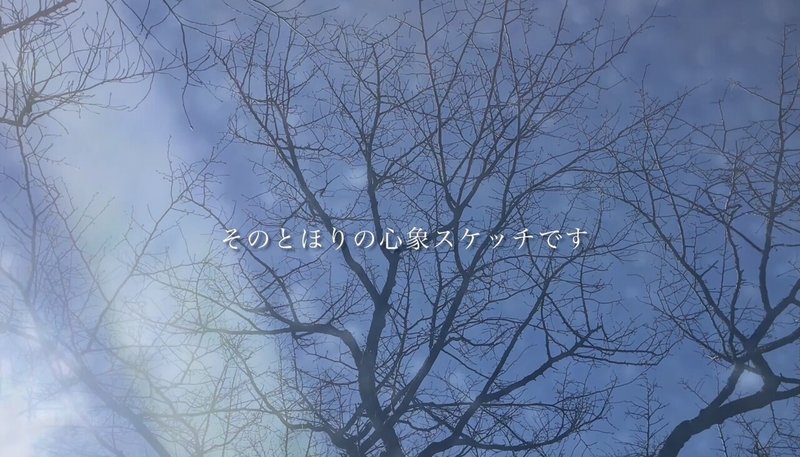
今回のコレクティブ・メンバーはプロのアーティストや新進の大学士、10代から50代までの社会的キャリアを越えた異分野・世代間交流です。なぜこのような編成が可能だったかといえば、彼らはこの数年、横浜の福祉作業所カプカプや港区コミュニティスペース「芝の家」で、即興力を要する「祭り」を共にする仲間だからです。特に昨年からのコロナ禍で経験したカプカプの「オンライン祭り」は(昨年秋にアートミーツケア学会でも報告させて頂きましたが)、非常に特異な身体感覚や時空のズレを経験する貴重な機会となりました。今回の撮影にはその時の経験も大きく反映されていると思います。
ある日突然コロナ時代に放り込まれ、私たちは今もなお先の見えない時間を過ごしています。そして宮沢賢治が『春と修羅』を出版した100年前にもスペイン風邪の流行や関東大震災がありました。賢治は表題作を記してからの22ヵ月の間に、憧れの街は震災で焼失し、最愛の妹はスペイン風邪の予後で亡くなってしまう経験をしています。その喪失を抱えた自らを「わたくしといふ現象は」と達観しながら最後に書かれた『序』は、この詩集の「あとがき」でもありました。厳しい現実と想像の世界を行き来する、静かな怒りにも似たひとりの青年の「心象スケッチ」は、「今」を生きる私たちの心とも深く響鳴します。賢治自身がこの「心象スケッチ」を「詩未満」と評したのは、それが「完成された作品」ではなく、過去と未来の4000年の時空を行き来する「わたくし」の心の風景の記録であり、しかも「今ここ」にしかない即興音楽のような現象だと感じていたからかもしれません。
しかし、ここから100年先にも賢治の言葉は間違いなく生き続けることでしょう。その普遍的な想像力、ひとりの人間の存在の尊さを少しでも感じて頂けたら幸いです。
『コロナ時代の”新しい音楽のかたち”を思考実験する②空耳図書館の活動を中心に』ササマユウコの音楽活動(文化庁文化芸術活動の継続支援事業)
〇空耳図書館コレクティブ参加メンバー(50音順)
新井英夫(Movement)、石橋鼓太郎(Reading)、板坂記代子(Textile)
小日山拓也(Mask)、ササマユウコ(Soundscape Design)、
三宅博子(Voice)
空耳図書館ディレクター ササマユウコ
(C)2021芸術教育デザイン室CONNECT/コネクト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
