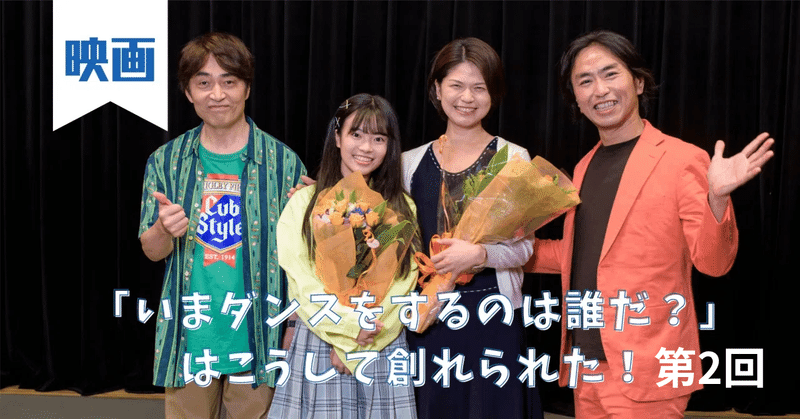
映画「いまダンスをするのは誰だ?」はこうして創られた!(第2回)
こんにちは😊
映画監督の古新舜といいます。
私は、独立系映画を長年続けて参りました。
初監督作品は、「ノー・ヴォイス」という映画を製作し、犬猫たちの殺処分という現実を如何にしたら解決していき、人間と犬猫とが共に幸せに暮らせる社会を如何にして実現していけるかを描きました。
2作目は、「あまのがわ」という映画を製作し、寝たきりの方が分身ロボットOriHimeを通じて、誰しもが活躍できる社会を如何にして実現していけるかを描きました。
最新作は、今回の投稿のタイトルにもあります「いまダンスをするのは誰だ?」(略して、いまダン)です。パーキンソン病という難病をテーマに、難病の理解とその方々の就労環境の向上、包摂性のある社会環境を生み出していくために製作を行いました。
お陰様で、全国で活動をさせていただいており、古新とお会いすると、
「私の話をもとに映画創って欲しい」「自分も映画製作をしたい!」「映画ってどうやって創られるの?」という声がわんさか届くため、今回のnoteを執筆しようと考えました。
最新作「いまダン」を題材として、製作過程をこと細かくお話しし、映画製作の裏側を知っていただくことで、映画の観方や捉え方を学んでいただきたいという目的があります。
全15章をnoteでは全8回に分けて、お届けしたいと思います。
第1回目はこちらに投稿いたしました。
今回は、第2回目の内容(第4章〜第6章)となります。

4:映画監督としての志が生まれた出来事
今から「いまダン」の話をと行きたいところですが、そこに行き着くまでに大切なことをお伝えさせてください。
映画監督デビューするまでは、短編映画の制作を長らくしていました。
お陰様で、全国の映画祭で多くの賞を受賞させていただき、若い頃はすっかり映画製作にのめり込んでいました。

短編映画でたくさんの評価をいただくと、次に目指すのは長編映画、すなわち劇場公開作品(長編映画)です。私もいろんな映画祭の応援を受けて、長編映画の企画を執筆しましたが、なかなかご縁に恵まれませんでした。
そんななか、友人の経営者からの紹介で企画が始まったのが、「ノー・ヴォイス」という作品でした。
犬猫の殺処分問題をテーマにした本作は、ペットショップで値段を付けて売られている犬や猫が多数ある反面、保健所に連れられて、1週間後にガス室で殺処分を受ける犬猫の悲しい現実を取り扱いました。一つひとつの命はどれも尊いはずであるのに、人間の身勝手さや無責任によって虐げられる命があることを多くの方々に伝えたい。そのような想いで4年間制作をし続けて完成された作品です。

DVDが購入され、自主上映会が続いています。
この作品を手がけてよかったと思えるのは、映画監督として自分が商業性重視のヒット作追求型の制作者の道ではなかったことに氣がつけたことでした。
短編映画で受賞を重ねていた当時は、売れる作品を作りたい、有名な作品にしたい、映画監督として注目されたいという野心が強くありました。そのため、映画監督になることが目的化してしまい、「なんのために」という目的を欠いたまま活動をしていました。
そんな中、この映画のテーマを授かり、そして2011年に東日本大震災で福島の南相馬でボランティア活動を2年間行ったことで、人間中心の社会での限界を感じたわけでした。

原発20km圏内に立ち入らせてもらって、「原子力明るい未来のエネルギー」と書かれた看板の街に、人間がいない中、犬猫たちが彷徨い歩き、家畜たちが野垂れ死ぬ光景を目の当たりにして、自分が撮るべき映画は、メジャー映画の道ではなく、大手メディアが扱えないようなテーマを取り上げていきたい。人間の優位性や人間中心の考えを取り払い、相対的に横の関係で、他者や対象を眼差していける作品を企画したい。そう考えるようになったのです。
そして、母校の早稲田大学の関係から、分身ロボットOriHimeの開発者の吉藤オリィさんと出会い、2作目の「あまのがわ」を企画することとなりました。
分身ロボットOriHimeは、体に障害を抱えた方がOriHimeを通じて外を散歩したり、仕事をすることができる遠隔コミュニケーションロボットです。オリィさんは、寝たきりで孤独を抱えている方々に向けて、人と接する機会を届け、社会参画へのきっかけを生み出してもらいたいという想いでこのロボットを生み出しました。

写真に写っている番田雄太さんは、4歳の時交通事故に遭遇し、20年以上病室の生活を強いられました。OriHimeと出会ってから、彼はエースパイロットとして、OriHimeを使って全国でオリィさんと共に講演会を行い、数千名のファンや友人ができました。彼は28歳で亡くなってしまいましたが、この映画を一緒に企画し、完成を強く待ち望んでいました。
「心が自由なら、どこへでも行き、なんでもできる」
という彼が残した言葉を胸に秘めて、2017年夏に屋久島・鹿児島市を舞台に撮影、2019年に公開させ、企画から足掛け約5年がかかりました。

お陰様でこの作品は第31回東京国際映画祭の特別招待作品に選ばれ、レッドカーペットを歩くことになりました。撮影前に亡くなった番田くんには、完成作品を見せてあげることはできませんでしたが、亡くなった彼の遺志は、しっかりと作品に吹き込むことができたと感じています。

天国の番田くんも一緒にこの場にいてくれたと感じています。
5:映画製作は人間力を試される
このように華やかな映画ですが、その背景では数多の関係者が関わり、長期間にわたり、製作に臨むわけなので、順風満帆なことばかりが起こるわけではありません。
古新が特に大切だと思ったことを以下に簡単にまとめたいと思います。
1)人間関係
映画を創りたい、映画に出演したいという方は山のようにいるわけですが、それぞれ想いが異なるわけです。昔の私のように有名になりたいという我が強い人も少なくありません。そのような人が映画に参加すると、どうなるかというとチームの関係性や雰囲氣が悪くなり、トラブルが多発するわけです。結果として、映画は完成しなくなり、最悪の場合、紛争や裁判というケースも考えられるわけです。古新の場合、作品が完成しないということはありませんでしたが、自分の人間力のなさで、たくさんの仲違いやトラブルを山ほど向き合ってきました。これらの出来事は、自分の人間性(感情のコントロールや対人関係のあり方)を向上させる大きなきっかけになりました。
2)お金のトラブル
独立系映画といえども、数百万円から数千万円までの費用がかかります。天候不順で撮影が延期されれば、一日で軽く百万円が追加でかかるというのは普通にあります。そのような映画製作ですので、映画の資金繰りというのは、大きなネックになってきます。資金が途中でショートすれば、作品は完成しないわけですから、製作統括者は是が非でも資金をかき集めてくるわけです。独立系映画では、映画への執念から、自宅を抵当に借金をするという話も少なからず聞きます。
また映画製作はブラックボックスになりがちで、慣習として契約書を巻くことが少ないこともトラブルの理由です。当社は、さまざまなトラブルを経験してきたので、現在は支払サイトは当月末〜翌月末払いとしていますが、支払いが履行されない、口約束で嘘をつかれたという話をたくさん聞きます。依頼していた提携会社が、支払う人に金員を支払わず、嘘をついてお金をとんずらするというケースも多々知っています。(真っ当に対応している人が、悪者扱いされるというケースです。)
本当に目を丸くするようなことが多いのですが、それだけ映画製作はブラックボックスかつ、ずる賢い人が少なからずいることは事実です。
小生もたくさん痛い目をあってきましたし、びっくりするような嘘もたくさん遭遇しましたが、これも全ては自分の人間性を高めるきっかけと捉え、自分がそういう人間にならないための試練だったと考えています。
3)仲間を信じる、大切にする
過重労働が多い映画の現場では、深夜を回る撮影も少なくありません。小生が体験してきた助監督時代は、29時、30時になることも少なくなく、睡眠時間も2、3時間で休みなしというのが普通でした。予算を抑えて、過酷な撮影を臨むわけなので、得てして長時間働けば(働かせれば)良いと考えがちですが、クリエイティブには体力も氣力も大切です。ですので、自分が助監督時代に受けてきたイジメや過重労働を、如何にして自分の立場では、それをせず(させず)に、この現場に参加できてよかった、次回もまたこのチームで撮影したいと思えるような関係にできるかを考えながら、撮影に向き合っています。
とはいえ、関係者があまりに多く、予測不可能なことも多々起きる撮影現場です。トラブルや不満が全くない現場というのは、きっと皆無なんだと思います。自身も完璧ではありませんから、一つひとつの失敗を糧にしながら、このトラブルはこうやって解決していこう、こういう不満はこういう形でケアしていこうと、常にスタッフさんやキャストさん、ステークホルダーとのコミュニケーションを大切にしながら、心理的安全性の高い撮影現場を心がけるようにしています。、
映画業界は、本当に特殊です。特に独自の文化や慣習があるため、製作チームもいつも同じメンバーとは限らず、新しいスタッフや関係者が参画することが往々にして多いです。ですので、自分の価値観を強く持っていたり、マウンティングをする人も少なからずおります。職人肌のスタッフが集まるので、意見の対立や考えの相違は必ず起こります。その上で大切なのは、チームをまとめ上げる人間性と精神性、くわえてコミュニケーションを取ることができるチーム作りが肝要になります。
自分が経験してきたことは、けっして他人が悪いと相手を責めるのではなく、自分の人間力を涵養させ、他者の人間性や性格を見抜ける大切な学びだったと捉えています。大切なことは、他者や出来事は変えられないが、自分の性格や物事の解釈は変えられるということです。
古新が自分の中で大切にしていることは、自己開示と合意形成です。
この辺りは、また別の機会にでもお話したいと思います。
6:映画製作における幸せ
過酷な映画製作で、課題や悩みは尽きませんが、それでも映画にのめり込む理由はさまざまあるかと思います。古新が下積み時代から監督業をする長い時間の上で感じたことをお話します。
1)作品が後世まで残る
やはりこれが一番大きいですね!よく知らない人に「古新さんの志事は形になって、後世の人にも観てもらえるのは幸せですよね」と言われます。どんな志事にも貴賎はありませんし、形に残らないものでも、心に残るのであれば、素晴らしいとお返事しているのですが、たしかに見える形で想いや思想を残せるのは、大変有難いことだと思っています。
映画は、歴代の先輩の映画製作者もそうですが、古びない普遍的な内容を暑かったり、当時の文化や生活様式を懐古できる時代を超越したコミュニケーションツールだと考えます。生きた証を残せて、感動を次世代に届けられる、映画の大きな魅力なのだと思います。
2)達成感が得られる
お金、人間関係、突発的なトラブルなどさまざまな試練を乗り越えて完成まで漕ぎ着けた時には、超難易度の高いロールプレイゲームをクリアした時のような達成感が味わえます。さまざまな仲間を集め、各々の能力やリソースを結集し、芸術作品を協働して生み出すことで、仲間との一体感や連帯感の延長にある唯一無二の達成感が得られます。
「あの時、あんなことがあったけど、なんとか乗り切れたよね」「もうダメかと思ったけど、奇跡が起きたね」というようなことは映画の製作では、多々起きてきます。レジリエンス(逆境力)とポジティブ思考は、映画製作者に求めらえる一つの素養かもしれません。これらがある人は、映画を長らく続けていますし、そうでないと、映画は辛い、大変だと愚痴っていつしか映画を辞めてしまっている方も多く見受けられます。義務感で創る映画というのはやはり長くは続かず、使命感や主体性無くして、作品製作は成り立たないのです。
よく若い方で、「映画が大好きで、昔から映画製作に憧れていました」と言って、映画撮影に参加される方が大変多くおられますが、撮影現場では、分刻みにでいろんな準備が進行するいわば借り物競走のような状況です。劇場で観客として観ている映画とは真逆の世界が繰り広げられており、1日で根をあげて、音信不通になるという方がいることは、私もよくお会いしましたし、他の現場でも頻繁に聞く話です。
「映画のエキストラとして参加したいです」という声もたくさん聞きますが、現場ではメイク・衣装・照明・撮影のセッティングに1シーンで1、2時間の準備を要することは日常茶飯事です。ですので、エキストラに初めて参加した人は、撮影が始まるまでこんなに準備が大変で待たされるなんて思ってもみなかったという話もしょっちゅう聞きます。
それだけ、観客として観る映画と、制作サイドで携わる映画とでは感じ方の相違は大きいのです。
3)お客さんから感謝の言葉をもらえる
映画祭で作品が受賞やノミネートをした際の感動は大変大きいですが、やはり観客の方々が、「感動しました!」「涙が止まりません」と歓喜の声を寄せてくれることは、製作者として何より嬉しいことです。
「いまダン」も、単館系の劇場で全国19箇所で公開されましたが、劇場で7、8回観たという方が少なからずいるなかで、18回観ましたという方もおられます。これには本当に驚かされました。
それだけ、自分たちが伝えたいメッセージがお客さんに届き、人生に希望や勇氣をもらえました、という言葉をいただけることは、映画製作者として何よりの幸せだと感じます。「いまダン」を観られた82歳のお婆様が、「私は82歳でもう人生終わったと思ったが、この映画を見てまだまだチャレンジすることがあると氣付きました」と伝えてもらえたことは、涙が出るほど嬉しい感想でした。

(お読み下さり有難うございます。第3回に続きます。次回をお愉しみに!)
>バリアフリー対応「いまダン」DVDご支援募集中です!温かい応援、よろしくお願いいたします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

