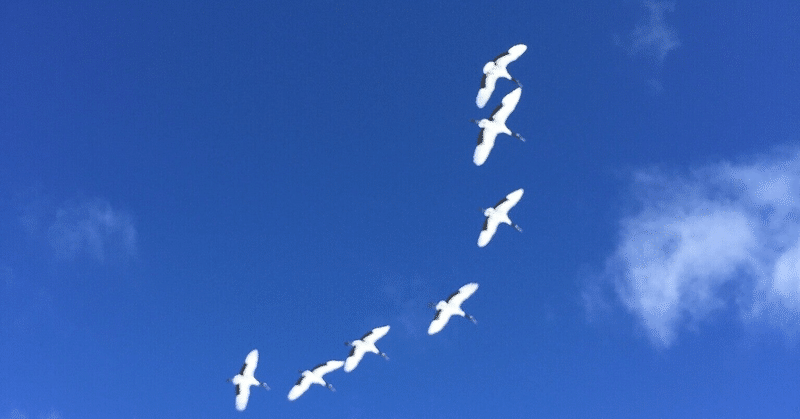
【短編小説】#わが子 (1/2)
廊下に面したアパートの換気扇を通して肉を炒める匂いがもれ漂ってくる。摺りガラスの向こうに淡い影が揺れる。
浩介はドアの前に立ち、呼び鈴を三回鳴らした。そのとたん、部屋の中から女の子の声がした。
「パパ」
その声と同時にドタドタという足音が近づいてきて、そしてカギの開く音がした。
「ただいま、結」
ドアを開けるとそこに待ち受けていた娘を抱きかかえ、浩介は部屋の中に入っていった。
「ちょっと、汚れるから服着替えてからにしてくれない」
景子は二人を追いながら言った。
結はそう言われると余計に強く抱きついて、鼻を父の肩に押し付けた。
浩介は笑いながら、結を高く持ち上げ、それから畳の上にゆっくりと降ろした。
浩介は汚れた作業着を脱いで先に風呂に入り、三人で夕食を食べ、それからテレビを眺めた。狭い部屋の中で身を寄せ合いながらこたつに入り、浩介は缶ビールを飲んだ。結は女の子の人形を大事そうに抱いている。結の母親が幼い頃に遊んでいた人形だった。結の母親がまだ幼かった頃、彼女の誕生日におばあちゃんが買ってきてくれたものだった。
結は人形の頭を撫で、それから「あかちゃん」とささやきながら母の膨らんだお腹を不器用に撫でた。妻はその手にそっと自分の手を重ねた。
「生まれてきたら、お人形貸してあげるね」
結は言い、景子は結の柔らかな髪の上に唇をあてた。
石油ストーブの上のやかんが小さく音を立てながら湯気を吹いている。浩介は立ち上がり、冷蔵庫からビールをもう一本持って戻ってきた。
「友だちの愛子の彼氏の写真よ」
景子は携帯電話のインスタグラムの画面を浩介に向けた。
「へえ。なかなかかっこいいやつだね。何してる人なんだろう」
「なんか工場で働いてる人みたいよ。なんの工場かはわかんないけど」彼女は言った。「でね、今度結婚するんだって」
「愛子さんって、一度うちに遊びに来てくれたことあったよな」
「うん、私らが結婚するときにお祝いを持ってきてくれたかな、たしか」
「じゃあ、俺らもまたお祝いをしてやらないとな」
浩介はそう言ってビールを飲んだ。
景子は自分たちのインスタグラムを開き、結と一緒に眺めはじめた。景子は自分たち家族の今の写真から次々と過去に遡ってめくり、結も時々何かを喋りながら自分たちが写っている写真を見つめた。
インスタグラムは彼らの楽しみのひとつだった。彼らは自分たちの写真を投稿し、友人たちからのコメントを読むのが好きだったし、友人たちの写真を見るのも好きだった。
浩介は二人の笑い声を聞きながらビールを飲み、テレビの画面を何とはなしに眺めた。テレビではくだらない番組が、まるで時間を埋めるためだけのように流れていた。
しばらくして娘を寝かしつけたあと、大きくなったお腹をさすりながら妻が戻ってきた。
「ねえ、今日さ、結の幼稚園でフリーマーケットをやってたの」景子は言った。「それでさ、赤ちゃんの服とかあったから一杯買ってきたの」
「へえ、そうなんだ」
浩介はテレビの画面を見やりながら答えた。
「フリーマーケットってなかなかいいわね。浩介は行ったことある、フリマって?」
「ああ、昔行ったことあるかな。なんかオカリナを買った覚えがあるよ。青くて小さくてきれいだったんだ。それからしばらく、オカリナの練習をしたりしてたんだけどな。そういえばあのオカリナ、どこやったっけかなぁ」
「へえ、あなたにオカリナなんて趣味があったなんて知らなかったわ」彼女は言った。「でね、今度またフリマを公園でやるみたいなんだけど、何か私も出してみるのもいいかなって思ったの。あなたのとか私のとか、もう着れなくなった服がいっぱいあるじゃない。あなたも私も随分太っちゃったからさ。だからそんなのを売ってみたらいいんじゃないかなって思うんだけど、いいかな?」
「いいんじゃないか」彼は言った。「でも売れそうな服なんてそんなにあったっけ?」
「あるある、山ほどあるわよ。あと、あなたの釣りの道具なんかも売っていいんじゃない。もう釣りなんか行ってないんだしさ」
彼女は言った。彼は腕を上に上げて体をぐっと伸ばした。
「いや、釣り道具は置いといてくれよ」
「なんで? もう使ってないじゃない」
「あれはだめだ。また落ち着いたら使うときが来るから」
「そうなの?」
彼女は残念そうにため息をついた。そしてまた携帯電話を眺めはじめた。浩介もその画面を覗き込み、一緒に友人の投稿を見ながらひとしきり話したり笑ったりした。それからその後、眠っている結の写真を撮り、早速その写真をアップした。そうして彼らのインスタグラムにまた一枚、微笑ましい写真が追加されたのだ。
テレビではニュース番組が流れていた。遠くの国で大きな地震が起きたことが報道されていた。
「もうお腹も大分大きくなったなあ」浩介は言った。「最近は赤ちゃんの様子はどうなんだい」
景子の肩に腕を回して浩介は尋ねた。
彼女は少し唇を突き出すようにした。
「そうね、今日はどうしてかこの子全く動かなかったのよ」彼女は首を傾げながら言った。「多分なにかに気分を損ねておへそを曲げちゃったのかも。あなたに似て結構気分屋なのかもしれないわね」
「そうなんだ。病院に行かなくて大丈夫かい」
「うん、大丈夫だと思う、しばらく様子をみることにするわ」
彼女は言った。浩介はうなずき、そして立ち上がった。
「お茶でも淹れようか」
「うん、お願い。ありがとう」
お腹に手を置いたまま、彼女は言った。
それから数日が過ぎたころ、景子は浩介に言った、お腹の赤ちゃんが動かないのだ、だから病院に一緒に行ってくれないかと。
次の日、結を幼稚園に送ったあと、彼ら夫婦は病院へ向かった。病院には多くの病人が詰めかけていた。駐車場に車を停めるのにも時間がかかったし、予約をしていなかったために待合室のソファの上で長い時間待たされることになった。
壁にかけられた時計の針の進むのが鉛のように重くゆっくりに感じられた。暖房が効きすぎているのか、じっと座っている間に段々と気分が悪くなってくるようだった。
景子は手を無意識のうちにその大きく膨らんだお腹の上に重ねていた。お腹の中の子は微動だにしない。ここで待たされている一刻一刻が事態を良くない方向に向かわせているようで、彼女の気持ちはいたたまれなくなった。
「大丈夫かい」
浩介は買ってきたペットボトルの水を差し出しながら尋ねた。彼女は黙ってペットボトルを受け取った。
「きっと大丈夫さ、赤ちゃんはきっと大丈夫だよ」
彼は彼女にそう声をかけた。
彼女はペットボトルの蓋を開け、ひと口だけ水を飲んだだけだった。そして、水の温度が室温と同じくらいになった頃、ようやく二人は診察室に呼ばれたのだ。
診察の後、神経質そうなその医者は彼女と彼を前にして静かに告げた。
「残念ながら、お腹の中のお子さんの心臓は動いていないようです」
彼女の目からどっと涙が溢れ出した。彼女は体を折り曲げ、激しく嗚咽したのだった。浩介は彼女の背中に手をやりながら、
「間違いないのでしょうか?」
と医師に尋ねた。医師は、黙って静かに頷いた。
「どうしてですか? どうして私たちの赤ちゃんがこんなことにならなければならないんですか? 私たちが一体何をしたっていうんでしょうか?」
隣で体を震わせている妻の背中をさすりながら彼は医師に聞いた。彼女の辛さや痛みが掌をとおしてまざまざと伝わってくる。医師は冷静な目で夫の質問を受け止めた。
「原因はまだはっきりとわかりません」医師は言った。「ただ、ごく稀にこういったことが起こるのです。それは誰にでも起こりうることなのです」
二人には、その医師の態度にある程度の誠実さを感じることができた。だがしかし、それでもまだ今の状況を受け入れることはできなかった。ただ呆然としながら、無機質な床に目をやり続けることしかできなかった。
医師は今後のことを淡々と語った。たとえ死産であったとしても、妻は出産をしなければならない。そして、日取りが決まればまた連絡をすると。
「このようなことになってしまったことは大変お気の毒です。どうかお気をしっかりとお持ちください」
医師はそう言うと、ふたりを病室の出口まで送り届けたのだった。
2/2へつづく
読んでいただいて、とてもうれしいです!
