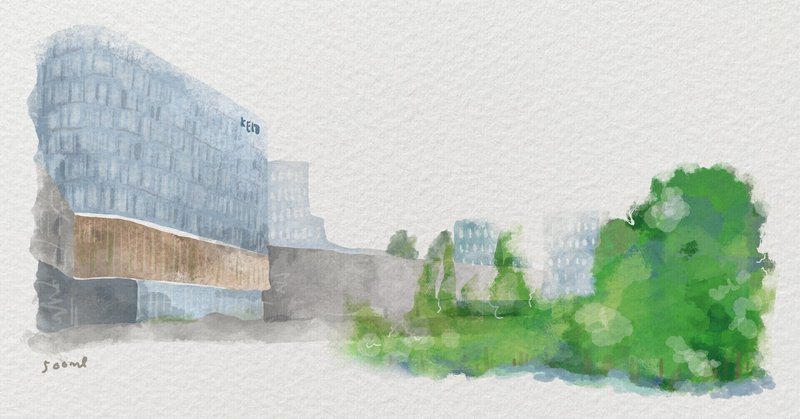
【ショートショート】傘
ぼくと彼女とは道端で時々出会う程度だ。仕事帰りや、昼休みに安食堂へ出かけるとき、ちょっとした仕事の息抜きなどで駅前を軽く散策するときなんかに彼女と出会うことがあるのだ。
彼女のことは実際のところ、まるで知らない。だからと言って、全くの他人でもないらしいのだから、少々困ってもいる。はじめて会った時に、彼女はぼくに、この辺で働いてるの?、と聞いてきた。
それ以来、ぼくと彼女とは中学時代の同級生ということになったのだ。あのさえない時代だった、まるで薄汚れた曇りガラスの中のような思春期のだ。
道端で出会った時には、彼女はいつも声をかけてくる。しかしどういうわけか、朝の通勤の時間帯だけは、すれ違ってこちらから声をかけようとしても彼女はぼくに気づかないことが多いのだけれど。彼女の拒むような固い表情に抑え込まれたぼくの声とほほえみを、ぼくは巧みに別の次元との隙間へと隠し込ませことができるのだ。彼女にだって彼女の事情もあるのだろうから。
彼女はぼくのことを宮川君、と呼ぶ。宮川というのは、確かにぼくのファミリーネームに間違いないのだけれど、ぼくは彼女の名前を―――一度聞いたはずなのだけれど―――思い出せない。彼女の記憶がまるでないのだ。
不思議なものだ。彼女はぼくのことを知っていて、ぼくは彼女のことを知らない。
仕事の帰り道、電車の高架下のベンチで缶コーヒーを飲んでいた。この街では、誰も知り合いはいない。アパートの暗い部屋に帰っても誰もいず、カッターシャツの襟ぐりが黒く汚れているのを見てげんなりするだけの毎日だ。名前も知らない彼女だけが、ここでの唯一の知り合いであり、全くの他人でもあった。
あの時もぼくは一人だった。ぼくが選挙権を得て間もないころだったから大学に入ってしばらくたってからの時期だったと思う。ある時本屋で立ち読みをしていると、高校の同級生の女の子とばったりであったのだ。その女の子は高校時代から魅力的で、紺色の制服がとてもよく似合っていて、その頃のぼくはほんの少し彼女が気になっていたのだ。
地元から遠く離れた街で、そんな彼女と出会ったことにびっくりしていると、その数日後に彼女から電話がかかってきて、今度一緒に食事でもどうかしら? と言うからさらに驚いてしまった。どうして電話番号を知ったのか、と聞くと、彼女はぼくの実家に電話をして教えてもらった、と言った。そしてぼくは彼女とデートすることになったのだが、待ち合わせのドーナツ店でドーナツを頬張りながら薄いコーヒーを飲んでいるときに、今度の選挙はどうするの? と彼女はいきなり聞いてきたのだ。ぼくはそのときは政治なんかにまるで興味がなかったので、特に何も考えてないということを答えた。すると彼女は、あるいかがわしい団体が支持する政党の名を告げ、臆することなくまっすぐにぼくの目を見つめながら、その政党にぜひ投票してくれるように頼んできたのだ。彼女は、ぼくの両親や友人にも、その政党に投票するよう頼んでほしい、ということだけ言うと、まだ昼前だというのにドーナツ屋からさっさと出て行ったのだ。あとにテーブルに残されたのは、ぼくのため息と、彼女とぼくの勘定だけだった。
そんなことがあっても、どういうわけかぼくはその後もどこかで彼女からの電話をまっていたのだ。
見知らぬ土地では誰しもが人恋しくなるのかもしれない。そして誰しもが何らかの事情を抱えて生きているものなのだ。
今日は昼過ぎからずっと小雨が降り続いていた。ぼくは傘をささずに駅に向かって歩いていた。すると、前から傘をさした彼女が歩いてきて、自分の傘を上下に振りながら言った。
「この傘、使ってちょうだい」
赤くて、大きな花柄の描かれた傘だった。
「駅まですぐだし、大丈夫だから」
ぼくは断わったけれど、彼女はぼくの手に自分の傘を強引に持たせてきた。彼女は自分のゆく手を指さして、私の家はすぐそこだから気にしないで。また今度返してくれたらいいから、と言って去っていった。
彼女とは今度いつ会えるのだろう?
そのときまで、ずっと彼女の傘を持ってぼくは歩き続けなければならないのだろうか?
いやそれよりも、はたして彼女は本当にぼくと知り合いなのだのだろうか?
読んでいただいて、とてもうれしいです!
