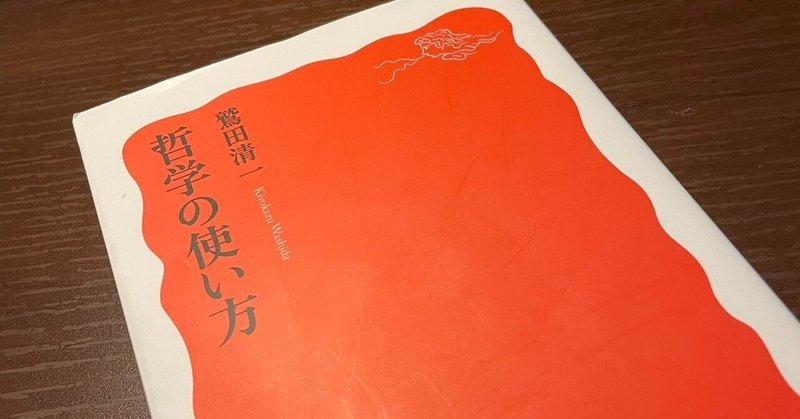
【読書】「哲学の使い方」
今回の読了本は『哲学の使い方』 鷲田清一著 岩波新書 です。
これまで哲学について学びたいと思いつつも、どこから踏み出そうかと迷っていたところ、書店の新書のコーナーで見つけました。
それなりに体力が必要である。
読んでいく時に強く感じたことです。
何かしらの専門書を読むときも近いものを感じますが、その場合は答え(事実)があり、自分の知識を付けていき理解度を深めていくといった具合ですが、哲学においては、すでに確立されている概念や知識に対して改めて質問を投げかけていく行為なので、彷徨い続けていく感覚に陥ります。
まるで宇宙の端っこを想像するような感じです。
永遠に繰り返す思考は、一周回ることがあっても、次はまた別のルートを辿っていきます。慣れた道よりも、初めて通る道の方が運転に疲れるような感覚です。
しかしながら、私はこの営みが心地よくとても好きなので継続し、体力をつけていきたいです。
初心者の私には…
ざっくり読後の感想ですが、
哲学の初心者(あえてここでは初心者と表現します)の私にとっては、少し難しい内容でした。
哲学史の知見はほとんどなく、「アプリオリ」とかカント、ソクラテスといった単語くらいは知っていましたが、大半が初めて触れる言葉で読むのが苦しいパートもありました。
その中でも興味深い箇所もあったので総合的には満足できました。
理解度としては1割にも満たないだろうと自己評価をしていますが、一回で理解できてしまっても面白くないので妥当な評価だと信じています(笑)
今回の記事はここまでにします
いくつか個人的に引用したい箇所がありましたが、それは別の機会で。
みなさんも一緒に哲学しましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
