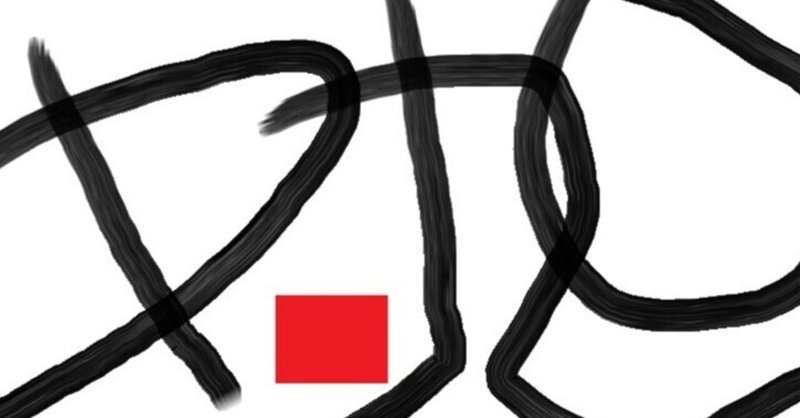
【超短編小説】海のパースペクティブ
もしも喝采を浴びるために生まれてきた男がいるとすれば、市長こそそれだとサンドラとぼくはいつも話していた。市長はまだ若く、多分30代半ばぐらいで、『或る夜の出来事』のクラーク・ゲーブルを思わせる針金っぽい髭を生やし、いつもビシッと髪を撫でつけ、英国紳士風のジャケットを粋に着こなしていた。そのくせ俗物じみたところがまるでないのは、誰といても君だけは特別だよと密かに告げるような、あのラクダっぽい睫毛とはしばみ色の瞳のせいに違いなかった。彼が市民ホールで演説をする時、ぼくらは毎回スタンディング・オベーションをし、女の子たちは歓声を上げて投げキッスをした。そんな時彼のまなざしは満足げに、あるいは物憂げに、空の彼方へと漂い流れるようだった。彼には天賦の才があったと、ぼくはどこででも証言する用意がある。その雄弁において、人心を把握し鼓舞するというリーダーにとって不可欠の資質において。
しかし市長の才能がもっともあからさまに発揮されるのは、その型にはまらない発想の独創性においてだった。彼はさまざまな施策、人々があっと驚くような斬新な事業計画を打ち出したが、彼にとってそれは息をするのと同じくらいごく自然なことだったに違いない。在職期間中に彼が次々と繰り出したアイデアはぼくらを幻惑し、高揚させ、この町に誇りを持たせてくれた。もちろん、あの壮大な海づくり構想もそんなアイデアの一つだった。
その日市民ホールの演壇に立った市長は、この町にもっとも必要なものは何でしょうかとぼくらに問いかけた。新しい市庁舎か? 駅か? バス路線か? スーパーマーケットか?
「いや、そんなものではありません」と彼のバリトンがホールに響き渡った。「そんなものは結局のところどうでもよく、退屈なだけです。私たちに必要なのはもっと根源的なもの、この町とそこに住む私たちを根本から変えるような何かなのです」それから彼はかつてエーゲ海に旅行した時の思い出を語った。朝日を浴びた海の輝き、どこまでも伸びていく水平線、この世のものとは思えない薄青い島の影たち、群れなすカモメたち。毎朝その光景の中に身を置いて私は生きる喜びに身を震わせたのです、と彼は語った。
「お分かりでしょう。この町に欠けているもの、それは海です。もし海があれば、私たちの生活は一変するでしょう。私たちは今以上にこの町を愛するようになるでしょう。考えてみて下さい、海があれば私たちは、夕暮れ時に潮風に吹かれながら波打ち際を散歩するでしょう。島影の向こうに沈む夕陽に涙し、家族への愛に息がつまりそうになるでしょう。あるいは夏の午後、若者たちは砂浜でビーチボーイズを聴くでしょう。犬は砂を蹴立てて走り回り、波しぶきをあげるでしょう。老夫婦は潮騒に耳を傾けて過ぎ去った日々の歓びを思い出し、長過ぎた歳月を慈しむために再び抱擁し合うでしょう。忘れないで下さい、人々の記憶に残る町にはみな海があります。海辺の街、なんという蠱惑的な響きでしょうか。しかし羨む必要はありません。私たちも海辺の街の住民になるのです。海をつくるのです。そのために、ぜひ皆さんの力を貸して下さい」
万雷の拍手が鳴り響く中、ぼくらの脳裏に来るべき未来の光景が広がった。砂丘に挟まれた僻地にではなく、潮風が吹き抜ける海辺の街で暮らすぼくら。紺碧の海に白いヨットで乗り出していくぼくら。サンドラの部屋に行ってビールを飲みながら、ぼくらは海への憧れについて語り合った。「私が憧れる町には全部海があるわ。サンフランシスコ、ニューヨーク、ナポリ、ヴェニス、リスボン」サンドラがホウとため息をつく。「パリとローマは?」「興味ないわ」
それからぼくらは、海が出てくる映画のタイトルを列挙していった。「太陽がいっぱい、グラン・ブルー、ジョーズ、気狂いピエロ」「渚にて、鳥、海の上のピアニスト、おもいでの夏」「レベッカ、キングコング、海辺のポーリーヌ」「レッドオクトーバーを追え、冒険者たち、ゴッドファーザー」「ゴッドファーザー? 海なんか出てきたっけ」「ほらあそこよ、兄貴が釣りに行って殺されるとこ」「あれ海だったかな」「海でしょ、だって釣りよ」
ぼくたちは愛を交わし、空腹を感じてピザを食べた。ペパロニを頬張りながらサンドラが言った。「市長の海づくりの件、レオはなんと言うかしら」「レオは関心ないよ、あんな市の事業なんて」「レオってクールよね。今恋人はいるの?」「フリーだよ」「どうして? ゲイじゃないんでしょう」「もう兄さんの話はやめよう」「あなた、もしかしてレオにコンプレックス持ってるんじゃない?」
もちろんぼくは知っていた、サンドラが昔からレオに特別な感情を抱いていることを。そもそもぼくと知り合ったのだって、当時フットボールのスターだったレオに近づくためだったということを。それでもぼくは構わなかったが、時々無性に腹が立つのはどうしようもない。兄があのアポロンみたいな完璧な顔立ちにニヤニヤ笑いを浮かべてぼくを見ると、時々殴りつけてやりたくなった。
市長が海づくりプランを発表すると同時に、町中がスタッフ募集のポスターで溢れかえった。ポスターには世界中の美しい海の光景があしらわれていた。リスボンの海や、ナポリの海や、アソーレス諸島の海や、ケープタウンの海。あるいはどことも知れない、幻みたいな異国の海。こんな海がぼくらの町にあったら、と思わずにはいられない夢のような光景の数々。ポスターはそんな海を従えてぼくらに手を伸ばし、呼びかけていた。プロジェクトに参加しよう、そして共に輝く未来を作ろうじゃないかと。「参加しようかな、どうせ失業中だし」とぼく。「半分ボランティアみたいな仕事らしいわよ」とサンドラ。「でも夢がある仕事だよ」「夢がある仕事って大体ブラックなのよ」
週刊誌T**が市長の海づくり構想に関するスキャンダル記事を掲載したのは、その数週間後のことだった。記事は海を作るなんてどんなテクノロジーをもってしても不可能であること、そんな戯言を信じるのはせいぜい小学生ぐらいであること、市長の本当の目的は砂丘の向こう側に住む人々を立ち退かせることだと断じていた。そして市長は業者と癒着し、利権にまみれた二枚舌の詐欺師だと厳しい調子で糾弾していた。一緒に掲載されている数々の写真や資料の写しは、その記事の信憑性を物語っていた。その日ぼくが居間に入っていくと、父が言った。「やっぱりな、こんなことだと思った」その手にはT**誌があった。父はアンチ市長だった。「あのちょび髭のペテン師めが。今度こそクビだぞ」その横でレオがソファーに寝そべってテレビを観ていた。
ぼくが失望と悲しみで口をきけないでいると、レオが言った。「父さん、そんな週刊誌の記事なんてろくなもんじゃないよ」「なんだって?」「前から考えてたんだけど」とアポロンの如き威厳とともに体を起こし、美しい笑みを浮かべ、驚きのあまり口をきけなくなっているぼくと父に告げた。「海づくりのプロジェクトに参加するよ。住み込みで働くから、この家を出ようと思う」「あのプロジェクトはインチキなんだぞ」「でも百万分の一の確率で本当に海を作るのだとしたら、ぼくもそれに関わりたい。ようやく気づいたんだよ、ぼくはこれまでずっとそんなことをやりたかったんだと。何か心を震わすようなロマンに、一度しかない人生を賭けてみたかったんだと」
なぜ兄があんなことを言ったのか、ぼくにはさっぱり分からない。レオはいつもクールでシニカルな都会人だったし、海や山みたいな自然が好きなのはいつもぼくの方で、レオはそんなぼくをからかってばかりいたのだ。けれども兄はその日の午後ボストンバックを持って家を出ていき、二度とこの家には戻らなかった。
もちろん、T**誌の記事は正しかった。最初から海なんて作れるわけがなかったのだ。すべてはペテンだった。記事の衝撃がぼくらの町を駆け抜けた後、市長の姿を公の場で見ることはなくなった。そして一カ月後にあっさり罷免され、そのままどこへともなく姿をくらましてしまった、自宅にあった数々の高価な美術品や陶器のコレクションとともに。海づくりプランは忘れ去られた。ぼくらの胸を騒がせた美しいポスターは黄ばんで破れ、風に吹き飛ばされた。あちこちにあったプレハブの事務所は閉鎖された。ぼくらはレオの帰りを待ったが、彼はそれっきり戻らなかった。
レオがいなくなってからサンドラはずっと不機嫌で、何かといえばぼくに八つ当たりした。父と母はぼくの前で兄のことを話さなくなった。ぼくはといえば、はるか昔、子供の頃レオと一緒に映画館で『シンドバッド7回目の航海』を観たことを思い出した。夜眠る前に子供部屋で、サイクロプスやロック鳥について語り合ったこと、骸骨剣士の真似をして遊んだことも。あの頃ぼくはいつもレオと一緒だった。そんなたくさんのことを、ぼくはすっかり忘れてしまっていたようだ。市長がいなくなって寒い季節がやってくると、また砂丘から砂混じりの風が吹いて来たが、ぼくとサンドラは長いことリスボンの海、ナポリの海、サントリーニ島の海のことを考えていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
