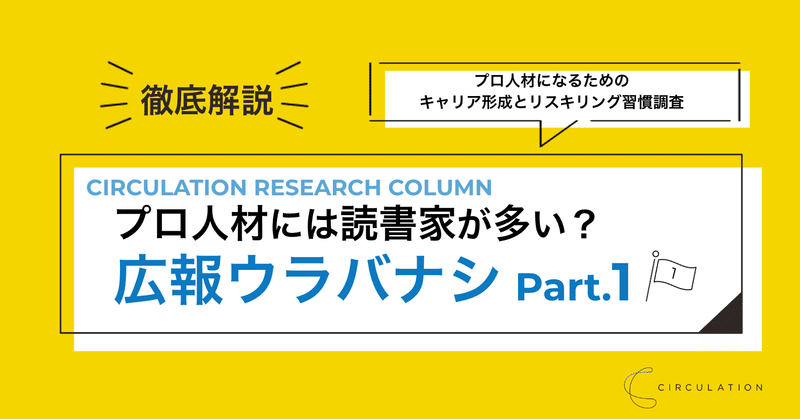
【徹底解説】プロ人材には読書家が多い?広報ウラバナシ Part.1
こんにちは。サーキュレーション広報の竹内です。
2022年10月にサーキュレーションから発表した「プロ人材になるためのキャリア形成とリスキリング調査」。
たくさんのプロ人材の方に協力いただき、貴重な調査データが集まりました。
「プレスだけさらっと見たけど、もっと知りたい!」
「調査やってて悩んだポイントってあった?」
などなど、発表後にもご質問を受けることが多く、今回noteで番外編として調査結果を独自に解説してみよう!ということになりました。
noteでは、3回に分けてその結果と考察について連載します。
プレスリリースと同じではつまらないので、広報竹内が勝手ながらコメントもつけさせていただこうと思います!
広報として調査に悩んだポイント、この調査だけではわからないことなども追記しましたので、同じ広報の方にとっても何か参考になれば幸いです。(Twitterでもたくさん調査について発信しています!)
この調査結果と解説が、プロシェアリング市場の理解だけでなく、働き方や学習習慣に悩む方々にも1つの参考としていただければ幸いです。

■なんで今調査したの?
背景には今、岸田内閣でも重視されている「人への投資」「リスキリング」などの動きがあります。また前提として、ここ5年ほどで「働き方」も変わりつつあります。2018年の働き方改革、そして2020年のコロナ禍以降、個人が1社の雇用に縛られないフリーランスや副業などの働き方への注目が高まり、2022年7月には厚労省も副業解禁に向けてガイドラインの改定を発表しました。その一方で、働き方の自由に伴うリスクも指摘されています。
個人の働き方も企業の人材活用のあり方も変わっていく今、
どうしたら高い能力を認められるプロ人材になれるのだろう?
プロ人材ってどのくらい勉強しているの?効果はあるの?
活躍し続けるビジネスパーソンは何をしているの?
などの疑問を解決したいという方も多いかもしれません。
実際に高度な専門性と生産性を武器にビジネス界で活躍しているトップクラスのプロ人材たちは、どのようなキャリアを会社員時代に歩み、日々どのような自己研鑽を行っているのでしょうか。調べてみました。
■そもそも「プロ人材」とは?
サーキュレーションは「プロ人材」を「高度な経営課題を解決できる人材」と捉えています。
ある特定の企業の出身者かどうか、高い役職に就いていたかどうか、特定の資格を保有しているか等の外形的情報だけでは、課題解決ができる人材かどうかは断定できません。
そのため、ご登録者に対してヒアリングを行い、過去ご経験されたプロジェクトや、キャリアのご志向などからプロとしての強みを分析しています。
サーキュレーション登録プロ人材の内訳・特徴はこちらからご覧いただけます。
■調査結果サマリー

これだけではまだどう受け取っていいか分かりませんよね。
ここではなんとなく、「稼いでいる人ほど勉強していそうだな…」と思っていただければOKです。
それでは、それぞれの結果について詳しく見ていきましょう。
■調査結果詳細
プロ人材の約8割は業務外での学習が習慣化している
「専門分野の技術やスキル向上、知識の習得」を目的として業務外で学習や能力開発などの取り組みを行っていると回答したプロ人材は約8割でした。全く何もしていないのは1.7%で、残りの18.5%は業務を通じて習得するという回答でした。

実は調査にあたって、ご支援いただいたプロ人材とはプチ議論がありました。
「プロ人材って本当に業務外で学習する必要があるんだっけ?」
という問いです。
最先端の知見を持つ「プロ」は最先端のプロジェクトに関わると仮定すると、本やニュースになる前の最先端のノウハウを得られるはず。
つまり、「業務中」だけでも十分学びがあるんじゃないの?と。
確かに、「業務を通じて習得する以外、特に何もしていない」と回答したプロ人材は18.5%と2割近くにのぼりました。仕事を通して成長する、いわば「セルフOJT」のサイクルが回っているということでしょう。(実際、どちらの学習パターンでも年収にあまり差はありませんでした。)
しかし結果は「ほぼ8割が業務外でも学習や能力開発を行っている」ということに。
次回の調査でも動機については出てきますが、やはり最先端の事例が生まれ続ける業界ということもあり、自身の案件だけで獲得できる経験・知見だけで留まらず、絶えず学び続けることが、ビジネス環境の変化に対応し続けるポイントなのかもしれません。
ちなみに株式会社パーソル総合研究所が日本を含むアジア太平洋地域(APAC)14の国・地域における就業実態・成長意識について調査した「APAC就業実態・成長意識調査(2019年)」によると、日本で働く人の46.3%が社外で自己研鑽しておらず、14の国・地域で最も高いという残念な結果になっています。学ばない日本人の中で、当たり前のように学び続ける人たちがプロ人材として活躍しているのはある意味納得できます。
年収が高い人たちほど毎日の学習習慣が定着している
総務省統計局の「平成 28年社会生活基本調査」によると、有業者が「学習・自己啓発・訓練」に充てる時間の平均値は一日にわずか6分でした。一方今回はプロ人材の学習頻度をたずねており、年収が高い層ほど学習頻度は高くなりました。市場価値の高い人材ほど、日常的なインプット習慣が身についていることが伺えます。

並べてみるとよく分かります。正直ここまで綺麗に差が出るとは思っていなかったので、びっくりしました。
注意すべき点は、アンケート調査だけでは「学習したから年収が高くなったのか」「年収が高くなったから学習するようになったのか」という時系列、因果関係は正確には分かりません。これを明らかにするには、ヒアリングなどを行う必要があります。しかし、実態として「年収が高い人は学習頻度が高い」ということは言えそうです。
「つい今日は疲れたから勉強したくないな」とか、「仕事が大変で気力がない」「物理的・プライベートに制限があって時間が取れない」など、さまざまな理由で勉強時間が取れない方は多いと思います。
しかし、やはり自分の能力や知識を高める時間を取れている方がプロ人材になっていくと考えると、「どうやって学習意欲を高めたり、時間を確保できるようになるか」というのは、私たち自身がより良い生き方を実現する上では大切なことではないかと個人的には感じます。
当然、こうした状況を打開するために、企業が自社社員従業員を「プロ」として育てていく上でも、リスキリングやキャリアを支援したり、エンパワーメントを行うことも大切でしょう。
今注目されている「人への投資」も、こうしたキャリア支援の取り組みに繋がるとよいですね。
プロ人材が選ぶ学習手段1位はやはり圧倒的に読書。オンライン学習も上位にランクイン
プロ人材の学習手段について、最も多かったのは「専門書」「ビジネス書」などの読書でした。その次に約3割程度がオンラインコンテンツを活用していると回答しています。

先ほど「本には最先端のプロジェクト内容は載っていないのでは?」という仮説を挙げましたが、やはり体系的に知識を獲得し、整理する上では本というのは優れたメディアなのではないかと個人的にも感じます。
私自身は広報として取材に協力いただくプロ人材や、異動前のプロシェアリングコンサルタント時代の3年間でプロ人材の方とお話しする機会が多いのですが、多読家が非常に多いなと感じていました。
中には「クライアント企業の社長と同じ本を読むことで、頭の中身を同じに近づけている」というプロ人材も。実際にそのプロ人材とタッグを組んだ社長からは「1を説明して10わかってもらえている」とコメントいただいていました。
では、日本人全体で読書習慣のある人はどのくらいなのでしょうか。
文化庁の調査がよく引用されています。平成30年度「国語に関する世論調査」では、1ヶ月に1冊も本を読まない人は47.3%もいました。先ほど紹介した「APAC就業実態・成長意識調査(2019年)」でも、アジア・オセアニア諸国の中で読書を行う人の平均が42.7%のなか、日本は最も低い27.4%でした。
「読書しない日本人」の姿を知ってこの結果を見ると、プロ人材として活躍されている方がインプット手段として読書を重視しているという回答に思うところのある方もいるのではないでしょうか。
61.9%のプロ人材が直近1年以内に新たな分野の学習を始めている
現在学習中の分野に取り組んでいる期間についてたずねたところ、 61.9%が直近1年以内に新たな分野を学習していることが分かりました。プロとして活躍し続けるため、常に幅広いインプットを怠らない「連続的学習」を実践している姿が伺えます。
一方、28.9%は3年以上の長期間に渡って同じ分野を学習し続けており、特定分野の専門性を高め続ける「継続的学習」戦略をとるプロ人材もいると想定されます。

学習期間が1年以内ということは、「比較的最近学び始めた分野である」ということが言えそうです。内容については今回調査できていませんが、プロ人材として専門性を確立している方でも、6割以上が新しい分野を学び始めているというのは継続的な学習サイクルが回っていることも伺えます。
もう少し詳しく、職種ごとに差がないか分解してみたのが次の図です。
職種で異なる2つの学習タイプ「短期サイクル型」と「継続学習型」

専門分野ごとに見ると、大きく2つの学習タイプに大別できそうです。
「現在学習している分野は1年以内に学習を始めた」と回答した人を、業務に活かす分野の更新が多く、直近のインプットテーマについて短期間で学習サイクルを回す意識の強い「短期サイクル型」、「3年以上前に学習を始めた」と回答した人を、業務の根幹となる1つの分野を中心にインプットを続ける「継続学習型」、それ以外を「バランス型」として分類してみたところ、短期サイクル型と継続学習型どちらかに偏る分野(職種)が存在していました。
専門分野ごとに、業務で活用する知見が次々に変わったり、逆に複数分野で共通の枠組みを活かしやすいなどの差があることも考えられます。
一方、年収別では学習タイプの分布差はほとんどありませんでした。
これはかなり作るのに苦労した表でした。
先ほどの回答で、今学習している分野に取り組んでいる期間が「1年以内」と答えた人と、「3年以上」と答えた人で大きく分かれそうだと思い、何がその差を分けているのか調べようと複数の切り口から見てみることにしました。
年収別ではほとんど回答の分布に差はありません。
性差、年齢差でもなさそうです。
そこで職種で分けてみたところ、かなり回答分布に差が現れました。それをランキングにしたものが上記の表です。
具体的に何を学んでいるのかについて、これ以上は一斉に調査をすることが難しかったため、範囲を絞って調査するか個別にヒアリングを行う必要があります。今後の調査で機会があれば、「自分の職種でプロとして活躍し続けるためにどんな学習スタンスが必要だと思うか」など、個々人の価値観が知れるような聞き取り調査を行うこともよいかもしれません。
終わりに
今回は、調査結果速報第1弾の解説についてご紹介しました。
ぜひ皆さんの感じたことや、もっとこんなことが知りたい!など、お気軽広報に聞かせていただければ幸いです。Twitterもnoteのシェアも大歓迎です。
次回以降もどうぞお楽しみに。
■調査概要

今回解説したプレスリリースはこちらからご覧いただけます!
調査についてのお問い合わせ先
株式会社サーキュレーション 広報/竹内
TEL: 03-6256-0467
FAX: 03-6256-0476
Email: public_relations@circu.co.jp
