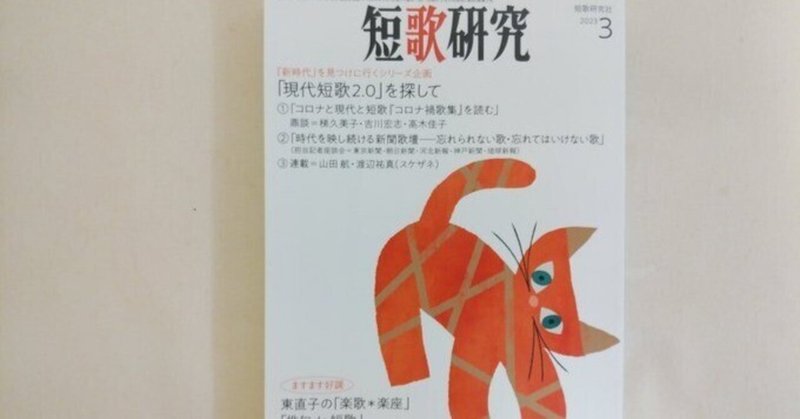
『短歌研究』2023年3月号
①三年を籠りゐて近隣の人の死も知らざりき死には音のなきゆゑ 佐藤通雅 コロナで三年間籠もっていて、近所の人が亡くなったのにも気づかなかった。コロナでお葬式も簡素化された。死には音が無いからとの理由づけが少し怖い。「し」音の連続が鋭い印象を与える。
②ふふふふと蝶は飛びつつたまゆらにひと焼き尽くす火のあることを 屋良健一郎 この火は実際の火なのか、情熱の火なのか。一首前が城跡にいる恋人同士の歌。首里城の火災を暗示して前者か。上句の思わせぶりな蝶から、後者か。どちらにしても燃える火が眼前する。
③草むらに自転車を乗り捨てたときそこだけ映画の真夏になった 千種創一 草むらに自転車を乗り捨てて、何か他の目的へ向かう。しかし別の自分が、草むらの中の自転車を映画の一場面のように俯瞰で見ている。そこに真夏の日が射し、自転車の銀色がそれを反射する。
④憎まれることを思うと生きたまま殻を剥がれたように苦しい 千種創一 人間に殻は無いが、この歌を読んだ者は、心や身体を覆う幻の殻を剥がされる感覚を追体験してしまう。人に憎まれること。そうしかできなかった行動によって誰かを深く傷つけてしまったのだ。
⑤会えなくなった人を愛する こころを 壊れた椅子のように軋ませ 千種創一 七七四七七と取った。三句の四音字足らずが不全感を出す。壊れた椅子の軋む音が幻聴のように響き、会えなくなった人の面影が蘇る。それは愛なのか。会えていた時は愛せていたのか。
⑥「二冊のコロナ禍歌集を読む」梯久美子・吉川宏志・高木佳子
高木〈参加者644人の644首から総体として何かが浮かび上ってくる。一人の歌人が作った歌集とはまた違う、強く見えてくる何かがあるのではないかと思いました。〉〈時が経てば記憶は薄れてしまうけれど『2020年コロナ禍歌集』には、そのときの空気が保存されているし、この2021年から2022年の『続コロナ禍歌集』の中にも、そのときの空気が保存されている。コロナ禍でそれぞれ違う環境にいる人たちの群像なんだけれど、一つの時代の群像として、本の中に収めることができたのではないかと思っているところです。〉
一人の歌集ならその作者の視点でしか描けないが、多数の作者の様々な視点で同じ時代を描くことによって、その時代が浮き彫りにされ、空気感が本の中に保存される。アンソロジーの優れた点であり、役割だと思う。
⑦「コロナ禍歌集を読む」
梯〈歌集は凝縮されたもので、十年に一回ぐらい出して、芸術的な高みをめざすというのはすごく理解できるんです。短歌はジャーナリステックなもの、文芸的なもの、日記みたいなもの。本当に多様性がありますね。〉
時事詠の特質でもある。
⑧「コロナ禍歌集を読む」
吉川〈見たことを詠うことによって、場面がまざまざと浮かび上がってくる歌があります。最近の短歌では、写実的な作品は、アララギ的、近代的だとして、もう古い表現と見なされている感じもあるんですよ。でも、島尾ミホさんが語っているように、物を見ることで自分と一体化する、という面は確かにあると感じました。見ることの大切さを改めて感じた言葉でしたね。〉
梯の著作『狂うひと』の中で島尾ミホが「見ることによって自分のものになる」と言っていた話について。読んでみたい本だ。見ることについての吉川の言葉も、示唆に富んでいる。
⑨特集「いままた注目の新聞歌壇」
この特集とても良かった。参加者の名前を書いておきたい。東京新聞 加古陽治氏、朝日新聞 佐々波幸子氏、河北新報 宮田建氏、神戸新聞 平松正子氏、琉球新報 高江洲洋子氏。全国紙と地方紙の両方を網羅しているのが良い。
⑩「新聞歌壇」
加古陽治〈まずは新聞歌壇の歴史について少しお話しします。一八九三(明治二六)年、落合直文が設立した短歌結社・あさ香社は自前の媒体を持っておらず、「日本」「二六新報」「自由新聞」といった新聞にあさ香社詠草として歌を出していました。これが新聞歌壇の始まりと言われています。今のように選歌欄を設けたのは一九〇〇(明治三三)年、「日本」が最初で選者は正岡子規でした。現存する新聞では一九〇三(明治三六)年に読売新聞が佐佐木信綱選で、都新聞(現東京新聞)が一九〇五(明治三八)年に与謝野晶子選、朝日新聞が一九一〇(明治四三)年に石川啄木選で始めました。〉
最初からこの歴史的な話で感動してしまった。まずはいつから新聞歌壇が始まったか…。このように詳しく説明されると、新聞歌壇担当者の方の本気が伝わって来て、思わず襟を正して読んだ。
⑪「新聞歌壇」〈東京新聞〉
加古〈東京歌壇で、過去五年間で印象に残った歌をご紹介します。年間賞、特選となった作品から選びました。
走れなくなった夏から鬼のままいつまでも夏至なんどでも夏至 (2019年8月25日/中森舞)
新聞歌壇は文学作品として物足りないという批判がありますが、この歌はそれに応える歌だと思います。作中主体の人の背景を多様に解釈できる、奥の深い歌だと思います。〉
詩を感じる。言葉は分かりやすいが、内容は単純ではない。その分、読者が自分の気持ちを反映しながら読める。
⑫「新聞歌壇」〈河北新報〉
宮田建〈他の社と重ならないようにあえて東北らしい歌を選びました。(…)
前世とは震災前の世にてあらむうつつの被災地に咲く山ざくら(2011年6月5日/仙台・泉 畠山みな子)
震災で生活はもちろん、価値観や人生観が大きく変わった人は少なくありません。「震災前」「震災後」は人生のさまざまな出来事を振り返るときの大きな境界になっています。〉
この畠山さんの歌は選者である佐藤通雅が『現代短歌』でも引いていて、特に心に残った歌だ。確かに自分の人生なのに、ほんの少し前の過去なのに、まるで前世のようにかけ離れたものに思えてしまう。そしてうつつ=現実の被災地は無惨に変わってしまっていて、そこに何も変わっていないかのように山桜が咲いている。二重三重に悲しみを秘め、かつ呆然とした気持ちが伝わる歌。
⑬「新聞歌壇」〈東京新聞〉
ガラス器の継がれてなおも立つ様を景色と呼べば遠い虐殺(2017年1月22日/穂崎円)
加古〈2017年の歌ですが、今ならウクライナ侵攻のことを詠んだ歌と読むこともできます。「景色と呼べば」深い感情移入がない。他人事です。それに対して「そんなことでいいの?」と問いかけている。時代を超えて心を揺さぶる、そういう力を「歌」は持っていると思います。〉象徴性の高い一首だから、どの虐殺にも当てはめて読める。自分にとって景色でしかない遠いできごとでも、虐殺は確かにあり、人の血が流されている。
⑭「新聞歌壇」その他、心に残った発言
加古〈歴史の中で埋もれがちな庶民の声を記録する装置、そういう意義があると思います。良くも悪くも新聞短歌には時代の空気、人々の考え方、風俗などが歌の中に保存されています。〉
『コロナ禍歌集』のところでも同感した。一人の歌集では出し切れない、時代の空気感というものが保存されているのだ。
あと、できれば投稿者に新聞を購読してほしいとか、メールによる投稿を検討している、やらざるを得ない、など切実な課題が語られている。一部は短歌結社の抱える課題とも被るところだと思った。
2023.3.10.~15.Twitterより編集再掲
