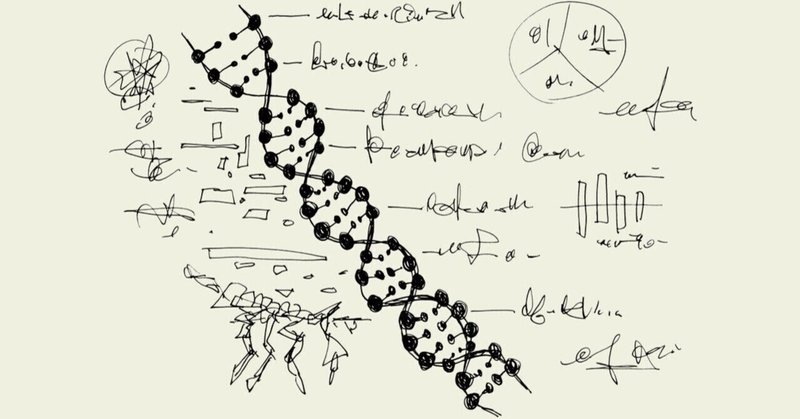
螺旋の向こうへ
あらすじ
国の研究機関でDNAの解析研究を行っていた野上祐子が新しく配属になったのは、あの有名な若き天才にして変人…青山治五郎教授の「節足動物総合研究2」であった。まさに奇才、青山教授と、チャラい見た目にそぐわず天才的な助手の志朗くん、そして、実は生物オタクの野上祐子が解き明かすDNAの不思議…。
野上祐子はきっちりとしたタイトなスーツに身をつつみ、A4サイズのバッグを肩から斜め掛けにし、歩きやすい平たい靴でスタスタと大学の廊下を進んでいた。
彼女は昨日まで、国立遺伝子解析センターでDNAの解析研究を行っていたのだが、今日からこの大学の研究室に配属となったのだ。
目的の部屋の前へ来ると、祐子は深呼吸をしてドアをノックした。すぐに中から「はいどうぞ」と返事があった。
祐子の新しい配属先は、あの有名な若き天才にして奇人…青山治五郎教授の「節足動物総合研究室〈2〉」である。
何でも教授のご指名で祐子が新しい助手として選ばれたのだと聞いた。なぜ教授が、会ったこともない平凡な一公務員にすぎない祐子を呼び寄せたのか、さっぱり見当もつかなかった。
今日は、その理由も探るべく、こうしてこの場所へとやって来たのだった。
祐子はそっと研究室のドアをあけた。
中はほこりっぽい薄暗い部屋で、研究室というには少々手狭に見えた。手前の机に若い男が座っていて、タブレットをいじっていた。祐子が入って行くと、その男が顔を上げて、ちーっすと言った。この子は教授じゃない…おそらく学生だ…。祐子は彼に軽く会釈すると、部屋の奥の方を覗き見た。そこには大きな机が置いてあり、本や書類が山のように積んであった。
祐子はわざと足音を立てながら歩くと、机の方へと向かった。書類の山の隙間を覗き込むと、向こう側に男が座っているのが見えた。
もじゃもじゃの頭、無精ひげ、黒縁眼鏡…。この男が青山治五郎に違いない。
「今日から配属になりました。野上祐子と申します」
祐子はなるべく事務的に聞こえるように声のトーンを調整して言い、ペコリと頭を下げた。
書類の向こうの男が顔を上げて、祐子の顔を見ようと覗き込んで来た。祐子は教授を覗き返した。
「はい。こんにちは。どうぞよろしく。ちょっとここやってから説明するから、悪いけど、そこに座って待ってて」
教授は、若い男の向かいの席を指しながら言った。
祐子は「はい」と返事をして席に座った。
向かい側の若い青年は相変わらずタブレットを見ていた。この類の研究室には似つかわしくない今どきのチャラい感じの男の子だった。熱心に何かをやっているが、仕事をしているとは思えなかった。彼女とメールでもしているのか、もしくはゲームか何かをしているのではないだろうか。
祐子は他にやることがなかったので、目の前の青年をじっと見ていた。
すると相手が視線に気が付き顔をあげ、彼女の方を見た。そして目が合うと、ウインクをしてにっこり微笑みかけてきたので、祐子はあわてて視線をそらした。
「ごめんごめん、待たせたね」
ここでちょうどよく教授が紙の山の向こうから出てきたので祐子は助かったと思った。
「知っていると思うけど、僕は青山治五郎だ。どうぞよろしく」
教授が右手を差し出してきたので、祐子は慌てて立ち上がり、その手を握った。ごつごつしているけれど乾いていて温かい手だった。
「野上祐子です」
「うん、さっき聞いた。で、こっちは志朗くん。僕の手伝いをしてくれてる学生さんだ」
紹介された志朗くんは、軽く頭を下げた。
「それで、君はどこまで説明されてここに来たの?」
「ご指名いただいたということしか聞いていません。あの…なぜ私なんでしょうか?」
青山教授がいつまでも握った手を放してくれないので、祐子はゆっくりと手を抜き取りながら言った。
「何でだと思う?」
「わかりません」
教授はふっふっふっ、と独特な笑いを漏らした。メガネが天井のライトに反射してキラリと光る。
若き天才…と言っても祐子より一回り年上だ。資料には38歳と書いてあったが、痩せているせいか、もう少し老けて見えた。
「君のSNSにさ、興味深いことを書いているのを見つけたんだよ。ほら、これ、“人間の言語遺伝子 FOXP2 は外部の何者かによって書き換えられていたりして…”ってやつ」
教授はポケットから携帯電話を取り出してSNSの画面を開くと祐子に見せた。
えっ?と祐子は息をのんだ。なぜなら、教授が見せてきたものは…。
「教授。そのアカウントは…えと…私の裏アカウントです」
「うん、知ってる。あ、僕のことは治五郎さんて呼んでよ。教授って呼ばれるの好きじゃないんだ」
祐子はこの仕事を受けてしまったことを猛烈に後悔し始めた。もしかして私、やばいところに来てしまったのでは…。
同僚はもちろん家族や友達にも知られていないはずの祐子の裏アカウント…。
現実から逃れるために作ったはずの密かなオアシスに、ズカズカと現実が入り込んで来た瞬間であった。
そんな祐子の様子に気が付いたのか、青山教授は真剣な顔になって話を続けた。
「怖がらせてしまったね。真面目な話なんだ。僕はね、この投稿を見つけて心臓が止まるんじゃないかってほど驚いたんだよ。
だってこれはまさに、僕が今ここで研究していることだからね。
“人間の言語遺伝子 FOXP2 は外部の何者かによって書き換えられている”
それで、こんなことを僕より先に気が付いた人がいるなら、ぜひ一緒に仕事をしなければ、と思って、何とか、ここにいる志朗くんに、このアカウントの主を探してもらったんだよ。運よく、彼はこの手のことが得意だったもんで」
志朗くんが少し気まずそうな顔をした。おそらく彼は裏アカウントを見られる屈辱を理解している。
それなのに、このマッドな教授に加担したのだ。このお礼はきっちりさせてもらうわよ。
祐子は志朗くんをにらみつけた。志朗くんはタブレットを持ち上げてその向こうに隠れてしまった。
「あ、大丈夫、これが君だってことは僕と志朗くん以外は知らないから」
(いや、大丈夫じゃないし…)
自分の裏アカを知っている人と仕事をするなんてありえない…。
初日から地獄すぎないか…。明日にでも配属替え希望を出すべきだろうか…。
祐子の頭の中にネガティブな思考が広がって行く。
しかし、さきほど教授が言ったことも同時に気になっていた。まずは説明を聞いてみる価値はあるかもしれない。
「教授は節足動物の研究をしているのではないんですか? FOXP2 とどう結びつくんです?」
FOXP2とは、様々な生物に見つかっている遺伝子で、具体的な働きは未解読だが、脳や肺の発達に関わる遺伝子らしいところまではわかっている。
そして、チンパンジーと人間の FOXP2 を比較すると、2か所だけ配列が異なっているところがある。この違いが、言語に関わっているとの説があり、FOXP2 は言語遺伝子と呼ばれることがある。
祐子はこのたった2か所の違いが、なぜ起こったのか、とても不自然に感じていて、誰かが意図的に操作したのではないのだろうか、という妄想を抱いていた。
もちろん、これはトンデモな発想であり、職場でこんなことを言ったら、たちまち変人扱いされてしまうだろう。
祐子の所属する国立遺伝子解析センターは国家機関だ。夢やロマンは立ち入る隙がない。
だから裏アカウントでその妄想を発散させたりしていたのだ。
そんな妄想の世界をこの人たちは真面目に研究しているというのか?
「我々の研究の発端について、話せば長くなるのだが…。あ、その前に、あのね、教授って呼ぶのやめてくれない。治五郎さんで」
祐子はやれやれとため息をついて続けた。
「はい、では治五郎さん…なぜ FOXP2 の研究をしてるのですか?」
「なぜ FOXP2 の研究をしてるのか…。いい質問です、祐子くん」
(祐子くん…)
「これ、何だか知ってる?」
治五郎さんが、資料の山をゴソゴソやって、何やらぬいぐるみのようなものを取り出してきた。
緑と青と黄色のマーブル柄の、セミのようなエビのような奇妙な生き物のぬいぐるみだった。
祐子はそれが何なのかすぐにわかった。
「オダライアですね。」
「そう! その通り! さすがです、祐子くん」
オダライアは今から約5億年前、カンブリア紀の海に生きていた節足動物の仲間である。
祐子は何を隠そう、カンブリア紀の生物マニアでもあるのだった。
そうだ…祐子の裏アカウントを見たのであればそのことも知っているのだろう。「カンブリア紀 萌え萌え生物」という漫画も投稿しているので。自分でも頭がおかしいと思う。
カンブリア紀は生命が爆発的に多様化した時代であり、この時代に現在ある動物の全ての「門」が出そろったと言われている。
カンブリア紀の海は神様の実験場だったのでは思えるほど、奇想天外でユニークな生き物で溢れ、祐子を決して飽きさせないのであった。
「僕はね、特にこのオダライアちゃんが大好きで、化石をいくつも集めているんだけど…。時々状態がものすごくよい子がいてね。もしかしたら、そこからDNAを取り出せるのではと思い立って、いくつものサンプルで試していたんだ」
化石からDNA…。まるでSF映画のような話だが、技術的には可能な話だ。
「もちろん、どんなに条件がよくても、化石から採取できるDNAはほんの少しだ。しかも周りの微生物のものもごちゃ混ぜだ。でも、それでもたくさんのサンプルから採取できれば、それなりのことがわかってくる」
祐子は治五郎さんの話にだんだんのめり込んで行った。
「ご存じのとおり、オダライアは節足動物の始まりに限りなく近い生き物だ。節足動物はこの地球上で最も発展した生き物と言っても過言ではない。DNAの解析ができれば、そんな生命の始まりの秘密がわかるかもしれないんだ。こんなにワクワクすることはないだろう?」
祐子はうんうんと何度も頷いた。
「それで、僕はまるでパズルのようにバラバラに採取されたオダライアのDNAを、何とかつなぎ合わせることはできないのか研究を始めたんだ。ああ、それをやりすぎて、五年前に節足動物総合研究室から追い出されて、この〈2〉ができたんだけどね」
治五郎さんはいかにも面白い、とでも言いようにぐふふと笑った。
「研究室を追い出されてしまったから、僕は仕方なく一人で研究を続けていたんだけど、どうもDNAの解析は苦手で…。君は専門だろうけど、あのATCGの4進法がしっくりこなくて…。まるでコンピュータプログラムじゃないか…。見ての通り僕はアナログ寄りな人間なもんでさ」
積みあがった紙の山を治五郎は指さす。
DNAの螺旋構造には、アデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G)という四種類の塩基が並んでいて、その配列によって遺伝情報が伝達されたり、タンパク質が生成されたりする。
そのために、DNAは4進法としばしば表現される。
「そんなこんなで、俺にはとてもじゃないがDNAの解析はできなかったのだ。そこでだ、このDNAの解析を、あえてDNAの基礎知識の全くないコンピューターや暗号の専門家にやらしてみたらどうなるのだろうか…と思いついてしまったんだよ。それで、志朗くんにお願いすることにしたんだ。彼は他校の学生なんだけど、特別にアルバイトで来てもらっている。こう見えても彼の暗号解読技術は日本トップレベルだ」
志朗くんは二本の指を立てて見せたが、祐子にはそれが何のサインなのかはわからなかった。
「彼の使っている暗号解読ソフトの制度を上げるためには、サンプルが多ければ多いほどよい、ということだったので、比較対象として、オダライアより前に存在していた節足動物に近い生き物のDNAや、オダライア後に出現した節足動物の仲間のDNAも渡した。古いものはどれも断片ばかりなんだけど、それでも志朗くんはすぐに要点を理解して、僕ひとりでは知りえなかったことを次々と発見してくれた」
治五郎さんは、ドサ、ドサと分厚い資料を祐子の机の上に載せた。祐子はそれをパラパラとめくって、たちまち夢中になってしまった。
国立遺伝子解析センターにもこれだけの資料はない。ないはずだ。
「これを? 志朗さんが全部やったんですか?」
「ちがいますよ、そっちは治五郎さんのオリジナルっす。俺のはこっちに入ってます」
タブレットの画面をトントンと叩きながら志朗くんが言った。
「見ます?」
志朗くんが画面を見せてきたので、祐子は覗き込んだ。棒グラフや円グラフがいくつも並んでいる画面だった。一瞬それが何を現しているのかわからなかったが、彼女はすぐに理解した。
「なるほど。同じ配列がどのくらいの頻度で出現するのかとか、近い種族の間でどの部分が異なっているのか。そういうことをチェックしているのね」
「これは解析結果のほんの一部っす」
「そして、志朗くんはとんでもない発見をしたんだ」
そう言いながら治五郎さんは葉書サイズのカードを祐子の前へ置いた。
そのカードにはこのように書かれていた。
add_ability { shareable_out; }
祐子はカードを拾い上げてまじまじと見た。意味は解らなかった。
「それは、志朗くんが開発した《LIFE》でヒトの FOXP2 の一部を表したものだ」
「らいふ?」
「《LIFE》については後程詳しく。そこに至るまでの話を先にさせてください」
志朗くんも自分の研究内容を話せる相手ができてうれしそうだった。
…確かにこんな話、私くらいにしかできないわ…と祐子は思った。
「治五郎さんからもらったDNAの情報を、俺はまずハッキングで使う暗号解読ソフトに入れてみたんすよ。そしたら、まあ、当たり前なんすけど、これは暗号ではないとの結果になって。人間の言語を基本にしている解析アルゴリズムではどうしてもDNAは解読できないんす。4進法だから人間のプログラム言語っぽく見えちゃうんすけどね、人間が作ったもんではないっすから。…だもんで、俺はまっさらなAIを作りました」
志朗くんがタブレットを操作して、画面に古めかしい本のページを表示させた。
「祐子さん、これ知ってます?」
画面を見ると、見たことがあるものだった。
「ヴォイニッチ手稿ね」
志朗くんはニヤリと笑いながら頷いた。
ヴォイニッチ手稿とは、未解読の文字と不可解な挿絵が書かれた世界一謎な本といわれる古書である。
現代においても何一つ解読できていない奇怪な本だ。
何ページにも渡ってびっしり文字があり、挿絵まであるのに、単語のひとつも解らない。
描かれている人物が何をしているのかも解らなければ、出て来る植物の種類もよく解らない。
「これを、AIが解読したかも…ってニュース覚えてます? 確かにAIならいつか解読するかもっすね。でも、その時、俺は思ったんす。もしもヴォイニッチ手稿が宇宙人によって書かれたものだったとしたら? 人間の言語を知らないAIが解読した方が効率よくね? って」
なるほど…この子は天才だわ。と祐子は思い始めていた。
「DNAの配列を見てて、俺はそれを思い出したんすよね。だから、俺のAIには人間の言語もコンピュータの言語も学習させずに、まずはDNAの配列だけを教えたんす。DNAの配列だけの世界で、この中に何を見出すのか…」
志朗くんは、再びサササッとタブレットを操作し、一つの表を映しだした。
「その結果がこれっす。まだ治五郎さんが拾い集めたDNAしか調べてないから確定ではないんすけど、少なくとも俺が調べたDNAは4種類の異なる言語が混ざって使われてました。それを仮に言語A、B、C、Dとして…図にするとこんな感じ」
タブレットを覗き込んでみたが、複雑な分布図のようなものだったので、祐子には理解はできなかった。
「あれっす、1曲をひとつの生物のサンプルと例えると、歌詞の一部が日本語だったり英語だったりするような感じっす。しかも、新しい年代のものほど言語が混ざっていて、古いものほど統一感があります」
「ちょっと見せて」
タブレットを受け取り、祐子はDNAの比較表を確認した。その中にはサソリのものがあった。サソリのDNAならば、たまたま先日ある報告書の作成をしたので、さんざん見たばかりだった。志朗くんのAIの解説によると、サソリは言語Aが60%、言語Bが25%、言語Cが15%で書かれているとのことだった。
祐子の頭の中でガラガラと複雑なパズルが音を立てて崩れて行った。
志朗くんの解説で、遺伝子の配列がよりクリアに理解できるような気がした。
「さっき、4つの言語って言ったわね。サソリには3つしか使われていないの?」
「そこなんすよ!」
志朗くんが急に興奮してぐっと顔を近づけてきたので、祐子はのけ反った。
「言語Dはごくごくたまにしか出現しません」
志朗くんがタブレットを祐子から受け取り、生物の名前が書かれた一覧を表示させた。
その中にはオダライアも含まれていた。
「これがこれまで発見した言語Dを持っている生物たちっす。これ見て何かわかります?」
祐子は一覧の名前をまじまじと見た。
「これは、種が分岐する境目にいるものが多い気がする」
「そのとおりだよ! 祐子くん!」
突然、治五郎さんが大きな声を出した。祐子はビクッとして彼を見た。
「言語Dは生物がその特徴を大きく変えるところで出現する。そこで僕はある仮設をたてた。言語Dは、おそらく、生物の進化に関わっていると」
「治五郎さんがこんなふうに言うんで、俺は面白半分でヒトのDNAをAIに解読させたんすよ。そしたら、FOXP2 の部分が言語Dだと出ました」
「それを聞いて僕は FOXP2 の虜になってしまったんだよ。チンパンジーやマウス、いろんな種が FOXP2 を持っているね。そのいくつかをAIに解読させてみたんだ。」
「ところが、ヒト以外の FOXP2 は調べた限りでは言語Bで書かれてるんすよね」
「今まで、なぜ人の FOXP2 だけ配列が違っているのか明確に答えられた人はいるかな? 志朗くんなら答えられる。ヒトの FOXP2 だけ言語が違うからなんだよ」
「す、すごいですよ!治五郎さん! あなたたちが発見したことの意味わかってます!?」
「充分すぎるほどわかっているよ、祐子くん。だから、まだこのことはどうか口外しないでほしい。まだ研究段階だからね。いいね」
祐子はごくりと唾を飲み込みながら頷いた。
「言語Dはそう頻繁には出現しない。要所要所で出てくるんだ。まだ、ここにあるサンプル分しか調べていないけど、どんな種の中に言語Dがあるのか、おおむね察しはついた」
「ここで俺たちは、どうしても、言語Dが何と言っているのか、具体的に知りたくなったんすよ。そんで、今までDNAしか知らなかったAIに、人間の言語を与えて、DNAの言語を俺たちにもわかるように翻訳してもらえないか試したんす」
「それで誕生したのが《LIFE》だ。これで我々はまるで本を読むようにDNAを読むことができるようになったのだ。と言っても、現在、この言語を解読できるのは、ここにいる志朗くんだけなんだがね」
志朗くんは照れたように鼻の下をこすった。
祐子は最初に見せられたヒトの FOXP2 の一部を《LIFE》で書いたというカードの文字列を眺めてみた。
「で、《LIFE》で翻訳したこの部分が言っている意味は…」
志朗くんはすーっと息を吸い込み、吐き出すように一気に言った。
「能力を追加、開始。言語。終了。」
しばらく祐子は無言でその言葉の解釈を探していた。が、見つからなかった。
「“言語” って翻訳、割と飛躍なんすけどね。何しろ他に比較できる配列がないもんで。直訳すると “共有できる出力” っす」
「…つまり、どういうことです?」
「そのままの意味だと思うよ。言語能力を追加したんだろうね」
混乱する祐子に向かって治五郎さんが答えにならない答えを答えた。
「追加って、誰が?」
「わからない…。この謎をぜひ、祐子くん、君と一緒に解いていきたいんだ。協力してくれるかな?」
聞かれるまでもなかった。祐子は二つ返事で彼らの研究に参加することを決めた。
その日は家に帰っても興奮が収まらなかった。
志朗くんに見せてもらったカードの文字列を何度も思い返した。
add_ability { shareable_out; }
「言語能力を追加…」
口に出して言うと、全身に鳥肌が立った。
…そんなことってある??
翌日から祐子はAIが言語Dだと判断した箇所の詳しい解析と、その部分の《LIFE》の翻訳を比較する作業をひたすらこなした。
また、言語Dが出現するのではないかと目星をつけたいくつかの種のDNA情報をかきあつめ、片っ端から志朗くんへ渡していった。
彼らは今まで古代の節足動物ばかりを調べていたのでサンプルがだいぶ偏っている。もっと広範囲にわたる研究が必要だ。
例の裏アカウントは初日の夜に「身バレしたので閉鎖します」と投稿し、翌日アカウントごと削除した。
フォロワーも数百人程度しかいないアカウントだったけど、少し寂しかった。
しかし、治五郎さんと志朗くんに知られているからにはしかたない。
カギをつけて続行しようかとも考えたが、既に奴らには既にフォローされているだろう。どのアカウントかわからなかったけど。
翌日、治五郎さんにアカウントを削除したことを大変残念がられたが、祐子はそれを無視した。
こうして祐子が「節足動物総合研究室〈2〉」で働き始めて2週間ほどがたったある日。
いつものように彼女が出勤すると、ぴっちりしたパンツ一枚の姿の治五郎さんが本棚の前に立って何やら資料を探しているところに出くわした。
祐子はギャっと声をあげ、柱の陰に隠れた。
「治五郎さん! 何してるんですかっ! 何で裸なんですかっ!」
治五郎さんは、「ん?」とこちらに振り返って祐子の様子を見ると、あははと笑った。
「ああ、これはすまない。長らく職場に女性がいない環境だったもので、うっかりしてた」
と言いながらも、治五郎は裸を隠すつもりはないらしく、そのままの姿で部屋の中をウロウロし続けていた。
それは、服を着ていないだけで、まるっきり普段通りの彼の動きだった。
祐子はしかたなく自分の席に座ると、パソコンを開き仕事を始めた。
しかし、視界にチラチラと入ってくる治五郎の裸が気になって全く集中できなかった。
意外なことに治五郎はかなりいい身体をしていた。
服を着ているとガリガリに見えていたのだが、ボクサーのように引き締まった肉体美だ。
そんなわけで、祐子はどうしても治五郎さんを見てしまうのであった。
「治五郎さん、気が散るので服着てくれませんか?」
治五郎が服を着る様子がないので、祐子は思い切ってお願いしてみた。
「それが、着たくても着れないんだよ」
何を言ってるのかしら、この人…。と祐子が少し不安に思ったところで志朗くんが入ってきた。
「治五郎さん、乾いたっす!」
「ああ、ありごとう。すまなかったね。助かったよ」
治五郎さんは志朗くんから紙袋を受け取ると、中から服を取り出しそれを着始めた。
「いやね、さっきここにくる途中で、植木に水をやっている人がいてね。おもいきり水を被ってしまったんだ。それで志朗くんにコインランドリーに乾かしに行ってもらっていたんだ」
治五郎さんは服を着ると、何事もなかったかのようにまた仕事に戻ってしまった。
祐子は向かいの席に座った志朗くんにこっそり話しかけた。
「治五郎さんて何者なの? ムキムキだったけど!? 教授にあんな筋肉いる?」
志朗くんはそれを聞くとあははと笑った。
「俺も最初見た時ビビったっす。治五郎さんは空手五段のバリバリの格闘家でもあるんすよ」
「ええ…!? 空手…」
「この業界は何かと物騒なこともあるからね。君も鍛えておいた方がいいよ」
治五郎さんが書類の向こうからひょいと顔を出して言った。
祐子に言っているのだった。
「え? 私? 無理ですよ。仕事だけで手一杯です。この部屋にずっといるのに、いったいいつ鍛えてるんですか?」
「祐子くんと僕がこの部屋で一緒にいるのはせいぜい週の30~40%だよ。その間にこの部屋にいるからといって “ずっとここにいる” と定義するのは乱暴過ぎないかい?」
「そ、そうですね。じゃあ、私も残りの60~70%でジムに行って身体を鍛えておきます」
「そうしてくれたまえ。早速、来週頭に君の元職場へ潜入しようと思っているのだ」
予想外の展開に祐子は目をぱちくりさせて驚いた。
「言語Dに気が付いたのはどうやら我々だけではないようだよ祐子くん。君はまだあそこの職員ってことになってるの? 入館証みたいの持ってる?」
「入館証はまだ持ってますよ、ここには出向という扱いですから。でも何なんです?」
「それは行ってのお楽しみだよ」
治五郎さんは不敵な笑みを浮かべながら書類の向こうに隠れてしまった。
翌週の火曜日の夕方、祐子は治五郎さんと志朗くんを連れ立って国立遺伝子解析センターを訪れていた。
夕方の訪問にした理由は、志朗くんの授業がちょうど終わる時間帯でもあったし、祐子の経験上、一番外部からの訪問者が多く、うろついていても目立たないだろうと思われたからだ。
治五郎がどうしても確認したい資料は、職員のみが閲覧可能な持ち出し禁止のものだった。
祐子が同伴して保管室に入り、しれっと見ちゃおうというずさんな計画だ。
変にコソコソするより、どうどうと行った方がバレないだろう、という志朗くんの案である。
ここで働いている当時の祐子だったら、絶対にこんな規則違反はしなかっただろうが、治五郎さんたちと1ヶ月近く共に働くうちに、少々彼らの破天荒な性分がうつってしまったようだ。
現に祐子は少しワクワクした気持ちになっていた。
彼らは難なくセンター内に侵入すると、保管室に入った。
治五郎さんは真っ先に「FOXP2」と書かれた引き出しの中の資料を漁り始めた。そして、目的のものを見つけたのか、ひとつのファイルを引き出し、中を見て、ぬがぁと変な声をだした。
「黒塗り地獄だ…」
治五郎さんが手渡して来た資料を開いてみて、祐子はギョッとした。それは、文章のほとんどが黒塗りにされている、三峰教授の論文だった。
三峰教授といえば、ヒトのDNA研究の第一人者であるが、残念ながら去年亡くなってしまった。
「何をしている!」
突然背後で声がして、三人は振り返った。そこには全身黒ずくめの長身の男が立っていた。
職員でも警備員でもなさそうだった。
こちらの返事を待たずに、黒ずくめの男はレスリングのタックルのような動きで飛びかかって来た。
すかさず治五郎さんが目にも止まらぬ速さで動き、男の腕を取った。そして間髪入れずに男の腹を蹴る。
男はギャッと声をだして、片膝を地面についた。
「志朗くん、祐子くんをつれて逃げなさい。」
「ラジャ!」
志朗くんは祐子の手を取ると、ためらうことなく、保管室から逃げ出した。
祐子は治五郎が心配になり、志朗くんの手を振りほどいて戻ろうとした。
「ダメだよゆうこりん!忘れたの? あの人はめっちゃ強い! 大丈夫だよ!」
それで祐子は自分が戻った方が危険だと悟り、志朗くんと共に足早に施設を後にした。
施設の最寄り駅の改札で待っていると、ほどなくして治五郎さんが何食わぬ顔でやってきた。
「あの男は施設に雇われたシークレット ガードマンだった。誰の命令だったのか全く口を割らない」
治五郎さんがガードマンからどうやって話を聞こうとしたのか知りたくもない…と思いつつ、アクションとは無縁と思っていた自分の人生にこんなことが起こるなんて、と祐子はドキドキしていた。
「見つかっちゃいましたけど、大丈夫なんでしょうか?」
「しばらくは大丈夫だろう。奴らにはどうしても知られたくないことがあるようだ。だから、シークレット ガードマンなんか雇っているんだし。僕らが何を探していたのか公表されたくないだろうから、全てを無かったことにしようとするだろう。僕はこれからどうするか考えるから、ひとまず君たちは家に帰りなさい。念のために人気のないところは歩かないように。戸締りはしっかり」
そういって、治五郎はタクシーを捕まえてどこかへ行ってしまった。
残された祐子と志朗もタクシーで帰ろうか悩んだが、人目の多い電車で帰るのがよさそうだとの結論に達した。
家に無事つくと、祐子は熱いシャワーを浴びた。普段ならそれでバタンキューなのだが、今夜は眠れそうもなかった。
祐子はほとんど眠れないまま翌朝を迎え、出勤した。
研究室に入ると、見知らぬ男が部屋の真ん中に立っていた。
祐子は昨日の調査で誰か来たのではと思い、あわててドアを閉めると部屋の外へ一度避難した。
すると中から治五郎さんの声がした。
「どうした? 今日の計画を話すから入っておいで」
祐子がおそるおそる部屋に入ると、やはり知らない男がこちらを向いて立っていた。
「じゃあ、始めるよ」
その男が言った。治五郎さんの声だった。
祐子は狐につままれたような気持ちで目の前の男をよくよく見てみた。
そして驚いた。
それは治五郎さんだった。髪をしっかりとかし、無精ひげをそり、眼鏡をはずして、びしっとしたスーツを着ている。
まるで別人に見える…。
「見とれすぎっすよ」
まるっきり視界に入っていなかった志朗くんに言われ、祐子はハッと我に返った。
「昨日のあの様子じゃもうあそこに侵入するのは無理だ。だから、これから玲子に直談判しに行く」
玲子?
誰だっけ? と祐子が考えていると、治五郎さんが急かすように彼女を呼んだ。
「ほらほら、祐子くん、ぼーっとしないで。三人で一緒に行くんだよ」
そこで、祐子ははたと気が付いた。
(玲子って、来宮玲子!!??)
それは…泣く子も黙る国立遺伝子解析センター副所長様だ。
事の成り行きを全く把握できないままに、祐子は治五郎さんたちと共に再び国立遺伝子解析センターへとやって来た。
昨日とは違い、今日は表門から堂々と三人は施設内へと入った。
「うちの副所長とお知り合いなら、最初から頼めばよかったじゃないですか」
「苦手なんだよ、あいつ。できれば会いたくない」
珍しく治五郎さんは弱気になっている様子だった。
(どういう関係なんだろう…玲子って呼び捨てだし…)
祐子は治五郎さんと来宮玲子の関係をあれこれ妄想してしまった。
しばらく応接室で待たされた後、秘書が三人を呼びに来た。
広い会議室に通されると、中では来宮玲子が一人で待っていた。
「私を呼び出すなんてよっぽどのことね。何があったの?」
挨拶の言葉もなく来宮玲子が話し始め二人の距離感を物語っていた。
「三峰教授のFOXP2に関する論文が見たいんだ。保管室にあったものはほとんど黒塗りだった。原本は君が持っているはずだ」
「さあ? 何の話? さっぱりわからないわ」
ここで、来宮玲子が祐子に気が付いた。
「その子はあなたが引き抜いたうちの職員ね。人質のつもり?」
「違うよ。祐子くんはとっても優秀な人材だ。僕にはどうしても彼女が必要なんだ」
ふん。と来宮玲子は鼻を鳴らした。
「野上さん。配属先の環境が悪かったら遠慮なく言ってね」
祐子は「はあ…」としか言えなかった。
「とにかく、私は三峰教授の論文なんて知らないわ。昨日のごたごたのことは無かったことにしてあげるから、もう今日は帰ってちょうだい」
治五郎さんはやれやれと言った感じで頭をかくと、ポケットから眼鏡を取り出し掛けた。彼はしばらく来宮玲子のことを見ていたが、これ以上彼女が何も言わないとわかると、くるりと後ろを向いて会議室から出て行ってしまった。
志朗くんもお辞儀をするとスタスタ出て行ったので、祐子は慌てて後を追った。
治五郎さんは速足で施設から出ると駅の改札へと戻って来た。やっと彼が立ち止まったので、「何もわかりませんででしたね…」と祐子は残念そうに言った。
すると、治五郎さんが振り返り、ぐっと祐子に顔を近づけてきた。
「いや、重要なことがわかったぞ。祐子くんは気が付かなかったのか?」
祐子はのけぞりながら、目をぱちくりさせた。
「何でしょうか?」
「モールス信号だよ」
治五郎さんは、ぐるっと首を回して志朗くんの方を向いた。
「志朗くんはわかったかい?」
志朗くんは、うんうん、と頷いて見せた。彼も興奮している様子だ。
「玲子は瞬きでモールス信号を送って来ていた」
治五郎さんは鼻の穴を膨らませて思い切り息を吸い込むと、震える声でこう言った。
「V・I・R・U・S、ウイルスだ」
「ウイルス…?」
「そうだ!玲子は “ウイルス” と送って来ていた! そうだね志朗くん?」
志朗くんは、再び、うんうん、と頷いた。
「これは盲点だった。ウイルスだよ、祐子くん。さっそく研究室に戻って調査を開始しよう」
治五郎さんはポンポンと祐子の肩を叩くと、改札に入って行ってしまった。祐子と志朗くんもそれに続いた。
研究室に戻ってくると、さっそく代表的なウイルスのDNAやRNAを集めて志朗くんのAIに解析させた。
その結果、その全てが言語Dであるとの判定になった。
「オールD…か…」
治五郎さんは噛みしめるように言った。
「言語Dは恐らく生物の進化に関わりがある…。そしてウイルスの遺伝子は言語Dでできている…」
「つまり…」
「つまり! ウイルスが生物の進化に大きくかかわっている!?」
治五郎さんは小さなガッツポーズを作りながら、研究室の中をウロウロ歩いた。
この結果を鵜呑みにしてはいけないと祐子の本能が言っていた。
冷静に…。こういうときほど冷静に。
「その説は以前からありますが、一般的には認められていません」
祐子はできるだけ平然と言ったつもりだった。だけれども声が震えてしまった。
「確かにそうだ、祐子くん。この説は既存のものだ。そして学会に相手にされて来なかったのは、明確な証拠を提示できていなかったからだ。
我々とて例外ではない。これだけではまだ証拠不十分。世に出すにはツッコミどころが多すぎだ。慎重にならないとオカルトとして片付けられて終わりだ。
志朗くん、ウイルスのDNAもしくはRNAを《LIFE》に変換してみてくれないか?」
「了解。どのウイルスをやります?」
「まずは インフルエンザ だな」
志朗くんがタブレットを操作した。変換には数秒かかる。結果が出たのか、志朗くんの表情がみるみる険しくなって行った。
それを見て、治五郎さんと祐子は彼の元に駆け寄り、タブレットの画面を覗きこんだ。
それは祐子が見ても一発で異常さが解る結果だった。
全身に鳥肌が立つ。
そこにはこんな数字が並んでいた。
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
祐子は数字を目で追った。この数字は…。これは…!
「…素数!?」
「志朗くん。他のウイルスも翻訳してみてくれ」
その他のタイプの違う様々なウイルスを調べてみたところ、ほとんどのウイルスの遺伝子の中に素数が隠されていることがわかった。
素数の出現パターンはまちまちで、冒頭にいきなり出て来たり、何の脈略もなく途中に出て来たり、文末に挿入されていたりした。
また、2~97までが並んでいることがほとんどだったが、時々997まであったり、47~461までと中途半端だったりもした。
もちろん、素数が全く出現しないウイルスもあった。
ウイルスの遺伝子情報を言語に変換すると、素数が出てくる…。いったいこれは何を意味しているのだろうか??
「素数を並べる時はどんな時だ?」
祐子は昔見たSF映画を思い出した。
「“素数を知っている” “知性がある” と知らせるため?」
「そうだな。そうだよな。ではなぜ、ウイルスに素数が??」
「ウイルスが素数を知っていると私たちに言っている?」
「まさか!?」
「ウイルスを作った奴らが、“我々は素数を知っている。これは意図的に作られたものだ” と言ってるんじゃないすか?」
志朗くんの意見に治五郎さんと祐子は息をのんだ。
祐子はもう一度、インフルエンザウイルスに出現した素数を見返した。去年の冬にインフルエンザにかかったのを思い出した。あの時に、こんな素数を持っている奴に侵入されたのかと思うとゾクっとした。
「ウイルスの言語を見ていて思ったんすよ。これ、俺たちがコンピューターウイルスと言っているものにすごく似ている。ウイルスの遺伝子には、いろいろ改ざんしたり、書き加えたり、削除したり、実行したり、そういう命令がたくさん出てくるんすよね」
「ということは、人間の FOXP2 もウイルスに書き加えられたという可能性があるってこと?」
「そうなりますね…。ここに出て来る命令のひとつひとつは遺伝子の配列を微妙に変える程度のチマチマしたものばかりす。何百世代も経たないと表に出てこないくらいのもんで。でも、複数のウイルスの言語が組み合わさると、時に “サルに言葉をインストール” とかいう極端な変化や、突然変異を起こさせたりもあり得るかもしれない」
“人間の言語遺伝子FOXP2は外部の何者かによって書き換えられていたりして…”
祐子は自分が面白半分に書いたつぶやきが現実味を帯びてきたことにめまいを覚えた。
「こうなってくると、“ウイルスを誰が作ったのか” 気になっちゃうよな~」
治五郎さんが顎に手を当てながら、研究室の中をウロウロ歩いた。
「…当たり前っすけど…ウイルスの方が人間の文明よりずっと古いっす…」
これが意味すること。祐子にはわかっていたが、口にするのははばかれた。
代わりに治五郎さんが引き継いだ。
「あくまでも仮設、ということにしておこう。…人類が誕生するずっと以前に、素数を知る何者かがウイルスを作り、それを使って様々な生物の進化に介入してきた…」
「ウイルスから素数が出たからには、人類より先に素数を知る奴がいたってことは明白っす。AIのバグって可能性もあるかもしれないけど、いくらなんでも何かを素数と誤解するってことはあり得ないっす」
志朗くんは確信しているようだ。
「つまり、人類より先に高度な文明を持った何者かがこの地球にいる、もしくはいた。志朗くんはそう思うのかい?」
「このDNAの調査を始めて、俺はずっと感じてたっす。こんなもの誰が作ったんだろうって。あまりにも複雑で美しく、そして完璧なプログラムだ。こんなものが自然にできるのかな? って。俺は、ウイルスだけじゃなくて、全ての生命が何者かによって作られたんじゃないかと思い始めてますよ。そしてこの素数は、やがて俺たちがこの事実に気が付けるように仕込まれたヒントなんじゃないかって」
しばらく誰も口を開かなった。祐子は志朗くんの言葉をかみしめていた。
あまりにも複雑で美しく、完璧なプログラム。それは祐子も長い間DNAと向き合ってきて感じてきたことだった。
「おっといけない。もうこんな時間だ」
治五郎さんの言葉に時計を見ると、既に夜の十時をまわっていた。
「まだまだ調べたいことは山ほどあるが、今日はこの辺でお開きにしよう。睡眠不足は仕事の精度を下げる。二人とも家に帰ってゆっくり休んでまた明日来てくれたまえ」
祐子と志朗くんはしぶしぶ帰宅することにした。
翌朝、少し早めに出勤すると、治五郎さんと志朗くんはまだ来ていなかった。昨日、あんな大発見をしたのだから、二人とも早く来ているかと思ったのに、拍子抜けだった。
志朗くんも今日は授業が午後しかないから朝から来るって言っていたのに。
しかたなく祐子は昨日の続きをしようとパソコンを開いたところで、志朗くんからの電話がなった。
電話に出ると、志朗くんはひどく動揺していて、何を言っているのかわからなかった。
「大丈夫? どうしたの? ゆっくり喋って?」
「ゆ、ゆ、ゆ、ゆうこさん。いま病院にいるんすけど、治五郎さんが事故にあって…!」
パニック状態の志朗くんを何とかなだめて聞き出した情報によると、道を歩いていた治五郎さんに乗用車がつっこんで、運転手は死亡。治五郎さんは意識不明の重体とのことだった。現在、治五郎さんの手術が行われているそうだ。
祐子はタクシーに飛び乗り病院へと向かった。
病院に到着すると、待合室で志朗くんが今にも失神しそうな様子でベンチに座っていた。顔面蒼白だった。
祐子は隣に座り彼の手を取った。
「俺、いつものように自転車で大学に向かっていたら、治五郎さんが前を歩いているのが見えたんす。それで、呼ぼうとしたら、車が突っ込んできて…それで…」
志朗くんは肩を震わして泣き始めた。治五郎さんが撥ねられるところを目の当たりにしてしまったのだ。
祐子はそっと志朗くんの肩を抱いてやった。
「治五郎さんは帰って来る。とにかく今は待ちましょう」
そうして二人は寄り添いながら、何時間も何時間も待った。
日が傾き、やがて夜になった。
外来の患者やお見舞いに訪れていた人たちも帰ってしまい、病院は静かになった。
治五郎さんには家族がいないのかしら…と祐子はぼんやり考えていた。
病院から大学へ連絡が行ったと聞いたが、誰も来ない。
それから数十分後、看護師がやって来て治五郎さんの手術が終わったことを二人に告げた。
治五郎さんの命は助かった。
ICUに案内されると、治五郎さんは呼吸器をつけ、おびただしい数の点滴をして横たわっていた。
枕元の機械が心拍数や心電図を表示して治五郎さんが生きていることを知らせていた。
「あなたたちは、彼の生徒ですか?」
「いいえ。助手です」
「彼にはすぐに連絡が取れるような親族がいないそうです。この時間までずっと待っててくださったということは、親しい間柄ですか? ご家族の代わりにお話をしてもいいでしょうか?」
祐子と志朗くんは頷いた。
「青山さんは一命を取り留めましたが、内臓の一部と脳が激しく損傷しています。おそらく、このまま意識が回復することはないでしょう」
祐子の体からス――ッと血の気が引いていくのがわかった。隣を見ると、志朗くんが真っ青な顔で今にも倒れそうにしている。祐子はそっと志朗くんの手を握った。志朗くんはぎゅっとその手を握り返して来た。
「こんな時間になってしまったので、明日の朝、大学の人たちが詳しい話を聞きに来ます。おそらく、この病院に長期入院となるでしょう。一週間程度はこのICUに入っている予定です」
そういうと、先生はお辞儀をして行ってしまった。入れ替わりで看護師さんが来て、点滴を交換したりしはじめた。
「今日はお二人ともつかれたでしょう。青山さんは私達がしっかり看てますから。明日またいらしてください」
二人は看護師さんにお礼を言ってICUを後にした。
祐子は志朗くんが心配だったので、彼の下宿先まで送って行った。大学の寮というと小汚い木造建築を想像してしまっていたが、意外と新しくきれいな建物だった。
玄関で彼の友人が出迎えてくれたので、祐子は志朗くんを託し、自分の家へと戻った。
布団に入って緊張がほどけると、じわじわと悲しみが襲ってきた。治五郎さんは死んだわけじゃない…と何度自分に言い聞かせてもだめだった。祐子はしくしくと独りで泣いた。
やがて一週間が過ぎ、治五郎さんは一般病棟に移ったが目を覚ます気配は全くなかった。
大学側は治五郎さんを名誉教授として在籍させ続けることを決定した。
だがしかし、治五郎さんの研究室は解散となった。
志朗くんは精神を病んでしまって山梨の実家に戻ってしまった。
祐子も似たようなもので、DNAの配列を見ると吐き気をもよおす精神疾患に陥り、この業界から完全に足を洗うことになった。
退職手続きをしにセンターを訪れた際に、副所長が辞任したと聞いて祐子は背筋が凍る思いをした。
その後、来宮玲子がどうなったのかは分からず仕舞いだ。
祐子は時々治五郎さんの様子を見に行ったが、ずっと容態は変わらずだった。
お見舞いに行くと、何となく見張られている気がして、そのうち祐子の足も遠のいてしまった。
そうして治五郎さんが目を覚まさないまま、三年の月日が流れた。
じりじりと焼けるような日差しが照り付ける8月。
祐子は山梨県にいた。
とある牧場に立ち寄りソフトクリームを購入すると、店員に「少し痩せたっすね」と言われた。
「そりゃあ、痩せもしますよ」
と祐子は言った。
店員は志朗くんだった。
「私が来なかったらどうするつもりだったの?」
「来るって信じてたっすよ」
ソフトクリームを食べ終わると、祐子と志朗くんは連れ立って奥の母屋へと入って行った。
彼らはこの時をじっと待っていたのだ。
潜伏期間が終わるのを。
自分たちがもう無害であると奴らに信じ込ませるために、脱落した人生を演じながら。
治五郎さんの事故の二日後、二人はとあるメールを受け取っていた。
そのメールにはこんなことが書かれていた。
前略 志朗くん 祐子くん
このメールを受け取っているということは、僕はもうこの世にいないか、全く自由のきかない状態になっているということだ。
一定の期間ログインがなかったらメールを送信する仕組みにしてあるのだ。
なおこのメールはどのログにも一切残らないようになっている。
二人も内容を把握したらすぐ完全に削除するように。
おそらく僕らの研究はまだ途中段階であろう。
それを前提にお願いするのだが、二人にはぜひ僕の研究を続けてほしい。
どんなことがあってもだ。
もしかしたら、僕は不可解な死に方をするかもしれない。
不当な逮捕などされるのかもしれない。
少しでも疑わしいところがあれば、どうか次のことを守ってほしい。
1. 君たちだけで僕の研究を続けることは不可能だと世間に思わせること。
2. 祐子くんは全く別の業界へ転職すること。
3. 最低でも三年間は研究を再開しないこと。
二人のことだからうまくやってくれると思うが、どうか細心の注意を払って行動してほしい。
何者かはわからないが、何がなんでもこの路線の研修を闇に葬りたい奴がいるようだ。
だが我々は学者だ。権力に屈しず研究を続けなくてはならない。
君たちを危険にさらすことは僕の本位ではないが、やるなと言っても君たちは研究を続けるだろう。
それもわかっている。
だから、お願いだから、どうか気を付けてほしい。
志朗くんはこっそり武術を学ぶように。
草々
青山治五郎
二人は特に示し合わせるでもなく、それぞれ最善と思われる行動を取った。
志朗くんが実家に戻ったとの話を何となく彼の友人から聞いて、それが彼からのメッセージと祐子は受け取った。
彼女は心に誓った。
三年間ダメ人間を演じ切って会いに行く。志朗くんに。
青山治五郎の研究は終わらない。それを続ける者がいるかぎり。
(おわり)
※この物語は完全にフィクションです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
