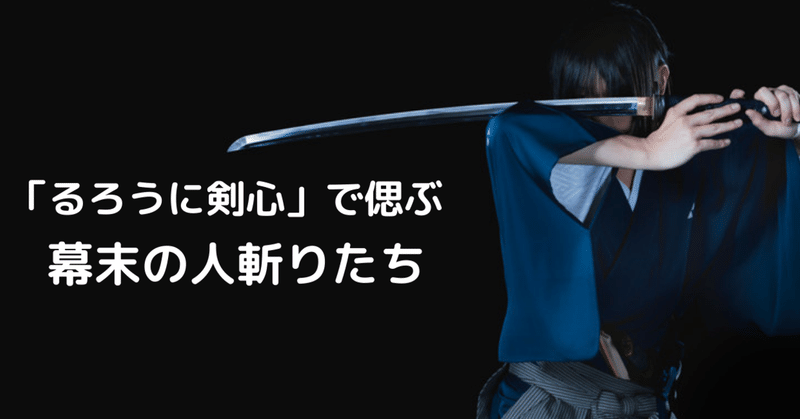
「るろうに剣心」を見終えて、幕末の"人斬り達"について考えてみた
るろうに剣心最終章 The Beginningを観ました。
これで全作見終えたことになります。
シリーズ中、途中のところどころで、マンガやな~!とツッコミ入れてしまう箇所はあるにはありましたが、二転三転する激動の時代に、世の中を変えようと蹶起になって暗躍した主人公・緋村剣心の"悲哀"が、全編通して軸となっていました。
それに殺陣がすごい!!
今までの時代劇には見られない速攻殺陣で、リズム的にはカンフーを意識したとか。
なるほど、確かに息をするのも忘れるほど見入ってしまう殺陣でした。
残念ながら、原作は読んでいないのですが、作者の和月伸宏さん、いいとこに着目したな。と思いました。
幕末~維新にかけてのお話は、それはもうたくさんありますが、有名な人物を脇役にして、”人斬り”と言われていた、秘密裏に働いていた暗殺者を主人公にして、その汚れた仕事にスポットを当て、人としての自分を取り戻して生きていく様を描いています。
主な読者である少年たちに、時代背景や奥に潜む心理まではわからなくても、登場する敵役の奇抜なキャラクタ―だけでも、楽しめるのでしょう。
この緋村剣心のモデルとなったのは河上彦斎(かわかみげんさい)である事は有名ですが、この時代には他にも暗躍した"人斬り"がいました。
この映画に刺激を受けて、幕末に実在した四大人斬りたちについて、思うところをまとめてみました。
さらに、それらの人生は誰が一番可哀想で不幸だったか、勝手にランキングしてみました。
河上彦斎は小柄で色白の知識人だった
肥後藩(熊本県)出身、身長約150cmで、瘦せ型色白、声音も柔らかい。
一見すると、女性が男装しているような姿でした。
この辺りは、剣心役の佐藤健さん、ぴったりハマり役です!
幼い頃から藩校・時習館に通い、藩に出仕後には茶道や生け花、和歌や漢詩に至るまで習得し、教養を蓄えた風流人でもありました。
人斬りというと、強面で無学の粗雑なイメージがありますが、彦斎(げんさい)は真逆だったのですねー。
肝心の剣は、伯耆流(ほうきりゅう)の居合いに我流がプラスされた型だったそうです。
伯耆流とは甲冑を着用した状態での実戦を想定して、甲冑のない所を狙う流派です。
居合いは、刀を抜きざまに素早く相手を仕留める技です。
という事は、両方の特性を併せ持つ、結構な恐ろしい技ですよね。
タイトルは失念してしまいましたが、新撰組の斎藤一のお話で、居合切りの一振りで相手の両手首と両足首を切り落し、そのまま放置して出血多量で致死させたという記述がありました。
あまりにも、その技の恐ろしさに驚愕してしまったので、その部分だけは忘れられません。
これと同じような事ができる技なのですね。
彦斎は小柄な自分の体形を生かして、膝が地面に着くほどの低い位置で足を前後に大きく広げ、下から上への逆袈裟斬り(ぎゃくけさぎり)を得意とするスタイルでした。
刀を抜く一瞬のうちに 無防備な低い位置から斜めに刀が襲い掛かるのですから、たまったものではありません。
尊王攘夷派の学者・宮部鼎蔵(みやべていぞう)や国学者の林桜園(はやしおうえん)らから学び、刺激されて強く尊王攘夷の志を持ちます。
しかし、熊本藩は佐幕派の姿勢のまま積極的に動きません。
やがて清河八郎との出会った事がキッカケで、運命は大きく変わります。
清河の口添えにより朝廷警護役として京都へ向かうのです。
清川八郎!
多くの尊王攘夷派を誕生させた人物でしたが、京都見回り組の佐々木只三郎にあっさりと暗殺されています。
近藤勇や芹沢鴨なども清河がキッカケとなって京都に上ったのですから、彼の存在がなかったら、新選組も誕生していなかったのかもしれないのです。
そう思うと、彼の存在の不思議さにも、歴史のイタズラを感じずにはいられません。
京都での彦斎は、やがて尊王攘夷派の公家である三条実美(さねとみ)に信頼され、肥後勤王党の幹部となります。
肥後勤王党とは言え、もちろん熊本藩は依然として積極的に動いていないので、公認ではありません。
やがて、京都の実権は薩摩藩と会津藩が握り、実美(さねとみ)も公卿を追われて長州藩に落ち延びます。実美と共に行動していた彦斎も長州藩に身を置くことになりました。
この頃、暗躍して多数の人斬りを実行したようです。
新選組の活躍による池田屋事件で、師である宮部鼎蔵(みやべていぞう)が殺害されたことを知り、佐幕派に対しての彦斎の怒りは沸騰します。
そんな折、公武合体の開国派で幕府の軍政顧問の佐久間象山(さくましょうざん)に着目します。
彦斎にとっては象山は仇としての対象となり、ちょうど京にいる事を知り、暗殺を実行します。
この時、現在の祇園神社の前にこの天誅の理由を書いた「斬奸状(ざんかんじょう)」を掲げたと言います。
この事も映画と一緒ですね。
他の人斬りは記録に残っていませんが、唯一、佐久間象山の暗殺が彦斎にとって確実に記録があり、最後の人斬りとなりました。
彦斎の人生を変えた暗殺だったのです。
後にこの時の事を彦斎はこう語っています。
~今まで数多の人間を斬ってきたが、まるで人形を斬るようで、何の感情もなかった。
しかし、象山を斬る時だけは、髪の毛が逆立ち、初めて人を斬る思いが生じた。そして、それは象山が絶大なる豪傑だったのだと悟り、これは自分の命も尽きる前兆であると感じ、これ以降、人斬りを止めると決意した。~
深い後悔の後、故郷の熊本に帰りますが、世の中は維新を迎え、すっかり開国ムードとなったにも関わらず、彦斎の尊王攘夷の意志変わりません。
危険人物として捕らえられ、吉田松陰も投獄された小伝馬町の牢屋敷に入れられ、38才で斬首されてしまったのです。
河上彦斎もまた、歴史のイタズラかと思えるような不思議な存在かもしれません。
佐久間象山は大物過ぎるでしょう!!
もし、この時暗殺されなかったら、必ずや新時代の要人となり、また違った維新になっていたかもしれません。
私も長野県を訪れた時、象山の神社や蟄居屋敷を見学し、彼の足跡に触れた時、暗殺者を恨んだ記憶があります。
ここで斃れるには惜し過ぎる人物だと思います。
逆の立場から言えば、彦斎の人生においての大仕事は、象山を倒す事だったとも言えるかもしれません。
少なくとも、彦斎という一人の熊本藩士が、その後の歴史を大きく変えてしまったのです。
岡田以蔵は土佐勤王党のパシリだった
岡田以蔵は、「るろうに剣心」では1作目に登場した吉川晃司さん演じる鵜堂刃衛(うどうじんえ)のモデルとなったと言われていますが、私の持つイメージではちょっと違うかな…殺人鬼として恐れられたという点は共通していますが。
ちょっと前に放映されていた「龍馬伝」では佐藤健さんが、以蔵役を演じていました。
るろうの主人公・緋村剣心役と龍馬伝の岡田以蔵役、両方が同じ佐藤健さんだったので、ちょっと変にリンクしてしまって、ややこしい所ではありますね。
それだけ演技が素晴らしかったという事ですね。
龍馬伝での岡田以蔵は、そのみじめさ、哀しさがグッと胸に迫って何とも言えない感動がありました。
以蔵は、土佐藩・郷士。あの坂本龍馬とは幼馴染でもあります。
体格は筋骨逞しく、大柄。性格は一見豪胆であるが、実は臆病な一面もあったようです。
残念だったのは学識がなかった事。
剣は鏡心明智流。その腕前は群を抜いていたと言います。
幕末には三大流派の一つとして数えられ、
「技の千葉」の千葉周作の北辰一刀流、「力の斎藤」の斎藤弥九郎の神道無念流、そして「位(くらい)の桃井」の桃井春蔵の鏡新明智流と言われて隆盛を誇っていました。
「技」でも「力」でもなく、「位」と言うのは、「品格」や「品位」の事で、修行を極めた者だけにそれが表れて、相手を威圧し、戦意を喪失させるほどの域に達する事を目的としている剣です。
正確に言うと、以蔵が直接桃井から習得したのではなく、それを修めた同郷の武市半平太(たけちはんぺいた)が、土佐で開いた道場で習ったのです。
一時は塾頭を務めるまでになったとの事ですから、相当な剣技だったのでしょう。
以蔵を語るには、まず土佐勤王党と武市半平太(たけちはんぺいた)について知らないと、その全容は見えません。
半平太は剣だけではなく、学問も収めた立派な知識人で、絵を描く事にも才能を発揮し、土佐では有名で一目置かれている存在でした。
以蔵はそんな半平太を、尊敬どころか崇拝していました。
半平太が、尊王攘夷の結社として作ったのが土佐勤王党で、当然、以蔵もそのメンバーに加わります。
以蔵の目には、半平太はどのような人間であれ分け隔てることなく接してくれていると写っていたので、自分を仲間として迎え、側に仕えさせてくれた事に感激し、ますます半平太に心酔していきます。
しかし、半平太の方はというと、以蔵の自分に対する思いをよーくわかった上で、自分の道具のように使おうとしか思っていませんでした。
やがて半平太は、土佐勤王党の攘夷実行に向けて、それに反する勢力や人物であるとみなした、土佐藩参政・吉田東洋を暗殺します。
藩主・山内容堂は激怒し、藩を挙げて犯人捜しをしますが、決定的な証拠のないまま時間は経ってしまいます。
以蔵は、この事件には絡んでなかったようですが、これを皮切りに勢いづいた半平太は、三条実美(さんじょうさねとみ)に通じて、国事に参加せんと京に上ります。
三条実美!!また登場ですね。河上彦斎にも工作していました!
なかなか、彼も何が何でも尊王攘夷だったのですね。
さて、京に上った武市半平太率いる土佐勤王党は、全盛期を迎える事になります。
この時期に半平太は、裏の暗殺者として以蔵を多用しました。とにかく自分(土佐勤王党)に敵対する人物を、次々に以蔵に命じて粛正させたのです。
これが、人斬り・以蔵として、恐れられた所以です。
その頃には脱藩して、とっくに土佐勤王党からも足を洗っていた坂本龍馬や、その師である勝海舟から、土佐勤王党から抜けるよう助言されるのですが、一途な以蔵は聞き入れません。
しかし、公武合体派である土佐藩は、ついに土佐勤王党の弾圧に乗り出します。
武市半平太はじめメンバーたちは次々に捕縛され、投獄されます。
逃げ回っていた以蔵もついに捕らえられてしまうのです。
名君と誉れ高い山内容堂は、実は吉田東洋暗殺を土佐勤王党だと疑っていながら、泳がせていたのかもしれません。
ここで誤解のないように言っておきますが、武市半平太は知識人です。
決して藩主に逆らおうとしたのではなく、むしろ忠誠心の塊りでした。
あくまでも尊王攘夷が土佐藩の為であり、ひいては山内家の為であると信じて疑わなかっただけです。
「龍馬伝」で名シーンがありましたね。
近藤正臣さん演じる山内容堂が、半平太の獄中へ訪ね、酒を酌み交わしたあと切腹を沙汰するシーンが。
藩主が罪人のもとへ訪ねるなど絶対にあり得ない事ではありますが、今でも忘れられない感動シーンのひとつです。
その後、半平太は腹を三文字に割腹し、それまで誰も成し得なかった、武法通りの見事な切腹を遂げます。
さて、岡田以蔵の話に戻しますが、捕らえられた後は連日連夜拷問され、吉田東洋の暗殺はじめ、数々の土佐勤王党の罪状について吐かせようとします。
それでもなかなか、口を割りません。
毎日毎日、拷問される以蔵の悲鳴が牢獄内に響き渡ります。
「龍馬伝」ではその声を聴いた半平太が涙するシーンもありました。
実際どうでしょう?以蔵を利用することで、一番の汚れ役をさせてしまった事を悔やんでいたのでしょうか??
以蔵は、激しい拷問の中で、半平太にパシリ使いのように使われていたことに気づいていたようなのです。
時世の句がそれを語っています。
君が為 尽くす心は 水の泡消えにし 後は澄み渡る空
意味:あなたに忠誠を尽くした私の気持ちなど、全てが水の泡となった。しかし罪人となった私の心は一点の曇りもなく澄み渡っている。
えぇー!
本当に学識はなかったの?!
ちょっと感動するほどの句なんですけど!
ちなみに「君」というのは最高位の人を指し、一般的には「天皇」の事なのですが、以蔵にとっての最高位の人物は、どんなに利用されていたとしても武市半平太という事なのでしょうか?
どこまでも愚直で、純粋すぎる人だったのですね。
1865年(慶応元)年 岡田以蔵、斬首。享年27歳。
武市半平太の身分は白札郷士と言われ、以蔵の郷士と比べると家格は上でしたので、処刑方法にも格段の差がありました。
以蔵は後ろ手に縛られて、穴の前に正座させられ首を落とされた上、さらし首となりました。
中村半次郎は愛されキャラだった
薩摩藩士で、剣は薬丸自顕流(やくまるじげんりゅう)。
一言でいうと「一太刀で敵を斃すための剣術」で、他とは格段に違った高いレベルだった剣術です。
あの新選組でさえ、「薩摩の初太刀は避けよ」と注意の申し送りがあったほど、危険な剣術でした。
その中でも半次郎の腕前は際立っていたと言います。幕末トップクラスの剣術流派の中の、それまたトップの実力を持っていたという事になります。
もし、日本全国で個人戦選手権があれば優勝していたほどの腕前だったかもしれません。
そういえばNHK大河ドラマ「西郷どん」で、郷中教育の一つにその稽古風景がありました。
気合の入った大きな声を出しながら、横木を力いっぱい打ち付けるシーンです。
薩摩では物心ついた頃から、精神を鍛える意味でも、自顕流は欠かせない教育科目だったわけです。
半次郎は学識はなかったのですが、愚鈍ではなく、よく気が付き、何事も命令されるだけではなく、自分で考えて行動を起こす人でした。
普段から周りに気配りができただけに、失敗をしても、大きな気持ちで許してもらえるような愛されキャラだったようです。
それだけに西郷は、半次郎の学の無さを嘆いていました。
それも仕方のない事で、超貧乏な中で育ったため、学問どころではなく、生きるために必死の生活を強いられて育ちました。
この時代の武士は、他藩も同様、貧困にあえいでいました。
武士が増えすぎて、ちょっとした理由でどんどん禄を減らされ、あるいは断絶されて、路頭に迷う浪人も増えていました。
徳川幕府の政治は、すでに何の役にも立たないどころか、成り立っていなかったのです。
半次郎の家も、父が島流しとなり、生活を支えていた長兄も生活の苦労が祟ったのか、この世を去り、困窮を極めていたのです。
郡方書役助となった西郷隆盛が、半次郎らのような薩摩の人々の困窮ぶりを目の当たりにしたことで、倒幕思想が芽生えたようです。
おそらく半次郎とも、この頃に知り合った可能性が高いです。
西郷は半次郎を目にかけ、半次郎も生涯をかけて西郷に尽くします。
岡田以蔵と違っていたのは、常に大きな愛情で包み込むような人間に出合えた事です。
西郷は生涯変わらず半次郎を理解し続け、2人の関係は変わることなく信頼し合える間柄だったようです。
最強の人斬りと言われた半次郎ですが、理由もなくやたらと人を殺めたのではないようです。
腕がやたらと立つ事と、いつも西郷のボディガードとして傍らにつき、鋭い殺気を放っていたので、そういう風に思われていたのかもしれません。
しかし、一つ重大な人斬りを犯しました。
それは上田藩出身の兵学者・赤松小三郎です。
赤松の兵学はイギリス式で「英国歩兵練法」を翻訳し、藩主・島津久光も支持していたほどの人物でした。
半次郎も赤松に学んでいたほどでしたが、赤松は、薩摩は幕府と一体になっての改革をすべきだと唱え、「幕薩一和」を目指しました。会津藩を守ろうと画策していた山本覚馬らと交流もあり、倒幕派と佐幕派の区別なく人々に接していました。
それが倒幕派の半次郎にとっては許せず、薩摩の情報を漏洩されてしまう危惧もありました。
赤松を斬る!
「斬ると決めたらただで収めるな」という、薩摩人の考え方があり、西郷に止められても、半次郎は収まりません。
これから先、赤松はどちらにつくかわかりません。とうとう西郷も軍事機密漏洩の防止という理由で実行を許すのです。
半次郎が京都探索中に、ばったり赤松と出くわすのですが、ピストルを構えた赤松に対して、一刀両断で斬り、殺害したのです。
ピストルにも勝てる薬丸自顕流の凄さ!
ハンパないです。
いや、使い手である半次郎が凄すぎたのか?
どちらにしても薩摩の剣は恐ろしいという事ですね。
しかし、その後、半次郎はこの事を大変後悔して、「あんなに偉大な人物であった赤松先生がもういないとは、残念なことだ」と言っているのです。
薩摩藩自体もこの事件を箝口令を敷いてふせ、赤松の遺族にも三百両という慰霊金を支払っています。
それってどうよ?
表向きはこうだったかもしれませんが、おそらく西郷や大久保からの命令で実行されたのではないでしょうか?
薩摩にとっては赤松の思想は邪魔だったし、薩摩がこれから実権を握るべく模索している時に、相当な危険人物でもあったわけです。
ここは、今のうちに抹殺しておかないと、後々ややこしくなると思ったはずです。
もしも、本当に半次郎の独断で実行したのなら、半次郎も処刑されていたのではないでしょうか?
いや、たぶんそうならそうで、西郷が守ってくれていたでしょうね。
なんせ愛されキャラですから。
その後、明治を迎え、新たに桐野利秋と名を改めて新政府の軍人となり、陸軍少将や部隊の司令長官となって、新時代に活躍します。
明治6年(1873年)征韓論がキッカケで西郷が下野し、鹿児島に帰ると半次郎もそれに従い帰郷します。
明治新政府に不満を持つ若い士族達が各地で反乱を起こし、薩摩でも西南戦争へと向かってしまいます。
半次郎は最後まで敬愛する西郷に付き従い、その死を見届けた後、額を撃ち抜かれて戦死しました。享年40歳。
田中新兵衛は謎だらけのまま自決した
薩摩出身。薬種屋か船頭の家に生まれたらしいのですが、はっきりとはわかっていません。少なくとも武士ではなかったという事です。
剣の流派も不明なのですが、おそらく薩摩特有の郷中教育にて、幼い頃より示現流を体得し、プラス我流の剣だったのではないかと思われます。
幼少期から武芸に励み、剣術はかなりの腕前になっていたようです。
先ほどの半次郎と同じく、薩摩の剣の恐ろしさは、あの新選組でさえ警戒するものです。
その薩摩内においてもトップクラスとなっていたのですから、相当なものだったのでしょう。
文久2年(1862)上京し、多くの尊王攘夷志士を弾圧した大老・井伊直弼による「安政の大獄」で、右腕となっていた島田左近の襲撃を計画します。
左近はそればかりか、幕府より多くの賄賂をも受け取っていて、大きな権力を持ち、志士達にに加えて民衆からも反感を買っていたのです。
しかし、その暗殺はなかなか成功しなかったので、新兵衛は1ヵ月ほども追い回し、ついに追い詰めて鴨川の河原にて惨殺し、晒し首にしました。
これが左近による「天誅」の始まりでした。
1ヵ月も追い回すなんて、なかなかの執念ですね。
追われていた左近にとっても、いつ殺されるかわからない状況のひと月は、さぞかし恐怖の日々だったでしょうね。
獲物を定めると、1点集中で何が何でも仕留めるという妄執ぶりが伺えます。
やがて、土佐勤王党の武市半平太(たけちはんぺいた)と出会い、お互いに認め合い、信頼し合える間柄となります。
これ以後、先の岡田以蔵と同じく、土佐勤王党の一員として命じられるままの暗殺を繰り返すこととなるのです。
その様子は情け容赦のない殺戮で、敵であろうが仲間であろうが関係なく、手あたり次第だったので、悪名がつき「人斬り新兵衛」と呼ばれて恐れられました。
その1年後、新兵衛の運命を変える、「朔平門外の変」(さくへいもんがいのへん)が起こります。
それは過激な攘夷論者である公家の姉小路公知(あねがこうじきんとも)が京都御所の朔平門(さくへいもん)にて何者かに襲われ、応戦しながら辛くも自宅まで逃げ帰ったのですが、翌日死亡したという事件です。
新兵衛の愛刀だった奥和泉守忠重(おくいずみのかみただしげ)と薩摩下駄が現場に残されていたため、新兵衛は捕らえられて尋問されますが、黙秘し続けます。
そのまま6日間も一切何も語らず、そして、町奉行の隙を見て、脇差で切腹して首の頸動脈を斬り、自害してしまったのです。
いったい何があったのか?
新兵衛は犯人なのか?ちがうのか?
確かに、新兵衛の愛刀と薩摩下駄は彼の所持品かもしれないが、わざわざ現場に置き忘れる事などあるでしょうか?
信頼関係にあった武市半平太と殺された姉小路公知(あねがこうじきんとも)とは、共に攘夷を唱える良好な関係にあったので、新兵衛が犯人なら疑問が残ります。
何より、これ以前の新兵衛は執拗に相手を追い詰め、狙った対象は確実に斬り殺しています。
しかし今回は、その場で確実に仕留める事ができず公知(きんとも)は負傷しながらも、自宅まで戻っているのです。
そこで、ちょっと私なりに妄想してみました。
新兵衛が犯人でないなら、誰かが刀と下駄は盗んで、濡れ衣を着せようとしたのでしょうか?
そして、新兵衛はその真犯人をかばって自決した?
新兵衛が犯人なら、その以前に坂本龍馬や勝海舟らと出会っていたらしく、開国派に変わりつつあり、同時に武市や公知の攘夷論に敵対する意志がすでにあったのか?
どちらが真実であってもおかしくないですが、どちらにしても自分の故郷である薩摩藩と、土佐勤王党との両方から、何らかの圧力がかかっていて、精神的に追い詰められていたのかもしれません。
ひょっとすると、命令したのは武市で、平気で公知を裏切る武市に大きな疑問を持ったのか?
そうだとすると、かなりの人間不信に陥っていた可能性だってあります。
ということは…、やっぱり犯人は新兵衛で、愛刀と下駄は置き忘れるわ、確実に仕留められないわで、心ここにあらずの、彼らしくない手際の悪い暗殺劇となったのかもしれません。
どうせ死を選ぶなら、真実を語るべきでしたよ。
何も語らず自決しただけに、新兵衛が実行犯だったにしても、黒幕は未だに闇の中で、ただただ妄想は尽きないのです。
田中新兵衛 享年22歳。
四大人斬りの不幸度をランキングしてみた!
【1位】岡田以蔵
どんなに道具のように利用されているとわかっていても、なおも武市半平太を崇拝し続ける一途な純真さが切なすぎて、不幸すぎる。
【2位】田中新兵衛
きっと、土佐勤王党と薩摩、あるいは攘夷と開国の板挟みとなって、病んでいたのかもしれない。何も語らなかったのは、語る事が出来なかった衝撃の事実があったのかもと思うと、不幸すぎる。
【3位】河上彦斎
以蔵と同じく投獄されて斬首となったが、最後まで攘夷の志を捨てることなく、自分の意思を貫き通したので、まだマシ。
【4位】中村半次郎
西郷に愛され、自らも西郷を敬愛し、決して道具のようにこき使われることなく、とても心の大きな良い上司に恵まれていたので、全然マシ。
4人共通してるのは、後になって暗殺を後悔している事。
いや、岡田以蔵だけは違いますね。最後まで武市半平太の志が最優先だったように思えます。
そう考えると、武市半平太は罪なヤツです。
岡田以蔵と田中新兵衛という、純真な若者を扇動し、その人生を穢してしまったのですから。
しかし、武市半平太も自分の志を信じて疑う事なく、貫き通したまでの事。
私はこの時代に生まれなくて良かった!
一寸先は闇と言えるほど、ころころ時世が変わる時代など不安すぎます。
平和な今に感謝です。
それにしても、ここ最近のコミックは凝っていて面白すぎます。
いくつか読んでいますが、どれも面白い。
歴史に沿いながらの創作物語、結構好きなんですよね。
時代背景にしろ、登場人物にしろ実際の史実の骨格は損なわず、それでいて大袈裟にイメージを膨らませて、面白くしているところが、私の感性をくすぐられてしまうのです。
実在の人物をちょっとイジったりしている個所など、ホントにいい!
サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。
