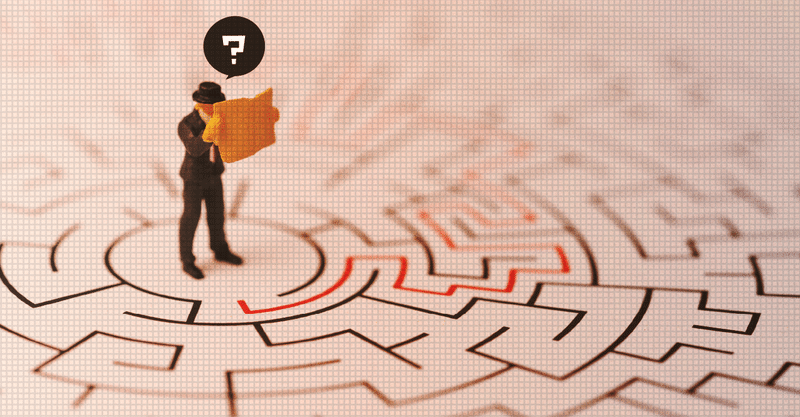
正統的周辺参加理論って反転できるんだろうか。
ファシリテーションを学ぶ効果的な方法とはー
「教わらない環境づくりを通したファシリテーションの学習」というタイトルで卒論を書いていて、教わらない環境に自ら飛び込んでワークショップを主催するのが有効という趣旨にする予定。
小さく始めるために、周辺的に関わって徐々に担う役割を増やしていくという正統的周辺参加理論に基づいて書いている。
周辺的参加をすっ飛ばして、いきなり小さな共同体をつくってメインでファシリテーションする学習方法を聞いて、ふと思った。
これって「中心のベテラン」と「周辺の初心者」を反転させた方法じゃないか。正統的周辺参加理論を反転させた方法じゃないか。
先行研究を読み込むのが足りなくて、これが既存の理論で言われていることなのか、既存の理論を間違って解釈しているのかはわからないけど、ファシリテーションの効果的な学習法だと思ったので言語化してみる。
(もし補足や指摘、先行研究の紹介があればコメントをいただきたいです)
正統的周辺参加理論とは
学習とは知識をインプットするんじゃなくて、「共同体に参加する過程である」と述べたのが、「正統的周辺参加」理論(Lave & Wenger, 1991)
実践の共同体にまずは「所属」し、隅っこで雑用とか見学をしているところから、徐々に担う役割を増やしていき、参加度合いを高めることが学習という考え方だ。
最初は影が薄いとはいえ、共同体のれっきとした一員だから「正統的」、小さな役割を担うところから始めるから「周辺」という言葉が使われている。
ファシリテーションの実践に当てはめると、まずはベテランのファシリテーションを見学して、設営をしたり見学したりレポートを書いたりして、徐々に企画運営を担っていく。
うん、まあ納得のプロセス。
正統的周辺参加理論を反転させると
正統的周辺参加の限界があるとすれば、周辺参加しているうちにモチベーションが下がったり実力を高めるのに時間がかかったりするということ。
じゃあ、いきなり実践しちゃえ!というのがこの反転型。
まず、リスクや心理的ハードルを下げるために、ごくごく小さな共同体をつくる(3人の友達の前で実践など)。
その人たちの前でワークショップ企画運営をやってみる。その際に、大きな共同体の中心部にいるベテランが周辺的参加者として、ワークショップの一部分だけ監修や介入をしながら見守る。
このように中心的な参加者の立ち位置を、ベテランから初心者にいきなり渡すと、ファシリテーションの全体像をいち早く身につけられ、観察するときの解像度も上がるんじゃないか。
ただ、この方法をとる際に、いくつか前提条件があると思われる。
それは、学ぶ側の熱意が高く、教わらず自ら学びを見出す力があること。
熱意がないと、いきなり前に立って主催なんて大きなチャレンジできない。
また、自ら学びを見出す力は、まずはやってみる度胸や経験から学ぶ素養があるということ。
もともととりあえずやってみる精神がある人が来てくれたらいいけど、教わらずに自ら学びを見出す力をつけるところからやろうとすると、正解捜しの学習観をリセットするフェーズが必要になりそうだ。
(私の場合は、そのフェーズがあったのが主催の助走期間として役に立った)
と、なんか難しく書いてしまったけど、要は「とりあえずやっちゃえ!」ということ。
これは正統的周辺参加理論の新たな見方なんだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
