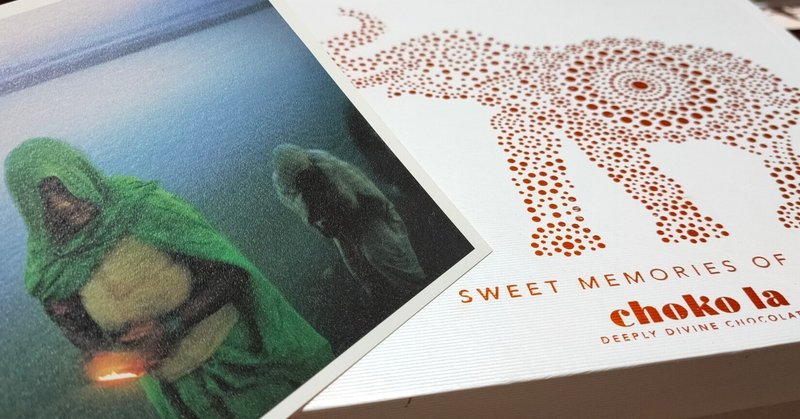
お葬式は誰の為
数日前に急なお悔やみがあり、お通夜に参列した。享年101歳の大往生。亡くなられた方は、お若い頃から某新興宗教に入信されていたそう。
お悔やみに伺う前に、そちらの新興宗教のしきたり等をネットで調べた。御香典のことや敬花について知りたく。御香典袋の種類、「御仏前」「御霊前」どちらがよいのか、また違うのか。
わたしの住む地域は、宗派は分かれても、ほとんどが浄土真宗。何度か四国や関西のお葬式に参列したことがあるけれど、葬儀のしきたり、お経やお坊様の雰囲気、様々なんだと知った。
新興宗教に入信している知人が何人かいるけれど、その中で宗教上の信念から色んな制約があるのだな、と感じる。知人を通じて、それらの宗教の冊子をいただいたり、入信を勧められたりすることもある。わたし自身は、特定の宗教を信仰していないけれど、目に見えない何かがあると信じている。そして先祖崇拝はしたいと思っている。元々、集団で同じ目的を持つような雰囲気は苦手なので、個人で心の中でお祈りする程度。それで構わないと考えている。だけれど、もし、わたしが死んだら、誰かに弔ってもらうとしたら、何処かのお坊様なりにお経をあげてもらうことになるのだろう。
もし、今わたしが死んだら、祖父母の眠るお墓に入るというのが濃厚。その場合、祖父母と同じお寺さんになる。祖父母のお葬式や法事でお経や法要をしていただいた尊師さんに感じるのは、職業として親御さんから受け継いだお坊さんをしているのであって志あってお坊様になっている訳ではなく、神々しさや、心に響く講話を聴けたと感じたことがない。依頼に対して金銭的な請求のもと、成立している関係。なんだかなぁといつも思うけれど、祖父母の地元であり馴染みがあり、ずっとそうであるから、祖父母も生前から異議はなかったであろうと思う。それが地の慣わしでもあるし。
数年前に遠い親戚の方が亡くなった。県外在住で生活保護を受けていた。わたしは個人的に幼少期にかわいがってもらったので、訃報を受けて、直ぐに会いに行くつもりだった。だけれど、その方が生活保護受給者であった為に、血の繋がりが遠くても親戚が居ることが判明したら、親戚全体で、その方が受給していた金銭を行政から請求される可能性があると言われ親族会議で、亡きその方に会いに行くのを禁じられた。その方は祖母の妹にあたる。夫婦二人暮らし、子どものいない方で、わたしと弟は孫みたいにかわいがってもらった。旦那さんは急な病で若くして亡くなった。それから、その方もご病気をされ、独りでがんばって生きてこられた。それなのに。
祖母もそんな妹に送り物をしたり、いつでもこちらへ移り住めるように住環境を整えていた。迷惑を掛けるから…と遠慮したのではないかと思う。結局、独りを貫いた。わたしと弟は交代で数年に一度、会いに行っていた。
祖母の妹は、自宅で倒れ病院で亡くなった。遠方の親族に連絡が入り、飛行機に乗って、亡き祖母の妹を迎えに行こうとする段取りの中で、親族会議が行われた。亡きおばさんを迎えに行ってお葬式を出せるような親族が居ることが判明した場合、他諸々の諸経費を請求される可能性がある(市町村によるらしい)と行政に詳しい親戚が言った。親族一同で、その諸経費を被ることは避けたいので、誰も亡きおばさんに近付かないように!と厳しく言われた。泣いたけれど、泣くしかなくて、どうしようもできなかった。弟が、俺がいつか連れてってやるから今回は諦めろ、と電話でなだめてくれた。
おばさんは、ひっそり、生活保護受給者の範囲内で直葬されたらしい。気持ちはあっても、迎えに行ってあげられなくて、悔しくて悲しかった。おじさんと同じお墓にも入れてあげられなかった。わたしが遊びに行っていた長屋の借家は家財道具全て没収(廃棄)されたそう。何一つ持ち出せず、病院に運ばれた時の貴重品が入った小さなバッグだけが残ったそう。亡くなる10日ほど前に、わたしが電話で話た時に「ラジオの電池が切れたから買いに行くんや」と言っていたのだけれど、その小さなバッグに乾電池が入っていたらしい。わたしは、その乾電池を下さいとお願いした。
小さなお骨になったおばさんが暫くしてから飛行機に乗って、こちらへ来た。親戚のおじさんがこっそり迎えに行ってくれて、お骨を分けてもらってきてくれた。おばさんが亡くなって数ヶ月後、小さな骨壷を囲んで、親戚一同でこっそり、こちらでお葬式をした。おばさんは、こちらの遠い親戚のお墓に眠っている。なので、今は時々、手を合わせに行くことが出来る。おじさんと一緒に眠らせてあげられなくて、ごめんね、と思うけれど、あちらで会えていたらいいな。
話をうんと戻す。101歳で亡くなられた方のお通夜やお葬式。その某新興宗教では、お坊様でなく友人葬という形式で行うと聞いていたけれど、結局、喪主である親族が未信者であるゆえ、一般葬となったようだ。戒名が与えられ、浄土真宗のお経があげられた。
若き頃から長年信心していて、結局、亡くなられた後には、別な宗教で見送られる様を拝見して、思った。お葬式は誰の為にあるか、と。故人を尊重するか、喪主が主体となって取り仕切らねばならないので、どちらの為かと。どちらの気持ちも分かる。喪主側も知らない新興宗教で葬儀を取り仕切れるはずもない訳で。結局、亡き後は、誰かしらかに委ねるしかないのだ。
わたしの叔母でクリスチャンの方がいる。仏教徒の法事には表立って出席しないけれど、いつも裏方で出来ることを心を尽くして立ち回ってくれている。叔父は未信者だけれど、その叔母の熱い信仰への想いを見聞きしているので、その叔母には是非、クリスチャン式の終末を迎えてほしいとわたしは願っている。
昨年末に観に行った映画🎥「土喰らう12ヶ月」もお葬式を手造りで執り行うシーンが際立っていた。映画のあとに、数冊、水上勉さんの著作を拝見したら、禅寺のこと、棺桶職人のこと、火葬場職員のこと、などその種の職業に携わる方のことが記述されていた。それらの本の内容が、わたしが経験したいくつかの、人の死やお葬式と重なってみえて、考えさせられた。
そして、藤原新也さんの「メメント・モリ」二十代の終わりくらいに、この写真集を手にして衝撃だった。犬に喰われる自由が特に。人の死とは何か。生とは何か。今回の展覧会で、大きなパネルで、藤原さんの写真を観た。以下、全て「藤原新也展 祈り」より。






「メメント・モリ」とは何か
「センス・オブ・ワンダー」とは何か
何故だか気になり、惹かれる、これらの
コトバの意味が分かりたくて調べれば調べるほど分からなくなる。これらは、どちらも言語化するのではなく、感じるものなのだろうな、と思った。
わたしは近い将来、これらを、もっと知りたくて(体感したくて)これらに近づける場所なり土地なりに行くのだろうと思う。

わたしは自分が感受していることを表現する術を未だ持ち合わせていないのだけれど、何であるかは未だ分からないけれど、この感受していることを表現できる何かを掴みたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
