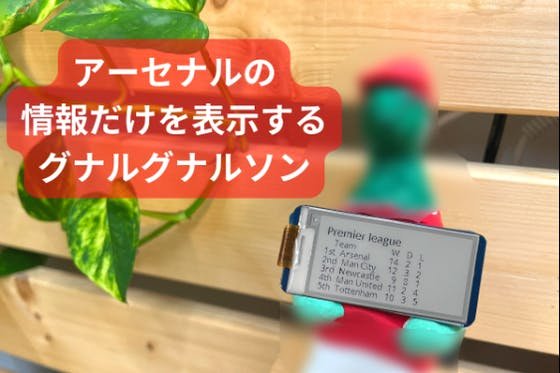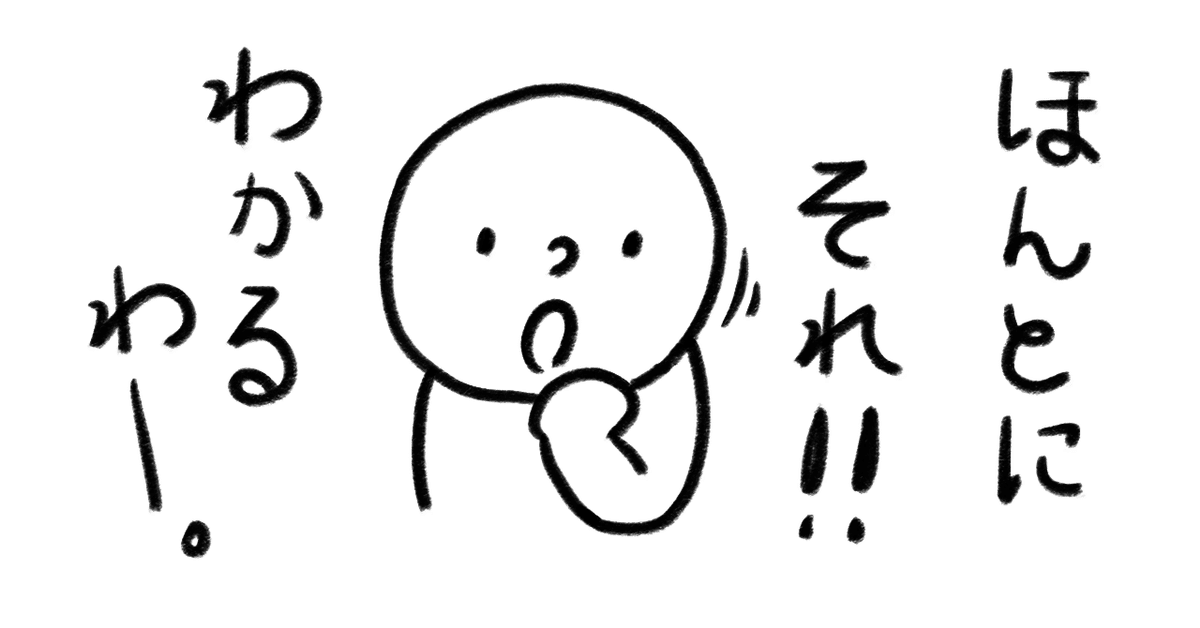
【クラウドファンディングに挑戦!②】成功の鍵は「共感」と「信頼」だ
こんにちは、ちーろってぃ(26歳)です。
普段は、世界の平和を守るサイバーセキュリティ(見習い)のお仕事をしています。その傍ら、IT技術を駆使して世の中の役に立ちそうで役に立たない、少し役に立つツールを生産しています。
■ 通勤の課題を解決するために
前回の記事では、クラウドファンディングに挑戦したいと思った経緯についてお話ししました。
今回の記事では、主に課題解決型のクラウドファンディングにフォーカスを当て、先駆者たちのプロジェクトを分析した結果をまとめました。出資者の視点から様々なプロジェクトのページを見ることで、どのようなプロジェクトがたくさんの人に応援してもらえるのかを探ってみました!
この記事を読むと、以下のことがわかります。
応援したくなるクラウドファンディングの傾向(課題解決型)
クラウドファンディングで注意すべきこと
■ 応援したくなるクラウドファンディングの傾向(課題解決型)
傾向①:適度な大きさの課題を扱っている
こちらのプロジェクトを参考にしました!
仕事人間のための趣味探しアプリ「Me Clip」(ミークリップ)
皆さんには趣味がありますか?毎日お仕事頑張っている方、プライベートは充実していますか?私には趣味がありませんが「趣味を探そうとも何をしたらいいのかわからない」という壁に当たり、自分を知れるアプリ「Me Clip」を開発しようと思いました。私と一緒に趣味を見つける第一歩を踏み出してみませんか?
私自身はどちらかというと多趣味なのでこのプロジェクトの課題感とはマッチしないのですが、「趣味がない!」と嘆いている友人には心当たりがあります。このプロジェクトの課題感が刺さる層が一定数いるということです。
その一方で、ファーストステップとして取り上げる課題は、大きすぎない方が良いと感じました。初めてのプロジェクトかつ個人でのチャレンジなのに、いきなり大きな社会問題を解決しようとする人に安易にお金を出せる出資者は少ないでしょう。ターゲットを絞ることは、出資者に「これは私のためのプロジェクトだ!」と思ってもらうことにもつながります。
傾向②:出資者参加型のリターンがある
こちらのプロジェクトを参考にしました!
未来のために今の自分を記録する【ウィルバンク】を作りたい!
ウィルバンクは気持ちを「整え」「育てる」ことを一緒に行うメンタルに関するアプリです。気持ちの記録と写真を使って、モヤモヤの解消とポジティブな気持ちを生み出すことを目指しています。
このプロジェクトで特に良いと思った点は、プロジェクトに参加できるリターンがあることです。

本当に課題を解決したい、そのためにこういうものが欲しいという思いがあれば、お金を出すだけではなくて知識や技術で協力したいと思う人もいるでしょう。私もクラウドファンディングではいっしょに課題を解決する仲間を見つけたいという思いがあるので、このような仲間集めにつながるリターンを検討しようと思います。
また、①Me Clip・②ウィルバンクともに、起案者が出資者の個人的な課題に寄り添ってくれるリターンがある点にも惹かれたので、ぜひ参考にしたいです!


傾向③:起案者の顔が見える
①Me Clipも、②ウィルバンクも、プロジェクトページで起案者の顔が見えるプロジェクトになっています。①Me Clipにいたってはアイキャッチに登場されていますね(笑) また、どちらもプロジェクトページ内での活動報告やSNSの投稿が活発です。
クラウドファンディングは見ず知らずの人に出資することが基本です。そのため、出資する側としては「本当にこの人は責任をもってプロジェクトを遂行してくれるのか?」という不安を感じざるを得ません。
出資者の不安を解消して信頼してもらうためにも、積極的に顔出しをしたり発信したりする活動は必要不可欠なのだと改めて気づかされました。
■ クラウドファンディングで注意すべき点
注意すべき点①:ターゲットが狭すぎると気づいてもらえないかも!?
こちらのプロジェクトを参考にしました!
アーセナルだけしか興味ない人に捧ぐデバイス~グナルグナルソン~
アーセナルファンの愛称はグーナーです。ラズベリーパイ・電子ペーパーを使ってオリジナルのデータ表示デバイスを作りたいです!いつ見てもアーセナルが首位にいる優越感に浸れるデバイス!このデバイスを作って試合がない時でも自己満足度を上げませんか?
プロジェクトページより
先ほど「取り上げる課題は大きすぎない方が良い」と言いましたが、小さすぎるのも考え物です。こちらのプロジェクトを例に考えると、世界的にはたくさんのアーセナルファンがいるのかもしれませんが、少なくとも私たちが行うクラウドファンディングが届く層には少ない気がします。
感覚値ではありますが、10人中3人くらいが共感できる課題を設定するのが適切ではないでしょうか。こちらのプロジェクトの場合、特定のチームだけではなく、様々なスポーツチームファンが使えるデバイスというターゲットの絞り方が適切な範囲設定だったかもしれません。
注意すべき点②:SNS戦略が要!?
こちらのプロジェクトを参考にしました!
誰もが安心して満員電車に乗れるように『ヘルスコンディション表示マーク』をつくる!
電車で具合悪くなってしまったけれど、声に出して「助けて」と言えない。 体調を崩しやすく、外に出るのが不安。そんな人たちのために。 あなたの体調を表示し、周囲から配慮を受けられる、お守りのようなマークを制作し、グッズ配布・広報に取り組みます。
プロジェクトページより
最初は通勤にまつわる課題解決を目指すプロジェクトであるということと、起案者が私と同じ大学の出身者であるということで興味を持ち、プロジェクトの内容も共感できるものだったので出資を考えました。
そこで、SNSでの活動状況を確認しました。するとTwitterやInstagramのアカウントは見つかりましたが、投稿数が少ないことや、イラストの投稿が多く起案者がどういう人なのかがわからないことがひっかかりました。
先ほども述べた通り、クラウドファンディングは見ず知らずの個人に出資することが多いため、起案者に特別な経歴がない場合、信頼できるかどうかを判断するにはSNSでの発信を確認する必要があります。したがって、SNSでの発信が少ないと「この人はちゃんと責任を持ってプロジェクトを遂行してくれるのかな?」と不安になってしまいます。
どんなに良いプロジェクトだったとしても、起案者を信頼できなければお金を出すハードルが高いということを実感しました。
■ まとめ:クラウドファンディング成功の鍵は「共感」と「信頼」だ!
今回の分析では、クラウドファンディング実施に向けた学びや気づきがたくさんありました。クラウドファンディング挑戦の際には、少なくとも以下の4点を意識したプロジェクトにします!
○ 共感を得るためには
10人中3人くらいに刺さり、そのうち1人くらいが「私のためのプロジェクトだ!」と思うような課題設定にする
出資者参加型のクラウドファンディングにする
○ 信頼を得るためには
積極的に顔出しする
SNSでの報連相を怠らない!
これからもクラウドファンディングサイトやSNSで様々な種類のプロジェクトを見て、知見を深めていこうと思います!
最後に、プロジェクトを参考にさせていただいた先駆者の皆さまに、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?