
平野啓一郎『本心』感想
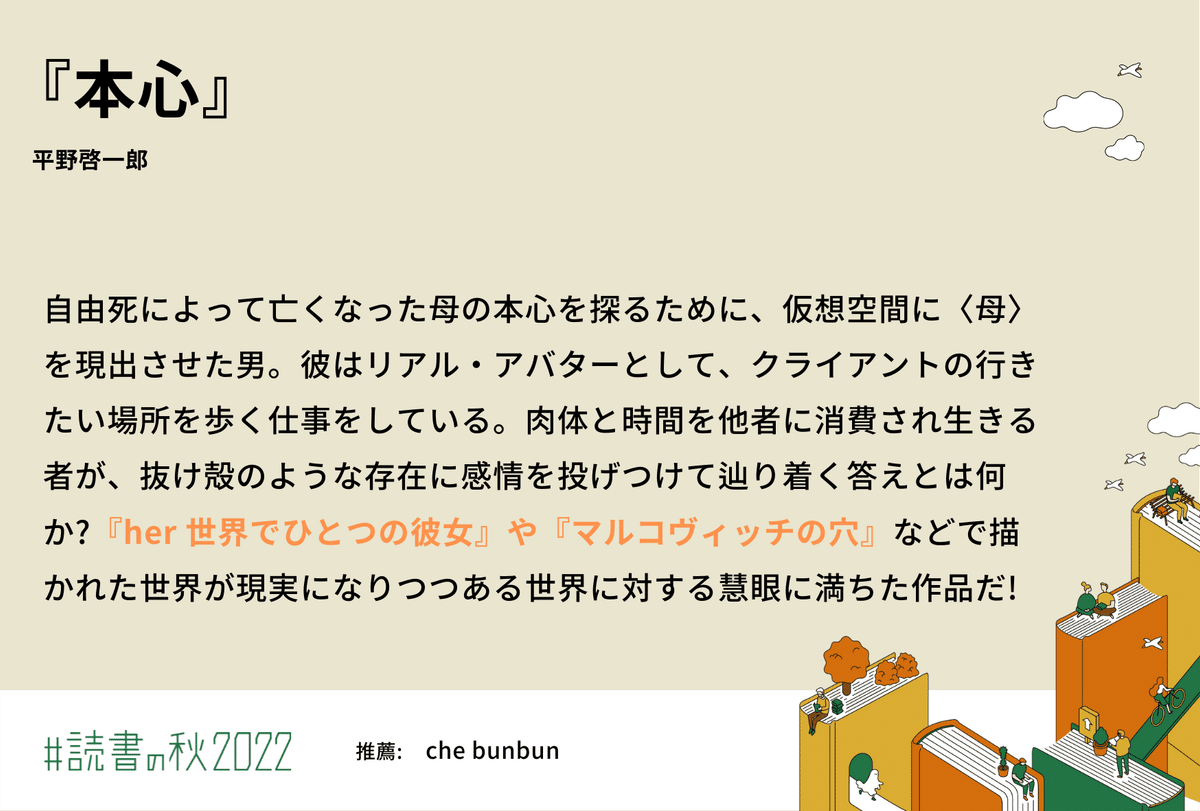
人工知能OS「サマンサ」と過ごすうちに愛が芽生える『her 世界でひとつの彼女』公開から10年が経とうとしている。10年後の世界において、AIと親密な関係になることが決してSF映画の世界ではなくなりつつある。メタバースやVTuber文化の躍進により、2020年代は立体的な仮面を纏う時代が紡がれつつあるのだから。
2010年代はSNSの普及により、人々は平面的なアイコンやハンドルネームを用いて、物理世界とは違った振る舞いを仮想世界の中で行なっていた。平面的な仮面を被っていたといえる。一方、メタバースやVTuberのように肉体とアバターが相互関係し合い現出する様は従来の仮面とは異なる。立体的な仮面を纏っていると言うのが正確な表現だろう。
さて、『マチネの終わりに』、『ある男』の原作で知られる平野啓一郎が、現在と『her 世界でひとつの彼女』の世界の間の時代を描いた小説を発表した。それが『本心』である。尊厳死(以下、原文にあわせ「自由死」とする)が合法化された近未来を舞台に、自由死によって亡くなった母を仮想世界上に蘇らせた男が巡る肉体と精神の関係性について扱っている。実際に読んでみると、平野氏の壮大で慧眼な社会考察にのめり込んだ。まさに、私も主人公「朔也」と共にVRゴーグルをつけて世界に身を委ねるような感覚があった。
今回はいくつかの視点から『本心』の感想を書いていく。
■肉体だけの存在に本心はあるのだろうか?
自由死によって亡くなった母を、数百万円かけてVF(ヴァーチャル・フィギュア)にする。母親に長らく指一本触れたことのない朔也は、膨大な質問票に答える中で彼女との記憶を手繰り寄せていく。
やがてVFは完成し、彼は仮想世界の中で虚構の〈母〉と対面する。話しかければかけるほど、〈母〉は学習し、母に近い仕草や言動をする。統語論的に振る舞っている状況にどこか冷めている朔也だったが、そんな彼をVRゴーグルへ向かわせる動機は「彼女はなぜ自由死を選んだのか?」を知ることにあった。膨大な母の記憶があるのなら、質問していけば統語論的に答えへ辿り着けるはず。しかし、彼女はなかなか応答しない。
「虚構の存在に本心はあるのか?」という問いを投げるところから本作は始まる。そして、奇妙な旅を通じて肉体と精神とのある視点がむき出しにされていく。
■〈自由死〉への願望は果たして本心なのか?
『本心』が面白いところは、多くの映画や小説で語られたであろうAIに心があるのだろうか?といったテーマを横に置いて、AIが当たり前となった世界における個と社会の関係を鋭く見つめている点にある。
例えば、「自由死」への願望は果たして本心によるものなのかといった観点がある。社会が老人や弱者を切り捨てるような状況下で、「自由死」が制度化されたとする。すると、自分が不要な存在であると感じた際に死へ向かわせるのではないか?その時の決断は本心なのだろうか?社会がそう決断させたと言えるのではないか?『本心』ではそこに切り込んでいる。
■『マルコヴィッチの穴』が現実的な世界になる時
朔也はリアル・アバターの仕事をしている。労働者が買い物をしたり旅行をしたりする様子をクライアントが画面越しで観るビジネスモデルだ。クライアントは労働者に指示を出すことができるので、まるでゲームのキャラクターのように人間を操作することができる。仮想世界におけるアバターのような挙動を物理世界で実行するため、リアル・アバターと呼ばれている。リアル・アバターは、肉体と時間をクライアントに貸すことで日銭を得るわけだ。先日、ロボットベンチャーのTelexistenceがコンビニの飲料陳列ロボットをVRで操作するオペレーターを募集していたが、その先の世界を魅せてくれる描写である。
何より驚いたのは、これはまさしく『マルコヴィッチの穴』の世界だったのだ。『マルコヴィッチの穴』とは、俳優のジョン・マルコヴィッチに一定時間なることができる穴を巡る物語である。ジョン・マルコヴィッチは、次々と穴に入ってくる人々に肉体と時間が奪われていく。従来、本作はヘンな映画として認知されていた。
しかし、リアル・アバターを前にそれはヘンな話だろうか?我々は、行けない場所への欲望を満たすようにYouTubeを観る。その延長にリアル・アバターがあることは全く変な話ではない。なんなら1年後に存在してもおかしくないビジネスだ。そして、物語はこのビジネスで発生するであろう生々しい問題を炙り出す。
ゲーム感覚でクライアントはリアル・アバターを操作する。それは自ずと主従関係を生み出す。その主従関係に陶酔するクライアントが朔也に嫌がらせを始めるのである。
松永伸司は「ビデオゲームの美学」の中で、映画や絵画を観ることとゲームをプレイすることは異なる体験があると述べている。前者は一般的に「鑑賞」と呼ばれ、提示されたものをそのものとして受け入れること行為となる。一方、ゲームをプレイすることは、ユーザーが操作し、それに応じてプログラミングされたシステムが応答を返す。それはインタラクティブな体験であるとし、本書では「受容」と定義している。リアル・アバターの体験はまさしく受容であろう。しかし、応答するのはプログラムではなく、生身の人間だ。しかし、ゲームをプレイするような錯覚は他者を踏み躙ることへと繋がる。生身の人間を受容することによる加害性を鋭く描いているといえる。
■肉体だけの存在になることで気づくこと
朔也は〈母〉と対話し、内なる孤独と対峙する中である事件に巻き込まれる。それをきっかけに、彼は仮想世界でアバターを纏い、そして周りから注目を集める存在となる。肉体だけの存在となった母に感情をぶつける彼が、肉体やラベリングされた情報でのみ判断され、感情を投げつけられる側に立つ。それを通じて、自分の中の本心に気付かされ、同時に次々と隠されていたことが明らかとなる。
『本心』を読むと、肉体は空間と同じ、内なる世界の一面を閉じ込めておくものなのかもしれないと感じた。デヴィッド・クローネンバーグ『ステレオ/均衡の遺失』における、テレパシーが当たり前となった世界で、他者からの干渉から守るために本心を別の箱に隠す理論を展開していたが、内に秘めた感情は物理世界であれ、仮想世界であれ、ある空間に流し込まれる。それは我々が生活する際の仕草に現れるのかもしれないし、アバターの表情に現れるかもしれない。本心とは、空間から滲み出る個の現実なのではと『本心』を通じ感じたのであった。
■参考資料
・「VTuberがVTuberとして現出するということ」山野弘樹
・ロボットをVR操作するアルバイト募集 遠隔でコンビニ飲料陳列 深夜・早朝なら時給1800円以上(ITmedia,2022/5/25)
・「ビデオゲームの美学」松永伸司
映画ブログ『チェ・ブンブンのティーマ』の管理人です。よろしければサポートよろしくお願いします。謎の映画探しの資金として活用させていただきます。
