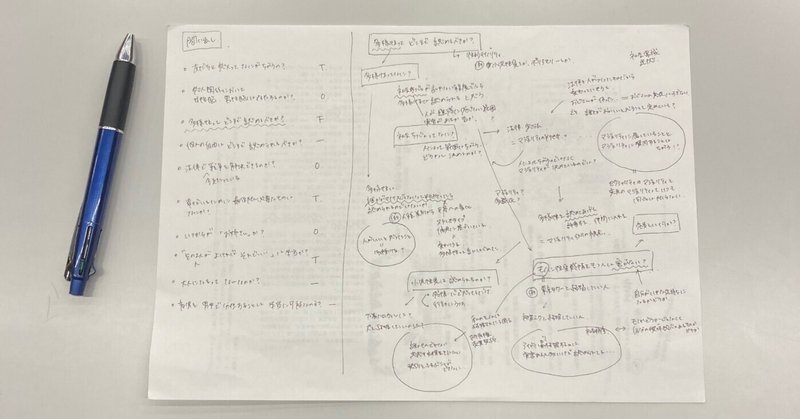
2023年の哲学対話の記録
ときどき、哲学対話というものをやっている。
出会ったのは大学1年の秋で、気づけばもう3年の終わりだから、丸2年くらいは哲学対話をやっていることになる。
わたしが初めて哲学対話に出会ったのは、『水中の哲学者たち』という、哲学書にしては異例のヒットを受けたエッセイを書いた人がいるのだけど、その著者の永井先生が担当している講義の第一回だった。
今日は、ただもう春休みになってしまったから、去年一年の(つまり2023年の)対話をなんとなく振り返ってみようと思って、このnoteを書いている。
はじめての投稿になるから、どんな人がこれを読んでいるかわからないけれど、ここまで来てくれてありがとう。
哲学対話とはなにか
知らない人のために最初にほんの少しだけ説明しておくと、哲学対話とは、一言でいえば「参加者が輪になって、問いについて一生懸命考えること」みたいな説明をされることが多い。
哲学という名前がついているけれど、偉い哲学者や難解な理論の話をするわけではなくて、ただ、普段は通り過ぎてしまうような問いに立ち止まってもっと深く考えてみること、自分一人ではたどり着けない答えをみんなと一緒に探しに行くこと。
世の中にはいろんな哲学対話があるから、少なくともわたしの知っている哲学対話はそんな感じだと言うことしかできないけれど、だいたいはこんな感じだと思う。
あと、わたしの説明だけでは心許ないと思うので、わたしの先生の定義もふたつ引いておく。
哲学対話とは簡単に言えば、哲学的なテーマについて、ひとと一緒にじっくり考え、聴きあうというものだ。普段当たり前だと思っていることを改めて問い直し、じりじり考えて話してみたり、ひとの考えを聴いてびっくりしたりする。
「哲学対話」とは、哲学者の名前や概念など哲学史の知識を一切必要とせず、「自由とは何か」、「働くとは何か」といった問いをめぐって、10名前後のグループでの対話を通じて考えを深める実践である。
わたしは大学でちょこっと哲学対話を勉強しているのと、先生の研究について小中学校での哲学対話に参加させてもらったり、たまに友達やサークルの人と哲学対話を開いたりしている。
1.「多様性をどこまで認めるべきか」という問い
今年を振り返っていちばんに思い出すのは、サークルのメンバーと教室の隅っこで話した「多様性をどこまで認めるべきか」という問いだと思う。
これはわたしが半年くらい抱えていた問いで、この問い方はとても傲慢だとは思うのだけど、「多様性を尊重しよう」とか「多様性を認め合おう」ということをみんなが言いながら、実際に認められていくのは「価値のある/有益な多様性だけ」である現状に強い反発心みたいなものがあって、こんな問いを考えていた。
東京タワーに恋する人がいたとして、わたしたちはそれを多様性として認められるのかとか、自分に影響がないと関心を持てないのはなぜだろうとか、性癖とセクシュアリティを厳密にはどう区別したらいいのかとか、そんな話をした気がする。
公共物とはなんだろうとか、結婚制度の意味とか、多様性自体の価値とか、対話のなかでそういうものがどんどん揺らいでわからなくなって、しばらく何に対しても価値判断を下したくない気分になった。
この対話が印象に残っているのは、たぶん、「自分に迷惑のかからない範囲ならどうでもいい」という後輩の発言が、あまりにもまっすぐ自分の心に刺さったからだと思う。
多様性という言葉を使うとき、わたしたちは大人たちのさまざまな思惑の交差点に立たされている、と感じる。経営の文脈とか、生物学の文脈とか、いろんなひとのいろんな定義や背景を持つその言葉をどう扱えばいいのか、わたしにはまだわからない。でも少なくとも、多様性がなにかの手段になることは正しくないという予感がわたしの中にあって、「自分の役に立つから」とか「自分に利益があるから」とかそういう理由で多様性が擁護されるのは違うんじゃないか、と思ったりする。
後輩の言葉はある意味で正しくて、それは「多くの大人がそう思っている」ということだけど、そこで終わってしまわずにそうじゃないなにかをもっと一緒に探してみたい、そんなふうに思った。
2.「信頼とはなにか」という問い
もうひとつ、今年を振り返って忘れられない対話がある。
冬の寒い日の午後、はじめて足を踏み入れる学校で、はじめましての中高生と「信頼とはなにか」という問いで哲学対話をした。ある子が「自分は最近、友達だと思っていた人を怒らせてしまって、あなたへの信頼はもうない、と言われてしまった」という話をしてくれて、そこから、信頼とはなにかという問いがテーマになったのだと思う。
「友人として信頼している」というときの信頼と「仕事仲間として信頼している」というときの信頼はなにが違うのか、ということをポツポツと話していて、どんな人が信頼に値するかの基準が人によって違ったり、友人と仕事仲間の境界線が実は曖昧だったり、そんなことに少しずつみんなで気づいていって、お互い近づいたり遠のいたりしながら答えを探している、そんな対話だった。
誰かを信じるというとき、わたしたちはなにを信じているのだろうとか、自分に見えないところに書き込まれたことのほうが、その人の本心みたいに感じられるのはどうしてなのかとか、問いの裏から揺らぐ中高生の気持ちが痛いほど伝わってきて愛おしかった。なにより、数年ぶりに聞いた「親友」という言葉がガツンときて、感激した。大学生になってから、おそらく一瞬もその言葉がわたしの頭に浮かんだことはない。特定の友人に執着してしまうあの気持ちとか、不安にまみれて過ごした日々とか、閉鎖的な空間にいたあの時期ならではの人間関係の苦悩を思い出して感慨深くなると同時に、その青さが眩しかった。
その人だから立てられる問いがあるし、その人だから言えることがある。なにかに傷ついたり、苦しんだり、悩んだり、そういう切実な記憶があるから、わたしたちはそこから何かをはじめることができるし、問うことができるのだと思う。対話のなかでそういう切実さに触れるたびに、背筋を伸ばして、わたしも本気で向き合おう、そんなふうに思わされる。
わたしが哲学対話をやっている理由
最初に、「ときどき、哲学対話というものをやっている」と書いた。
わたしは自分の考えていることを誰かに話すのはあまり好きじゃないし、対話は自分のやわらかい部分に誰かが踏み込んでくるような気がしていつも怖い。誰かの発言が自分をひどく打ちのめすこともあるし、自分の考えがひっくり返って跡形もなくなってしまうこともある。自分が傷つくこともあるし、誰かを傷つけてしまうこともある。
でも、対話中の誰かの何気ない言葉に救われたり、一人ではたどり着けなかったところに誰かが連れていってくれたりもする。少しずつ言葉にしていくなかで新しい自分を見つけたり、世界の美しさや豊さにふと出会ったりすることもある。
だから、なぜ哲学対話をやっているのかは自分にもまだよくわからないのだけど、ただ自分の探しているなにかがそこにありそうな気がして、そんな瞬間を掴みたくて、いまもやめられないでいる。おそらく、これからも。
読書案内
あまり適当なことを書くと先生に怒られそうなので、哲学対話に関する書籍をいくつか貼っておきます。もっと知りたいと思った方がいればぜひ、わたしではなくこちらを参照していただけると幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
