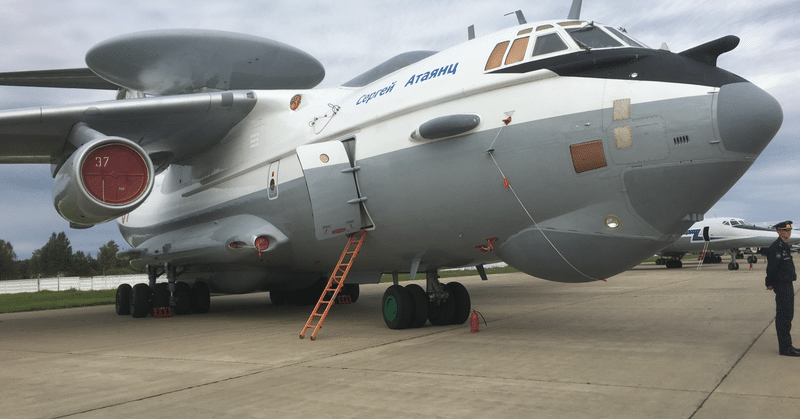
第121号(2021年3月15日) 春休み読書企画 戦争について考える
存在感を増す「軍事大国ロシア」を軍事アナリスト小泉悠とともに読み解くメールマガジンをお届けします。
定期購読はこちらからどうぞ。
【春休み読書企画】 戦争について考える
なんとなく「おうちの人から戦争の体験を聞いてきましょう」みたいなタイトルになってしまいましたが、そういう話ではなくてですね(そういえばもう近頃のおうちには戦争体験のある人っていないでしょうしね)。
戦争という現象は現代の世界でどのように位置づけられるのかについて、最近読んだ本をいくつか紹介してみようという企画です。昨年の夏休み読書企画が割と評判よかったので、今回は春休み編。
・多湖淳『戦争とは何か 国際政治学の挑戦』中央公論新社、2020年
最初に取り上げるのは早稲田大学の多湖淳教授が昨年上梓した『戦争とは何か』。
Amazonのレビュー欄を見てみると分かりますが、この本は毀誉褒貶がものすごく激しいです。ひとことで言えば全方面に喧嘩売ってる本だからですね。
著者の多湖先生は、序章において「科学として戦争を考える」、つまり「透明性の高い手順で構築され、かつ妥当とされる方法論をあてはめて処理されたデータ分析の結果があり、分析の質や内容を再確認できる形の「エビデンス」(証拠)が提示される」ようなやり方の重要性を強調します(19-20頁)。
これは全くお説ごもっともというところで、後から取り上げる中井遼先生の『欧州の排外主義とナショナリズム』なんか読んでると、科学的な手法というのは(その無味乾燥な印象とは裏腹に)こんなに豊かに「政治」や「社会」を描けるんだなぁと感心させられます。
他方、多くの国際政治学徒がカチンときているのは、古典的な国際政治学に対する態度でしょう。以上で引用した箇所に続いて、多湖先生は「本書と対極にある国際政治の考え方について」という項を設け、「極」の数に着目するウォルツ以来のシステム論やリアリズム、リベラリズム、コンストラクティヴィズムの限界を指摘します。
まぁこれもその通りですね、という感じではあるのですが、既存の国際政治学を「風が吹けば桶屋が儲かる」式のものとし、その代表格を高坂正堯になぞらえる(189頁)となると大分頭に来る人もいるでしょう。
正直言って、最初に本書を手に取ったとき、私はそういう感情を持ちました(「おお、俺ってこんなに古典的な国際政治学にシンパシーがあったのか」と思ったり)。国際安全保障学会の会報『国際安全保障』第48巻第2号に本書の書評を寄せた籠谷公司氏(大阪経済大学准教授)が次のように述べているのは、こうした感情的反発を見越してのことでしょう。
「ただ、著者が一般理論(「イズム」)から脱却して科学的手続きに基づいた国際政治学研究の推進を強調しているため、一般理論に基づく研究が仮想敵であるような印象を持つ人もいるかもしれない。しかしながら、これは誤解であり、科学的な国際政治研究は一般理論の影響を少なからず受けている。評者として、この点だけを補足しておきたい。」
「したがって、本書で紹介される知見は、現実主義や自由主義といった一般理論の精緻化ならびに検証が繰り返されてきた科学的営みの成果として捉えるようにしてもらいたい。」
「多湖君いいこと言ってるんだけど言い方ってもんがあるよ」という感じがひしひしと伝わってきますし、まぁ実際そうだなと私も思います。
私が早稲田大学の政治学研究科にいた頃というのは統計理論が日本の政治学に大々的に導入され、院政の中には「統計にあらずんば研究にあらず」みたいなことを言って息巻く人が結構いたのですが、なんとなくそのノリを想起しました。
ただ、この文章を描くために本書を再読してみて、少し印象が変わった部分もあります。多湖先生の問題意識は「いかにして戦争を起こさせないか」であり、そのためには精度の高い国際政治研究の手法が開発されて政策に生かされねばならんのだ、という点で一貫しています。
本書のあとがきで述べられている家族への温かい感情(まぁ三歳児にナッシュ均衡を暗記させるのはどうかとも思うものの)を見ても、その根底にあるのは非常にヒューマニスティックな考え方なのだろうと思います。
と同時に、本書を読み直してもなお残る疑問というのはあります。
多湖先生は「ユニークな戦争はありえない」(25頁)として戦争を一般化して扱えるというテーゼを掲げますが、ロシアという「わかりにくい」国を見ているとどうもそういう感じがしないのです。
たしかに統計を用いた科学的な戦争研究は「戦争と平和をめぐる一般的な傾向の把握を可能」とするのでしょうが、それでは個別事例についてはどうなのか。本書が前提とするように、国家は常に合理的に振る舞うとか、戦争は高コストなものであるから回避しようとするはずである、といった諸前提はどこまで正しいのか。
例えば何を以て国家が「合理的」であるとするのか。
ジョンスソンの『ロシアの戦争理解』をはじめとする多くのロシア軍事研究が明らかにするとおり「西側はロシア弱体化を目論んで公然・非公然、軍事的・非軍事的様々の「目に見えない侵略」を仕掛けてきている」という陰謀論的世界観に政治・軍事指導部が凝り固まっている場合、その世界観の中での「合理性」は科学的研究手法の想定する合理性とはかなり乖離するはずです。
また、戦争は高コストであって、それは軍需産業や為政者にとってもそうだという議論は果たして妥当なのか。この点は、少なくとも本書では「エビデンス」のある形では論証されていません。一般的にはそうだと言えるかもしれないけれども、「この戦争に限っては低コストにやれる」という認識が(正しいか誤っているかは別として)抱かれている場合はどうなるのか。ロシアによるクリミア・ドンバスへの介入などは、こうしたミス・カルキュレーションの下に始まったものであるように思うわけです。
そして「戦争は数えられる」と本書は述べます(3頁)。本書の定義によれば、「戦争は二つ以上の政治的な意思決定を行うアクター(集団)が組織的に暴力を用い、継続的に対立している状態」とされます。さらに、戦争ほどの暴力が行使されない緊張・対立状態までを含めた紛争、戦争と平和の「きわ」としての危機があると整理した上で、戦争の定義にあてはまるものは同列に比較できると前提されています。
しかし、ウクライナ危機のように政治・経済的コストはともかくとして軍事的烈度がそこまで高くない軍事力行使と、第二次世界大戦のような破滅的な大規模戦争とではコスト計算がかなり変わってくる筈であり、この辺も「戦争全般」の理論構築としてはよくても個別の戦争を論じるにはどうかな、という感じがします。
いろいろと言いましたが、本書はたしかに科学的な戦争研究の手法を学ぶ上では格好の入門書ではあるでしょう。とすると本書のタイトルは『戦争とは何か』というよりも(というのも、本書の定義でいうと戦争とは大規模な組織的暴力の行使である、という以上のことにはならないので)『科学的戦争研究とは何か』のほうがピタッと嵌まったかなという気がしてくるわけですが。
まぁ科学的な研究も非科学的な(とは別に思ってないですが)研究も仲良くやってきましょうや。
・廣瀬陽子『ハイブリッド戦争 ロシアの新しい国家戦略』講談社、2021年
次は慶應大学の廣瀬先生による新著です。第118号で述べたように、私は本書をダブってどころか3冊買っちゃったわけですが、その後廣瀬先生自身からも1冊ご恵贈頂いたので現在研究室には4冊あります。重ねると9mm弾くらいは止められます(多分)。
さて肝心の内容ですが、ウクライナ危機でロシアが用いた曖昧な軍事介入、米国や欧州に対するサイバー・情報戦、世界中で暗躍する民間軍事会社(PMC)などが豊富な実例とともに紹介されており、私としても学ぶところ非常に大でした。
世界的な大国であらんとする理想像と、現実にはそうでないという国力のギャップを埋めるために捻り出されてきたのが「ハイブリッド戦争」と総称されるこの種の対外政策であったのでしょう。
それから本書は「ハイブリッド戦争」の思想的バックボーンとされるエフゲニー・メッスネルの思想を日本語で詳しく紹介した初の書物でもあります。メッスネルの思想の重要性はこれまでもレンツの『ロシアの軍事的復活』等、英語の研究書では指摘されてきたところですが、この意味では本書は日本の「ハイブリッド戦争」理解を世界レベルに引き上げるものと言えます。
メッスネルの思想で重要なのは、現代の国家間闘争は相手国民の心理を掌握したり動揺させたりするための認知領域を主な舞台とするという点でしょう。したがって、戦争はもはやひとつながりの戦線を挟んで物理力を行使する形態(線形戦争)ではなく、社会のあらゆる領域を戦場とする「非線形戦争」になるというのがメッスネルのテーゼでした。また、非線形戦争には明確なはじまりやおわりはなく、平時と有事の境界も曖昧になるとされています。
しかし、このような闘争形態は冷戦期から行われていたものであり、米国のジョージ・ケナンは1949年にこれをソ連の「政治戦(Political Warfare)」と名付けて警鐘を鳴らしています。
さらに時代が下って1980年代には、こうしたソ連の干渉手法が「アクティブ・メジャーズ」として米国で注目されるようになり、ロシアの「ハイブリッド戦争」が注目されるようになった昨今ではこれをテーマとした本が英語ばかりか日本語でも盛んに出版されるようになりました。ウクライナの元国家安全保障会議書記であるホルブーリンの『世界ハイブリッド戦争』で言われている「ハイブリッド戦争」も、前提としているのはこの種の「戦争」です。
この点は日本も無縁ではありません。真田尚剛『「大国」日本の防衛政策 防衛大綱に至る過程 1968〜1976年』の第1章を読むとよく分かりますが、1960年代くらいまでの日本で真剣に懸念されていたのは古典的な大規模侵略というよりも、ソ連による内政への干渉・撹乱であり、要するに冷戦下の日本でも「政治戦」はずっと意識され続けてきたということになるでしょう。
とすると、ロシアが現在用いている手法の効果や、その対処に関する必要性・緊急性は別として、この種の闘争手段が決して目新しいものであるという感じはどうもしてきません(これについては多くのロシア研究者が指摘しているのでいずれ紹介していきたいと思います)。
もうひとつ、私がずっと気になっているのは、情報や心理を用いた非軍事的な闘争と、古典的な軍事的闘争との関連性です。前述のジョンスソンは、2000年代以降にロシアの軍事政策サークルの中で非軍事的闘争論が非常な隆盛を極めるようになったことを実証的に明らかにしている点で興味深いのですが、これだけ通読するともはやロシア軍の中では軍事力の価値が「オワコン」とみなされているような印象を抱きます。
『ロシアの戦争理解』の序章では、ジョンスソン自身がそうした見方は誤りであるとして先行研究をコテンパンに批判しているのですが、本文を読んでいくと彼自身もそうしたバイアスをかなり受けてしまっているように見えるのです。
これについてジョンスソンは、ロシア軍内部では非軍事的闘争が失敗した場合に軍事力が登場するという「二段階アプローチ」の考え方があることを紹介していますが、ではこのアプローチの存在と非軍事的闘争論は具体的にどう接続しているのか、具体的にどのような戦略として定式化されているのかは彼の著書からはいまひとつ明らかでないように思います。
さらにジョンスソンは終章で、「ロシア軍で非軍事的闘争論が盛り上がったのは、陰謀論的な世界観に染まった政治的指導部への忖度では」みたいなことを突然言い出すわけですが、そうなると「これまでの議論はなんだったのよ」ということになり、いまひとつ不誠実な印象も拭えません。
そこで5月にちくま新書から出る拙著『現代ロシアの軍事戦略』ではこの辺について、ロシアの軍事力行使や大規模演習を題材として理論と現実の接続を図ってみました、というわけで新著が出ますんでよろしくお願いいたします(結局これが言いたかったのかという)。
・中井遼『欧州の排外主義とナショナリズム 調査から見る世論の本質』新泉社、2021年
今回はもう一冊、「科学的研究」の本として、北九州市立大学の中井遼准教授による『欧州の排外主義とナショナリズム』をご紹介したいと思います(そういえば本書もご本人からご恵贈いただきました。ありがとうございます。なお自分でも買ったので本書もダブっています)。
ラトヴィアを中心とするバルト諸国の計量的政治研究で知られる中井先生ですが、本書はバルトを含めて西欧から東欧まで、広くヨーロッパ全域をカバーしつつ昨今の排外主義の背景を論じています。
印象的なのは、まさに多湖先生がいう「風が吹けば桶屋が儲かる」的な床屋政談を徹底的に排除した、科学的な研究姿勢です。
まず俎上に載せられるのは、欧州はそもそも排外主義化しているのか、という大前提ですが、統計的に見ていくと実は排外主義自体への支持は高まっているわけではなく、むしろ若干緩和の傾向さえある、という予想外の調査結果から本書は始まります。
と同時に、排外主義を掲げる右翼政党への支持はたしかに伸びている。
ではこのアンビバレンスをどう説明したらいいのか。この点をめぐって、本書では様々な議論が展開されていきますが、これは門外漢から見ても非常に面白かった。
例えば欧州の排外主義化(とされる現象)については、移民によって失業の恐れにさらされる経済的弱者が主な支持者であると説明されることが多く、これは僕のような専門外の人間もよく聞く話なのですが、本書はここに二重三重のどんでん返しがあることを明らかにしていきます。
曰く、実は貧困層はそう排外主義的なわけではない。曰く、人は自分の貧困よりも自分が属する社会全体の貧困化を恐れ流。曰く、排外主義は移民そのものよりも移民の受け入れを強要する政治エリートや欧州統合に向けられている…などなどで、なるほどこういう機微を描き出せるところに科学的研究の醍醐味というのはあるのだろうなと思わされました。
それから本書はなんというか、良い意味で非合理的なものを引き受けている、という印象を持ちました。例えば、
人々は政治主張に合致する政党を支持するのではなく、支持する政党の主張を受け入れている。
人々は世論調査で、自らの属するコミュニティにとって望ましいことを言おうとするため、それほど右翼的でない人が右翼的なことを言ったり、リベラルでなくてもリベラル的なことを言ったりする。
排外主義に感化されやすいのは実は「意識の高い人」である…などなど。
「ああ人間てそういうもんだよなぁ」と膝(や腹肉)を叩くことが本書を読み進める間幾度もありました。
この辺が合理的選択論とどう結びつくのかは、私は門外漢でよく分かりませんが、科学的研究手法というのはこの種の不合理さを織り込む形をとった時にこそ威力を発揮するのではないか、と思うわけです。その意味では中井先生のように強固な地域研究の基盤がある人が統計的手法を駆使する、というのが最強なのかもしれませんね。
あとどうでもいい話ですが、「世論調査は外注に出せる」ということを本書を読んで初めて知りました。まぁ企業とか国家とかが委託してやってるのだろうなとは思っていたんですが、研究者が研究予算の範囲内で調査を委託できるようなプラットフォームというかビジネスがちゃんとあるんですね。
こういう「外の世界」のことを知れるのも読書の面白みだと思います。ああ結局最後は脇道に逸れてしまった。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
