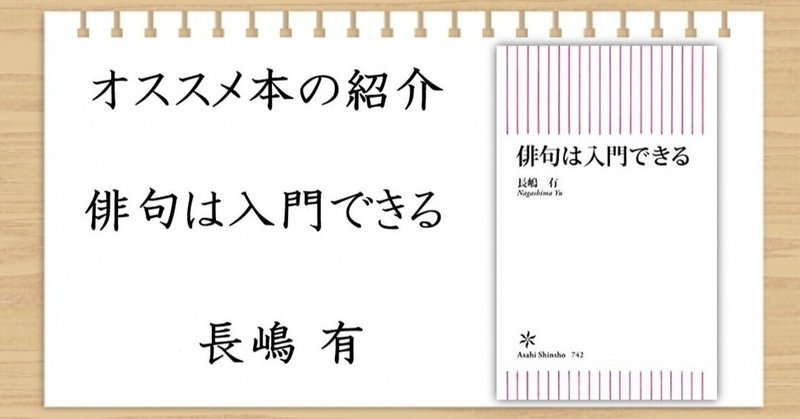
「俳句なんかやっている場合か!」って時こそ俳句を作ろう。俳句は入門できる(長嶋有著)を読んで
芥川賞作家にして俳人の長嶋有の新書の紹介である。読了後のアウトプットと合わせて行いたい。
特に面白かったのは
初鮫は片足残しくれにけり 長嶋有
と言う句の紹介だ。安心して欲しい。この句は、フィクションである。「俳句とはわざわざ人が作って成立するものだ」という、至極当然のことに気が付いた著者が、その気付きに感動して句に残したものだという。辞世の句があるように、俳句は「そんな非常時に俳句なんかやっている場合か!」という時にでも、割と平気で詠まれていたりする。それが俳人の性というものだろうか。
などと考えていたら小生も、剃刀での髭剃りに失敗して、大量止血した際に
血が流れでる白夜なら美しい 亀山こうき
などと、のんきに詠んでいた変態であることに気がついた。句歴は浅いがどうやら小生、根っからの俳人らしい。
俳句の入門書としても、俳句について深く考察する書としても、エッセーとしても非常に面白い本であった。一読をお勧めする。
・俳句を作るとは当事者ではないという事(P39~40)
(横山白虹の名句「ラガー等のそのかちうたのみじかけれ」を例に挙げて)
俳句を作るというのは「その人は当事者じゃない」感のある行いだ。カメラのシャッターを切ることに似て、その人は現場にいるけど参加してない人、ということになる。だから、まあいいんだ。いいんだけども。特にここ(ラグビー)では、対象が肉体を具体的に駆使する存在なだけに、文筆というもののナヨナヨ感がことさら露呈するのは作品自体の邪魔になる。僕は「ラグビーを俳句にするなら、実際にやれ、そうでないと本質は実感できない」と言いたいわけではない。ただ、まろび出てしまうその露呈について、自覚を持たないでいることを危ういと思う。歳時記をめくれば。誰かがああだこうだ考えて季語とみなしてくれた言葉がたくさん載っている。でもそこから語を取り出す際、それらを、また一から自分だけの頭で検証してもいいのだ。ラガー等は横山さんの句だけあればいいとさえ思う。
・「こんなの詩じゃない」はありえない(P45)
すべての詩にはそれぞれ巧拙があり、評者はいくらでも個々の詩を否定していいが、ただ一つ「こんなの詩じゃない」という言葉だけは嘘だと思っている。巧拙を問われていることはあっても、詩はその人が「詩だ」とみなしたものは全て詩だ、というのが僕の考えだ。
・たとえ添削によって改悪されても、添削自体には意味がある(P56)
(添削をうけて、添削前の方が良いと感じることもある。だから添削は不必要だという意見に対して)
(添削を受けて)アノー、前ので別によくね?と思う人もいるはずだ。それはしかし、「添削なんて無意味」ということではない。前の句がよくみえるのにも理由がある。人はわざわざ脳を使って記憶したものを、それだけで少し愛しく思うのだ。だから既に一回覚えた句の方が、後のプランよりもわずかに愛しい。また、一人だけの力で生まれたものの方が、(下手くそでも)無垢なものにみえる。だから「他者」が赤マジックを入れる現場にヒヤリとした気持ちを抱くのであろう。
・文学の意味(P132)
「文学なんて生きていく役に立たない」という人がいる。そうかもしれない。生涯、文学の必要ない人はきっといる。「生きるか死ぬかの非常時にはなおさらだ。死にそうなとき、ピンチのとき、創作活動なんてしている暇はない」そういう人もいる。僕はそれは嘘だと思う。非日常の、ピンチの時にこそ文学や詩や歌を「使う」のだ。心の中で思い出したり、諳んじたり。俳句は短いから、作ることさえできる。運動神経や、サバイバル術がときに人を生き延びさせることと、まるで同じことのように僕は思う。
・短時間で兼題俳句の佳句をつくるヒント(P148)
(コーヒーというお題で、数分で句をつくらなければならない時、俳人小澤實がわずか1分そこそこで「高階のコーヒー甘し花持てる」を作った。その句作過程を著者は想像する)
まず小澤は、コーヒーを「コー」と「ヒー」にすぐ分けてしまった。題の「コーヒー」自体は真ん中の五七五の七のところにおくとして、「コー」を前半の五に、「ヒー」を後半の五に振り分けて考える。つまり意味は世界ではなく、まず句全体の「韻」を整えるのだ。それで「コー」という音から高層階を表す高階という、普段ならあまり使わなそうな言葉を思いついた。一方の「ヒー」の方は 、ヒ ではなく「ハフヘホ」にスライドさせた。コーコーヒーヒーではちょっと調子がよすぎるから。さて、コーヒーは季語ではない。高階もだ。つまり上の真ん中に季語が入らないのだから、下はハ行の「季語」にすることは確定。花が素直に浮かび、あと甘かったり花を持ったりで整える。
・「暗記できる」ことと句の良し悪しに因果関係はない(P160)
(NHKの朝ドラは朝の忙しい人にも見てもらえるように、ナレーションや説明的なセリフを多くしている。いわば見逃されることが前提のドラマである。俳句もこの朝ドラに近いことに作者は触れて)
伝達に一語一語すべてが使われなくてもいいと思いながら句作するというのは「季語が動いても」まあいいや、みたいに思っているということでもある。それもまたルーズで危ういことだけど、十七音しかないのだから丹精して、みたいにやってなお、暗記してもらえないのかもしれない、一番いいたかった言葉やフレーズさえ伝われば、成功なんじゃないの、とも思うわけだ。うろ覚えの読者も一読者だ。僕は遠ざけたくない。……まあ、一句全てを暗唱できたほうがその場において、「かっこいい」ことは、これは間違いないのだけれども。
・今の俳句世界に欠けているもの(P181)
今の俳句の世界に欠けているものは、「優れた俳句」でも「若手の存在」でもない。「優れた俳句を紹介する存在」や「批評」でもない。欠けているのは「逸話」だ。面白い世界、多くの人の心を長く灯し続け、熱く語られる醍醐味のある世界には、必ず多くの「逸話」がまつわる。漏れ出る。
・俳句と写真、小説の決定的な違い(P188)
写真なんか、間違ってシャッターを押しちゃっても写真だ。でも、間違って俳句ができることはない。文字をそのように並べて発表した人が必ずいる。つまり、俳句には「そういうことを俳句にした人がいる」という文字情報が添付されている。そして、定型と切れ字という格好付けが、「そう言おうとした人」の存在を輪郭付けている 。そんなの当たり前だという人は冴えていない。小説にだって、「ということを小説にした人がいる」という情報のテキストは添付されている。でも、小説本体は「ということを小説にした人がいる」というテキストよりも圧倒的に長い。俳句はたった十七音だから、「ということを俳句にした人がいる」は、拮抗する長さの情報なのだ。僕はこれは重大なことだと思う。
・「俳句なんか作っている場合か!」って時こそ俳句を作ろう(P189)
(前まとめを受けて)
「ということを俳句にする」にもさらに付帯する言葉がある。それは「わざわざ」だ。我々はわざわざ俳句を作っているのだ。そうでない俳人はいない。俳句を作り続けるということは、どこまで「わざわざ」創作できるかという試みをするということでもある。
中略
すべての俳句の末尾に「……ということを俳句にした」という情報が付帯されているのならば、挑戦できる面白さに「ていうか、俳句なんか作ってる場合か!」がある。わざわざ、を活かすわけだ。
・ちょこっとメモ
・著者主催の並選句をなくした句会「タイマン甲子園」と言う句会があるらしい。面白そうだ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!楽しんでいただけたら幸いです。また、小生の記事は全て投げ銭形式になっています。お気に入り記事がありましたら、是非よろしくお願いします。サポートやスキも、とても励みになります。応援よろしくお願いいたします!
