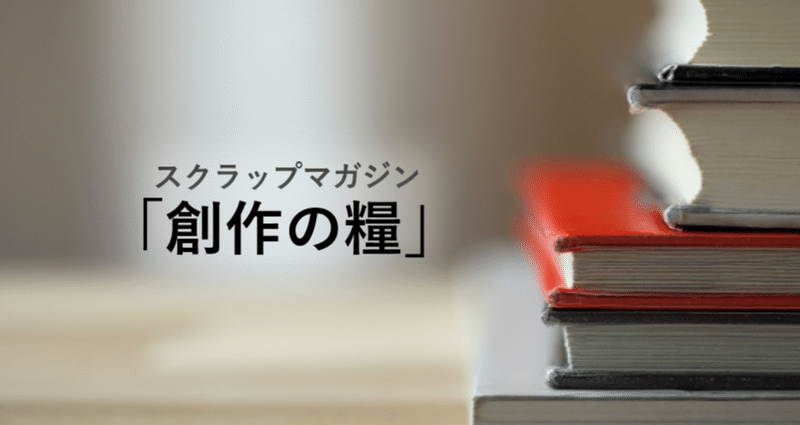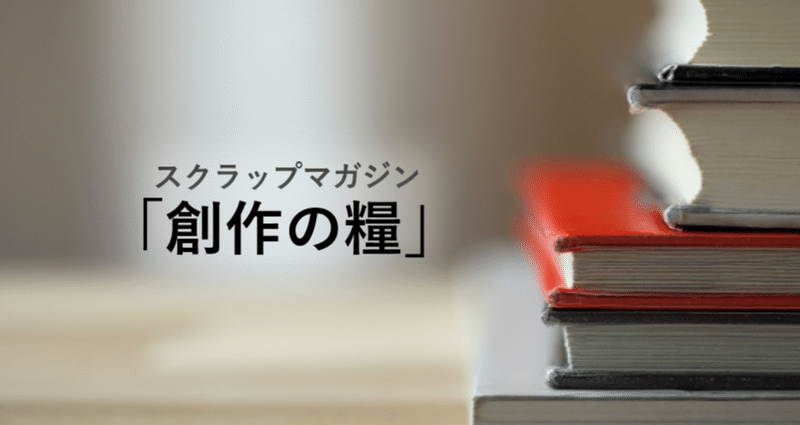作者の人格と作品は別なのか
日本史学者の呉座勇一先生が、Twitterの非公開アカウントで英文学者の北村紗衣先生への誹謗中傷を繰り返していたことが発覚し、大きなバッシングを受け、ついには考証を担当していた来年度の大河ドラマの降板を自ら申し入れるまでに発展した。
このように、問題のある言動をした人物を、その職場からも追放しようとする動きは、近年アメリカで盛んになっているが、日本でもそうした運動を目にする機会が増えてきた。
呉座先生が追放されることを望んでいた人たちは、彼のように卑劣で差別的な人間はNHKの