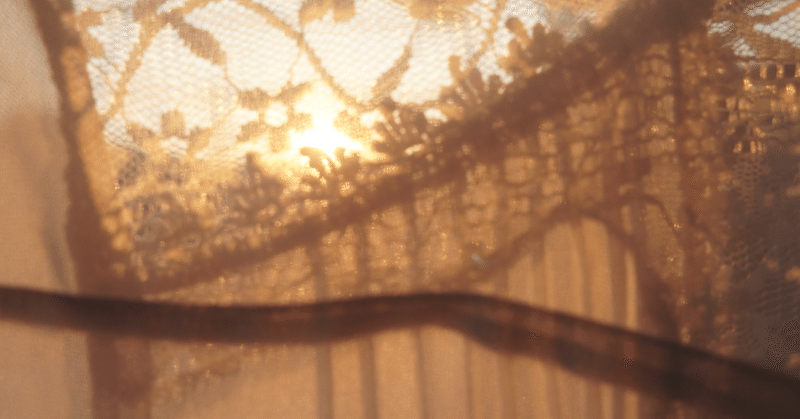
Cadd9 #32 「いま、俺の手の中にあるものは」
薄いカーテンが揺れている。
陽射しは真上から照りつけ、汗ばんだ肌をじりじりと焼いた。耳障りな蝉の声に、夢の中ですら気分が悪くなる。
大きな窓に縁どられたその光景は、古い絵画のように静止し、周囲にある鮮やかな植物たちも静止し、なぜかカーテンだけが風もないのに揺れていた。
その奥に見える人影は、永遠にそこに佇んでいる。時間が止まった空間の、何もかもから見捨てられた、空白のような永遠の中に。その人の名前を呼ぼうとしたが、からからに乾いた風のような息しか出なかった。そしてカーテンがふくらむたびに、誰の名前を呼ぼうとしているのかすら、曖昧になっていった。
樹はそこに閉じ込められたものたちのことを思い、今となっては永遠に選ぶことのできないもうひとつの選択肢と、その先にある物事のことを思った。この気持ちは、後悔とも悲しみとも言えない。失ったものは返ってこない。こんな夢をくりかえし見せられたところで、今さらどうしようもないのだ。そう思った途端、何かが軋む音がして、扉がゆっくりと閉まるように、樹は少しずつその場所から切り離されていった。
目を開けて、眩しさに目を細めた。眠っている間に、太陽の光をまともに顔に受けていたらしい。視界が、赤みがかった黄色に見える。このところ、日中に眠ると同じ夢ばかり見てしまう。樹は両目を手のひらで覆い、ため息をついた。
宏一の運転する車は、高速道路を下りて左折し、国道に出たところだった。海がすぐ近くに見える。少し前は見慣れていたはずの光景なのに、以前とは全く違って見える。
そういえば、入試のためにバスでこの街を訪れた時には、窓の外の景色なんて気にも留めなかった。樹は窓に額をつけ、海に反射する光や、通り過ぎてゆくいくつもの電柱を見ていた。
「沙耶ちゃん、きっとびっくりするでしょうね。樹くんが帰ってきてくれて、どんなに喜ぶかしら」
助手席に座る百合美が言った。珍しく覇気のある声だった。宏一がオーディオのボリュームをしぼる。樹は窓から額を離し、シートに背中を預けた。
特急と新幹線を乗り継ぎ、四時間半をかけてここまで来た。駅まで迎えに来た二人を見つけたとき、何も百合美さんまで来る必要はないじゃないかと、樹は思った。
「沙耶には、本当に何も伝えてないんですね」
「そうよ。びっくりさせたくて」
百合美は車内のデジタル時計を見た。
「いい時間ね。ちょうど塾から帰ってくるころだわ」
「塾に行ってるんですか?」
「そうよ。英語を教わってるの。家にいても宿題や読書ばかりしてるものだから、せっかくなら友達と勉強できたほうがいいと思って。最初は心配していたんだけれど、本人はけっこう楽しいみたいよ。友達も増えて、よく一緒に出かけてるわ。成績がいいのはきっと遺伝よね。早苗さんも優秀な人だったから」
音楽といい成績といい、彼女は何かと子と母親を関連付けたがる。彼女から母親の話を聞くたびに、樹はどことなくばつが悪くなってしまう。無意識かもしれないが彼女は、今はいない樹の本当の母親に、何かしらの劣等感や引け目を感じているようなところが、どうしてもある気がする。
樹は鞄を開けて、百合美から受け取っていた沙耶の写真を取り出してみた。時を経るごとに、さまざまな表情を浮かべ、彼女だけの雰囲気を身にまとい、少しずつ少女らしくなっていく俺の妹。長い間離れて暮らしていても、沙耶が妹であることはずっと変わらない。それでも、二年近く別々に暮らしていた人間といきなり同居することになるのは、いくら兄妹でも戸惑うものだろう。百合美はサプライズだと浮わついているが、樹は沙耶を振り回してしまわないか心配だった。
十センチほど窓を開けた。冷たい春風とともに、潮のにおいを含んだ風が頬をなでていく。樹は、遊園地で身体を寄せ合う早苗と沙耶の姿を思い出した。あの日の自分と今の自分が同じ人間だとは、とても思えなかった。俺は沙耶にどう説明すればいいのだろう。彼女の大切なものを奪ったのは自分なのだと、いったいどんな言葉で伝えればいいのだろう。沙耶に嘘をつきたくはなかった。だからこそ、いつか母親の死について沙耶に問われる時がくることが、とても怖かった。
宏一は駐車場の一角に車をとめた。
まだ正午を過ぎたばかりだが、客用の駐車場の半分はすでに県外車で埋まっていた。旅館の正面玄関に吊り下げられた巨大な提灯にも明かりが灯り、魚屋らしい数人の男が木箱を持って往来していた。それほど多くの人の姿が見えるわけでもなければ、声が聞こえるわけでもないが、建物内が活気づいている雰囲気が外まで漂っている。樹はそれに気を取られつつも、トランクに積んでいた荷物を降ろし、久しぶりに多川家へ足を踏み入れた。
以前とそう変わりはないが、樹は荷物を両方の肩にかけたままリビングを見わたした。そのとき、隅に置かれたハンガーラックと、そこにかけられている白いブラウスが目に留まった。
そのブラウスは襟が丸く、合わせ部分には貝殻のような小さなボタンが六個ついていた。沙耶が通っている小学校の制服だ。百合美がカーテンを開けると、リビングに日が射し込んだ。薄い生地でつくられたブラウスが、そのまま光の中に消えていくように見えた。樹は思わず、指先でそのブラウスに触れた。生地の柔らかさと、かすかなあたたかみのある優しい質感が、なぜかひどく痛々しく感じられた。
「樹くん。前と同じ部屋を使ってね」
百合美はそう言って洗面所へ手を洗いに行った。彼女が念入りに手洗いとうがいをしているあいだ、宏一も廊下に立って洗面所が空くのを待ちながら、まだ洗っていない手をぶらぶらさせていた。ここで暮らしていたときのことを、樹は少しずつ思い出しはじめた。そうだった。二人はきれい好きなのだ。俺もあとであれくらい念入りに洗ったほうがいいのだろう。
荷物を抱えて階段を昇った。短い廊下があり、左の壁には小さな窓がついていて、右には襖が閉められた部屋がある。以前、樹が使っていた和室だ。廊下のつきあたりには木目の扉のついた洋室がある。そこは今、沙耶の部屋になっているらしい。
和室の襖を開けると、懐かしいにおいがした。畳と檜のにおいだ。百合美が気に入って、以前からよく使っていた檜の芳香剤が、部屋のすみに置かれていた。液状の中身は半分ほどに減っている。畳も、壁の柱も、窓際にある障子の枠にも、ちりひとつなかった。一度にまとめて掃除をしたのではなく、日頃からきっちりと部屋の手入れがされていたような感じだった。その清潔さは部屋によく馴染んで、とても自然だったのだ。
障子と窓を開けた。海と魚港と、灯台が見渡せる。ちょうど船が港に帰っていくのが見えた。サーファーが何人か海に入っていたが、風が弱いので波には乗れずにいるようだった。
樹はしばらく窓辺に立ってぼんやりとその風景を眺めていた。頭の中に、いろいろな疑問が泡のように浮かんでは消えていった。俺はこれからどうすればいいのだろう。ここで日々が過ぎて、俺はまた前のように壊れていくんだろうか。ふいに言いようのない不安が胸をかすめ、樹は頭を振って、それを振り払った。
そのとき、玄関が開く音がして、一階から「ただいま」という声が聞こえた。おかえりなさい、と百合美が返している。樹は廊下に顔を出して、耳を澄ましてみた。
「百合美さん。塔子ちゃんのお母さんが、これ渡してって」
「なあに、これ」
「わかんない」
「わからないって……。あら、わらびじゃない」
沙耶の声は、ビニール袋のかさかさという音に混じって、はっきりと耳に届いた。すぐに階段を駆け上がってくる気配がして、樹は咄嗟に襖の後ろに隠れた。沙耶は襖一枚を隔てた廊下を、羽のように軽い足取りで通り過ぎると、隣の洋室の扉を開けた。鞄を開けて、中身に触れる物音がする。「手を洗いなさいね」と一階から百合美が叫ぶ。
「はーい」
沙耶がふたたび廊下を通り、階段を下っていくとき、その後ろ姿が見えた。さらさらと揺れる明るい髪に、細くなだらかな肩。細かいレースのついた靴下と、白い足。樹はそのとき、この家を離れてからの二年間で、一番と言っていいほど緊張していた。心臓が激しく脈を打ち、鼓動が耳元で音を立てた。それでも樹は、自分の口もとが自然とほころび、笑みを浮かべていることに気がついて、安堵した。
ずっとここに隠れているわけにはいかない。ずっと逃げ続けるわけにはいかない。樹は目を閉じて大きく深呼吸をしたあと、一階に降りていった。
沙耶は手を洗い、リビングのソファに座ったところだった。隣には宏一が座っている。ふたりとも、こちらに背中を向けて、テレビを見ていた。樹は廊下に立ったまま、ふたりの背中を見つめていた。
しばらくして、キッチンから百合美が出てきた。手に持っている盆には、オレンジジュースの入ったグラスがふたつのせてある。百合美は廊下で立ち尽くしている樹を見つけると、何も言わずに微笑み、沙耶の前にふたつのグラスを置いた。沙耶はテレビに夢中のようで、画面から顔をそらすことなくグラスをとる。
「沙耶」
樹は言った。沙耶はグラスに口をつけたまま、不思議そうにくるりと振り向いた。そして樹の姿を捉えると、目と口をぱっくりと大きく開き、宏一と百合美を交互に見て、また樹を見た。
そして、ほとんど無意識にグラスを宏一の胸に押しつけると、彼の胸元にこぼれたオレンジジュースにはおかまいなしに、ソファの背もたれを飛び越えた。そのまま樹に駆け寄り、体当たりのようにしがみつく。
「お兄ちゃん」
「沙耶、ただいま」
小さな体からは想像もつかない力ですがりつく沙耶の髪に、樹は鼻先をうずめた。
「お兄ちゃん、あたしずっと寂しかったのよ、わかってるの?」
「わかってるよ。ごめんな」
「嘘言わないでよ。本当にわかってたら、もっと早くにこうしてるはずだもの」
沙耶は顔を真っ赤にして、わあわあと大声をあげて泣き始めた。あんまり元気よく泣くので、樹も思わず笑ってしまうほどだった。
「あたし、ずっとわかんなかった。どうしてお兄ちゃんがあたしを置いて、遠くへ行っちゃうのか」
「うん」
「でも、あたしだってちょっとは変わったの。だからわかったのよ。お兄ちゃんが最後にあたしに見せた顔をよく思い出してみたら。お兄ちゃんはあたしから逃げたんだって」
「うん」
「でも、なぜなの。なぜあたしから逃げるの」
「それは……」
言葉につまる樹を、沙耶は赤い顔でじっと見上げた。
「お前が大事だから、壊したくなかったんだ」
「バカじゃないの。あたしに向き合えないんだったら、誰とだって無理よ」
沙耶は両手で樹の胸をどんどんと叩いた。樹はその手を優しく受け止めたあと、沙耶の顔を両方の手のひらで包みこんで目を合わせた。ころんとこぼれ落ちてしまいそうなほど大きな瞳から、泉のように涙が溢れ出ていた。誰が美人だとか、不美人だとか、樹にはいつも、よくわからなかった。でも、沙耶の顔を見て思った。今、俺の手の中にあるものは、世界で一番美しい素顔なのだと。
「本当にごめん」
樹は言った。
沙耶は一度だけ頷くと、顔じゅうにしわをよせて目をぎゅっと閉じ、今度は声を押し殺してしくしく泣いた。樹は沙耶の頭に手のひらをあてて、もう一度抱き寄せた。母さんが死んだ日の俺たちのようだと、樹は思った。でも、もう二度とあんな目には合わせない。
顔をあげると、宏一は歯を食いしばりながら、腕で自分の涙を拭っていた。百合美は盆を抱えたまま、樹と沙耶を見つめている。それはピエタ像のようにどこか悲しげで、それでいて深く安らいだ、母の心そのもののような微笑みだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
