
「鏡は横にひび割れて」〜理想と現実の折り合わせ、過去に向き合うことの難しさ〜
今更話すことでもないが、最近アガサ・クリスティの小説にどハマりしている。
特にエルキュール・ポワロシリーズが大好きで原作全巻揃えるほどになったが、最近はクリスティのもう一人の名探偵、ミス・マープルにも手を出し始めた。
ミス・マープルを簡単に説明すると、
• 本名、ジェーン・マープル。
• イギリスのセント・メアリ・ミードという村に住む老婦人。
• 編み物と庭いじりと田舎の噂話が好き。
• 一見ただの穏やかな老婦人だが、鋭い人間観察力と洞察力を兼ね備えた名探偵。その実力は、ロンドン警視庁の元警視総監も一目置くほど。
こんな感じか。
ポワロと同じく大変に魅力的な人物だ(もっともポワロのようにエキセントリックな人間ではないが)。
そんなミス・マープルシリーズの作品の中に、1962年に発表された『鏡は横にひび割れて(原題:The Mirror Crack’d from Side to Side)」という作品がある。
クリスティ作品としては後期の作品にあたり、作品の描写からもシリーズ開始から月日が経っていることが伺える。
簡単なあらすじを記しておく。
穏やかなセント・メアリ・ミードの村にも、近代化の波が押し寄せてきた。新興住宅が作られ、新しい住人がやってくる。まもなくアメリカの女優がいわくつきの家に引っ越してきた。彼女の家で盛大なパーティが開かれるが、その最中、招待客が変死を遂げた。呪われた事件に永遠不滅の老婦人探偵ミス・マープルが挑む。
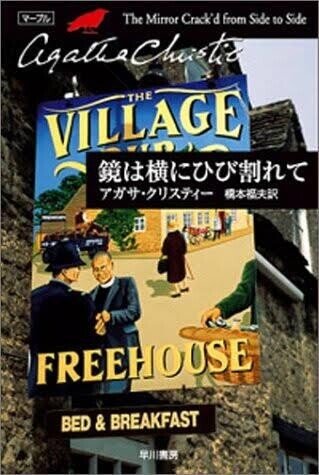
一見何の変哲もない、ありふれた推理小説のあらすじのように見える。
私も読む前はそういう軽い感じでいた。
しかし、実際に読み終わると、読後は今までに感じたことのないくらいの後味の悪さと、あまりにやるせない真相と結末に哀しさを覚えた。
ネタバレも交えて、説明していこうと思う。
(以下、ネタバレあり)
序盤から、ミス・マープルはかなり暗い描かれ方をしている。
病を患ったことが原因で医者からは趣味の庭いじりさえも禁じられ、視力も衰え、もう一つの趣味の編み物も満足にできない始末。心配した甥が親切心から通いの付き添いの女性を派遣したものの、この付き添いの女性がかなり読んでいて不愉快さを感じさせる人物。
別に悪い人でもなく、甲斐甲斐しくミス・マープルに仕えてはいるが、基本ミス・マープルをお年寄り扱い。「お年寄りは誰かそばにいてあげないと何もできない」といったような感じを無意識のうちに持っているからだろう。そのせいか、やることなすことがミス・マープルだけでなく、読者にさえも一抹の不愉快さを味わわせる。ミス・マープルも彼女をあまり快くは思っておらず、彼女にしては珍しく遠回しに嫌味的なことを言ったり、ある時は「彼女を殺してしまいかねない」とまで言わせるほど。
また、セント・メアリ・ミードの村も時代の変化には逆らえず、醜い新興住宅地ができて、スーパーマーケットなどの近代的なものが立ち並び、古くからの住人たちは警戒し、敬遠し、時代の移ろいを嘆く。
また、マープルシリーズの長編第二作『書斎の死体』の舞台にもなったゴシントン・ホールは売りに出され、シリーズ初期に出てきた登場人物も何人かは鬼籍に入った。ミス・マープルの友人で、ゴシントン・ホールの所有者でもあったドリー・バントリーの夫、バントリー大佐もその一人。
時代の移ろいと変化を、心の中では嘆きつつも、それはそれとして受け入れるミス・マープル。付き添いの目を盗んで散歩に出かけ、新興住宅地とその住民たちの様子を実際に観察し、実際に交流することで「人間の本質・人間性というものは、いつの時代でも変わらない」ということを再確認する。人は時代の変化にはなかなかついていけないものだが、変化を嘆きながらも受け止めるミス・マープル。流石、見習わないと。
そして、ドリーが所有していたゴシントン・ホールに新たな買い手が見つかる。それがアメリカの大女優マリーナ・グレッグとその夫で映画プロデューサーのジェースン・ラッドだった。
マリーナ・グレッグは最近まで女優業をセーブしており、愛する夫の献身的な支えもあり、やっとイギリスの片田舎に居を構え、心機一転女優として再スタートを切っていこうというところ。セーブしていた理由は、もともと心の弱かった彼女が精神的に病んでいたことによるもの。彼女は前から自身の子供を産んで、幸せな家庭を築きたいという思いがあり、その理想を実現すべく結婚を繰り返していたが、なかなか子宝に恵まれなかった。一時期は養子を取っていたが、妊娠したとわかった途端、その養子たちは資金力に物を言わせ、程よくお払い箱。だが、待望の子供は重度の知的障害を持って生まれてきた。このことでマリーナは多大な精神的ショックを受けたというのが真相だ。
まずこの時点で、読者はマリーナ・グレッグに共感はできないだろう。養子を取っておきながら、実子を身籠った途端にお払い箱というのは、あまりにも無責任で自己中心的で養子の子たちにも失礼だし、また生まれてきた実子が知的障害持ちなことにもショックを受けて半ば育児放棄みたいな状態にしてしまったのも、親としてどうなのかと思わざるを得ない。
しかし、ある意味彼女は哀れでもある。実子が知的障害持ちでも、それなりに幸せは見出せたはずだ。だが出来なかった。彼女の追い求める理想は、彼女が思い描いていた通りでなければならなかった。彼女の追い求めたのは、心身ともに健康な子供に囲まれながら幸せな生活を送ることだった。人が幸せや理想を追い求める時、それが自身が思い描いていたとおりに実現することはない。どこか妥協点を見つけながら、それを受け入れるしかないのだ。だからマリーナは一生幸せにはなれないのだ。哀れではある。
そんな中でも彼女はなんとか立ち上がり、引っ越し記念に自宅で盛大なパーティーを開いた。ドリーもその招待客のうちの一人(ミス・マープルは前日に足を挫いてしまい不参加)。だが、前述のあらすじの通り、そこで招待客の一人が謎の死を遂げた。
被害者はヘザー・バドコックという女性。彼女は新興住宅地の住人であり、またマリーナの大ファンでもあった。ミス・マープルは以前にヘザーと遭遇しており、蹴躓いて足を挫いたミス・マープルを介抱したのが彼女だった。彼女は慈善事業活動にも熱心であり、これだけ見ればヘザーは「いい人」という評価がつくが、介抱時の時からミス・マープルはヘザー・バドコックは確かにいい人ではあるが、独善的であるが故に自分の行動が他人にどんな影響を及ぼすのかまでには考えが及ばないタイプの人間であると見抜いた。こういうタイプの人間は、意外と身近にいるなと感じた人も多いのではなかろうか。「善意」「親切」という名の押し付けをする人。クリスティは「身近にこういう人間っているよな」と思わせるような人物の描写がずば抜けて上手い。
パーティーに招待されたヘザーは憧れのマリーナ・グレッグに会えるとあって有頂天。マリーナ夫妻がいる別室に特別に招待された時も、マリーナを前にいかに自分が彼女のファンであるかをとうとうと力説。昔、自分がバミューダの野戦病院に入院していた時、マリーナが慰問で現地を訪れたというのを耳にして、医者から絶対安静と言われていたにも関わらず夜中にお化粧を施してこっそり抜け出し、マリーナと5分ほど会話した上にサインまで貰ったという話を長々とマリーナに向かって話していた。まるで自身の武勇伝であるかのように。
少し離れた場所にいたミス・マープルの友人・ドリーもその様子を見ていたが、その際、ヘザーが長々と喋っている間、マリーナ本人は明らかに上の空状態で、しかもヘザーの肩越しのある一点を見つめながら凍りついたような表情を浮かべていることに気づく。それからしばらくののち、ヘザーは意識不明の重体に陥り、そのまま死んだ。
死因は彼女が飲んでいたカクテルに、致死量の睡眠薬が混入された事によるもので、しかもそのカクテルは元々はマリーナが飲むはずのものだった。そこから殺人事件であるとの疑いが濃くなり、警察の捜査がスタート。警察は犯人の真の狙いはマリーナであり、間違えて無関係の人間が殺されてしまったものと仮定し、パーティーの招待客の中にマリーナに恨みを持つものがいないか捜査をする。ミス・マープルはドリーから一部始終を聞き、特にマリーナがヘザーの話を聞いている間、凍りついたような表情を浮かべていたという事実に興味を覚える。その際、ドリーはイギリスの著名な詩人アルフレッド・テニスンの詩『シャロット姫』の一節を引用し、その時の表情を説明した。
織物はとび散り、ひろがれり、
鏡は横にひび割れぬ
「ああ、呪いはわが身に」と、
シャロット姫は叫べり
ミス・マープルはこの話から、ヘザーが話していた「武勇伝」の内容の中に、マリーナにこの表情を浮かべさせた何かがあると推察した。
捜査は一向にはかどらない中、第二・第三の殺人が起こる。一人目はマリーナの夫・ジェースンの個人秘書で、二人目はグレッグ夫妻の執事だった。どうやらこの二人は、真犯人を恐喝していたらしいのだが。。
ヘザーの武勇伝の内容、そしてヘザーが患っていたとされる病気の名前を突き止めたミス・マープルはやっと真相にたどり着き、警察を引き連れながら単身ゴシントン・ホールへ乗り込み、マリーナの夫ジェースンにマリーナへの面会を申し込む。だが、ジェースンの口から知らされたのは、マリーナが昨夜睡眠薬の過剰摂取で亡くなったという報せだった。
ジェースン・警察関係者を前に、ミス・マープルは事件の真相を語る。
ヘザー・バドコック、そして第二・第三の殺人事件の真犯人は、マリーナ・グレッグその人だった。
でもなぜ、人から恨まれることをした覚えのないヘザーが殺さなければならなかったのか?
マリーナの実子は重度の知的障害を持って産まれてきたが、それはマリーナが妊娠初期の段階で風疹にかかったことが原因だった。
風疹(原作ではGerman measle[ドイツ風疹]と紹介される)は感染症の一種で、発熱・発疹などの症状が現れる。死に至る病ではなく、治療をすれば治る病気だが、感染性が強い病気として知られる。また、妊娠初期の段階に罹ると胎児に悪影響を及ぼす事でも知られる。
ヘザーがバミューダの野戦病院で罹っていた病気は風疹だった。お化粧をしたのは発疹を隠すため。そして会った際、風疹がマリーナにうつったのだ。
マリーナはこのことを知ってショックを受けると同時に、知らず知らずのうちに自身に風疹をうつした顔も知らない「犯人」への憎悪を募らせていった。
それでも愛する夫の支えもあって何とか立ちなおろうとしていた矢先、突然目の前にその「真犯人」が現れる。
その時のマリーナの心境はどんなものだったのか。
まさか目の前の立っている女が全ての元凶だったとは。
そう思った時のショックと絶望と怒り。
しかも、そいつは自身の「犯行」を悪いことと思っておらず、むしろ誇らしげに語っている。
マリーナに一度冷静になるほどの理性があれば良かったが、残念ながら彼女はあまりにも憎しみに侵されすぎていた。
「目の前のこの女を自分の手で罰してやりたい」そういう衝動に突き動かされての犯行だった。
ヘザーの悲劇は、独善的で周りの気持ちを慮ることをせずに「いい人」であり続けたこと。
そしてマリーナの悲劇は、自分の理想と現実の折り合いをつけることができずに、哀しいまでに理想を追い求め、そして自分を追い込んだこと。そして、過去に拘り続け、未来に目を向けられなかったこと。
個人的にはヘザーのような人物は救いようのない人としか言いようがないが、マリーナの場合はまだ救える余地があったのではないかと思う。
前にも述べたように、自分が思い描いていた通りの幸せや未来が来ることは100%ない。
だからいかに現実と折り合いをつけ、そこから幸せを掴んでいくか。
この本は、そのことの重要性を教えてくれた気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
