
本日の「読了」
1 エイドリアン・マッキンティ『コールド・コールド・グラウンド』(武藤陽生訳 早川書房 2018)
2 村瀬孝生『シンクロと自由』(医学書院 2022)
3 畠中恵『こいごころ』(新潮社 2022)
読み始めた順序は3→1→2、読了順は1→2→3
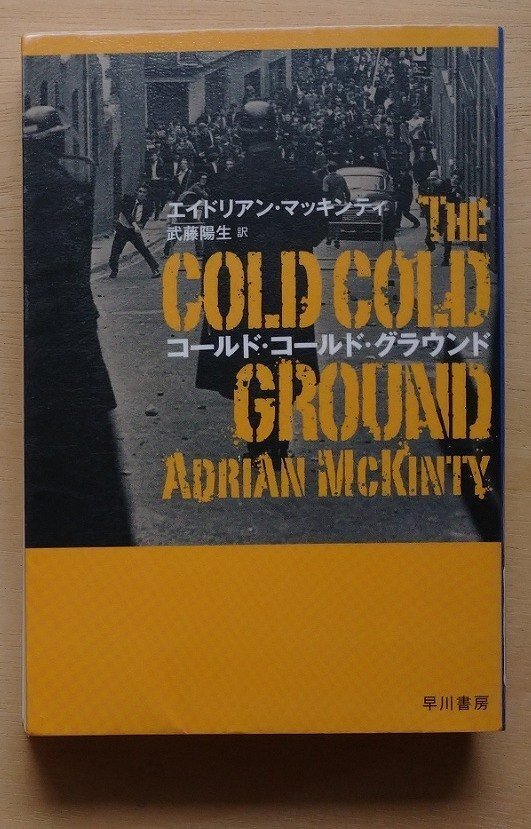
『コールド・コールド・グラウンド』は刑事ショーン・ダフィシリーズの1作目。
主人公は車に乗る前には必ず車の底に爆弾が仕掛けられていないか確認し、「シートベルトは締めない。今年に入って交通事故で死んだ警官は四人。シートベルトをしていたせいで、車両から降りる間もなく射殺されたのが九人。王立アルスター警察隊の統計部門は、総じて見ればシートベルトを着用しないほうが安全だと考え」た時代の北アイルランドを舞台とした警察小説。
ダフィシリーズは6作刊行されており、なかには、日本の島田荘司氏の影響を受けたものもあるとか。海外もので久しぶりにシリーズを読み進めずにはいられない作品。
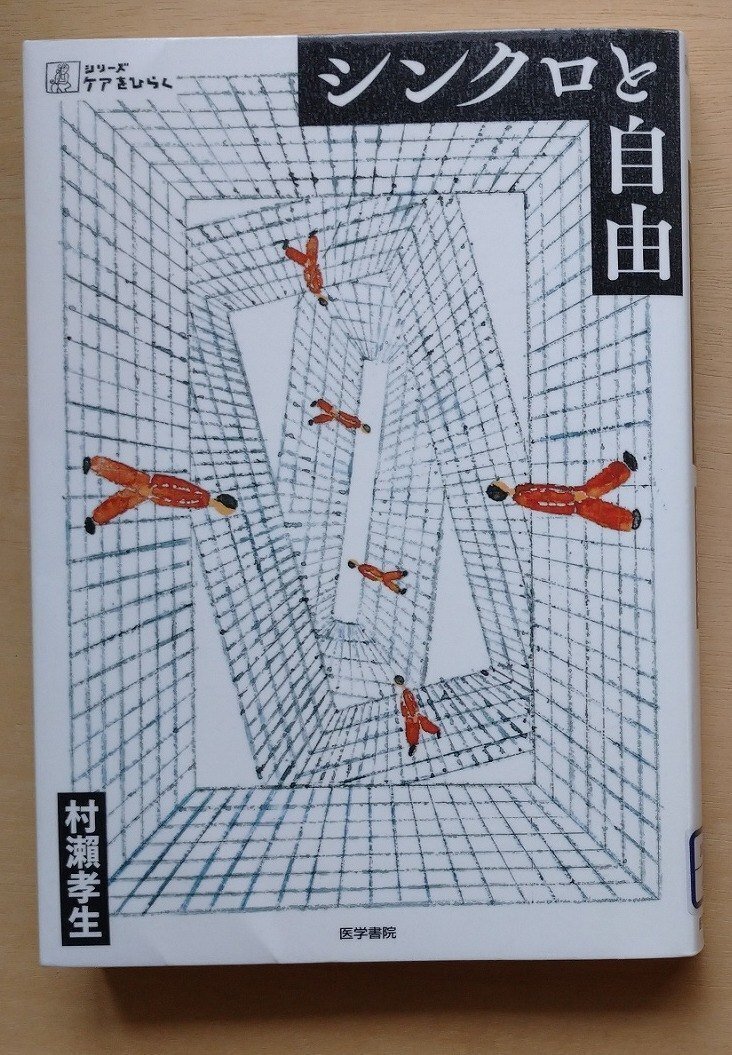
『シンクロと自由』は介護職による物語。
日本の介護施設には「家系」とでもいうべき「宅老所」というジャンルがあり、各地に名の知れた施設があるが、著者は、九州福岡の「宅老所よりあい」のスタッフ(※海外には、例えば日本で介護洗身国とみられる北欧には家系があるのだろうか?)。
この本、読み手の立場で印象がずいぶんと違うかもしれない。
介護を必要とする人の近くで、進んで一緒に七転八倒したり途方にくれたりする姿勢を羨ましく、また、まぶしく感じる人もいるだろうし、そこいらじゅうに放尿する人、物品を自分の意のままに移動させる人などが10人束になってかかってきたら、悠長なこと言ってられるか! と憤慨する人、やはり介護に生産性も科学も通用しないよねと首肯する人などなど。
わたしはと言えば、トイレで一緒に「ヒィッヒッフゥー」などと言う場面やそれに続く「今日は大きな子が生まれました」的な家族への報告、「家に帰る」と出て行ってしまう人の後をつけて、途方に暮れたところで一緒に戻るとか、意味不明不可解な行動を真似してみるとか、その人の生活歴から生まれてきているであろう「世界」に入って、その地平でものを見る、その方を動かすスイッチを見つけたときの職員一同のガッツポーズ等々、観察、分析、アウトプット、玉砕の繰り返しを途方に暮れつつ楽しんでいた自分や当人の表情や同僚の動きを思い出し、ノスタルジーに浸った。
前書きに「本書は個人の実感と主観に満ちており、(中略)よって、明日からの介護にすぐ役立つことはありません。エビデンス重視の時代と逆行する本だと思います」とあり、著者の立ち位置が、昨今、介護界で言われる「エビデンス、それに基づいた科学的介護、さらには、生産性効率重視の運営には乗らない」ということが分かる。
私自身は必ずしもその意見に与しない。著者や版元は、「この本に描かれる物語のどこにエビデンスがあり、科学が介入余地がどこにあると思いますか!?」と、問いを突き付けているのだろうが、介護におけるエビデンスや科学への応用の源は「物語」こそにあると思うとだけ言っておく。
蛇足だが、介護現場の効率化や科学、IT化を目指す政府の検討委員会にはぜひとも「家系」介護施設も加えてほしいものだ。日ごろ、効率とは真逆を言っているような現場にこそ、効率化のヒントがあると思う。
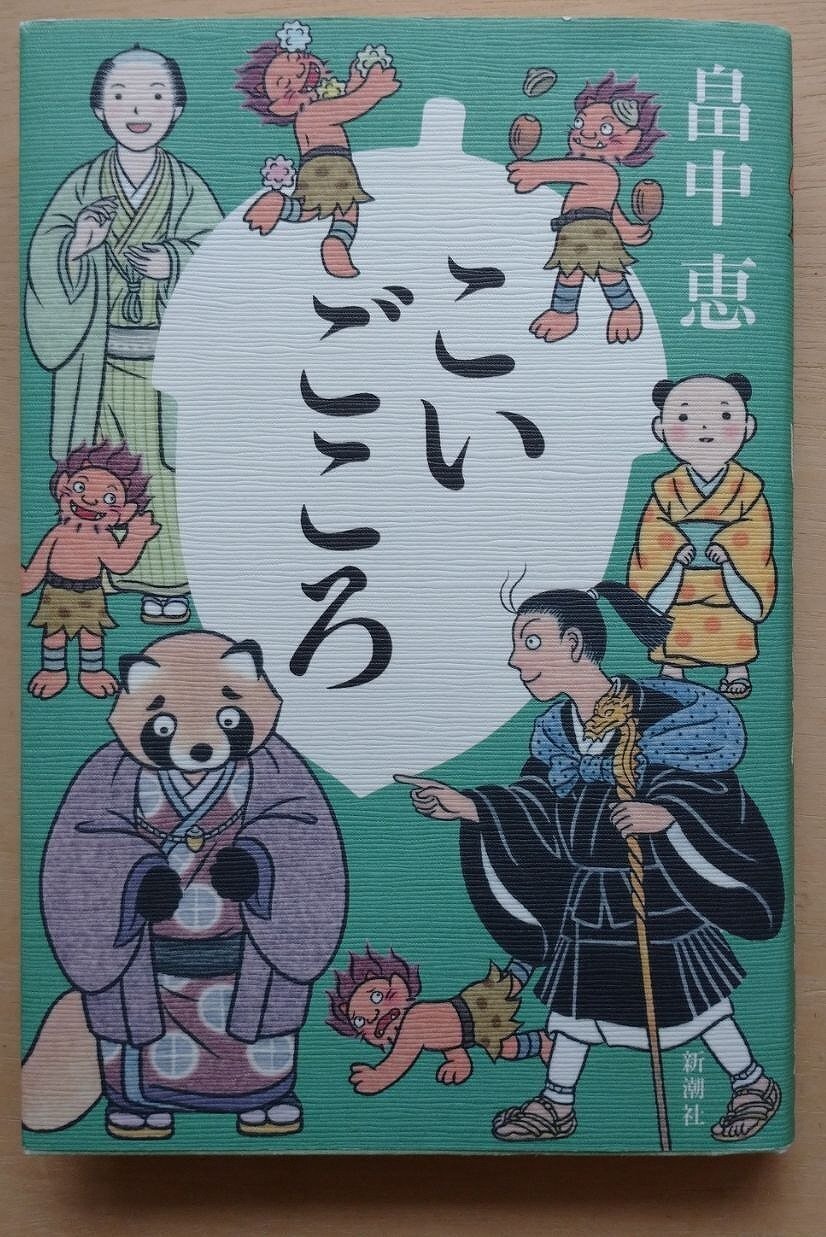
『こいごころ』はフアンも多いので、感想を言うまでもない。
ただ、最近は、長崎屋の離れの妖が表世界に出て活躍することが多く、二つの世界の「あいだ」の怪しさとか、秘密めいたところが薄くなってきていると思うのはおっさんだかけか。
ともあれ、安定感の面白さ。
[2022.09.08.ぶんろく]
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
